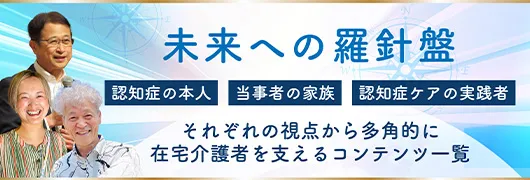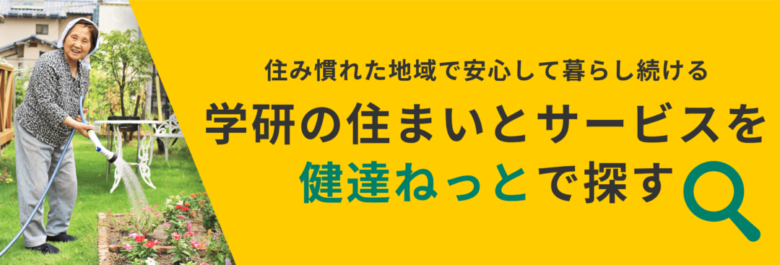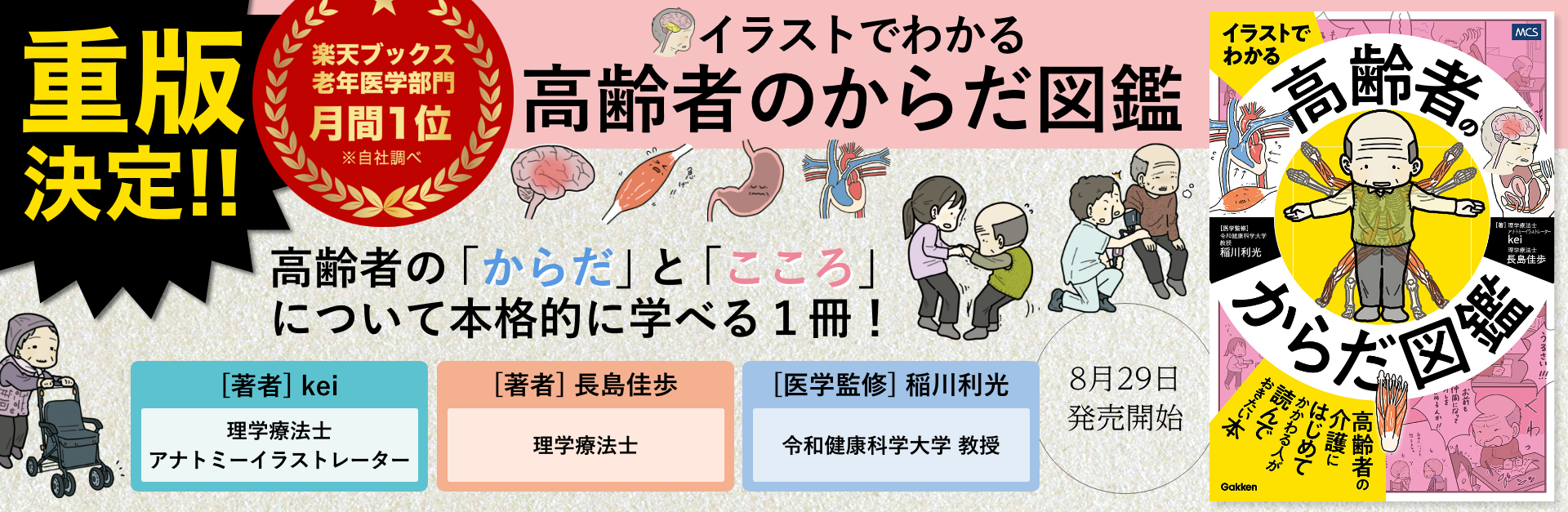不要になった土地や建物などの不動産は、売却することによって利益を得られます。
不動産売却では、一度に多額の利益を得られますが、売却時の手続きや売却の利益に対して税金がかかります。
では、具体的にはどのような税金がかかるのでしょうか?
また、税金を少しでも安く抑えるために、どのような対策が有効なのでしょうか?
本記事では不動産売却の税金について、以下の点を中心にご紹介します。
- 不動産売却にかかる税金とは
- 税金の計算方法
- 税金対策として活用できる制度
- 不動産売却で損をしないための注意点
不動産売却時の税金について、みなさまが知るきっかけになれたら幸いです。
近いうちに不動産の売却を検討している方も、将来的に不動産を売却する可能性のある方も、ぜひ最後までお読みください。
不動産売却にかかる税金とは?
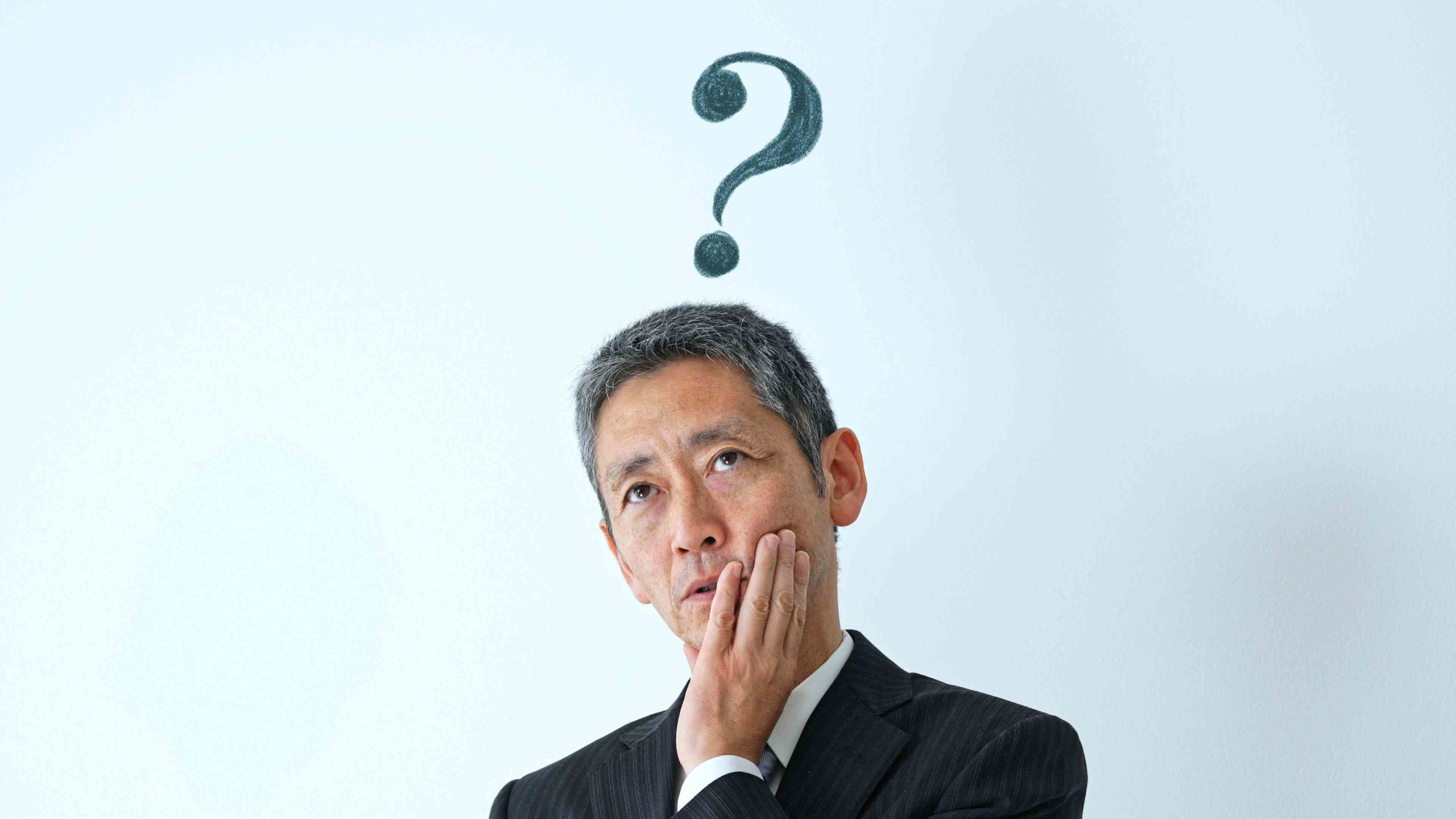
不動産売却にかかる税金は、全部で4種類です。
不動産売買の手続きによって発生する
- 印紙税
- 登録免許税
不動産の売却益に対して発生する
- 住民税・復興特別所得税
- 譲渡所得税
一つずつ詳しく見ていきましょう。
不動産売却にかかる税金は「4種類」

不動産売却にかかる税金は4種類あります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 住民税・復興特別所得税
- 譲渡所得税
順番に解説します。
印紙税
まず一つ目は、印紙税です。
不動産を売却する際は、売買に関する契約書を作成します。
このような契約書は課税文書と呼ばれ、契約金額に応じて収入印紙を貼り付けることが義務付けられています。
収入印紙を貼付し、消印することで印紙税を納めることになります。
| 契約金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満 | 0円 |
| 1万円を超え10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
平成26年から令和6年3月31日までに作成される不動産売買契約書については特例措置で印紙税が軽減されます。
【特例措置による軽減後の印紙税】
| 契約金額(1通につき) | 税額 |
| 1万円以上50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
この税率は変動する可能性があります。
最新の情報は国税庁のWEBサイトで確認しておきましょう。
なお、収入印紙の貼付と消印をしなかった場合は、懲罰の対象となります。
- 契約書に収入印紙を貼付しなかった場合は、本来の印紙税+印紙税の2倍の過怠税
- 収入印紙を貼付しても、消印しなかった場合は、本来の印紙税+印紙税と同額の過怠税
このようなペナルティが課せられますので、不動産売却の際は忘れないようにしましょう。
登録免許税
ひとつひとつの土地や建物ごとの所有者や、担保の有無(抵当権)を公示することを、登記と言います。
不動産を第三者に売却し、その不動産にかかっていた所有権を変更する際は、不動産を登記する必要があります。
登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金です。
登記は法務局にて行いますが、法務局の職員に登記を変更してもらうための手数料として、登録免許税を支払うというようなイメージです。
所有権を移転する場合
所有権の移転に関する登記は、慣習として買い手側が負担することが一般的です。
とはいえ、法的に定められているというわけでもないので、特約として売主側が負担することもできます。
登録免許税は、具体的に以下のような税率になります。
| 登記原因 | 課税標準 | 税率 |
| 売買による所有権移転登記 | 不動産の価額 | 土地 1,000分の20(※注) |
| 建物 1,000分の20 | ||
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 |
※注:平成25年4月1日から令和5年3月31日まで1,000分の15
住民税・復興特別所得税
住民税や復興特別所得税は、不動産売却の利益によって変動します。
住民税は、前年の所得の金額を基礎として計算されます。
給与明細などを見てみると、毎月、住民税が徴収されているため、ご存じの方も多いことでしょう。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために、所得に対して一時的に徴収される税金のことです。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は、お給料などの所得からも毎回引かれている税金なのです。
復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの間に徴収されます。
税額は、所得税の2.1%相当額に設定されています。
譲渡所得税
不動産を売却したときの利益は、譲渡所得として取り扱います。
譲渡所得は、不動産の売却金額から、売却に要した手数料などを差し引いて計算します。
また、譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって大きく異なります。
先述した、住民税・復興特別所得税も、譲渡所得の金額によって変動するため、
不動産売却の際は譲渡所得についてよく理解しておくと良いでしょう。
ここからは、譲渡所得の計算方法や税率について詳しくご紹介します。
譲渡所得税の計算方法と注意点!

ここでは、譲渡所得と所得税の計算方法や、税額計算の際の注意点を紹介します。
譲渡所得の計算方法
ステップ1:譲渡所得を理解する。
譲渡所得というのは、簡単に言うと
「その不動産を売却したことによって、いくら儲けたか」
という意味になります。
ここで注意したいのが、不動産を売却した時の金額=譲渡所得ではないということです。
譲渡所得は儲け=利益を意味します。
そのため、不動産の売却金額(譲渡価額)から、不動産の購入金額(取得費)と売却時にかかった諸費用(譲渡費用)を差し引いて計算します。
ステップ2:特別控除額を差し引く
要件を満たしていれば、不動産の譲渡所得に対する特例を受けられます。
特例を受けることで、譲渡所得から3,000万円控除できたり、税率が軽減できたりというメリットがあります。
詳しくは後述の「不動産売却時に知っておきたい5つの特例・特別控除」を参照ください。
特別控除額を差し引いた後の金額が、正式な譲渡所得となります。
計算式で表すと、次のようになります。
譲渡所得=売却時の金額−(取得時の費用+売却時の手数料+特別控除額)
ステップ3:税率をかける
譲渡所得の金額が分かったら、その数字に税率をかけて、税額を計算します。
不動産を所有している期間によって、所得税率が変わるので注意しましょう。
注意点1:不動産の所有期間によって税率が変わる。
不動産を売却した時の利益である譲渡所得は、その不動産を取得してから売却するまで、どれだけの期間所有していたかによって税率が変わります。
不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合(つまり6年以上)は「長期譲渡所得」として区分されます。ここで注意しておくべきなのが、所有期間の計算方法です。
所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているか否かで判断されます。
たとえば、2015年5月に取得した不動産を2020年10月に譲渡した場合、
この時に生じた所得は短期譲渡所得と長期譲渡所得のどちらに分類されるでしょうか?
このケースでは、売却した年の2020年1月1日時点において、所有期間が5年を経過していませんので、短期譲渡所得として取り扱われます。
注意点2:取得費・売却費用には仲介手数料も含まれる。
建物や土地を購入したり、建設したりするにはお金がかかりますよね。
不動産会社を経由した場合は仲介手数料がかかります。
これらの所得費や手数料などは、譲渡所得を計算する際に、売却時の金額から差し引けます。
もし、不動産を取得した時の金額が分からない場合でも、売却時の金額の5%を取得費にできます。
不動産の譲渡所得にかかる税率
ここまでで、譲渡所得の金額の計算方法や、短期譲渡所得・長期譲渡所得の分類について分かりました。
譲渡所得に特定の税率をかけて、実際に支払う税額を計算していきましょう。
譲渡所得税額の早見表
それぞれの税率を以下の表でご紹介します。
| 譲渡所得の分類 | 所有期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
ここまで紹介してきたことを元に、譲渡所得の額と税額を計算してみましょう。
たとえば、2020年4月に購入して2026年5月に売却、
売却価格が5,000万円、取得費が1,500万円、売却時の仲介手数料が200万円とします。
譲渡所得=5,000万円−(1,500万円+200万円)=3,300万円
長期譲渡所得に分類されるため、
所得税額=3,300万円×15%=495万円(復興特別所得税除く)
このような計算式になります。
不動産売却時に知っておきたい5つの特例・特別控除

不動産売却時の特例を利用すると、次のようなメリットがあります。
- 譲渡所得を計算する時に、特別控除額を適用できる
- 一般よりも低い税率が適用される
つまり、特例の利用によって所得税や住民税の節税効果が見込めるのです。
しかし、特例を適用させるには、一定の条件を満たしている必要があります。
ここからは、不動産売却時の5つの特例をご紹介します。
また、それぞれの特例を紹介した後に、国税庁のwebサイトのリンクを記載しています。
より詳しく知りたいという方は参考にすると良いでしょう。
読者の皆様が活用できそうな特例はあるかもしれません。
ぜひチェックしてみてください。
マイホーム(居住用不動産)を売った時の特例
正式名称は「居住用財産の3,000万円の特別控除」です。
省略して「3,000万円の特別控除」と呼ばれることが多いです。
この特例では、居住用財産(家や、家が立てられた土地)を売却した時に、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できるという内容になります。
たとえば、売却価格が5,000万円、取得費が1,500万円、売却時の仲介手数料が200万円で、3,000万円の特別控除が適用された場合、
譲渡所得=5,000万円−(1,500万円+200万円+3,000万円)=300万円
ちなみに、特例を利用しなかった場合の譲渡所得は3,300万円になります。
特例の利用によって300万円まで減額されました。
控除された3,000万円の分だけ、所得税や住民税が減額されることになります。
かなりお得な特例であることがわかりますね。
こちらの特例のポイントと注意点を下記にまとめます。
- 居住用財産の譲渡時に限り適用できる(事業用財産は不可)
- 不動産の所有期間が短期でも長期でもOK
- この後紹介する、「居住用財産の軽減税率の特例」と合わせて適用できる
- 配偶者、父母、子などへの譲渡は適用外
- 居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡しなければいけない
- この特例は3年に1回しか受けられない
参考:国税庁【No.3302 マイホームを売ったときの特例】
所有期間が10年を超える不動産を売った時の特例
こちらは正式には「居住用財産の軽減税率の特例」といいます。
省略して「軽減税率の特例」と呼ばれることが多いです。
ひとつ前にご紹介した「3,000万円の特別控除」と何が違うかと言いますと、
この特例では、所得税を計算する際の税率が軽減されるのです。
所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、
譲渡価格の6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されるというものです。
この特例を利用した場合の税率を、下記にまとめました。
| 譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 14% |
| 6,000万円を超える部分 | 15% | 5% | 20% |
※こちらの所得税とは別に、復興特別所得税として、所得税の2.1%相当額がかかります。
ひとつ前にご紹介した「3,000万円の特別控除」と合わせて受けられるため、
譲渡所得を3,000万円減額させたうえで、実際に納付する所得税・住民税まで減額できます。
これらを踏まえ、例に基づいて税額を計算していきましょう。
例えば、所有期間15年の居住用財産を売却したとします。
売却金額は2億円、取得費8,000万円、売却時の手数料が400万円でした。
この場合の所得税と住民税は、それぞれいくらになるでしょうか?
この場合、「3,000万円の特別控除」および「軽減税率の特例」の対象となります。
譲渡所得は
譲渡所得=2億円−(8,000万円+400万円+3,000万円)=8,600万円
所得税=6,000万円×10%+(8,600万円−6,000万円)×15%=990万円
住民税=6,000万円×4%+(8,600万円−6,000万円)×5%=370万円
図にするとこのようなイメージです。
| 譲渡収入2億円 | |||
| 取得費 8,000万円 | 譲渡費用 400万円 | 特別控除 3,000万円 | 譲渡価格 8,600万円 |
↙︎ ↘
| 6,000万円以下の部分 →所得税10% 住民税4% | 600万円を超える部分 →所得税15% 住民税5% |
こちらの特例のポイントと注意点を以下にまとめます。
- 居住用財産の譲渡時に限り適用できる(事業用財産は不可)
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要がある
- 譲渡所得の6,000万円以下の部分について、14%の軽減税率(所得税10%、住民税4%)が適用される
参考:国税庁【No.3305 マイホームを売った時の軽減税率の特例】
マイホームを買い替えた時の特例
こちらは、正式名称を「特定居住用財産の買換えの特例」といいます。
省略して「買換えの特例」と呼ばれることが多いです。
※税法上、「買い替え」は「買換え」と表記されていますので、ここからは「買換え」に統一して記載します。
この特例では、居住用財産を売却し、新たに居住用財産を購入したとき、所得税や住民税を繰り延べられます。
たとえば、2,000万円で購入したマイホームを6,000万円で売却し、新たなマイホームを7,000万円で購入したとします。
本来であれば、売却益である4,000万円の部分が課税対象となります。
しかし、この特例を利用すると、売却した年には売却益4,000万円に対する課税は行われず、新しく購入したマイホームを売却する時まで、課税が繰り延べられます。
こちらの特例では、売却する居住用財産、購入する居住用財産の両方に要件が設けられています。
売却する居住用財産の要件
- 現に自分が居住しており、居住期間が10年以上
- 過去に自分が10年以上居住していた住宅で、自分が住まなくなってから3年後の12月31日までに売却されるもの
- 10年以上居住していた住宅が、災害によって滅失した場合、その住宅を引き続き所有していたとしたら、その年の1月1日時点の所有期間が10年以上
- 売却金額が1億円までであること
購入する居住用財産の要件
- 前年の1月1日から、売却した年の翌年の12月31日までに買換えすること
- 取得者自身が居住する不動産であること
- 家屋の床面積は50㎡以上
- 土地の面歴は500㎡以上
- 中古住宅の場合は、新耐震基準に適合しているか、一定の耐火建築物以外のものである場合には建築後年数が25年を経過している必要がある
なお、この特例は他の特例と併用できません。
- 買換えの特例のみを利用
- 3,000万円の特別控除と軽減税率の特例を併用
どちらを選択した方が税金の節約になるかは、売却時の金額やその他の要件によって異なります。
実際に計算をした上で、有利な方を利用するのをおすすめします。
参考:国税庁【No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例】
平成21年および22年に取得した土地を売った時の特例
こちらは期間限定の特例になります。
平成21〜22年の間に購入した土地を売却した場合、売却金額から1,000万円を特別控除できるというものになります。
こちらの特例のポイントや注意点を以下にまとめます。
- 平成21年から22年の間に購入した土地であること
- 売却する年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていること
- 父母、配偶者、生計を共にする親族など、特別な間柄から取得した土地は不可
- 法人から取得した土地は不可
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁償および所有権移転外リース取引により取得した土地は不可
- 売却した土地について、他の特例の適用を受けていないこと
この特例では、他の特例と併用できません。
1,000万円の特別控除のみの特例を受けるか、その他の特例を適用するかは、売却時の要件によって異なります。
実際に計算してみて、有利な方を選択するようにしましょう。
参考:国税庁【No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円の特別控除】
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
この特例は、譲渡損失が出た場合に、源泉徴収額が戻ってくる特例です。
まず、譲渡損失についてご説明します。
例えば、1,000万円で購入したマイホームを1,100万円で売却し、手数料が200万円かかったとします。
この場合ですと、
譲渡所得=1,100万円−(1,000万円+200万円)=▲100万円
このように、譲渡所得はマイナスとなり、100万円の赤字となってしまいます。
※▲は損失を意味する
譲渡所得がマイナスの場合は、もちろん所得税や住民税は発生しません。
特例の適用を受けることによって、売却した年に発生した損失を、翌年以降3年にわたって「損益通算」を受けられます。
損益通算とは、給与所得などのプラスの所得から、譲渡損失を差し引くことをいいます。
たとえば、その年の給与所得が800万円とします。
1,000万円で購入したマイホームを1,100万円で売却し、手数料が200万円かかりました。
この場合、譲渡損失はマイナス100万円ですね。
この譲渡損失を、給与所得から差し引きます。
給与所得800万円−譲渡損失100万円=700万円
この700万円を所得として扱えます。
これを「損益通算」といいます。
所得の金額が減額される分、所得税や住民税が軽減されるというしくみです。
もし、譲渡損失が2,000万円で、その年の給与所得が700万円だったという場合ですと、下記のような計算式になり、所得はゼロとして扱われます。
給与所得700万円−譲渡損失2,000万円=▲1300万円
譲渡損失の2000万円は3年間にわたって損益通算できますので、はじめに損益通算できなかった残りの損失については、2年目、3年目に繰り越して損益通算します。
【2年目】
給与所得700万円−1,300万円=▲600万円
【3年目】
給与所得700万円−600万円=100万円
このケースですと、2年目までの所得はゼロとして扱われ、3年目の所得は100万円となりますね。
また、この特例を受けるには、居住用財産の買換えをしていることが条件になります。
売却する居住用財産、購入する居住用財産の両方に要件が設けられているので、確認していきましょう。
売却する居住用財産の要件
- 売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えていること
- 以下の1から4のうち、いずれかに該当していること
- 現在、自分が住んでいる住宅
- 以前住んでいた住宅で、自分が住まなくなってから3年後の12月31日までに売却したもの
- 1、2の住宅及びその敷地
- 火災によって滅失した1の住宅の敷地であり、その住宅が滅失しなかったならば、売却したとしの1月1日時点の所有期間が5年を超えていること。ただし、火災があった日から3年が経過した日を属する年の12月31日までに売却していること
購入する居住用財産の要件
- 自己の居住用として取得した不動産であること
- 家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること
- 取得した翌年の12月31日までの間に居住すること、または居住の見込みであること
- 繰越控除を受ける年の12月31日において、返済期間10年以上の住宅ローンを有していること
参考:国税庁【No.3370 マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)】
不動産売却で譲渡益が出た場合
ここまでで、不動産売却時に活用できる5つの特例についてご紹介いたしました。
不動産売却に伴って譲渡益が発生した場合は、特例の適用を受けることによって所得税や住民税の節税を図れます。
また、譲渡損が発生した場合は、他の所得から損失分を差し引くことで、税金の払い過ぎを防げます。
これまで紹介した特例を簡単にまとめます。
マイホームを売って利益が出た時
- マイホームを売った時の特例(3,000万円の特別控除)
- 所有期間が10年を超える不動産を売った時の特例(軽減税率の特例)
マイホームを買換えて、利益または損失が出た時
- マイホームを買い替えた時の特例(買換えの特例)
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
土地を売却した時
- 平成21年および22年に取得した土地を売った時の特例
みなさんが活用できそうな特例はありますか?
それぞれの項目の下部に、国税庁のリンクを貼付しております。
もっと詳しく知りたいという方は、参考にしてみてください。
不動産売却で損をしないための準備

大切な不動産を売却するのですから、できるだけ損をしたくないですよね。
不動産業者の中には悪徳な業者も潜んでおり、高額な仲介手数料を要求されたり、不動産を相場未満の安値で買い叩かれたりするリスクがあります。
しかし、そのようなリスクは、事前に知識を付けておくことで回避できます。
ここからは、不動産売却時に損をしないためには、どのように準備しておくと良いのか、紹介していきます。
相場を知る
まずは、売却予定の不動産が、だいたいいくらで取引されているのか、相場を知ることが大切です。
不動産の価格は、面積や間取り、築年数の他に、立地やその時の人気度などによって変動します。
近くに大きな駅やショッピングモールが建設される予定があれば、その土地の人気は高まり、相場は高くなるでしょう。
逆に、築年数が浅く、面積の広い不動産であっても、過疎地では高価な値段はつきにくいのが現実です。
相場より安く買われることの無いように、不動産の簡易査定などを利用しておおまかな相場を把握しておきましょう。
過去の事例などを参考に価格帯を知る
売却予定の不動産と似ている条件の不動産を見つけて、それらがいくらで取引されたのかをチェックするのもおすすめです。
不動産の取引事例は、「土地総合情報システム」という公的な機関が運営しているサイトで簡単にチェックできます。
参考:【土地総合情報システム】
取引事例を確認する際は、以下の条件を比較して、自分が売却を検討している不動産と似ているものを探しましょう。
- 近隣の地域であること
- 戸建か、マンションか、土地のみか
- 木造か、鉄筋コンクリートか
- 築年数
- 床面積・土地の面積
簡易査定を複数の会社に依頼する
不動産業者に簡易査定を依頼することで、売却予定の不動産の相場を簡単に知ることができます。
その際は複数の査定を受けることで、相場を把握しやすくなり、以上に安値で買い叩かれることも防げます。
不動産一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産会社に査定を依頼できるため、おすすめです。
不動産売却の税金対策での注意点

不動産売却の税金対策にはいくつかの注意点があります。
下記の点に気を付けてください。
併用できない税金控除がある
「3,000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」など、併用することでさらに節税効果を図れる特例もあります。
しかし、特例の中には、他の特例と併用することが禁止されているものもあります。
併用できる特例
- 3,000万円の特別控除と軽減税率の特例
併用できない特例
- マイホームの買換えの特例
- 平成21年および22年に取得した土地の1,000万円の特別控除
ふたつの特例を併用した方がお得なのか、併用せずに単独で特例を受けた方がお得なのかは、その他の条件で異なります。
自分の不動産はどの特例を受けるのが一番お得なのか、まずは実際に計算してみましょう。
その上で、どの特例を選ぶのか決めることをおすすめします。
確定申告が必要となるケースがある
不動産売却によって、不動産所得(=課税所得)が20万円以上になる場合は、その年度末に確定申告する必要があります。
また、不動産所得がマイナスとなり、確定申告が不要な場合でも、譲渡損失が発生し、損益通算や繰越控除する場合は確定申告が必要になります。
確定申告の対象であるにもかかわらず、申告しなかった場合はどうなるのでしょうか?
その場合、税務署からの指摘を受け、「期間後申告」として扱われます。
帰還後申告では、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」を納めなければなりません。
つまりは罰金のようなものです。
無申告加算税は、納付する税額のうち50万円までは10%の税率、50万円を超えた部分は15%の税率が加算されます。
特定申告の申告書類は、税務署から送られてくるか、税務署で直接もらえます。
確定申告を忘れると、良いことが一つもありません。
確定申告の対象となる場合は、期限までに必ず提出するようにしましょう。
相続した不動産の売却には別の税金がかかる
親や配偶者などからの相続によって不動産を取得した際は、相続税や、名義変更のための登録免許税がかかります。
相続によって取得した不動産を売却する段階になって、その不動産の名義が被相続人のままだった場合は、不動産取引が正当であることを証明するために名義変更しなければなりません。
名義変更する際にかかる登録免許税は、不動産の価格の0.4%とされています。
名義変更の手続きは法務局で行えるほか、司法書士に依頼して行えます。
よくある事例とシミュレーション

ここでは、不動産売却時に活用できる特例の条件をおおまかにご説明します。
もっと詳しく知りたいという方は、貼付しているリンクより、国税庁webサイトの該当ページをご覧ください。
マイホーム(居住用財産)を売った時の特例
譲渡所得の金額から、最大3,000万円を特別控除できます。
- 居住用財産の譲渡時に限り適用できる(事業用財産は不可)
- 不動産の所有期間が短期でも長期でもOK
- この後紹介する、「居住用財産の軽減税率の特例」と合わせて適用できる
- 配偶者、父母、子などへの譲渡は適用外
- 居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡しなければいけない
- この特例は3年に1回しか受けられない
参考:国税庁【No.3302 マイホームを売ったときの特例】
所有期間が10年を超える不動産を売った時の特例
所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、
譲渡価格の6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されるというものです
この特例を利用した場合の税率を、下記にまとめました。
| 譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 14% |
| 6,000万円を超える部分 | 15% | 5% | 20% |
※こちらの所得税とは別に、復興特別所得税として、所得税の2.1%相当額がかかります。
ひとつ前にご紹介した「3,000万円の特別控除」と合わせて受けられるため、
譲渡所得を3,000万円減額させたうえで、実際に納付する所得税・住民税まで減額できます。
- 居住用財産の譲渡時に限り適用できる(事業用財産は不可)
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要がある
- 譲渡所得の6,000万円以下の部分について、14%の軽減税率(所得税10%、住民税4%)が適用される
参考:国税庁【No.3305 マイホームを売った時の軽減税率の特例】
マイホームを買い替えた時の特例
この特例では、居住用財産を売却し、新たに居住用財産を購入したとき、所得税や住民税を繰り延べられます。
売却する居住用財産、購入する居住用財産の両方に要件が設けられています。
売却する居住用財産の要件
- 現に自分が居住しており、居住期間が10年以上
- 過去に自分が10年以上居住していた住宅で、自分が住まなくなってから3年後の12月31日までに売却されるもの
- 10年以上居住していた住宅が、災害によって滅失した場合、その住宅を引き続き所有していたとしたら、その年の1月1日時点の所有期間が10年以上
- 売却金額が1億円までであること
購入する居住用財産の要件
- 前年の1月1日から、売却した年の翌年の12月31日までに買換えすること
- 取得者自身が居住する不動産であること
- 家屋の床面積は50㎡以上
- 土地の面歴は500㎡以上
- 中古住宅の場合は、新耐震基準に適合しているか、一定の耐火建築物以外のものである場合には建築後年数が25年を経過している必要がある
なお、この特例は他の特例と併用できません。
- 買換えの特例のみを利用
- 3000万円の特別控除と軽減税率の特例を併用
どちらを選択した方が税金の節約になるかは、売却時の金額やその他の要件によって異なります。
実際に計算をした上で、有利な方を利用するのをおすすめします。
参考:国税庁【No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例】
平成21年および22年に取得した土地を売った時の特例
こちらは期間限定の特例になります。
平成21〜22年の間に購入した土地を売却した場合、売却金額から1000万円を特別控除できるというものになります。
こちらの特例のポイントや注意点を以下にまとめます。
- 平成21年から22年の間に購入した土地であること
- 売却する年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていること
- 父母、配偶者、生計を共にする親族など、特別な間柄から取得した土地は不可
- 法人から取得した土地は不可
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁償および所有権移転外リース取引により取得した土地は不可
- 売却した土地について、他の特例の適用を受けていないこと
- 他の特例との併用は不可
参考:国税庁【No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円の特別控除】
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
譲渡損失が出た場合に、源泉徴収額が戻ってくる特例です。
この特例を受けるには、居住用財産を買換していることが条件になります。
売却する居住用財産、購入する居住用財産の両方に要件が設けられているので、確認していきましょう。
売却する居住用財産の要件
- 売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えていること
- 以下の1から4のうち、いずれかに該当していること
- 1 現在、自分が住んでいる住宅
- 2 以前住んでいた住宅で、自分が住まなくなってから3年後の12月31日までに売却したもの
- 3 1、2の住宅及びその敷地
- 4 火災によって滅失した1の住宅の敷地であり、その住宅が滅失しなかったならば、売却したとしの1月1日時点の所有期間が5年を 超えていること。ただし、火災があった日から3年が経過した日を属する年の12月31日までに売却していること
購入する居住用財産の要件
- 自己の居住用として取得した不動産であること
- 家屋の居住部分の床面積が50㎡以上であること
- 取得した翌年の12月31日までの間に居住すること、または居住の見込みであること
- 繰越控除を受ける年の12月31日において、返済期間10年以上の住宅ローンを有していること
参考:国税庁【No.3370 マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)】
不動産売却についてのよくある質問

ここでは、不動産売却時によくある疑問にお答えします。
土地と建物(マンション、アパート)の売却における税金の違いはありますか。
- 土地のみを売却した場合
- 建物のみを売却した場合
- 土地と建物を合わせて売却した場合
どのケースも、譲渡所得にかかる税率には違いがありません。
ただし、特例を受ける場合は、特定の年数居住した不動産にかかる特例、特定の年に取得した土地にかかる特例など、不動産の条件によって所得金額や税率が軽減される可能性があります。
そのため、売却を検討する時点で、自分の不動産はどの特例を受けられるか把握しておくことが重要です。
相続した土地を売却する時の税金はどうなりますか?
相続によって取得した不動産は、所有期間の計算方法が少々特殊になります。
一般的には、自分が取得してから売却するまでの期間を所有期間としますが、
相続した不動産の場合は、被相続人が所得してから、自分が売却するまでの期間が所有期間になります。
つまり、相続による不動産の取得から1年ほどしか経っていなくても、被相続人が五年以上所有していた場合は、長期譲渡所得として取り扱われます。
また、相続から売却までの期間が3年以内の場合は、不動産の相続時にかかった相続税を所得費として、売却金額から差し引くこともできます。
税金の納付時期はいつですか?
不動産を売却した際は、数種類の税金がかかります。
ここでは、それぞれの税金の納付期限についてご紹介します。
| 納付時期 | 納付方法 | |
| 印紙税 | 売却契約を結んだとき | 収入印紙を購入し、契約書に貼付・消印して納付 |
| 登録免許税 | 引渡時、抵当権などの抹消登記などの登記申請をしたとき | 収入印紙で納付 |
| 所得税 | 売却した翌年の確定申告後 (2/16〜3/15) | 所得税の確定申告を提出後、納付書で納付 |
| 住民税 | 売却した翌年度の6月以降 | 給与所得者は手続き不要(源泉徴収により納付) 給与所得者以外は、納付書で納付 |
| 復興特別税 | 売却した翌年の確定申告後 (2/16〜3/15) | 所得税の確定申告を提出後、納付書で納付 |
不動産売却にかかる税金まとめ

ここまで、不動産売却にかかる税金についてご紹介しました。
不動産売却の税金についての要点を、以下にまとめます。
- 不動産売却時は、印紙税・登録免許税・所得税・住民税・特別復興税がかかる
- 税額の計算時は、その時の条件に応じて異なる税率を使う
- 税金対策として特例を活用する方法があるため、自分がどの特例を受けられるか知ることが重要
- 不動産売却で損をしないためには、相場を知っておき、事前知識を蓄えておく必要がある。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。