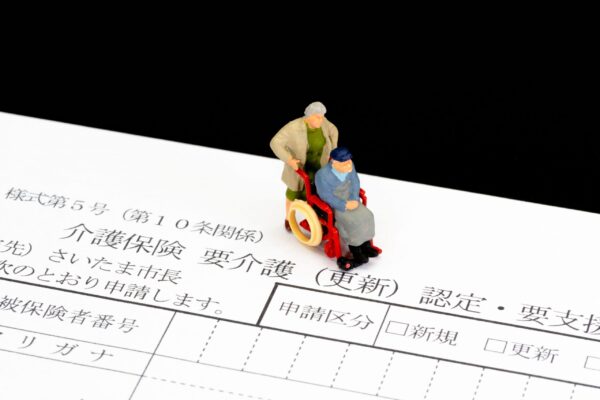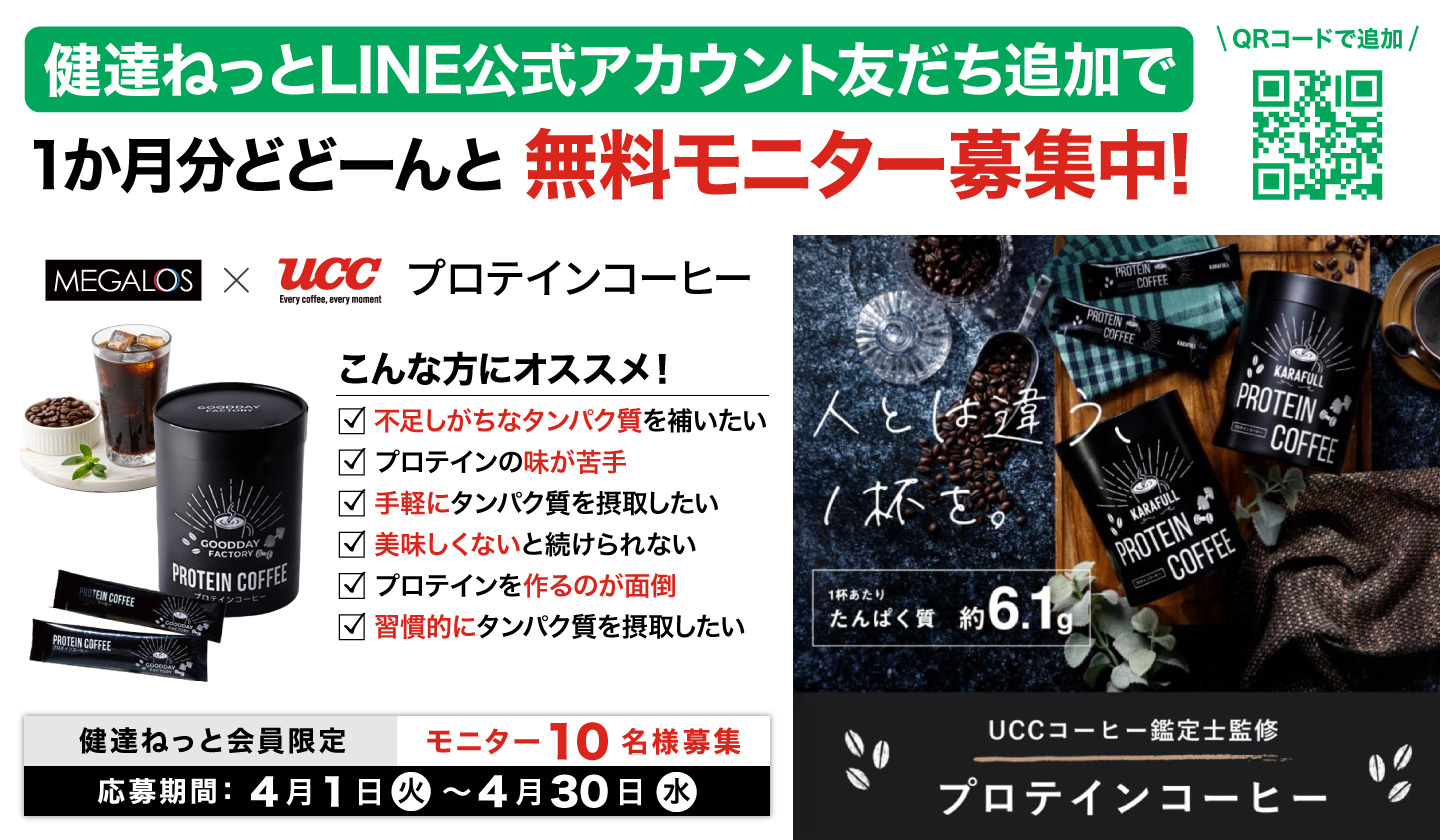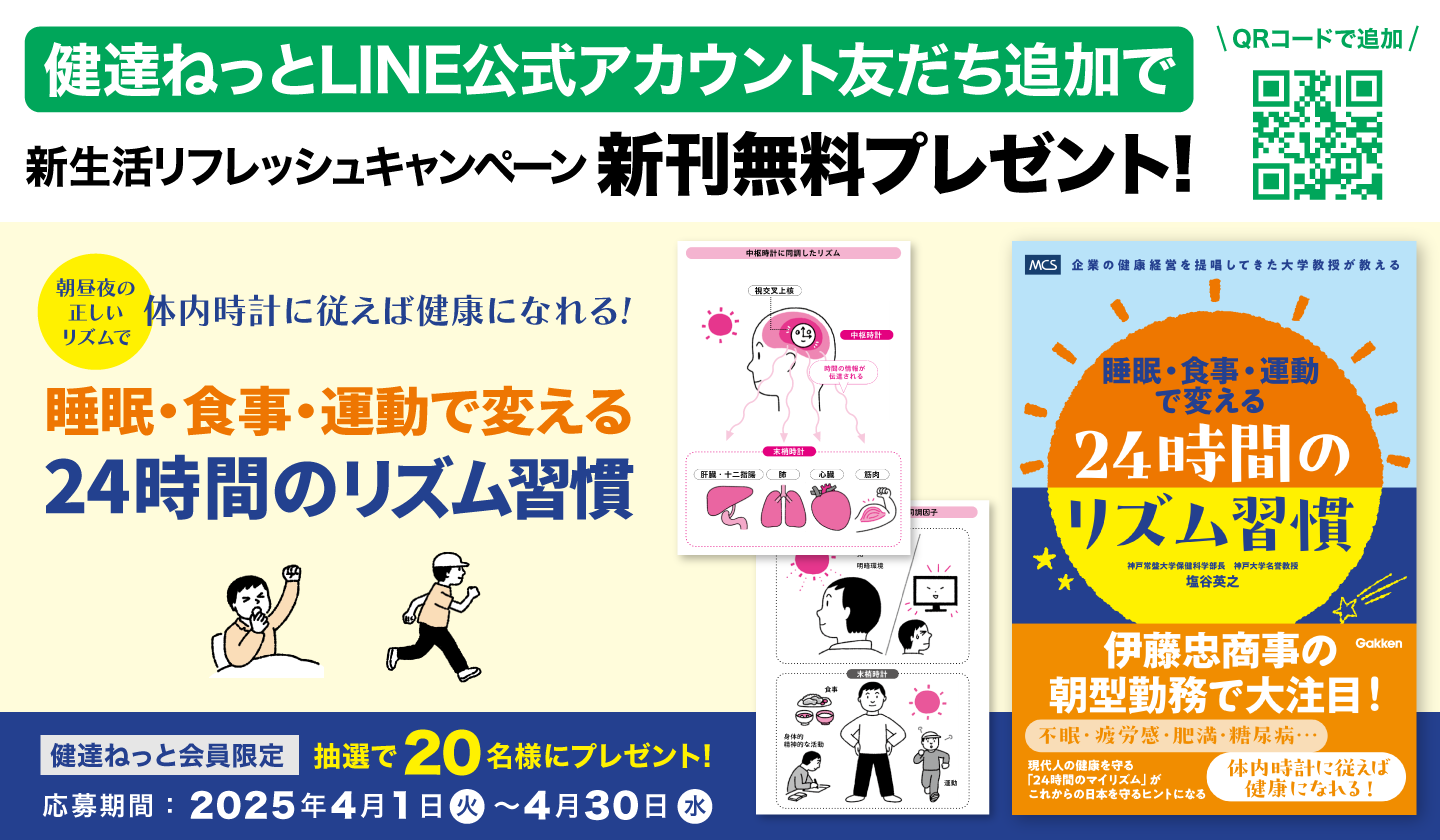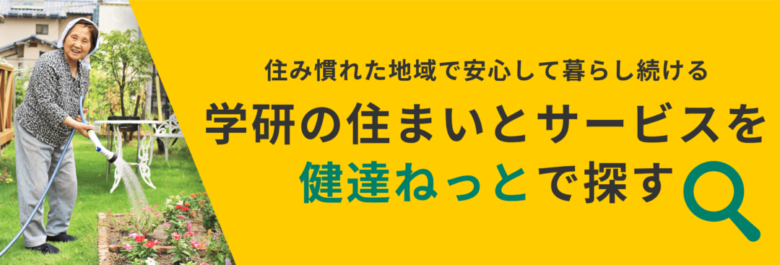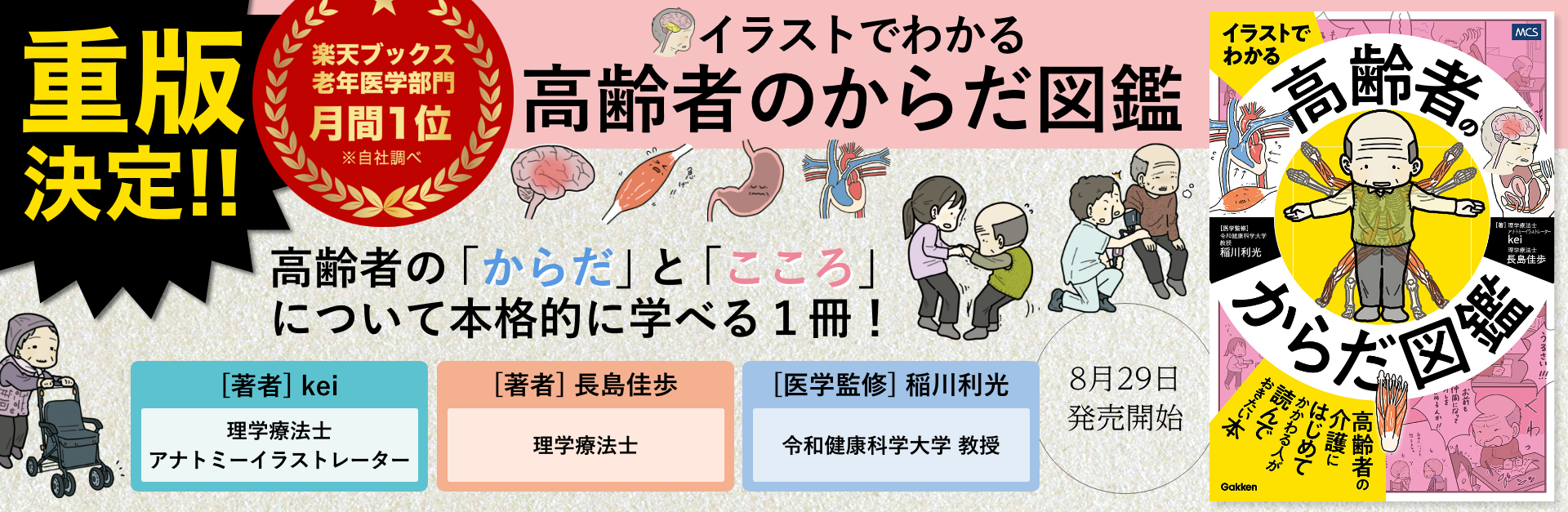「介護認定」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし実際に介護認定がどのようなものかを知らないという方も多いでしょう。
今回は認知症の方の介護認定について、以下の点を中心にご紹介します。
- 介護認定の受け方
- 要支援と要介護の違い
- 介護認定で受けられる支援内容
- 介護認定の度合いによる支援の違い
認知症の方の介護認定を受ける時のためにも、参考にしていただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
【フェルラブレインPLUS】|認知機能低下の予防に!
認知症をサプリで予防・改善したくありませんか。
フェルラブレインPLUSには、社会問題である認知症予防の効果が期待される成分「フェルラ酸」を150mg、さらに脳の働きを活性化させる栄養素としてホスファチジルセリンを180mg配合。
ご家族が年齢を重ね「認知症が気になる・・・」「最近忘れっぽくなった?」「認知症が怖い」という方は是非一度手に取って効果を実感してみてください。
スポンサーリンク
認知症の方が介護認定を受ける流れ

介護保険サービスを受けるためには、介護認定が必要になります。
介護認定について考える際、まずは介護認定を受けるための相談場所や条件などを知ることが重要です。
ここからは、介護認定を受けるためにはどこへ相談し、どんな基準があるのかをご説明します。
どこに行けばいい?
介護認定をされるために申請を行う場所は、認知症の方が住んでいる地区町村の役所窓口です。
役所窓口は「福祉課」になりますが、場所によっては「介護保険課」や「高齢者支援課」など名称が異なる場合があります。
認知症の方本人が行けない場合は、家族が代わりに行って申請手続きを行うことができます。
申請時の持ち物は以下の4点です。
- 介護認定の申請書
- 介護保険被保険者証、または健康保険の保険証(65歳以下の場合)
- マイナンバー
- 身分証明書
また、役所に行けない理由がある方は、「地域包括支援センター」でも申請を受け付けています。
地域包括支援センターでは、社会福祉法人や介護支援専門員など介護のプロが勤務しています。
悩みを相談をしやすく、親身になって話を聞いてもらえます。
基準について
介護認定の基準には、1次判定と2次判定があります。
1次判定の基準を以下に記載します。
身体機能
介護認定希望者が、生活する上で必要な基本動作をどのくらい行えるかを確認します。
調べる項目は身体の麻痺や関節の動き、視力や聴力などです。
生活機能
食事や排せつなどの日常生活に伴う行動がどれくらいできるかを中心に確認します。
認知機能
自分の生年月日や年齢、名前などを答えられるかを確認します。
精神や行動障害
過去1ヶ月を振り返り、社会生活の中で適切な行動ができていたかを確認します。
たとえば、感情が不安定になり大声を出すことがあったかなどを調べます。
社会生活への適応
買い物や料理などの社会生活を行う能力があるかを確認します。
過去14日間で受けた医療
医師の指示により、透析や中心静脈栄養などの特別な医療行為が行われたかを確認します。
また、基準には要介護認定等基準時間があります。
要介護認定等基準時間とは、介護に必要な時間を表したものです。
介護の必要性を判断するための重要な基準になります。
2次判定は1次判定の結果に主治医意見書と認定調査の特記事項を加えて行われます。
スポンサーリンク
要支援と要介護の違いについて

要介護以外にも、要支援という段階があります。
名前だけを聞くと、違いが分からないという方も多いでしょう。
ここからは、要支援と要介護の違いについてご紹介していきます。
要支援
要支援は、日常生活で必要な基本動作をほぼ自分で行うことができますが、多少の支援が必要な状態です。
要介護状態への悪化を予防することが目的となっています。
食事や入浴を問題なく行うことができても、掃除ができないといった具体的な支援が必要な状態です。
要介護
要介護は、日常生活で必要な基本動作を自分で行うことが困難であり、何らかの介護を必要とする状態です。
要介護は運動機能の低下だけではなく、思考力や理解力の低下もみられます。
したがって、入浴や排せつなどの基本的な行動に介護を要する状態です。
要介護認定調査はやり直しできるの?

要介護認定調査の結果に納得がいかないこともあります。
認知症の方の介護度が想定よりも低くなってしまうなど、納得がいかない場合はやり直しが可能です。
やり直しを求める際は、地域の市区町村の「介護保険課認定審査係」に行き不服申し立てを行うことができます。
要介護認定を受け取った翌日から60日以内に行う必要があるので、期限が過ぎる前に早めに行いましょう。
しかし、不服申し立てをしてから再度調査がやり直しになると、介護認定を受け取るまでに時間を要します。
そこで、要介護認定の区分変更申請を行うこともできます。
本来は介護認定者の状態に変化があったときに行うものですが、認定結果を不服とする場合でも行うことができます。
区分変更申請を行うときは、地域包括支援センターに相談しましょう。
【フェルラブレインPLUS】|認知機能低下の予防に!
認知症をサプリで予防・改善したくありませんか。
フェルラブレインPLUSには、社会問題である認知症予防の効果が期待される成分「フェルラ酸」を150mg、さらに脳の働きを活性化させる栄養素としてホスファチジルセリンを180mg配合。
ご家族が年齢を重ね「認知症が気になる・・・」「最近忘れっぽくなった?」「認知症が怖い」という方は是非一度手に取って効果を実感してみてください。
要介護認定によってどんなサービスが受けられるの?
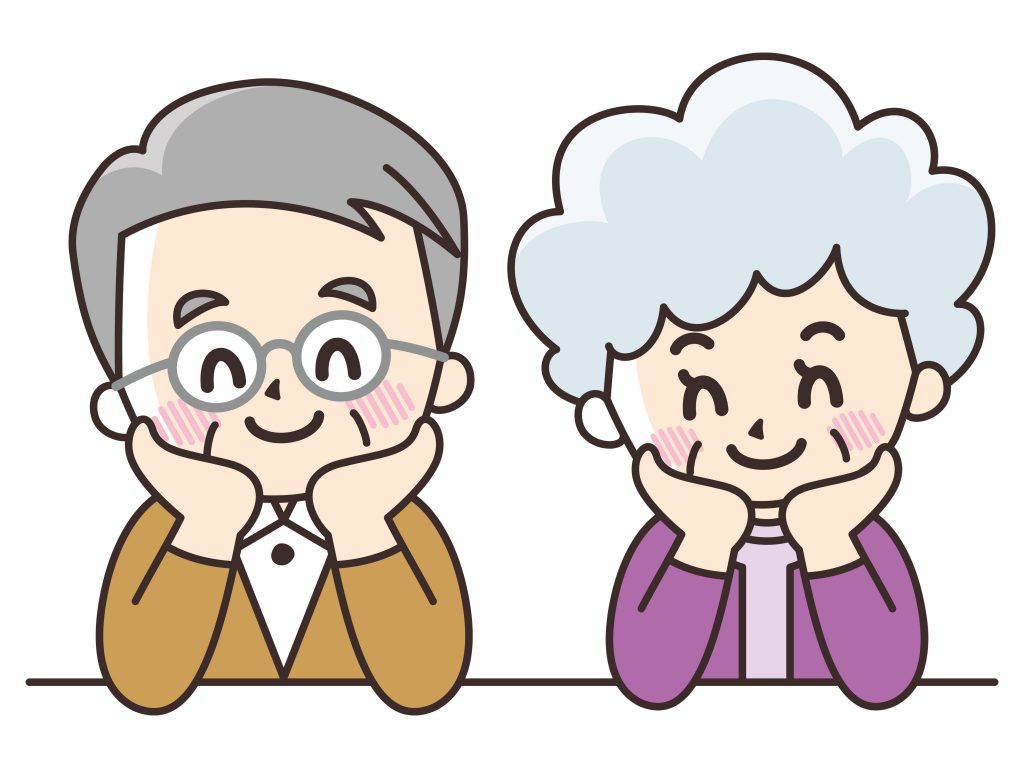
介護認定をされた場合、どんな支援を受けられるかが1番の疑問点でしょう。
要介護認定によって受けられる支援を以下にまとめます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- デイサービスやデイケア
- 福祉用具貸与
認知症介護認定レベル

ここでは、要介護に応じた認定の目安と、どの程度介護が必要か(介護レベルの特徴)についてご紹介します。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 介護レベルの特徴 |
要支援1 | 日常生活の動作は自分で行える。 介助や支援の必要性はほとんどない。 | 食事・排泄・入浴など日常生活における身の回りの動作(セルフケア)は自分でできる。 立つ・座る動作や買い物・掃除などの家事に一部支援が必要。 |
要支援2 | 要支援1よりも、介助や支援が必要な部分が出てくる。 状態の維持・改善を目的に介護予防サービスの利用が有効。 心身の状態は安定しており、日常生活における認知機能の低下はあってもわずか。 | 食事・排泄は自分で行える。入浴に一部介助が必要。(背中を洗う、浴槽をまたぐなど) 立っている時や歩くときに支えが必要なことがある。 要支援1よりも状態の維持にかかわるサポートが必要。 家事は介助を要することがふえる。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行に不安定さが見られる。 以下の1もしくは2が該当。 1.認知機能や思考・感情等の障害あり。 介護予防サービスの利用に関する適切な理解が難しい。意思決定や判断力が低下している状態。(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上が目安) 2.短期間で心身の状態の変化が予測され、要介護度が重度になるおそれがある。(概ね6か月程度以内に要介護状態等の再評価が必要) | 排泄時ズボンの上げ下ろしや、入浴時着替え等に介助を要する。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では難しいことがふえる。 日常生活全般において部分的に介助が必要となる。 | 排泄・入浴は介助を要す部分が多い。 着替えは見守りがあれば可能。 身体の衰えもあらわれ、身の回りの動きにおいて全般的に見守りなどが必要になる。 介護用ベッドや車椅子を必要とする場合が多い。 身の回りの管理(金銭管理・服薬管理・日常の意思決定など)が難しくなる。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行は自力では難しい。 日常生活全般に多くの介助が必要。 日常生活に影響を及ぼす認知症の症状がある。 | 排泄・入浴・着替えのほとんどすべてに介助が必要。 転倒や転落の危険性が高くなる。 認知症の症状になんらかの対応が必要になり、目を話せないことが増える。 特別養護老人ホームへの入居が可能になる。 |
要介護4 | 立ち上がりや歩行はほとんどできない。 日常生活全般に全介助に近いくらいの介護が必要。 理解力・判断力の低下が著しく、コミュニケーションの難しさも目立つ。 | 排泄・入浴・着替え・食事に全て介助が必要。 認知症の症状により多くの対応が必要。 自力で起きる、座る、立つなどの動作が難しくなり、転倒・転落の危険性がさらに高くなる。 |
要介護5 | 寝たきりになり、日常生活全般において全介助となる場合が多い。 コミュニケーションがまったくとれないこともあり。 | 排泄・入浴・着替え・食事などすべてにおいて、全介助が必要。 ベッドで寝返りや起き上がりも困難なため、床ずれ予防が必要。 (定期的に体位を変える介助が必要になる) 話しかけに返答がなかったり、介護に抵抗したり、簡単なコミュニケーションの面でも支障が大きい さまざまな介護サービスの組み合わせで本人・家族の安心と安全を確保する必要性が高い。 |
表に示した状態に必ず一致するとは限らないため、注意が必要です。
例えば認知症の症状が著しく進んでおり
- 徘徊
- 暴力
などの行動が見られても運動機能にほとんど問題ない場合もあります。
介護に関する手間(要介護認定基準時間)を総合的に判断して認定されることを知っておくとよいでしょう。
介護の度合いで受けられる支援が違う?

要介護認定は、要介護度1から5まであります。
要介護の度合いで受けられる支援や、給付される金額にも違いがあります。
ここからは、要介護度合い別の支援内容や給付金をご紹介します。
要介護1
給付金
1万6千円
サービス
- 週3回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 月4回のデイサービス
要介護2
給付金
1万9千円
サービス
- 週3回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 月4回のショートステイ
要介護3
給付金
2万7千円
サービス
- 週3回の訪問介護
- 週1回の訪問看護
- 月7回のショートステイ
- ベッドや徘徊センサーなどの介護用具レンタル
要介護4
給付金
3万円
サービス
- 週6回の訪問介護
- 週2回の訪問看護
- 週1回の訪問入浴
- ベッドや車いすなどの介護用具レンタル
要介護5
給付金
3万6千円
サービス
- 週6回の訪問介護
- 週2回の訪問看護
- 週1回の訪問入浴
- ベッドやエアマットなどの介護用具レンタル
※サービス内容は、要介護認定者の状態や希望によって組み合わせが異なります。
認知症要介護者の自立度について

認知症で要介護認定された方の自立度は、要介護の度合いによっても違いがあります。
ここからは、認知症要介護者の自立度をご紹介していきます。
できること
食事や入浴、排せつなどの日常生活で必要な基本行動が自分の力ででき、在宅生活が可能な方がいます。
また、家族や周囲の支えがあれば基本的なことを問題なく行える方もいます。
できないこと
要介護度が高いほど、できないことが多くなります。
たとえば、着替えや食事が1人でできない、内服管理ができないなどです。
また、意思疎通が困難な方や外出してから1人で自宅に帰れない方もいます。
スポンサーリンク
介護認定で調査員と家族の認識の差を減らすために

調査員と家族の認識に差が出てしまうと、納得できる結果に繋がる可能性があります。
そうなると、不服申し立てや区分変更申請を行うことになり、介護認定を受けるまでに時間がかかってしまいます。
ここからは、調査員と家族の認識の差を減らすために必要なことをご紹介します。
家族が調査に同席する
認知症の方が自分の状態を上手く伝えられず、できないことを「できる」と言ってしまう可能性があります。
また、認知症の方本人と実際に介護をしている家族の間に認識のズレがある場合も珍しくありません。
その結果調査員と家族の認識の差が生じ、望む結果が受け取れなくなります。
なので、調査には認知症の方本人だけではなく、家族も一緒に同席しましょう。
普段の状態をメモする
認知症の方の普段の様子や家族の介護の様子、困っていることや悩みなどを事前にメモしておくと調査時に役立ちます。
調査では色々な質問をされる可能性を考え、何を質問されても答えられるようにしておく必要があります。
きちんと答えられなければ、正確な状態を知ってもらうことができません。
大切なことを伝え忘れてしまったり、忘れたことを後から思い出して後悔する場合もあります。
どんなに些細なことも、しっかりとメモを取っておきましょう。
答えるのが難しければ、調査員にメモを見せることも1つの方法です。
体は元気だけど認知症かも?
体は元気でも認知症だった場合、
- 健脚のため遠くまで行って帰ってこられなくなる
- 近隣トラブルによりけがをさせてしまう
などの危険性が考えられます。
体が元気であるゆえに起こる問題であり、介護者を困らせる原因になるでしょう。
介護認定において、体は元気でも認知症の精神行動障害が目立つ場合は、従来よりも高い介護度で認定されることがあります。
つまり、認知症の症状に対してより多くの支援が必要だといえます。
よって、介護サービスを利用しご本人や周囲が安心・安全に生活するためには介護認定を受けることは有効といえます。
周囲の人は
- 徘徊することを予測しGPSの使用を検討する
- 一人暮らしの方には、防犯カメラや外出時に作動するセンサーを導入する
- 近隣の方にも体は元気でも認知症の症状があることを知らせておく
など対策をとることで、トラブルを未然に防げる可能性があります。
命に関わる問題が生じる前に、早めの対策をとりましょう。
医師に意見書を書いてもらう
介護認定の調査では、調査結果と医師の意見書に基づいて行われます。
そのため、医師に意見書を書いてもらう必要があります。
意見書を書いてもらうためには、認知症の方の状態を医師にしっかり伝えることが大切です。
認知症の方本人の意見ももちろん大事ですが、家族の意見も細かくきっちり伝えましょう。
スポンサーリンク
認知症と介護認定のまとめ

今回は、認知症の介護認定についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 地域の市区町村の役所か地域包括支援センターで申請を行う
- 調査結果に納得がいかない場合は、不服申し立てや区分変更申請を行うことができる
- 要介護認定を受けると、訪問介護やデイサービスなど様々な支援を受けることができる
- 介護認定では、介護の度合いによって受けるサービスと給付金が異なる
- 家族が調査に同席したり、事前にメモを取るなどして調査員と家族の間に認識の差が生まれないよう準備が必要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります