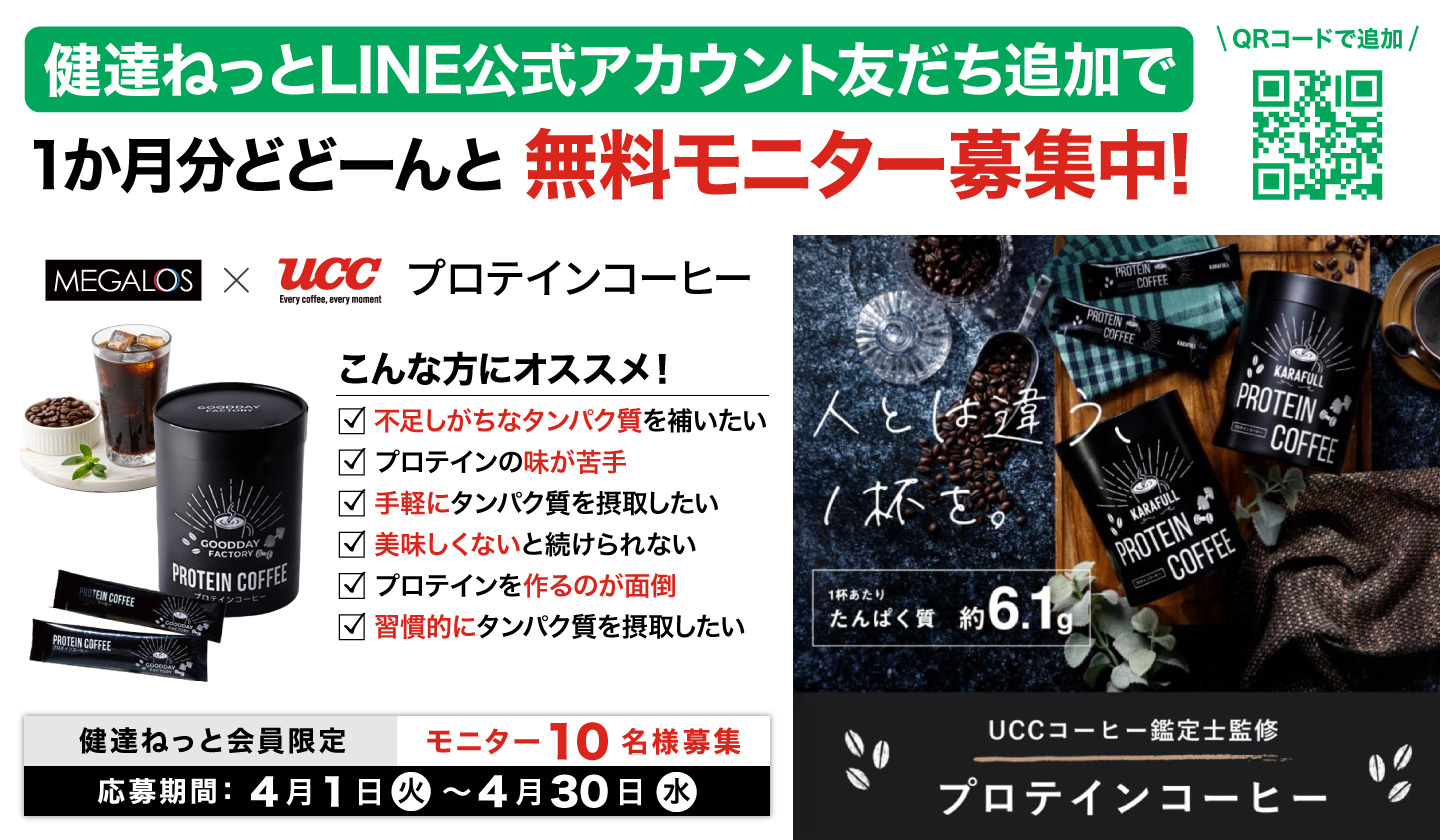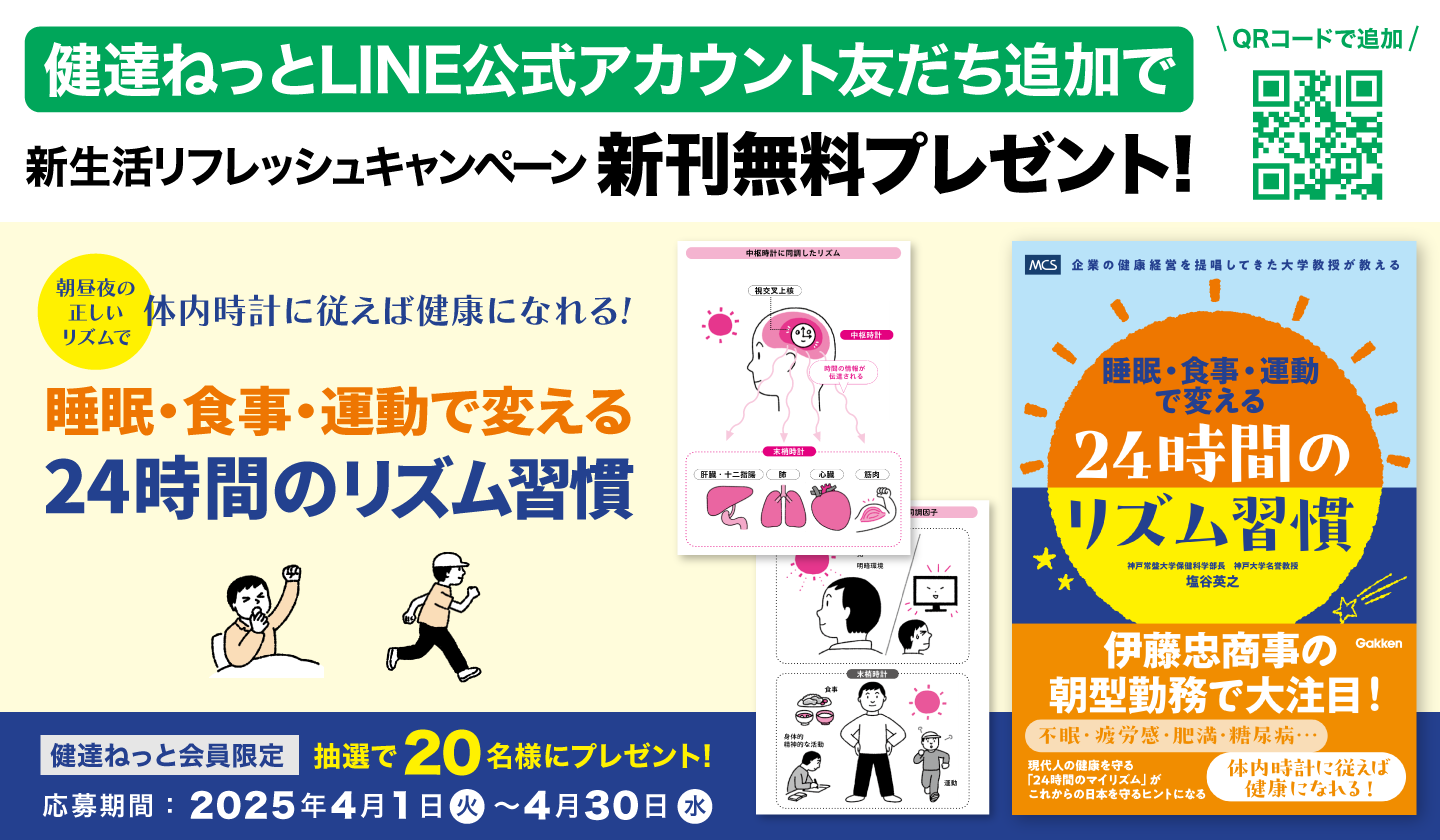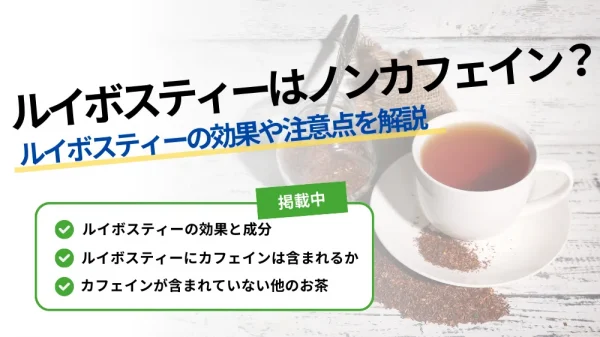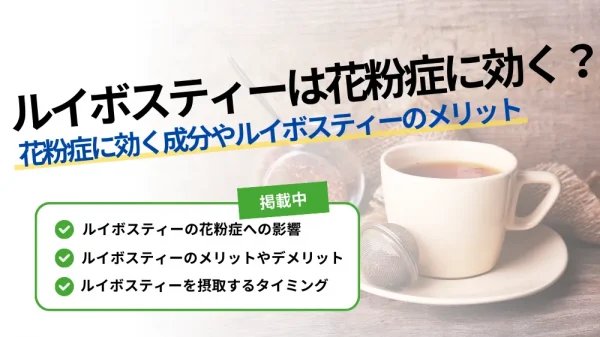くも膜下出血を予防するには、生活習慣に注意する必要があります。
くも膜下出血の予防に、手術以外の方法は即効性がありません。
そもそも、くも膜下出血とはどういうものなのでしょうか?
くも膜下出血を予防するにはどうすればよいのでしょうか?
本記事ではくも膜下出血の予防について以下の点を中心にご紹介します。
- くも膜下出血について
- くも膜下出血を予防する方法
- くも膜下出血の再発を予防する方法
くも膜下出血の予防について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
くも膜下出血とは

くも膜下出血とは、脳梗塞・脳出血と並ぶ、脳卒中の分類の1つです。
脳内のくも膜と軟膜の間にある、くも膜下腔に出血のある状態を指します。
脳の動脈にできたこぶ(脳動脈瘤)の破裂によって発症することが多いです。
ほかに、頭部外傷や脳動静脈奇形の破裂などが契機となる場合があります。
脳動脈瘤が破裂して出血した場合、突然激しい頭痛がおこることが多いです。
男性に比べて女性に多く発症し、40代以降からリスクが高くなります。
スポンサーリンク
くも膜下出血の原因

くも膜下出血の原因として、脳動脈瘤の破裂が8割以上になります。
脳動脈瘤が破裂しやすい要因が、くも膜下出血の主な原因になります。
高血圧
正常の場合に比べて、高血圧のくも膜下出血による死亡リスクは、
男性は2.97倍、女性は2.70倍、高くなります。
血圧が高いと、動脈瘤への圧力も高く、破裂のリスクも高くなると考えられています。
出典:東京メディカルクリニック「くも膜下出血について」
喫煙
たばこの煙にはさまざまな有害な物質が含まれています。
煙の成分には、血管を狭めたり、動脈硬化を促進したりする作用があります。
たばこ喫煙とくも膜下出血の関係は強く、たばこを吸う方は、全く吸わない方に比べて、
男性で3.6倍、女性で2.7倍、くも膜下出血を発症しやすいことが示されました。
1日に喫煙の本数が増えるほど、くも膜下出血の発症リスクが段階的に増えます。
出典:国立がん研究センター「男女別、喫煙と脳卒中病型別発症との関係について」
飲酒
アルコールは血管運動中枢に作用し、血管を拡張して熱の放散を促進させます。
そして、腎臓での抗利尿ホルモンを抑制し、水分の再吸収を阻害する作用があります。
さらに、アルコール代謝の過程でも水分が消費されます。
そのため、体は脱水状態になり、血液がドロドロになって血圧が上昇します。
低栄養
低栄養の状態も、くも膜下出血の発生の原因になります。
低栄養になると以下の状態になりやすくなります。
- 低アルブミン血症(低たんぱく)
- 低HDLコレステロール血症(善玉コレステロールが少ない)
低アルブミンの状態が長く続くと血管がもろくなり、脳出血などのリスクが上昇します。
善玉コレステロールが少ないと、血管が詰まったり動脈硬化になりやすくなります。
脳梗塞というと、突然倒れて意識を失うイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、それは脳梗塞の症状のほんの一部なのです。脳梗塞の原因や症状についてよく理解することで、もしもの時に適切な対応ができるようにしましょう。また、[…]
くも膜下出血を予防するには?

くも膜下出血を予防するには、日常の生活習慣から注意する必要があります。
- 食事の栄養バランス
- 喫煙・飲酒・水分補給
- 適度な運動習慣
など、予防には即効性は無いため、継続して続けることが大切です。
食事
くも膜下出血を予防するには、高血圧を予防することが重要になります。
高血圧を予防するには、食事のときに以下のコントロールが必要です
- 塩分摂取量を調整(日本高血圧学会では1日6g未満を推奨)
- カロリーの調整(内臓脂肪は高血圧や血栓につながる)
- コレステロールの調整(動脈硬化の原因になる)
出典:日本高血圧学会「高血圧の予防のためにも食塩制限を」
以下に具体的なレシピを紹介します。
豆腐と鶏ささみのおろし煮
材料(2人分)
- 木綿豆腐:200g
- ささみ:2本(120g)
- ほうれん草:100g
- 大根:200g
- A:だし汁:300ml
- A:塩:少々
- A:しょうゆ:少々
作り方
- ①ほうれん草は色よくゆでて手早く冷まし、水気をしぼって4cmの長さに切る
- ②大根はすりおろして水気を切る
- ③ささみは筋を引いて、ひと口大のそぎ切りにする
- ④鍋にAを合わせて中火にかけ、木綿豆腐を大きめのひと口大に割って加える
- ⑤煮立ったら大根おろしを加えてふたをし、4~5分煮て火を通す
- ⑥ほうれん草を入れ、再び煮立ったら大根おろしを広げてのせ、さらに煮る
ブリとカブのユズ煮
材料(2人分)
- ブリ:2切れ(200g)
- カブ:4個
- ユズ:1/2個
- コンブ:4cm角×2枚
- 水:400ml
- 塩:少々
作り方
- ①鍋にコンブと分量の水を合わせ、20分ほどおく
- ②ブリは半分に切る。ユズはくし形に4等分に切る。
- ③カブの葉は茎を2〜3cm残して切り落とし、3cmの長さに切る。
- ④①の鍋を中火にかけ、カブ、ユズを加えてふたをして15分ほど煮る
- ⑤ブリを入れてさらに10分煮る。
- ⑥カブがやわらかくなったら、塩、カブの葉を加えてひと煮する。
生活習慣(喫煙、アルコール、水分)
くも膜下出血を予防するためには、たばこを吸わないようにすることが重要です。
アルコールは1日平均20g以下を目安に、週2日は休肝日にすると依存も予防できます。
飲酒の回数が少なくても、大量に飲むことで体を傷めたりします。
女性や高齢者、すぐに顔などが赤くなる方は、飲酒量をさらに控えましょう。
出典:厚生労働省「飲酒のガイドライン」
水分補給は多すぎても少なすぎても、体に悪影響があります。
水分の過剰摂取は心臓の負担になり、心不全を引き起こす場合があります。
しかし、ほとんどの日本人は、水分の摂取量が不足傾向にあります。
血圧が高めの場合などは、コップの水をあと2杯多く飲むことが大切です。
運動
脳卒中予防は軽度な運動を一定時間継続し、新陳代謝などを促す有酸素運動が効果的です。
有酸素運動により血行がよくなると、血管内皮細胞から一酸化窒素が分泌されます。
分泌された一酸化窒素は血管の内皮細胞に作用し、血管を柔らかくして血管を拡張します。
そのため、高血圧や動脈硬化の予防に効果的といわれています。
有酸素運動の代表的なものとして、
- ウォーキング
- ジョギング
- サイクリング
- 水泳
- 体操
などがあり、1日20分以上行うことが動脈硬化の予防に効果的とされています。
予防薬
生活習慣の改善でも高血圧が持続する場合は、血圧を下げる降圧薬の使用が必要です。
降圧薬にはさまざまな種類があり、それぞれの症状により選択される薬は異なります。
主に使用される降圧薬は以下のものになります。
- Ca拮抗薬(比較的安全に使用でき、日本で最も多く使用)
- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(慢性腎臓病など)
- アンジオテンシン変換酵素阻害薬(誤嚥性肺炎など)
- 利尿薬(高齢者など)
- α遮断薬(脂質代謝異常、前立腺肥大など)
- β遮断薬(頻脈、狭心症など)
上記の薬は自己判断で中止せず、継続的に使用し続ける必要があります。
くも膜下出血「再発」の予防方法は?
くも膜下出血の再発予防は、基本的には以下の外科手術になります。
- 脳を直接触る開頭クリッピング術
- カテーテルを入れる血管内手術
外科手術
開頭クリッピング術とは、クリップで血液を遮断し脳動脈瘤の破裂を防ぐ方法です。
基本的に皮膚を切開して頭蓋骨の一部を外して行う開頭手術で行います。
動脈瘤の根元にチタンなどのクリップを挟み、動脈瘤への血流を遮断します。
動脈瘤が挟める場所にある場合に行い、直接動脈瘤を確認してクリップを挟みます。
全身麻酔をかけて頭を開くため、体への負担が大きいです。
血管内手術
手術の方法は、動脈からカテーテルを使った方法で行います。
脳動脈瘤内にマイクロカテーテルという非常に細く柔らかい管を入れます。
さらに、脳動脈瘤内にプラチナ製のコイルを入れ内側から閉塞します。
コイルで閉塞しきれない場合は、ステントアシストを併用して閉塞します。
ステントアシストとは、コイルが血管内に抜け出すのを防ぐ措置のことです。
開頭クリッピング術に比べると、脳を触らないため、体への負担は少ないです。
くも膜下出血を予防のための検査

くも膜下出血を予防するには、脳動脈瘤を発見して治療することが重要です。
以下に脳動脈瘤を確認する検査を紹介します。
脳ドック
くも膜下出血のリスクは、脳ドックの検査で調べられます。
くも膜下出血のリスクとなる未破裂脳動脈瘤を発見するには頭部MRA検査が有用です。
頭部MRA検査は、血管の細部を確認するのに適した検査方法です。
脳梗塞は、同じ脳ドックの頭部MRI検査で発見できます。
未破裂脳動脈瘤を発見し治療することで、くも膜下出血を予防できます。
脳血管造影・頭部CT
脳血管造影検査は脳の血管に造影剤を注入し、X線撮影により血管の確認をする検査です。
脳血管造影検査では細い血管の状態まで、詳細に確認することができます。
頭部CTは、X線を使って頭の中の断層写真を撮影する検査です。
丸い筒の中に頭を入れ、X線を頭の周りを一周するように照射します。
データを計算して重ね合わせると、頭部を輪切りにしたような画像になります。
脳ドックで動脈瘤の疑いがある場合には、上記の検査が続けて行われることがあります。
くも膜下出血の罹患者(年間の死亡者数)

厚生労働省発表によると2020年の1年間で、約11万人が脳血管疾患で死亡しています。
脳血管疾患は全死因の4位で全体の7.5%を占めています。
そのうち、くも膜下出血は1万1,416人(男性4,114人、女性7,302名)となります。
くも膜下出血で死亡するケースは多く、日常的に身の回りに起こり得る疾患です。
栄養バランスのよい食事や適度な運動で、くも膜下出血の予防が重要です。
脳ドックを受けることで、動脈瘤を早期発見・治療することで、予防につながります。
出典:厚生労働省「令和2年 (2020)人口動態統計(確定数)の概況(第6表、第7表)」
くも膜下出血の予防のまとめ

今回は、くも膜下出血の予防についてお伝えしてきました。
くも膜下出血の予防の要点をまとめると以下の通りです。
- くも膜下出血とはくも膜下腔に出血がある状態を指す
- くも膜下出血を予防するには、生活習慣を整えることが重要
- くも膜下出血の再発を予防するには、基本的に手術を行う
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。