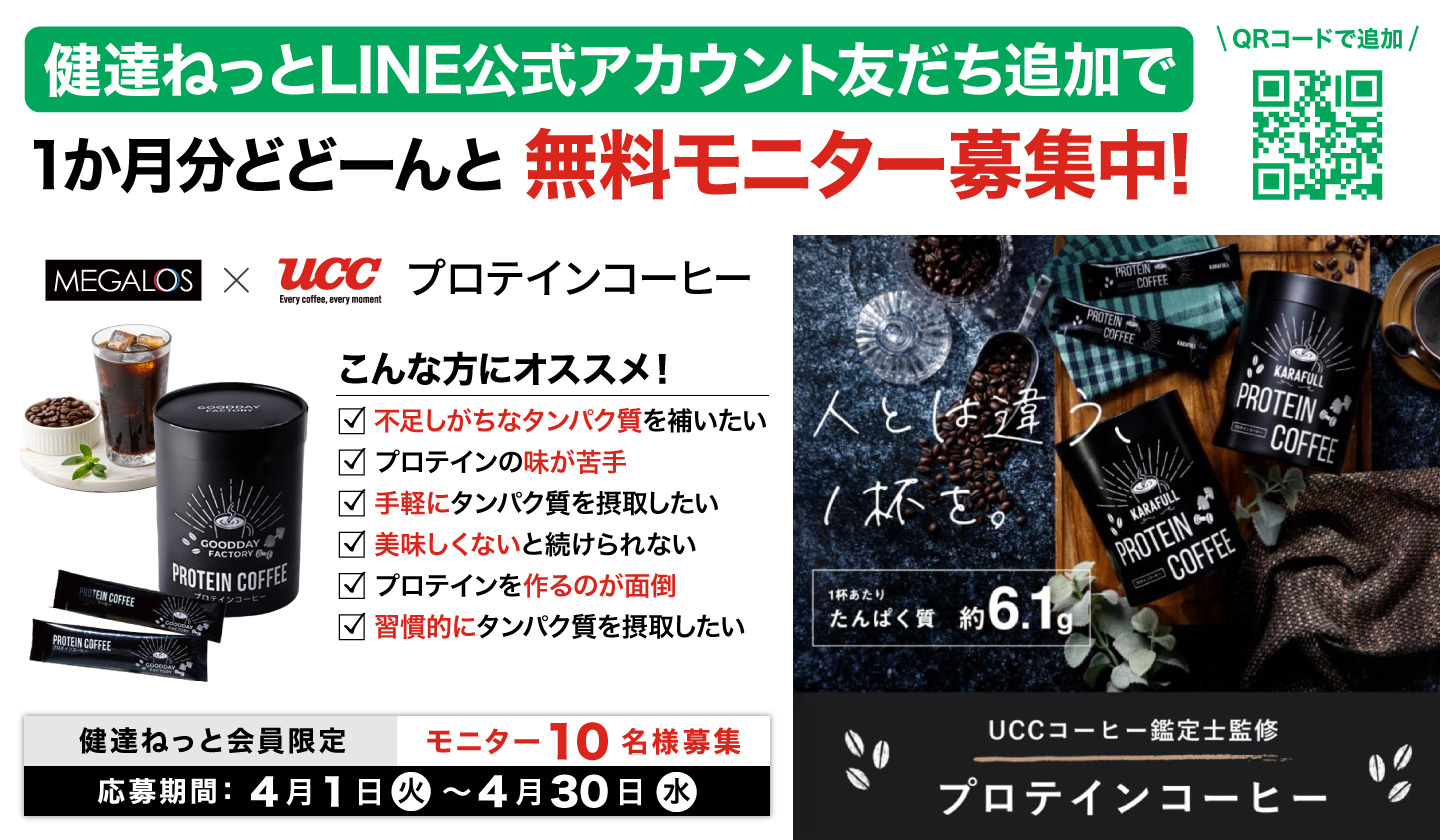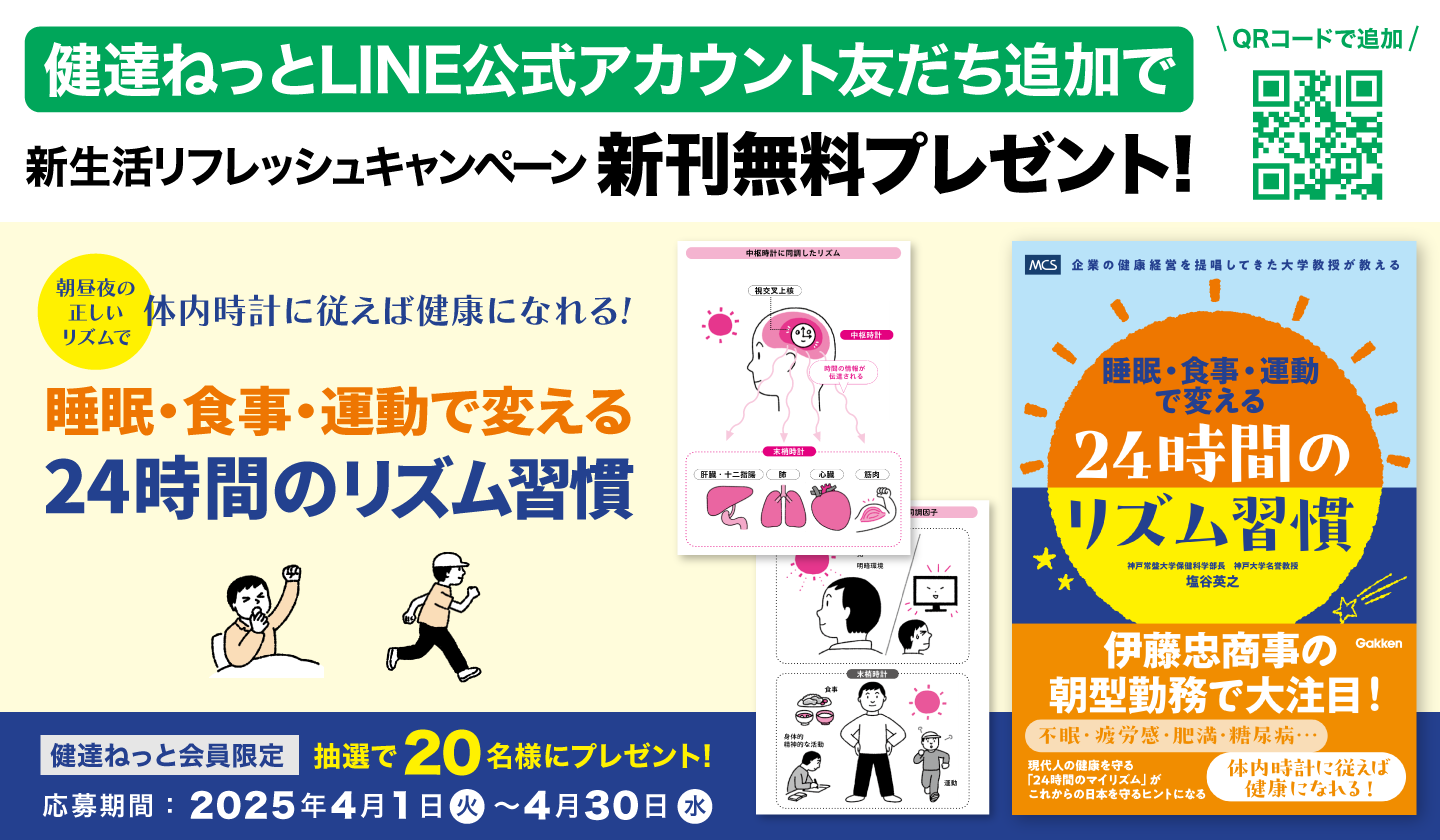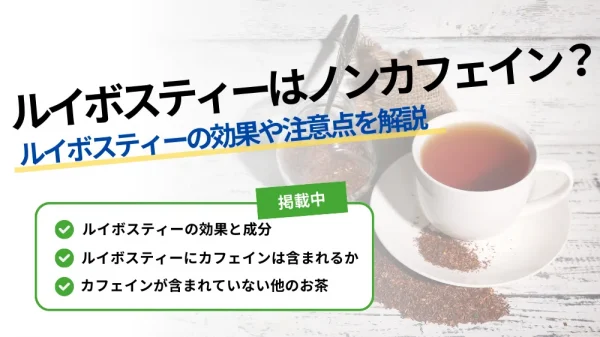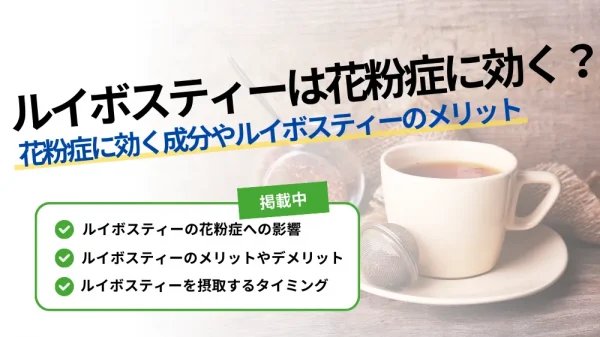不整脈とは、脈が正常よりも速くなったり、遅くなったりする状態のことです。
不整脈が原因で、心不全や脳梗塞の原因になることもあります。
不整脈の検査はどのようにするのでしょうか?
また、不整脈の治療方法には何があるのでしょうか?
本記事では、不整脈の検査について以下の点を中心にご紹介します。
- 不整脈の検査方法について
- 不整脈の検査を受けたほうがよい症状とは
- 不整脈の治療方法とは
不整脈の検査について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
不整脈とは

不整脈とは、脈が極端に速くなったり、正常より遅くなったりする状態のことです。
脈が1分間に50回以下の場合は徐脈性不整脈、100回以上の場合は頻脈性不整脈といいます。
また、脈が飛ぶように感じる症状は、期外収縮です。
心臓は、全身に血液を回すポンプのような働きをします。
ポンプを動かしているのは、電気刺激です。
心臓の右心房にある洞結節という部分が興奮し、電気刺激が心筋へと伝わっていきます。
心臓の興奮が正常に伝わらない状態が、不整脈です。
健康な方でも不整脈が続く場合は、心不全や脳梗塞を起こす可能性があります。
そのため、不整脈の検査をして原因を調べることが大切です。
スポンサーリンク
不整脈の検査は何科?

不整脈の症状がある方は、まず循環器内科を受診するか、かかりつけ医に相談しましょう。
かかりつけ医に相談し、専門医療機関への受診が必要か判断してもらうのがおすすめです。
専門医療機関では、詳しい不整脈の検査をしています。
不整脈の検査が必要かどうか判断してもらうためにも、循環器内科やかかりつけ医に相談しましょう。
脈が乱れたり心臓がドキドキする場合、不整脈が起こっている可能性があります。不整脈は心臓病だけでなく、ストレスなどによっても引き起こされます。そもそも不整脈とはどのようなものでしょうか?なぜストレスが不整脈の原因となるのでしょ[…]
不整脈の検査方法

不整脈の検査方法には、以下のものがあります。
- 心電図検査
- 胸部X線
- 血液検査
- ホルター心電図
- 運動負荷心電図
- 心臓超音波検査
それぞれ具体的にご紹介します。
心電図検査
心電図検査は、短時間で不整脈の有無を調べられます。
一般的に広く普及している検査方法です。
通常、人間ドックや健康診断で行われる心電図検査は、12誘導心電図検査といわれるものです。
12誘導心電図検査は安静時に行い、手首と足首に専用器具をつけます。
さらに、前胸部の6か所に電気信号を認識するための吸盤をつけて検査します。
胸部X線
胸部X線は、肺の様子を確認するために行う検査です。
不整脈の検査では、胸郭に対する心陰影の大きさを確認します。
また、心不全などのときに、胸に水が溜まっていないかなども調べられます。
血液検査
血液検査は、心不全マーカーや甲状腺ホルモンの数値を確認できます。
不整脈にはさまざまな原因があり、心不全や甲状腺ホルモンの異常が原因の場合もあります。
ホルター心電図
ホルター心電図は、携帯型心電図記録装置を使用して、24時間の心電図を記録する検査です。
24時間の心電図を記録することで、不整脈や狭心症の発作を捉えられます。
一般的に人間ドックや健康診断で行う心電図検査では、心臓の状態を正確に記録できない場合があります。
そのため、患者の生活に合わせて1日分の心電図を記録し、詳しく心臓の状態を確認することが必要です。
運動負荷心電図
運動負荷心電図は、トレッドミルや階段昇降などの運動負荷をかけながら記録する検査です。
安静にしているときは、不整脈の症状が見られないことがあります。
逆に安静にしているときに不整脈の症状があらわれ、運動していると改善することがあります。
そのため、検査室内で運動負荷をかけながら、不整脈の症状を確かめることが必要です。
心臓超音波検査
心臓超音波検査では、心臓の収縮力、弁や筋肉の動き、心臓の部屋の大きさなどを調べます。
心臓病の診断や重症度を診断するためには、心臓弁や心臓の筋肉の詳しい診断が必要です。
心臓超音波検査をすることで、不整脈の診断に必要な心臓の病気の有無が確かめられます。
不整脈の検査を受けたほうがよい症状

不整脈の検査を受けたほうがよい症状には、以下のものがあります。
- 強い動悸やめまい
- 安静時の胸痛や息切れ
- 立ちくらみや意識障害
- 心臓の鼓動が速いまたは遅い
- 左胸、歯、首が痛い
気になる症状がある場合は、早期発見することで重症化するのを防げます。
また、運動や階段の上り下りが急に息苦しくなる場合も、不整脈で起こりやすい症状です。
さらに、足のむくみなども心臓の問題で起こりやすい症状といえます。
気になる症状がある場合は、循環器内科を受診することで深刻な病気の予防につながります。
不整脈のセルフチェックをする方法

不整脈をセルフチェックする方法は、以下の2通りがあります。
- 症状からチェックする
- 脈拍をチェックする
それぞれ解説します。
症状からチェックする
症状からチェックする方法について、以下の表にまとめています。
| 安静時でも心拍が目立ちドキドキすることがある | 脈が乱れたような感じがする |
| 日常生活で息切れ、だるさ、疲れやすさが目立つ | 頻繁にめまいがする |
| 目の前が暗くなり失神をしたことがある | 階段を昇る際や速足で歩くと息切れする |
| アルコールやコーヒーをよく飲む | 過剰なストレスや過労が溜まっている |
| 熟眠できないなどの睡眠障害を抱えている |
心臓には電気信号の通り道があります。
電気信号の通り道を通り、脈拍が一定の間隔で伝わることで規則正しく心臓が動いています。
通常の心臓の拍動は、1分間に約60〜100回のペースです。
しかし、異常な電気刺激が生じることで、脈が速くなったり遅くなったり、飛んだりします。
心臓が拍動するリズムが不規則になると、脈の乱れが起こり不整脈の症状があらわれます。
表にあらわしている症状を確認することで、不整脈かどうか、セルフチェックしましょう。
脈拍をチェックする
脈拍とチェックする方法は以下の通りです。
- 手のひらを上向にする
- 親指側の手首をまげてしわができる位置に人差し指、中指、薬指の指先を当てる
- 指先を少し立て、15秒ほどかけて脈をとる
- 不規則に感じる場合、1~2分ほど図り続け、リズムが乱れている場合は不整脈を疑う
一定のリズムで脈がとれていれば、ひとまず正常と判断できます。
しかし、脈が飛んだり、不規則になったりする場合は、病院で相談してください。
また、定期的に脈をとっていると、まれに不整脈の症状が見られることがあります。
そのため、定期的に脈をとることは正確な診断に役立ちます。
不整脈の治療方法

不整脈の治療方法には、以下のものがあります。
- 薬物治療
- 薬以外の治療
それぞれ具体的にご紹介します。
薬物治療
不整脈の薬物治療では、頻脈性不整脈に対して、抗不整脈薬を服用します。
薬物治療が行われるのは、そこまで症状が重くない場合です。
また期外収縮では、薬物治療はあまり行われません。
しかし、症状が強い場合は薬物治療が行われることもあります。
薬以外の治療
薬以外の治療には、以下のものがあります。
- ペースメーカー
- 植え込み型除細動器(ICD)
- カテーテルアブレーション
それぞれ解説します。
ペースメーカー
ペースメーカーは、徐脈性不整脈の治療で使用します。
ペースメーカーの適用は、洞結節に異常がある場合です。
洞結節からの興奮が生じない、もしくは興奮が起こりにくい状態などがあります。
また、心室に興奮が伝わらないなどのときにも適用されます。
植込み型ペースメーカーは性能がよく、小型で軽量化されていて、電池も長持ちです。
ペースメーカーの使用後も、今までとほとんど変わらない生活を送れます。
しかし、ペースメーカーを長く使用するために、使用制限や注意が必要な電気機器もあります。
さらに、近寄ってはいけない場所などもあり、使用には注意が必要です。
植え込み型除細動器(ICD)
植え込み型除細動器(ICD)が使用されるのは、重症の不整脈治療のときです。
心室頻拍、心室細動などの治療で使われ、心臓の動きを常に監視し、頻脈が見られたときに治療します。
ICDには、導線を心臓の中に留置するものと、胸骨の上に留置するもの(S-ICD)の2種類があります。
S-ICDは導線が心臓や血管に触れないため、合併症の発症率が低い方法です。
また、ICDを使用する際は、近づかない方がよい場所や、注意が必要な電気機器などがあります。
カテーテルアブレーション
カテーテルアブレーションは、局所麻酔で直径2mmほどのカテーテルを心臓内に挿入します。
不整脈の原因となる異常な部分に、高周波の電流を流して焼灼します。
外科手術に比べると、患者への負担は少ない治療方法です。
カテーテルアブレーションの治療中は、熱さや軽度の痛みを感じる場合もあります。
痛みが強く感じるときは、スタッフへ伝えましょう。
不整脈による死亡数と死亡率

厚生労働省による、不整脈の死亡数と死亡率を調査した結果があります。
令和2年の不整脈による死亡数は、3万986人で、死亡率は25.1%です。
死亡総数に占める割合は2.3%で、さまざまな死因がある中で、低くない数値です。
不整脈は、突然死の原因にもなることがあります。
また、不整脈により血栓ができやすくなる可能性もあります。
不整脈を早期発見するためにも、セルフチェックすることが大切です。
少しでも不整脈の症状が見られる場合は、医療機関を受診しましょう。
出典:厚生労働省【令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況】(P33参照)
スポンサーリンク
不整脈の検査のまとめ

ここまで不整脈の検査についてお伝えしてきました。
不整脈の検査の要点をまとめると以下の通りです。
- 不整脈の検査方法は、心電図検査・胸部X線検査・血液検査などがある
- 検査が必要な症状には、強い動悸やめまい、安静時の胸痛や息切れなどがある
- 治療方法は、薬物治療・ペースメーカー・植え込み型除細動器などがある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。