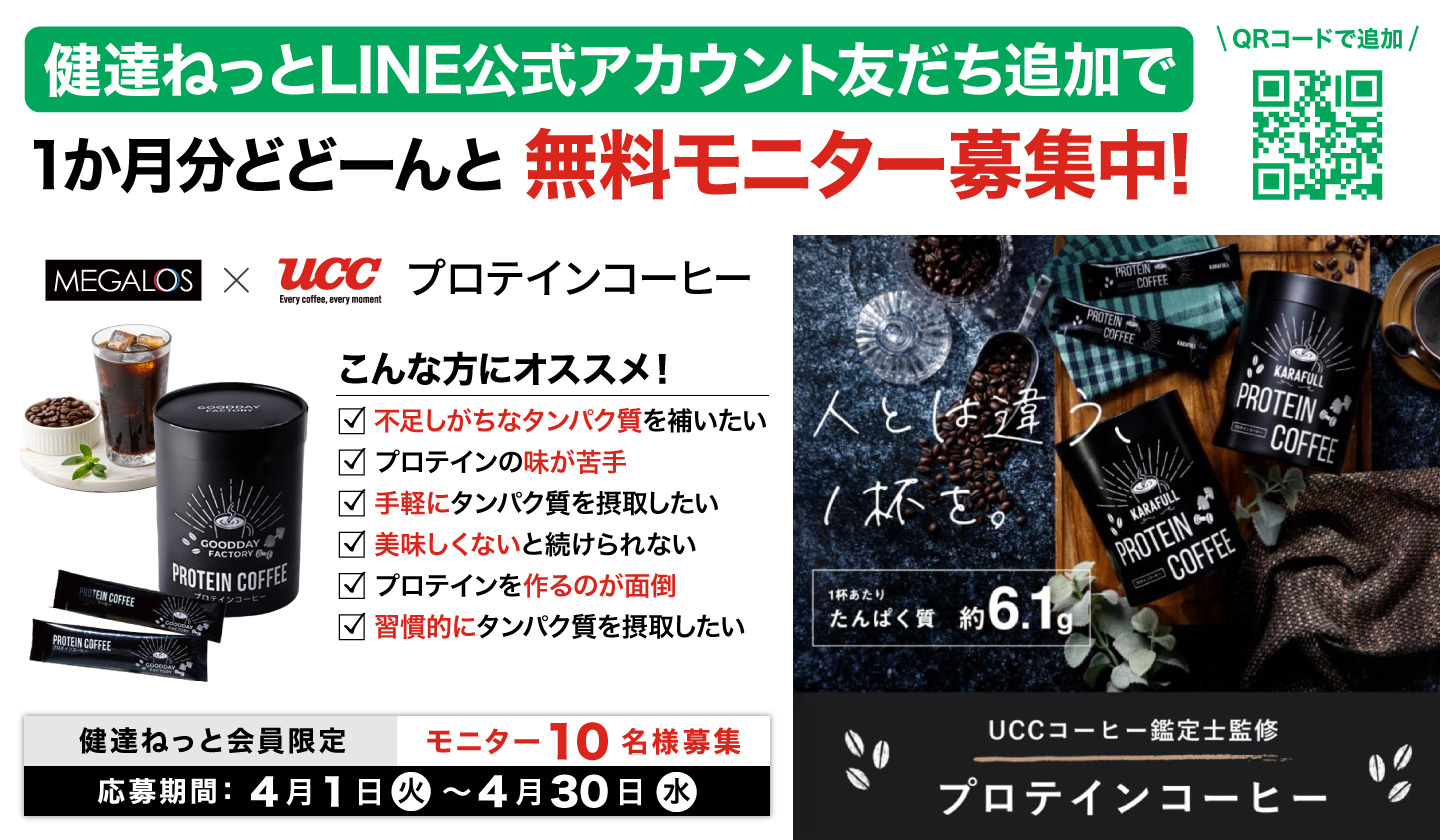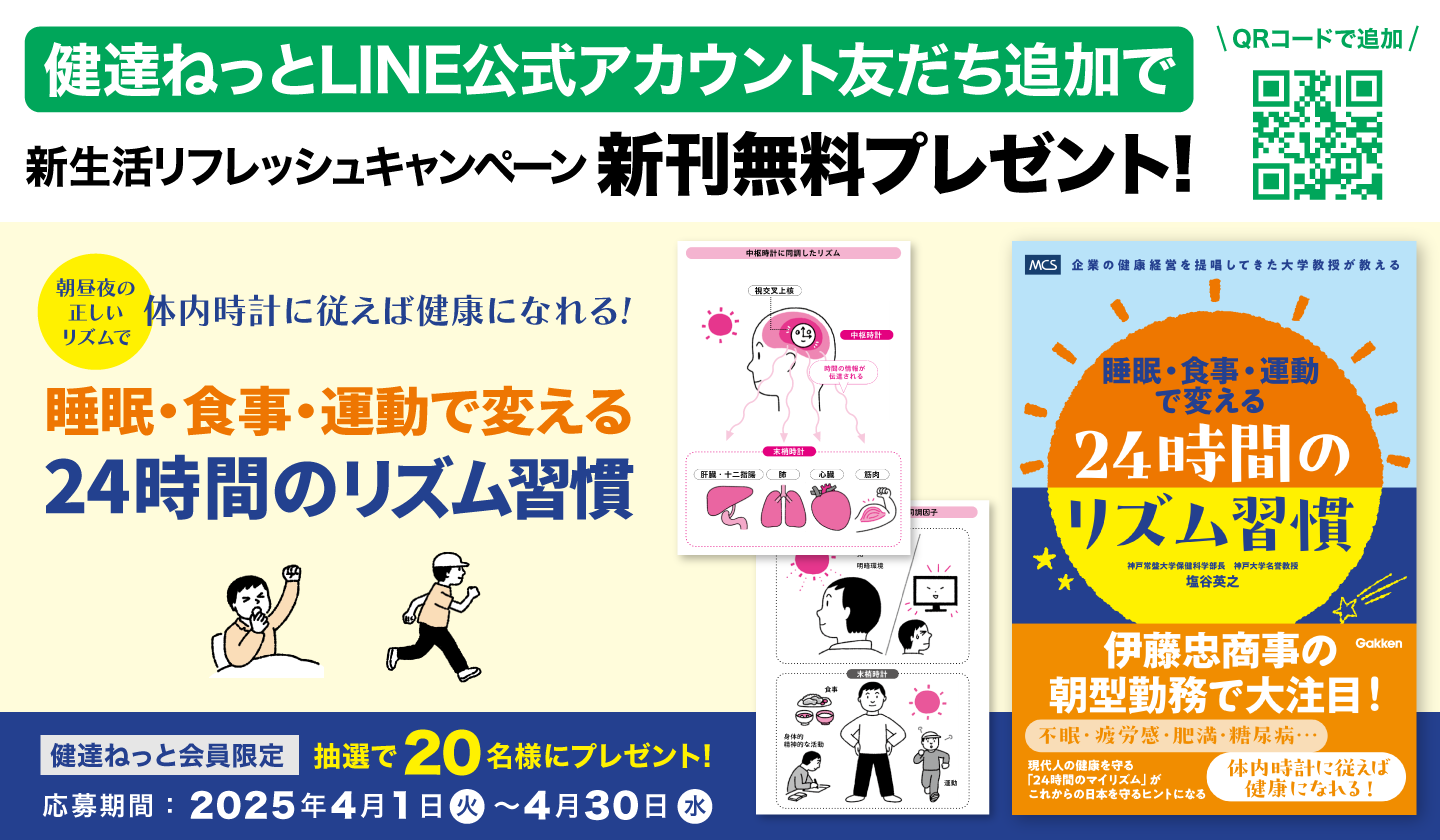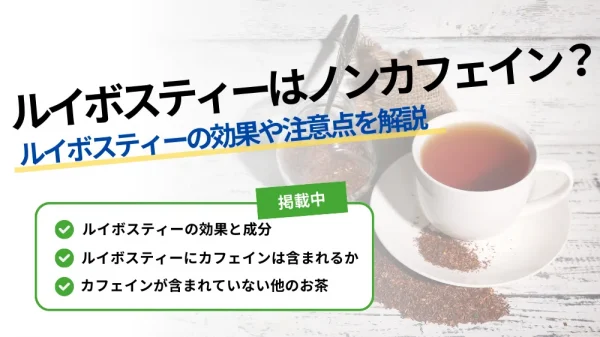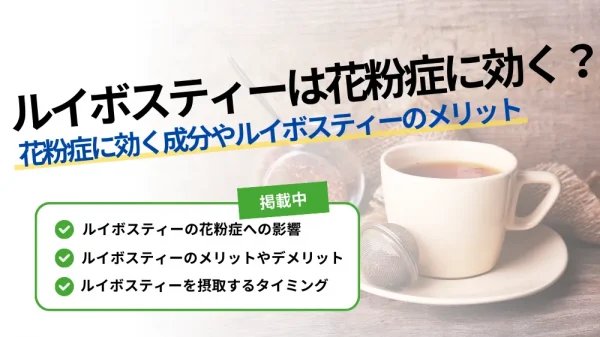健康診断では、検便を行うことが一般的です。
健康診断の検便では、何が分かるのでしょうか。
また、検便の結果はどのように受け止めればよいのでしょうか。
本記事では、健康診断の検便について以下の点を中心にご紹介します。
- 健康診断の検便で分かることとは
- 健康診断の検便の結果の見方
- 健康診断の検便で陽性になった場合は
健康診断の検便について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
健康診断とは

健康診断とは、身体測定や各種検査を行うことで、個人の健康の尺度を把握することです。
主な目的は、生活習慣病を始めとしたさまざまな病気の早期発見および治療や病気の予防です。
健康診断では、さまざまな検査を行います。
健康診断の中には、レントゲン・バリウム検査・検便などがあります。
出典:厚生労働省【健診 | e-ヘルスネット(厚生労働省)】
スポンサーリンク
健康診断の検便でわかること

多くの場合、健康診断では検便が行われます。
健康診断の検便では、2回分の便を採取することが一般的です。
健康診断の検便には、専用のキットを用います。
専用キットは、キャップ付きの細い棒のような形状をしています。
便を採取するときは、棒の先の小さな溝に便をすくい取るようにします。
ところで、健康診断の検便ではなにが分かるのでしょうか。
ここからは、検便の目的や検便で分かる病気についてご紹介します。
検便をする意味
健康診断の検便は「便潜血検査」とも呼ばれています。
便潜血検査とは、名前の通り便に血が混じっていないかを目的として行われます。
より具体的には、検便とは消化管(大腸)からの出血を調べるための検査です。
検便によってわかる病気
健康診断の検便で分かる病気は次の通りです。
- 大腸がん
- 潰瘍性大腸炎
- 胃がん
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
代表的な病気は大腸がんです。
検便では進行性の大腸がんの約80〜90%が分かると考えられています。
早期の大腸がんの発見率は約50%です。
便に血が混じっていれば、必ずしも大腸がんというわけではありません。
出血は、大腸の良性のポリープで起こっている可能性もあるためです。
反対に、健康診断の検便で血が検出されなかったからといって、大腸がんではないという断定もできません。
健康診断の検便の結果の見方

健康診断の検便の結果の見方をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
陰性
陰性とは、便から血液が検出されなかったということです。
陰性は(-)と表示されることが一般的です。
陰性の場合は、消化管からの出血はありません。
つまり大腸がんのリスクは低いと判断できます。
ただし、大腸がんなどの病気のリスクはゼロではありません。
がんがある場合でも、常に出血しているとは限らないためです。
また、初期の大腸がんは出血が起こらないことも多いです。
半陽性
半陽性とは、2回分の検便のうち1回が陽性だった状態です。
結果は、(-)(+)などと表示されることが一般的です。
1回でも陽性の場合は、消化器官からの出血が疑われます。
従って、半陽性の場合は精密検査に進むことが多いです。
陽性
陽性は、便から血が検出されたという状態です。
(+)などと表示されることが一般的です。
便から血が検出されたということは、消化管から出血が起こっている可能性が高い状態です。
そのため、検便で陽性の結果が出た方は、精密検査を勧められることがほとんどです。
ただし、陽性だったからといって必ずしも大腸がんなどの深刻な病気とは限りません。
たとえば良性の大腸ポリープや、排便の際に肛門が切れて出血した可能性もあります。
いずれにしろ、検便の結果だけでは出血の原因は特定できません。
原因を特定するためにも、医療機関での精密検査を受けましょう。
健康診断の検便で異常がでた場合

健康診断の検便で陽性になった場合は、医療機関での精密検査を受けましょう。
今日・明日中に受診する必要はありませんが、できる限り早いタイミングでの受診がおすすめです。
大腸がんでの出血は、病状がある程度進行してから起こることが多いためです。
つまり、便に血が混じっている方は、すでに大腸がんが進んでいる可能性があるのです。
病気の早期治療につなげるためにも、検便で陽性だった場合は、できる限り早めに検査を受けることが大切です。
検便が陽性だった場合に受ける検査としては、大腸カメラが一般的です。
ただし、どのような検査を行うかは、医療機関などによって異なります。
健康診断の検便をとるタイミング

検便用として提出する便は、次のようなタイミングで採取してください。
- 細菌検査:提出日の3日以内
- ノロウイルス検査:提出日の2日以内
長くとも、提出日の1週間以内に採取した便を提出する必要があります。
1週間以上経過すると、便の成分などが変質して正しい診断結果が出にくくなります。
また、便の変質を防ぐために、採取した便は直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。
便秘などで普段から便が出にくい方は、検便にあわせて便秘の解消に努めてください。
たとえば水分・牛乳・食物繊維などを多めに摂ると、便秘が解消されやすくなります。
どうしても便が出ない場合は、便秘薬を飲んでもかまいません。
生理中や痔の場合の健康診断の検便

生理中や痔のときに検便すると、経血や肛門からの出血が便に混じりやすくなります。
つまり検便の結果が陽性となるため、再検査が行われることが一般的です。
生理中の方や痔の方の検便の対応は、医療機関などによって異なります。
たとえば生理中でもOKという場合もあれば、生理後の採取を求められる場合もあります。
もし生理・痔などで検便を行ってもよいか気になるときは、あらかじめ医療機関に問い合わせるのも1つの方法です。
健康診断の検便で早期発見できれば治癒も可能
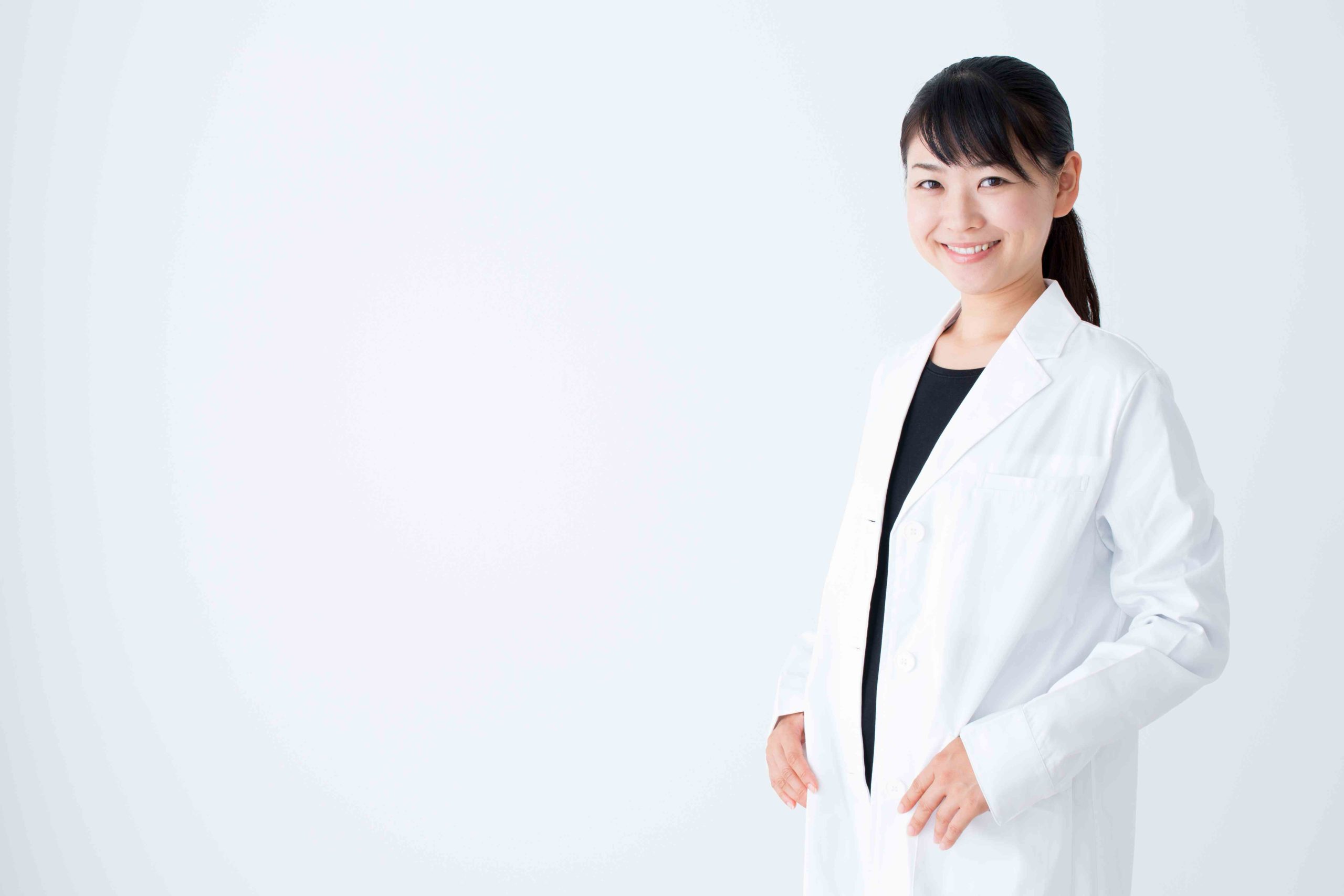
健康診断の検便で大腸がんが発見された場合は、治癒できる可能性が高いです。
理由は健康診断の検便で見つかる大腸がんは、ステージがごく初期であることが多いためです。
大腸がんの自覚症状は、ある程度病状が進行してからあらわれることが一般的です。
個人差はありますが、がんは早期に治療を開始するほど完治の可能性が高まります。
自覚症状がない初期の大腸がんが検便で見つかれば、早期の治療が可能になります。
早期のがん発見につなげるためにも、健康診断の検便は定期的に受けることが大切です。
スポンサーリンク
健康診断の検便のまとめ

ここまで健康診断の検便についてお伝えしてきました。
健康診断の検便の要点を以下にまとめます。
- 健康診断の検便で分かることは消化管からの出血で、たとえば大腸がんや胃潰瘍の発見に役立つ
- 健康診断の検便の結果の見方は、陰性ならば異常なし・陽性ならば消化器系の病気が疑われる
- 健康診断の検便で陽性になった場合は、出血の原因を特定するためにも病院での精密検査が必要
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。