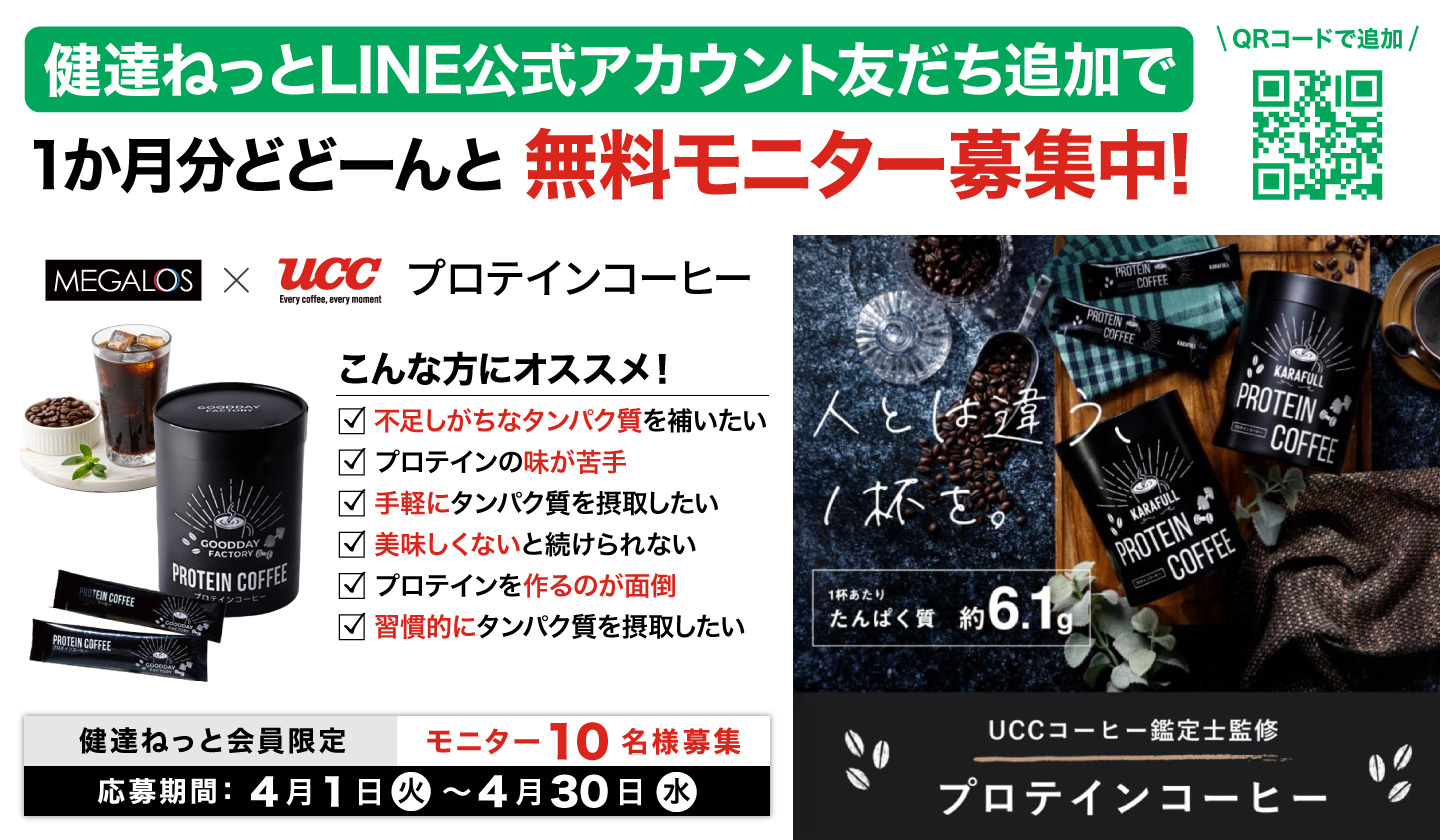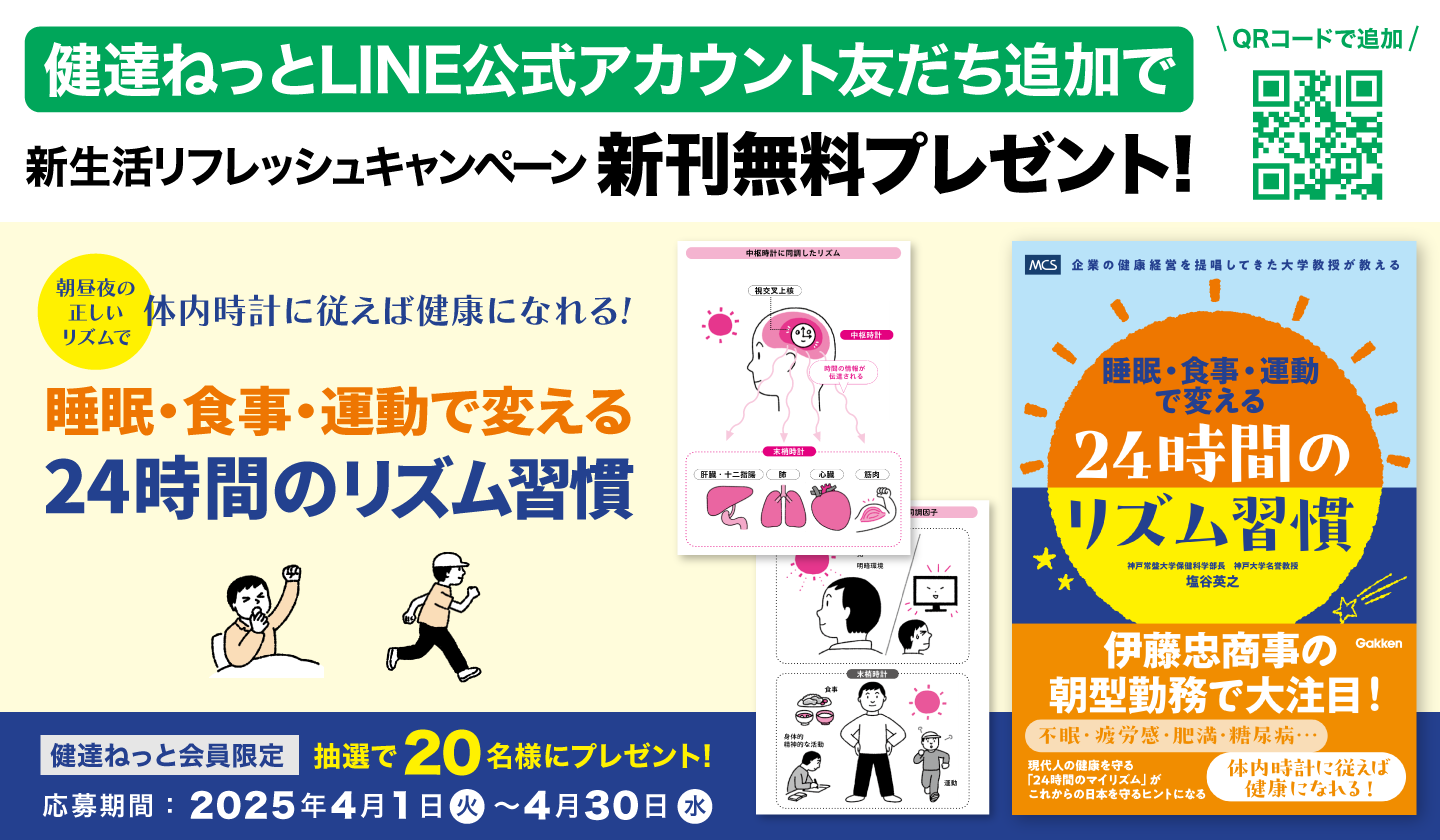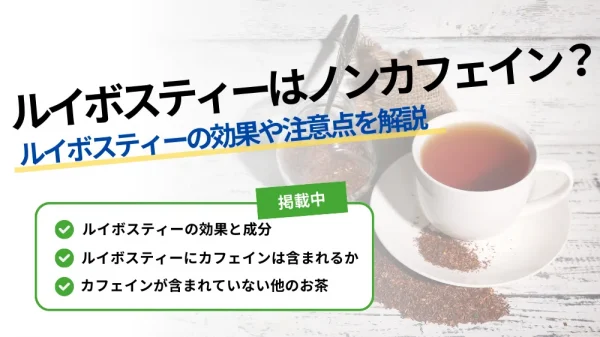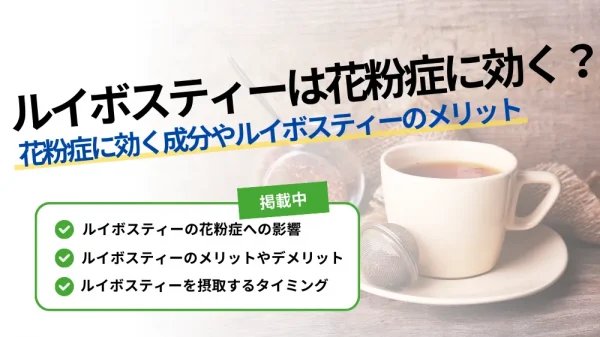「健康診断は時間がかかるもの…」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。
健康診断の所要時間が不明だと、健診後の予定を立てる際にも支障が出ます。
一体健康診断には、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。
本記事では、健康診断の時間について以下の点を中心にご紹介します。
- 健康診断の所要時間
- 健康診断の検査はしなくてもよいのか
- 健康診断の検査時間を短くできるのか
健康診断の時間について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
健康診断とは

健康診断とは、身体測定や各種検査によって個人の健康の尺度を把握することです。
主な目的は、生活習慣病を始めとする種々の病気の早期発見・治療です。
病気そのものを予防する目的もあります。
健康診断では、血液検査・尿検査・検便などの様々な検査などを行います。
出典:厚生労働省【健診 | e-ヘルスネット(厚生労働省)】
スポンサーリンク
健康診断の所要時間
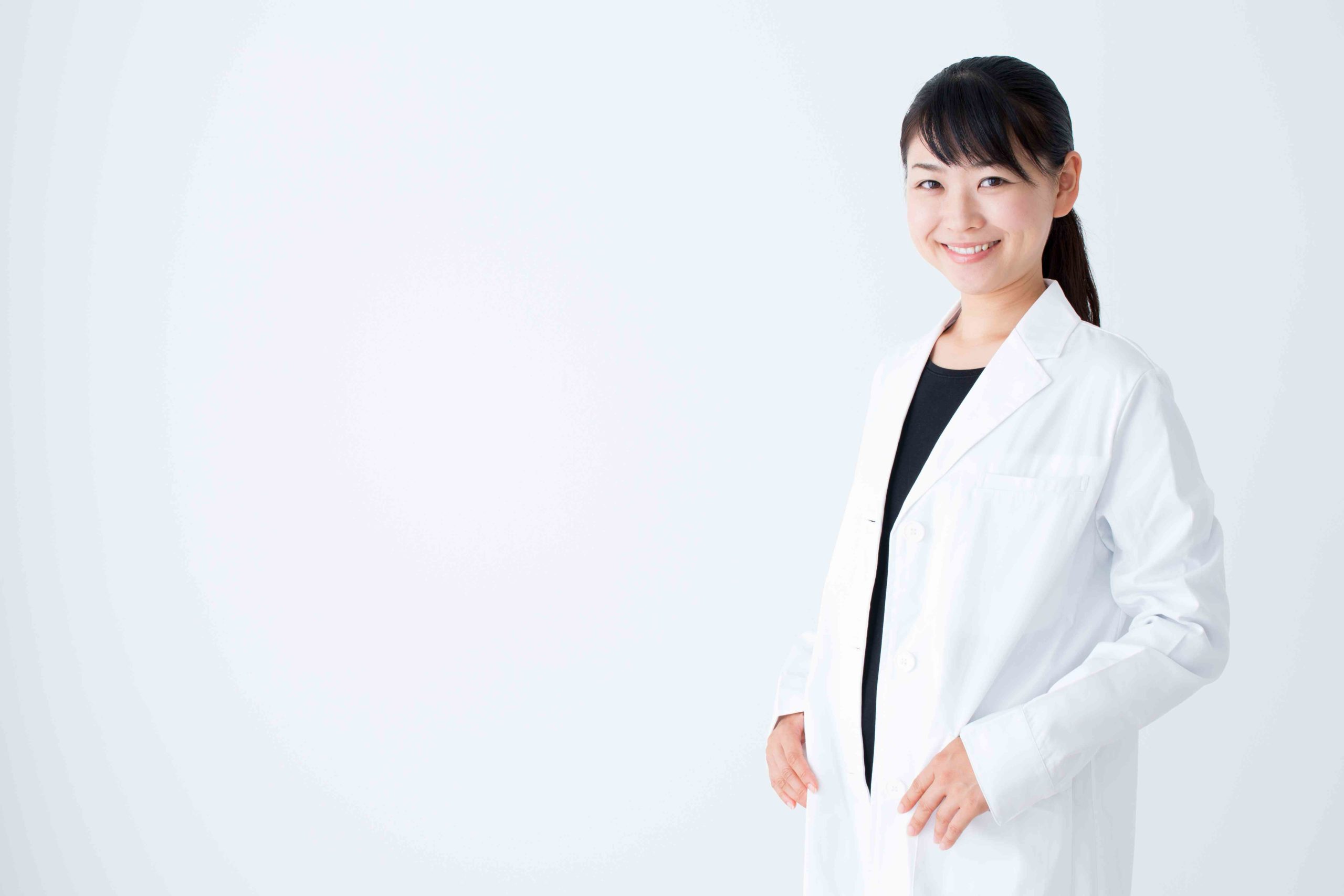
健康診断の所要時間の相場をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
所要時間の平均
健康診断にかかる時間は、健康診断の種類などによって異なります。
代表的な健康診断の種類と、おおまかな時間の目安は次の通りです。
- 定期健康診断:1時間~1時間半
- 人間ドック:2時間
- 生活習慣病予防検診:2時間
検査項目が多いほど、健康診断にかかる時間も長くなります。
たとえば定期健康診断に比べると、人間ドックや生活習慣病予防検診は項目数が多めです。
そのため、所要時間も長くなる傾向があります。
また、検査項目は35歳前後でも異なります。
35歳以上の方は、35歳以下の方に比べると検査項目が多いため、所要時間も多くかかります。
健康診断の時間は、当日の検査機関の混雑具合によっても多少変動します。
受診人数が多い場合は、待ち時間がプラスされるため、全体の所要時間も長くなります。
検査は何時から受けられる?
健康診断が受けられる時間は、検査機関の営業時間内です。
医療機関によっては、曜日を設定していたり、午前・午後のどちらかのみ対応していたりする場合もあります。
具体的な受付時間は、検査機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、営業時間内であればいつでも健康診断を受けられるわけではない点にも留意してください。
たとえば、昼休憩や終業時間が近い場合が該当します。
検査には時間がかかるため、休憩・終業時刻を過ぎると予測される場合は、受付を断られる可能性があります。
年に1度の健康診断は受けていますか?つい面倒で、しばらく受けていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。健康診断は、病気の早期発見や予防に欠かせません。 本記事では健康診断について以下の点を中心に[…]
健康診断は受診しなくても大丈夫?
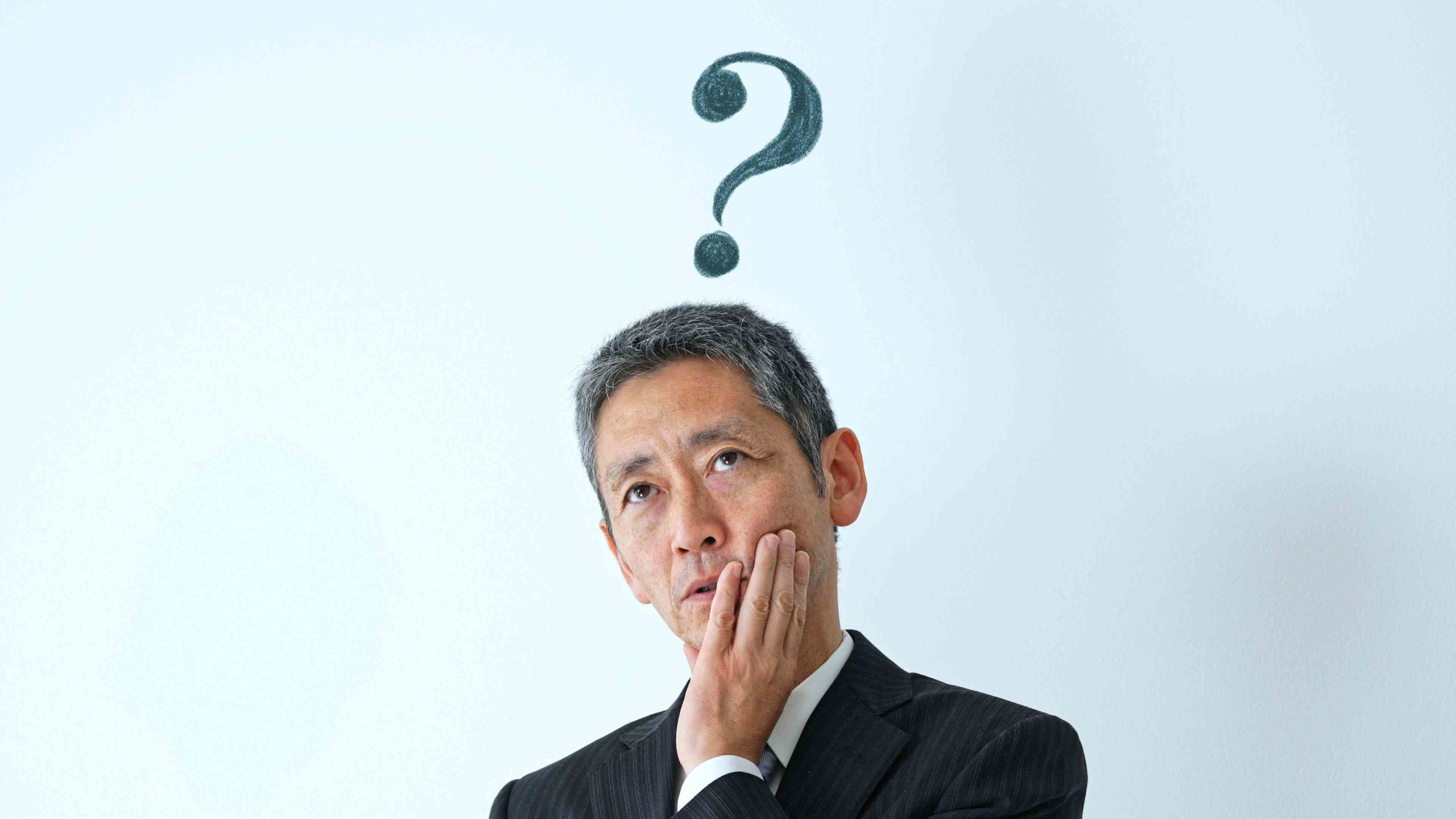
企業に勤めている方の場合、健康診断は必ず受診しなくてはなりません。
企業には、従業員に定期的に健康診断を受けさせる義務があるためです。
自動的に従業員も健康診断を受けざるを得ないというわけです。
企業に勤めていない方の健康診断は、任意になります。
そのため、受けなくても問題はありません。
ただし、任意であっても健康診断は受けるのがおすすめです。
健康診断は、病気を発見するキッカケになることも少なくないためです。
健康診断の流れ

健康診断当日の大まかな流れは、次の通りです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出典:総合健康センター【検診当日の流れ】
健康診断の結果が届くのは、2週間〜6週間後が一般的です。
結果は郵送で届くケースが多いです。
健康診断の検査内容

健康診断で行われる検査は、次のようなものが一般的です。
| 種類 | 内容 | 発見が期待できる病気 |
| 尿検査 | 尿中の糖やタンパクを調べる | 腎臓疾患・糖尿病・肝臓疾患・膀胱炎・尿路結石 |
| 便潜血検査 | 大腸などの消化器官からの出血を調べる | 大腸がん・胃がん・胃潰瘍・十二指腸潰瘍 |
| 身体計測 | 身長・体重・胸囲・腹囲などを計測する | メタボリックシンドローム・骨粗鬆症 |
| 視力検査 | 視力を計測する | 視力低下・白内障・緑内障 |
| 聴力検査 | 聴力を計測する | 聴力低下・難聴 |
| 血圧測定 | 血圧を測定する | 高血圧・動脈硬化・心疾患 |
| 採血 | 血液を採取して成分を調べる | 糖尿病・肝臓疾患・腎臓疾患・脂質異常症・白血病・貧血 |
| 胸部レントゲン | 肺や心臓のレントゲン撮影 | 肺炎・肺がん・気管支炎・心疾患・心肥大 |
| 心電図 | 心臓の電気活動を調べる | 狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・不整脈 |
検査項目を減らせば時間の短縮ができる?

健康診断は、検査項目が多いほど時間がかかります。
では、時間短縮のために任意で検査項目を減らすことはできるのでしょうか。
答えは、原則NOです。
健康診断の検査項目は、検査を受ける側が減らすことはできません。
ただし、医師が不要と判断した場合に限り、一部の検査項目が省略できることもあります。
もし少しでも時間を短縮したい場合は、医師に検査項目を減らせないか確認してみましょう。
減らせる検査項目は、たとえば身体計測や喀痰検査などが該当します。
健康診断の時間に遅れたら検査できない?

健康診断の受付時間が指定されている場合、遅刻したら受けられないのでしょうか。
基本的には、遅刻しても健康診断は受けられます。
ただし、受付時間通りに来ている方が優先されますので、遅刻した方は少し待たされる場合があります。
また、大幅に遅刻した場合は、健診自体を断られる可能性もあります。
どうしても遅刻しそうな場合は、遅刻が分かった時点で検査機関に連絡を入れましょう。
場合によっては受付時間を変更したり、健診日を変更したりできる場合もあります。
スポンサーリンク
食事による時間の制限

健康診断の前日は、次の時間までに食事を済ませておきましょう。
- 午前中の健診の場合:前日の21時
- 午後の健診の場合:当日の7時
基本的に、食事は健診の8時間以内は摂ってはいけません。
理由は、胃に消化物が残っていたり、血液検査の値が変動したりするおそれがあるためです。
スポンサーリンク
人間ドックの所要時間

健康診断に似たものに、人間ドックがあります。
人間ドックは、健康診断よりも検査項目が多く、より詳細に身体のことを調べられます。
人間ドックの平均所要時間は、2〜3時間です。
コースによっては、1泊して検査を受けることもあります。
スポンサーリンク
健康診断の受診率

2020年度は、健康診断の受診率が低いという結果が出ています。
具体的な受診率を年代・性別ごとにまとめました。
| 男性(%) | 女性(%) | |
| 20代 | 47.3 | 41.6 |
| 30代 | 58.9 | 42.5 |
| 40代 | 67.6 | 57.3 |
| 50代 | 69.1 | 55.7 |
| 60代 | 67.0 | 57.8 |
| 70代 | 62.2 | 58.0 |
前年度と比べると、受診率が最も下がったのは20代の女性でした。
具体的には、2019年の20代女性の受診率は65.9%でした。
健康診断の受診を控える理由としては、次のようなものが挙げられます。
- 新型コロナ感染症対策のため
- 健康に不安がなく、健診の必要性を感じないため
- 面倒なため
- 時間がとれないため
- 体調に不安があるときは医療機関を受診すればよいため
健康診断は、病気の早期発見のキッカケになることも少なくありません。
健康を守るためにも、年に1回は健康診断を受けることが望まれます。
出典:厚生労働省【5 健診(健康診断や健康診査)や人間ドックの受診状況】
出典:メディカルカンパニー【みんなの健診&検診意識調査】
健康診断の時間まとめ

ここまで健康診断の時間についてお伝えしてきました。
健康診断の時間の要点を以下にまとめます。
- 健康診断の所要時間は、1時間~1時間半が平均的
- 健康診断の検査は、企業に勤めている方は必ず受けなければならない
- 健康診断の検査時間は、医師に相談すれば一部省略できることもある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。