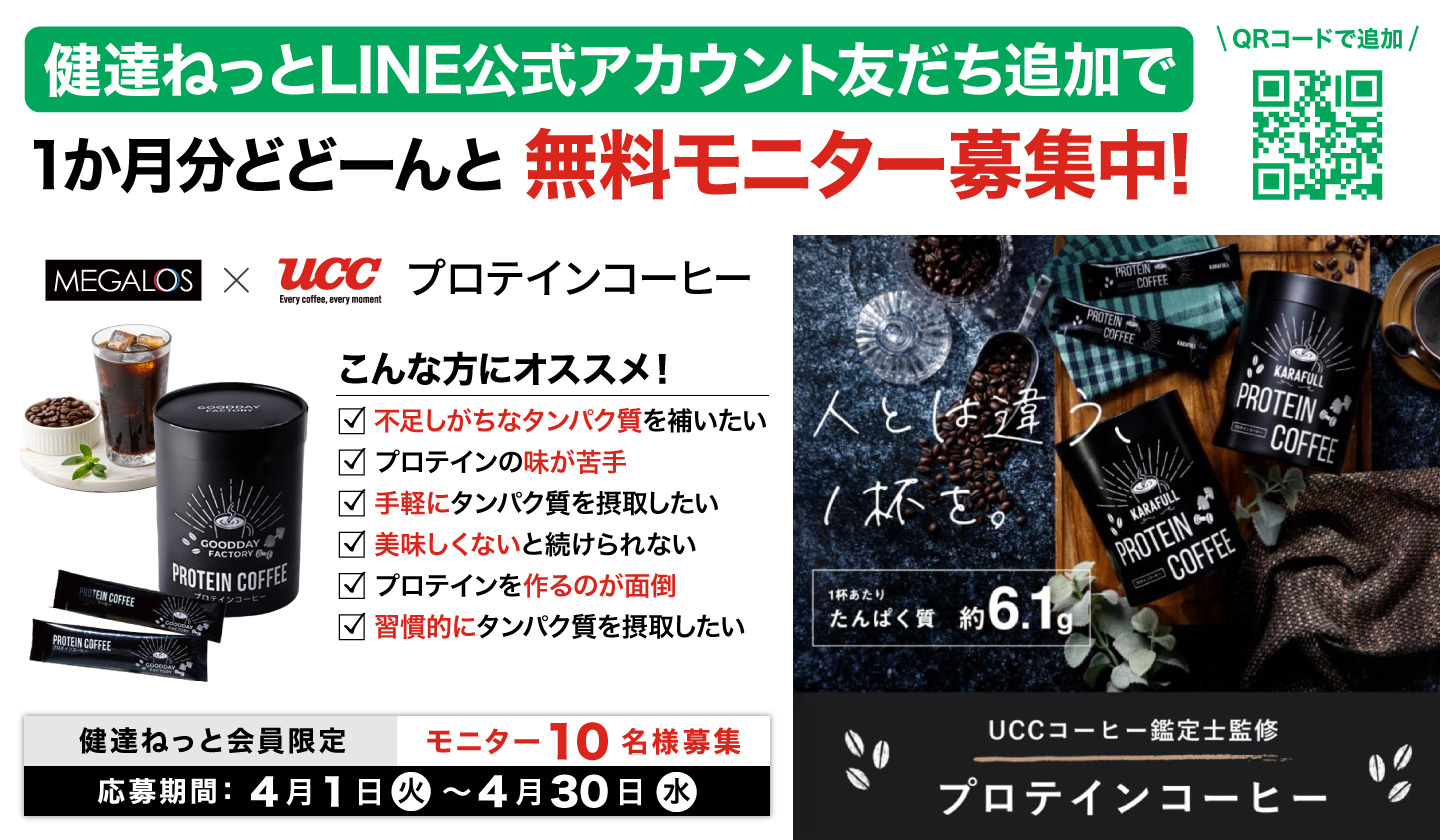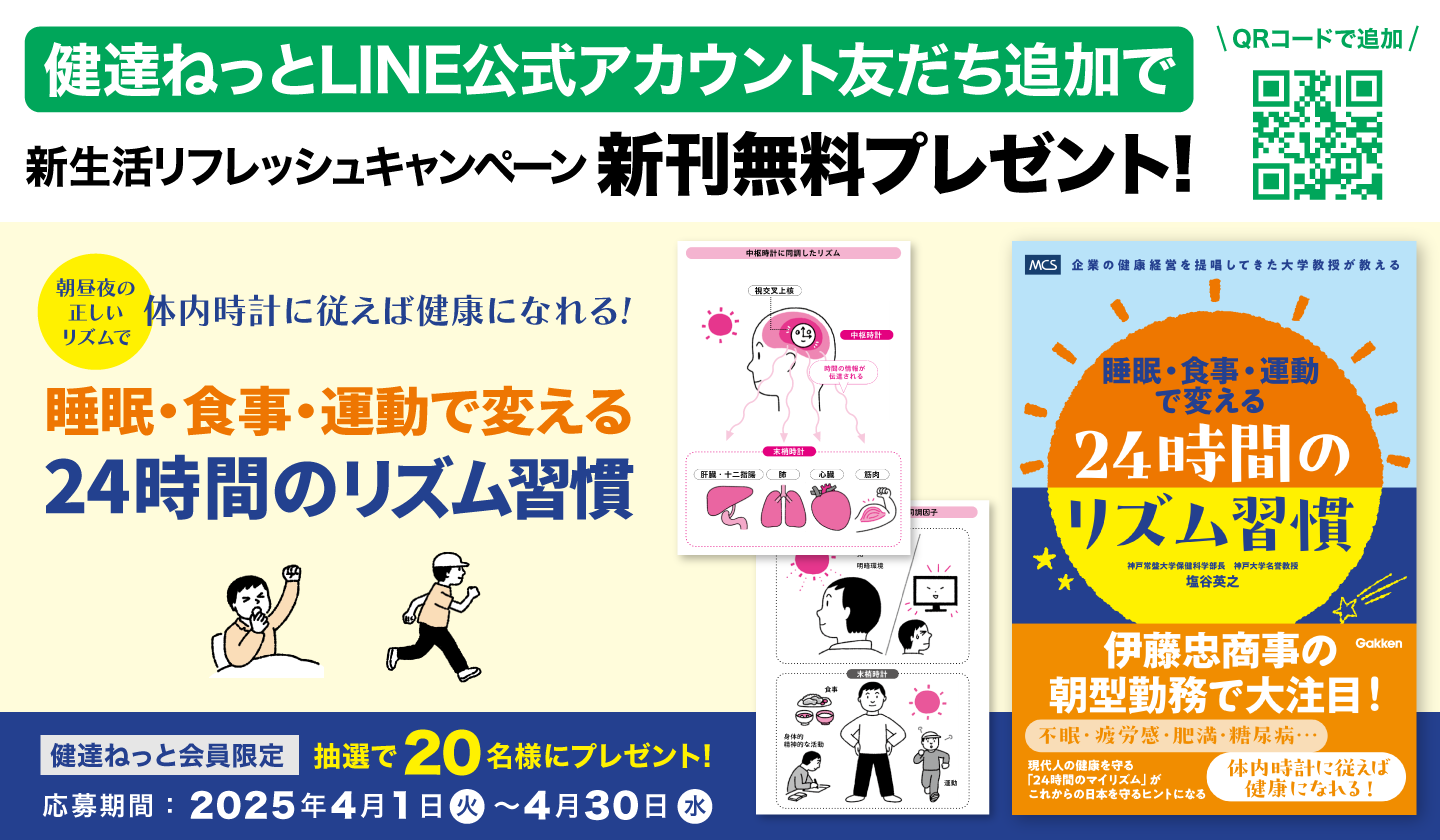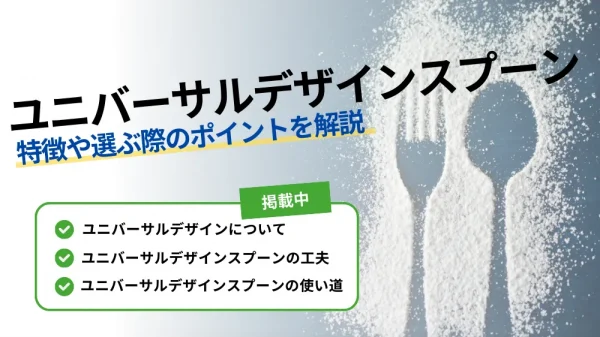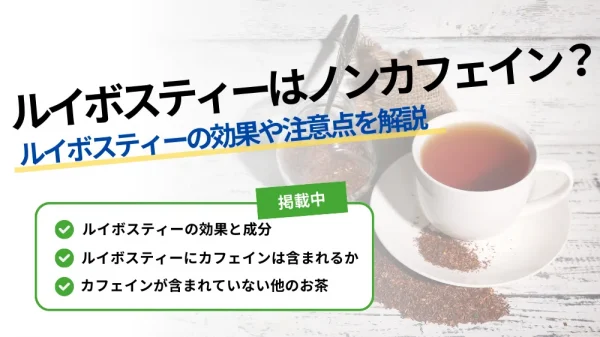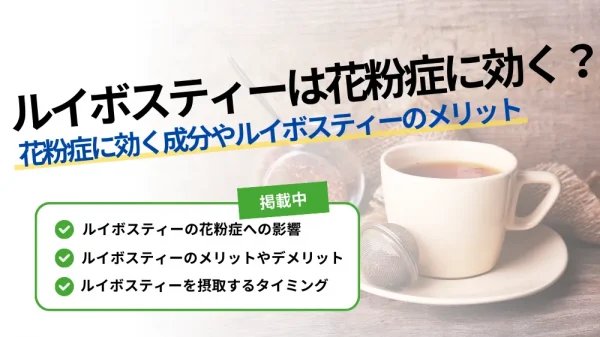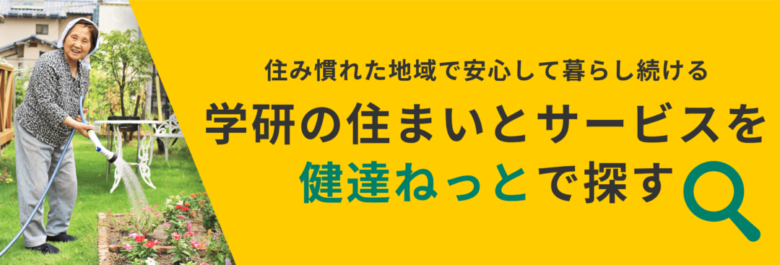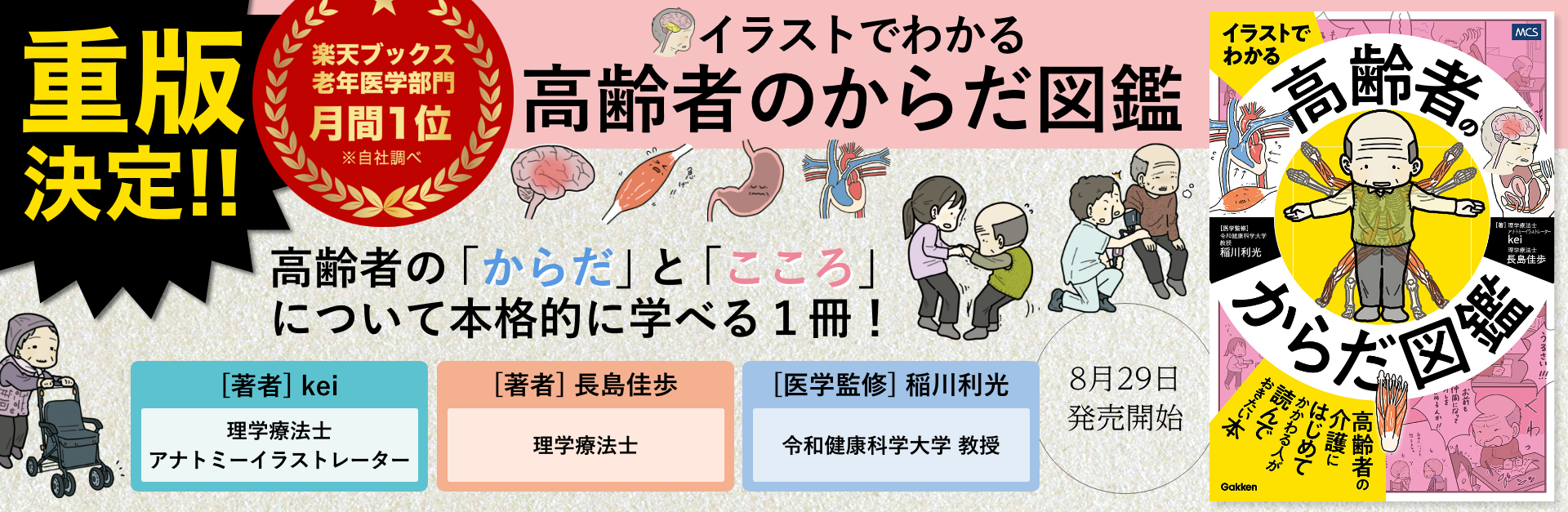カルニチンは脂肪の代謝に重要な役割を持っています。
カルニチンが不足すると、「カルニチン欠乏症」を引き起こすこともあります。
カルニチンはどのような食べ物に多く含まれているのでしょうか?
カルニチンはどのように摂取すれば効果的でしょうか?
本記事ではカルニチンを含む食べ物について以下の点を中心にご紹介します。
- カルニチンの効果とは
- カルニチンを多く含む食べ物とは
- カルニチンのダイエット法とは
カルニチンを含む食べ物について理解するためにも参考にしていただければ幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
カルニチンとは

カルニチンとは、アミノ酸の一種です。
ラテン語で肉を意味する「carnus」に由来します。
ロシアの科学者によって肉から抽出されたエキスから発見されました。
またカルニチンはL-カルニチンやアセチル-L-カルニチン、プロピオニル-L-カルニチンなどの総称です。
ほとんどの人が、必要とされる分のカルニチンは体内で作られます。
どこで作られている?
カルニチンは必須アミノ酸のメチオニンとリジンの働きによって肝臓や腎臓で作られています。
体内で生成されるカルニチンは全体の4分の1です。
残りの4分の3は食事から補給されます。
しかし高齢の方やダイエット中の方は注意が必要です。
加齢によりカルニチンの生成能力が低下していきます。
そのため、高齢になるとカルニチン濃度が低下するといわれています。
ダイエットや偏食な方もカルニチン不足に陥りやすいです。
年齢関係なくカルニチンをある程度摂取することは重要です。
働き
カルニチンはエネルギーを生み出すことに重要な役割を担っています。
カルニチンは脂肪酸をミトコンドリア内に運び、燃焼させることでエネルギーを作ります。
脂肪酸は脂質の構成要素の1つです。
脂肪酸を運ぶ働きができるのはカルニチンのみとなっているため、非常に重要な成分です。
カルニチンには、L-カルニチンとD-カルニチンが存在します。
L-カルニチンは心筋や骨格筋群に存在し、代謝に重要な成分です。
D-カルニチンは何か重要な働きをすることはなく、L-カルニチンの働きを邪魔するといわれています。
スポンサーリンク
カルニチンを含む食べ物にはどんな効果が期待できる?

ここではカルニチンの効果について解説していきます。
カルニチンの効果は大きく3つです。
脂肪燃焼の促進
カルニチンはエネルギーを作るために脂肪酸(脂質)を使います。
そのため脂肪燃焼促進に効果的です。
脂肪の燃焼はミトコンドリア内でのみ行われます。
カルニチンは脂肪酸をミトコンドリアに運びます。
カルニチンの働きがないと脂質はミトコンドリアにたどり着くこともできません。
この脂肪燃焼の促進はメタボリックシンドローム対策にも効果的です。
カルニチンが脂肪を燃焼させることで、食事面からダイエットをアシストします。
エネルギーを生産して運動の効率を高める
糖質が瞬発的なエネルギーの生成を担う一方で、脂質によるエネルギー生成は持続的なエネルギーの生成を担います。
持続的なエネルギーの生成によって、筋肉や心臓の筋肉を絶え間なく動かしているのです。
実際に心臓の働きが弱くなった人にカルニチン治療薬を投与すると症状が和らぎました。
その結果をもとに、L-カルニチンは心臓病の治療薬として用いられるようになりました。
しかしL-カルニチンは心臓以外の筋肉を動かす際にも有効な成分だといわれています。
1980年のモスクワオリンピックでカルニチンのサプリメントを摂取したチームが好成績を残しました。
治療薬として注目されていたカルニチンですが、食品としても注目されています。
疲労回復を促進する
L-カルニチンは疲労回復の促進に効果的です。
特に慢性的に疲れを感じる人は、L-カルニチンが不足していることが考えられます。
疲労回復には、エネルギーを生成するカルニチンを摂取することが重要です。
カルニチンは体内の有害物質を除去する効果があり、その点でも疲労回復の効果が期待できます。
タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]
カルニチンの多い食べ物

ここではカルニチンが多く含まれている食べ物を7つ紹介します。
なおカルニチンの含有量は食べ物100g当たりの含有量です。
1位:羊肉
羊肉の中でもマトンのロースやかたには、カルニチンが約190mgと最も多く含まれています。
ラム肉のカルニチン含有量は約110mgで、マトン肉より少ないです。
マトン肉とラム肉の違いは羊の年齢です。
マトン肉は生後1年以上経った羊肉、ラム肉は生後1年未満の子羊の肉をさします。
マトン肉はラム肉よりも、独特のにおいで苦手だという人も少なくありません。
しょうゆやにんにく、スパイスなどにつけて調理するとにおいを軽減させられます。
肉質がしっかりしているため、カレーや煮込み料理に活用することをおすすめします。
ラム肉はにおいが少なく、肉質も柔らかいためマトン肉より食べやすいです。
野菜炒めなどで野菜と一緒に召し上がることをおすすめします。
2位:赤貝
赤貝もL-カルニチンを豊富に含んでおり、含有量は108mgです。
基本的に肉類に多く含まれているカルニチンですが、肉類以外で豊富な赤貝は貴重です。
赤貝はカロリーが低いため、ダイエットにも効果的な食材といえます。
赤貝の旬は冬で、炊き込みご飯に活用するとうまみが出ておすすめです。
3位:牛肉
一般的に入手しやすい食べ物の中では牛肉が最も含有量が多いです。
含有量はかた肉が多く76〜95mgほどです。
輸入肉の方が国産肉より含有量は多くなっています。
摂取方法としてはステーキや焼肉など火を入れすぎないことをおすすめします。
火を入れすぎないほうが消化しやすく、栄養分を吸収しやすいです。
わさびやにんにくなどの薬味は消化酵素を含んでおり、消化を助けてくれるためおすすめです。
4位:豚肉
牛肉よりは含有量が少ないものの、他の食べ物よりは多めにカルニチンが含まれています。
ロース肉のカルニチン含有量は22mgです。
豚肉はビタミンB1が豊富に含まれています。
ビタミンB1は糖質代謝をサポートする働きがあり、糖分を素早くエネルギーにすることが可能です。
ビタミンB1はカルニチンと同様に疲労回復に効果的です。
慢性的に疲れが溜まっていたり、身体のだるさが気になる方は豚肉の摂取をおすすめします。
5位:鶏肉
肉類の中では含有量が少ないものの、鶏肉にもカルニチンが含まれています。
カルニチンの含有量は25mgほどです。
カルニチンの含有量は牛肉の約4分の1程度ですが、肉類の中でも安価で入手しやすいです。
部位によって含まれている成分は違いますが、どの部位もタンパク質が豊富に含まれています。
鶏肉は低脂肪でもあるためダイエットしている方や筋肉をつけたい方におすすめです。
6位:豆類
豆類は肉類より少ないものの、野菜よりはカルニチンを多く含んでいます。
豆類はビタミンB群を豊富に含んでおり、エネルギーの生成や健康維持に役立ちます。
それでも豆類はカルニチンを多く含んでいるということではありません。
カルニチンを摂りたい方は肉類から摂取することがおすすめです。
7位:牛乳
飲み物の中では牛乳が最もカルニチンを含んでいます。
牛乳には三大栄養素タンパク質・炭水化物・脂質)が多く含まれています。
牛乳の炭水化物は乳糖と呼ばれるもので、腸の動きを良くすることに有効です。
さらに牛乳にはビタミンAを筆頭に様々なビタミンが含まれています。
カルニチンの食べ物を使った効果的なダイエット法

ここではカルニチンの食べ物を使ったダイエット法について紹介します。
以下のことに注意すればよりダイエット効果が期待できます。
ぜひ参考にしてみてください。
食べるだけでは痩せない
カルニチンは脂肪燃焼の効果がありますが、摂取するだけで痩せるわけではありません。
カルニチンの効果を得るためには、正しい食事や運動習慣が重要です。
また何も考えず摂取するのではなく、摂取量やタイミングも考える必要があります。
カルニチンはある程度体内でも生成されますが、加齢によって生成能力が低下します。
生成能力は20代がピークで徐々に減少し、60代の生成能力は20代の約6割ほどです。
カルニチンの摂り過ぎを防ぐには、サプリメントでの摂取をおすすめします。
サプリメントからカルニチンを摂取すると、摂取量がわかりやすいためです。
運動することによってカルニチンの効果があがる
カルニチンを摂取してから運動すると、ダイエットの効果を大きく得られます。
カルニチンはエネルギーを作り出す作用があるためです。
さらに運動によって筋肉が増えると、その分体内のミトコンドリアの数が増えます。
数が増えた分脂肪燃焼の効率が上がるといえます。
カルニチンを摂りつつトレーニングすると、ダイエット効果も高いです。
入浴中に足を動かしたり、家事などスキマ時間に身体を動かすだけでも効果があります。
カルニチンを単純に多く摂っても効果は薄い
カルニチンをただ多く摂っても効果は薄いです。
カルニチンの運搬先であるミトコンドリアの数が少ないと意味がありません。
ミトコンドリアの総数を多くするためには先述の通り筋肉を増やすことが有効です。
カルニチンを多く摂取している方は、運動を合わせて行うことが重要です。
カルニチンと他の栄養素を組み合わせると効果が高くなる
カルニチンだけでなく、他の栄養素と組み合わせることでより高い効果を期待できます。
カルニチンは体内でリジン・メチオニンを原料に作られます。
しかしリジンやメチオニンは体内で生成されず、外部から補給しなければいけません。
リジン・メチオニンは肉類や乳製品、大豆製品などに多く含まれています。
また脂肪燃焼の効率を上げるビタミンB1を摂取すると、カルニチンの効果が高くなります。
α-リポ酸・コエンザイムQ10の組み合わせもおすすめです。
α-リポ酸・コエンザイムQ10はミトコンドリア内でのエネルギー生成をサポートします。
運動時の代謝を良くしてカロリーを多く消費させます。
カルニチンが不足するとどうなる?
カルニチン欠乏症は、さまざまな年齢層で
- 意識障害
- けいれん
- 横紋筋融解症
- 脳症
- 頻回の嘔吐
- 精神・運動発達の遅延
- 心肥大
- 心筋症
- 心機能の低下
- 突然死
といった深刻な症状を引き起こす可能性があります。
この欠乏症は、先天性の代謝異常症に限らず、肝硬変や肝不全の方、食欲不振症の方、高齢者などの低栄養状態にある方、腎不全の方にも見られます。
さらに、カルニチンを含まない経管栄養や完全静脈栄養(TPN)、一部の牛乳アレルギー対応調整粉乳を使用している方など、適切な栄養管理がされていない場合にも発症するリスクがあります。
また、カルニチン欠乏症は、バルプロ酸やピボキシル基を含む抗菌薬、抗がん剤などの薬剤投与によっても引き起こされる可能性があり、これらの薬剤を使用している方は特に注意が必要です。
この欠乏症は、日常臨床において決して稀なものではなく、特に慢性疾患を抱える方や高齢者、重症の代謝異常を持つ方は、積極的な観察が必要です。
出典:日本小児科学会「カルニチン欠乏症の診断・治療指針 2016について」
カルニチンを食べ物から摂取する際の注意点

カルニチンを摂取する際の注意点は3つです。
カルニチンを摂取しようと考えている方は以下の点に気を付けてください。
食べ物以外でカルニチンを取れるのはサプリだけ
食べ物以外でカルニチンを取れるのはサプリメントのみです。
それほどカルニチンは意識して摂取しなければならない成分といえます。
カルニチンを多く含むのは主に肉類だけとなります。
安定してカルニチンを摂取するにはサプリメントの活用がおすすめです。
過剰摂取すると副作用が出る可能性がある
カルニチンを過剰摂取すると、副作用が生じる可能性があり危険です。
副作用の症状としては以下の通りです。
- 吐き気
- 嘔吐
- 腹部痙攣
- 下痢
- 生臭い体臭
副作用が生じる目安は約3g/日となります。
ダイエットしたいからといって過剰摂取せず、推奨摂取量を守るようにしましょう。
D-カルニチンと間違えない
カルニチンにはL-カルニチンとD-カルニチンの2種類が存在します。
D-カルニチンはL-カルニチンの働きを阻害する作用があるため、知らずに摂取することは危険です。
D-カルニチンは基本的に食べ物には含まれていません。
しかしサプリメントにD-カルニチンが含まれている可能性があります。
特に海外製のサプリメントだと成分表が記載されていないことも少なくありません。
D-カルニチンが入っていることも考えられます。
サプリメントを利用するときは成分表をみて、D-カルニチンが入っていないか確認しましょう。
カルニチンは無理に食べ物で摂る必要はない

カルニチンは無理に食べ物やサプリメントで摂る必要がありません。
カルニチンの摂取量が少なくとも、体内の肝臓や腎臓で作られるためです。
特に若い世代はカルニチンを生成する能力が高いため、無理に食べ物で取る必要性は少ないです。
以下に当てはまる方はサプリメントや食べ物でカルニチンを摂取しても問題ないでしょう。
- 年配の方
- 運動習慣がありダイエット中の方
歳を重ねるにつれてカルニチンの生成能力が低下するため、年配の方はある程度意識してカルニチンを摂取する必要があります。
また運動習慣があり、ダイエット中の方も積極的なカルニチンの摂取がおすすめです。
エネルギーを多く必要とし、脂肪燃焼をより効率的に行うためです。
出典:厚生労働省【『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』カルニチン】
カルニチンを含む食べ物まとめ

ここまでカルニチンを含む食べ物についてお伝えしてきました。
カルニチンを含む食べ物の要点をまとめると以下の通りです。
- カルニチンは脂肪燃焼や疲労回復、運動の効率化が期待できる
- カルニチンは肉類に多く含まれており、特に羊肉に多い
- カルニチンを摂るだけでは痩せない、運動することが重要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。