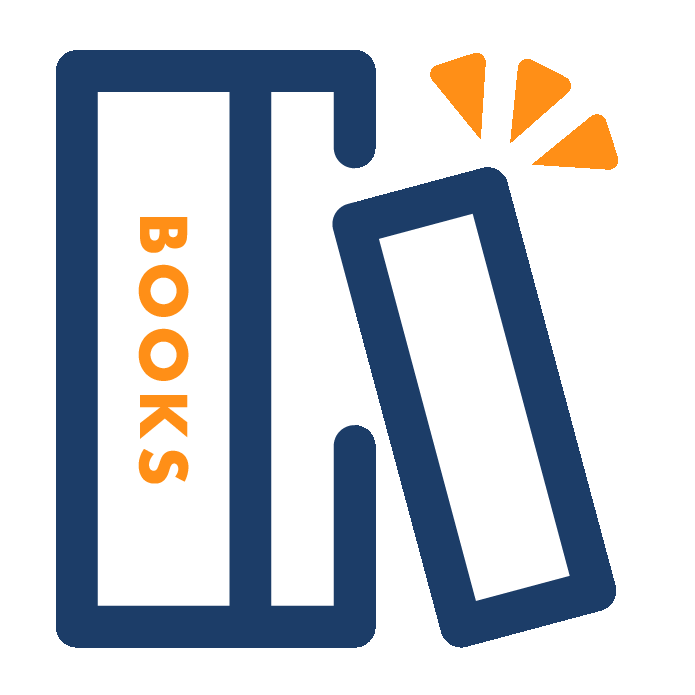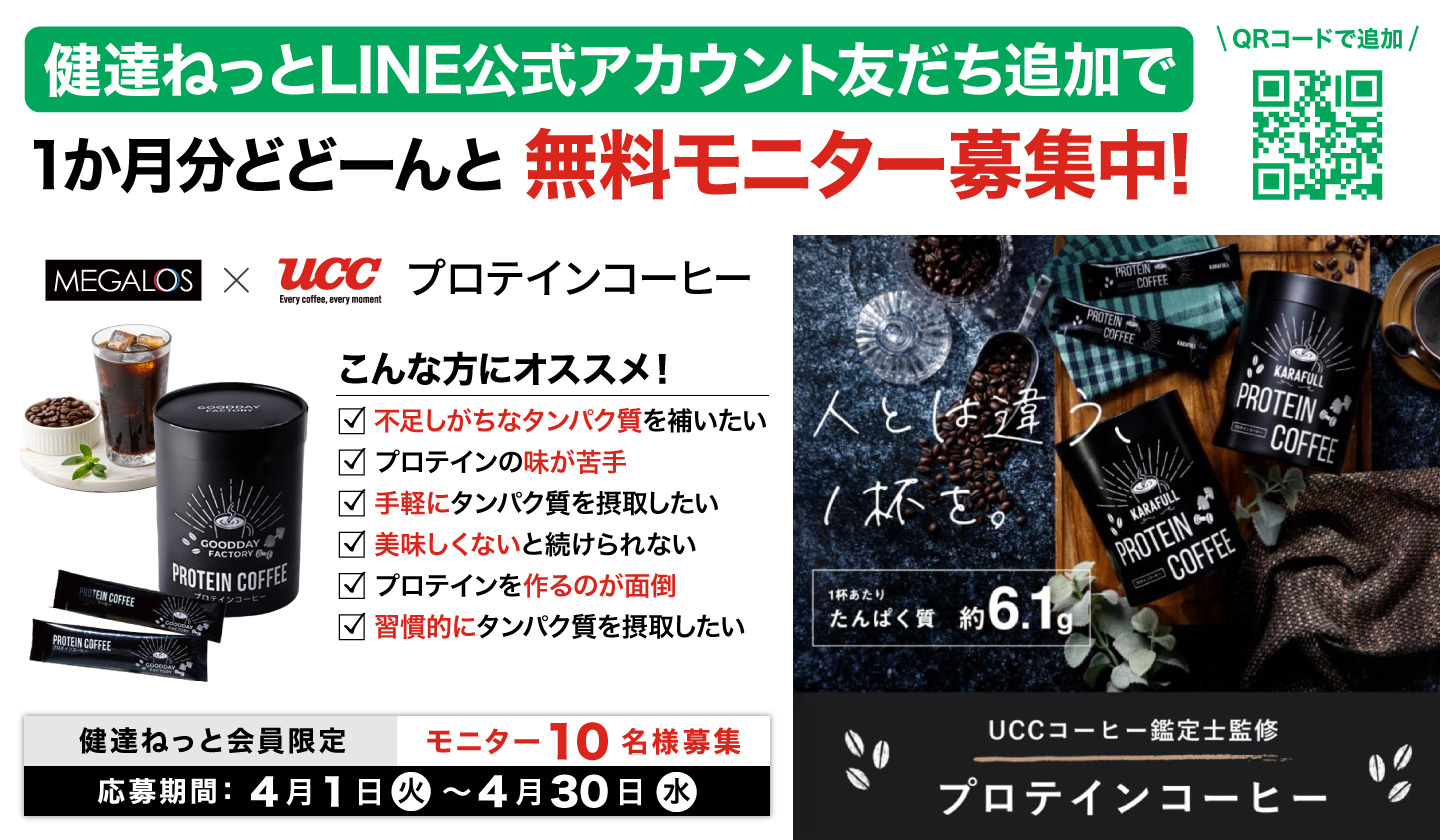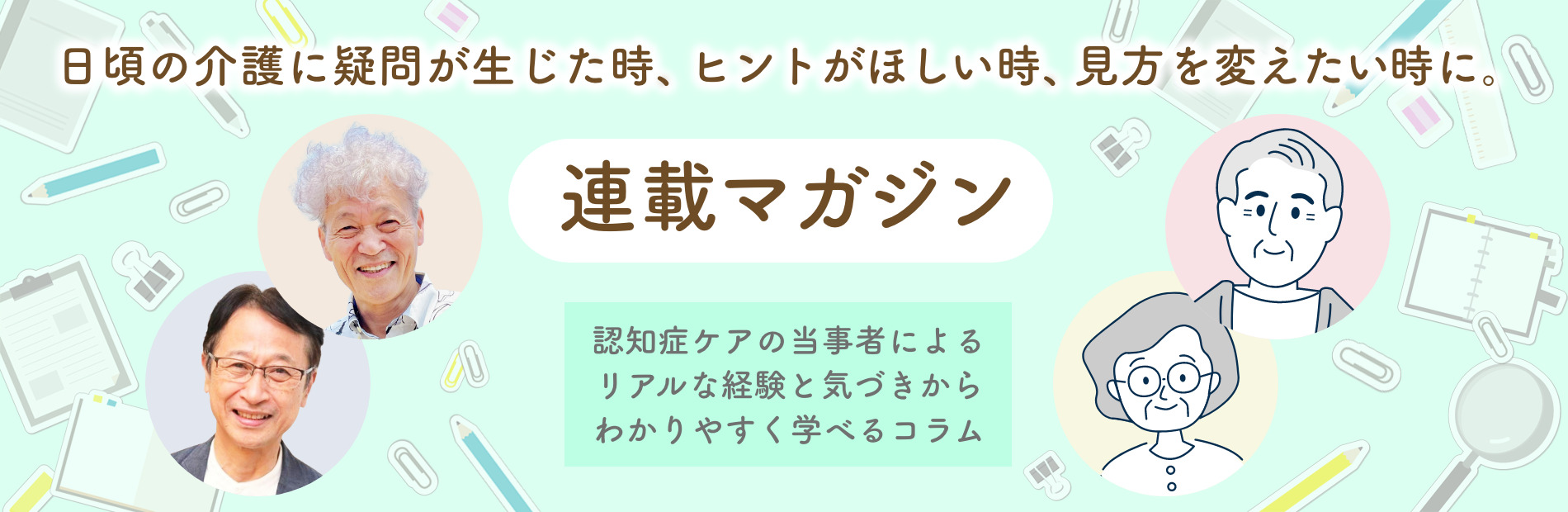本間 昭 先生
スポンサーリンク
認知症を患う人の一人暮らしが増えている
近年、独居および高齢者だけの世帯が増加しつつあり、それに伴い、独居している認知症の人も増加していることは周知の事実です。
「独居」の認知症の人を支える上では、病院の内外を問わず、“関係者間”で本人の治療目標を共有することが重要で、イコール「認知症の地域連携」が重要であるといえます。
治療薬を処方することのみが、認知症の人に対する医療ではないということは明白です。
スポンサーリンク
独居への“自覚のない不安”が、認知症の症状に影響する
1つの例をもとに説明しましょう。
84歳の女性、Aさんのケースです。
Aさんは、足腰はきわめて達者で、一人で生活しています。
隣の市に長女が住んでいますが、フルタイムで仕事をしており、Aさんのところへは月に数回顔を出す程度だといいます。
半年ほど前より、仕事中の長女のもとに、Aさんから頻繁に電話が入るようになりました。
さらに、夜中に何回も救急車や警察を呼ぶことがあり、心配した隣人が地域包括支援センターに連絡。
Aさんは、地域包括支援センターの担当者と長女と一緒に、認知症外来を受診することになりました。
それまでかかりつけ医の外来には、動悸やめまいなどの訴えで頻繁に受診しており、頭部CT検査を含めて、特に身体的には何ら問題ないということでした。
初診時、Aさんは、歩行はしっかりしていましたが、表情は硬く、雑談をしても表情にはほとんど変化がみられませんでした。
長女の話では、元来きれい好きできちんと整頓ができていたのが、今では部屋のあちこちに衣類が散らばり、トイレは自立しているものの、「きちんと入浴ができていない」、「ゴミを決まった日に出せていない」、「洗い物が台所にたまっている」、「かかりつけ医より処方された内服薬も手がつけられていない」という状況。
長女は久しぶりに会った母親の状態に当惑している様子で、また、仕事中でも本人から頻繁に電話があるため、仕事に支障をきたしているという訴えもありました。
問診と検査の結果、Aさんに意識障害はなく、HDS-R(*1)は18点。
神経所見がないこと、さらに長女の話から健忘(物忘れ)が進行性であることを確認して、「アルツハイマー型認知症」と診断されました。
加えて、認知症自体の重症度は軽度(CDR:1)でしたが、独居という環境による心理的な要因により、「混乱状態、不安状態が前面に現れている」と判断しました。
また、Aさんは1年前に介護保険の利用申請をしていて、要介護度は「要支援2」。
本人の希望は、「このまま一人での生活を続けたい」というものでした。
このような例は、最近では外来でしばしば見かけられます。
本人は自覚していませんが、独居でいることによる不安症状・不安状態への対応がまず必要になります。
服薬がきちんとできていないわけですから、抗不安薬を処方することはできません。
また、「アルツハイマー型認知症」という診断でも、この段階からその治療薬を出すこともできません。
介護と連携して、不安を取り除けるようなサポート体制をつくる
Aさんのケースでは、本人は「家事はできていて生活には何の支障もないし、人に手助けをしてもらうこともない」と言っており、ヘルパー(訪問介護)の導入は受け入れられない可能性が高いと判断。
そこで「訪問看護」の利用を、介護保険サービス導入のきっかけにすることを選択しました。
まず、地域包括支援センターの職員と訪問看護師、そしてAさんの長女を交えて、「健康チェックを通して本人の心気的な訴えに耳を傾け、ケアする」という対応を行いました。
結果として、月に2回の健康チェックやフットケアなどの身体的な関わりを通して、本人との信頼関係を構築でき、本人が不安になったときには長女ではなく、訪問看護ステーションに電話が入るように。
このことによって長女の心理的な負担は大きく軽減し、Aさん本人の今後についても、余裕をもって考えることができるようになったのです。
次に行ったのが、「服薬」と「食事摂取」のサポートの検討です。
「要支援2」ではサービスの利用に限界があるため、Aさんには介護保険の区分変更を申請してもらうことにしました(*2)。
初診後の半年間で2回の区分変更申請をすることになりましたが、結果としてAさんは「要介護1」と認定され、介護保険サービスを使った服薬確認体制ができ、デイサービスなどの利用にもつなげることができました。
そして初診から1年後の時点で、AさんのHDS-Rの検査結果は21点に改善。
今も独居を続けながら、長女が付き添って月1回のペースで通院しています。
医療と介護、家族が一丸となって“生活”を支えていく
Aさんのケースは、環境あるいは心理的要因への介入によって不安症状が消失し、独居を続けることができている例です。
しかし、このような例では、診察室の中だけで本人への対応は完結できません。
地域包括支援センターの職員、訪問看護師、家族、介護保険サービス事業所の職員、そして主治医という関係者が、認知症を患う人が独居を続けるためにはどのような支援が必要なのかという共通の意識をもつこと。
また、共通の認識を持つためには、それぞれの地域でどのようなリソースを活用できるかを把握しておく必要があります。
認知症の進行を抑えるという効果は、一人で生活を続ける上で大きな意味があります。
ただ、その効果をよりはっきりさせるためには、上述のように環境をいかに整備することができるかにかかっているのです。
キーワードを1つあげるとすると、「生活」ではないでしょうか。
医療であってもケアであっても、生活を支えるという視点が、そして手段が、それぞれ異なるのは当然です。
だからこそ、本人の望む生活をしっかりとイメージして全員で共有することが大切です。
関係者が持つべき共通の認識の目標は「認知症の地域連携」であることを、ここに強調したいと思います。
【注釈】
*1 改訂長谷川式簡易知能評価スケール。認知機能の状態を評価するもので、30点中20点以下で「認知症の疑いがある」と評価される。
*2 本人の状態が認定を受けた当時より悪化したときなどには、再度、認定調査を申し込むことができる。