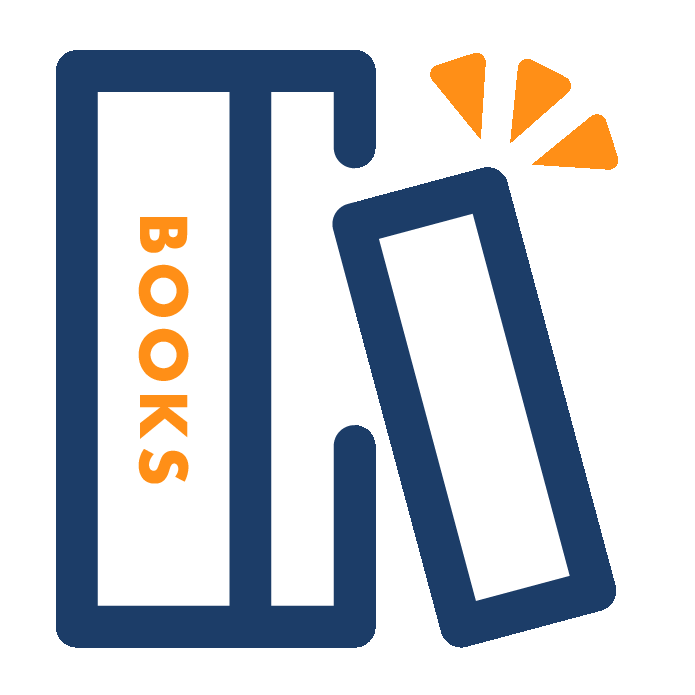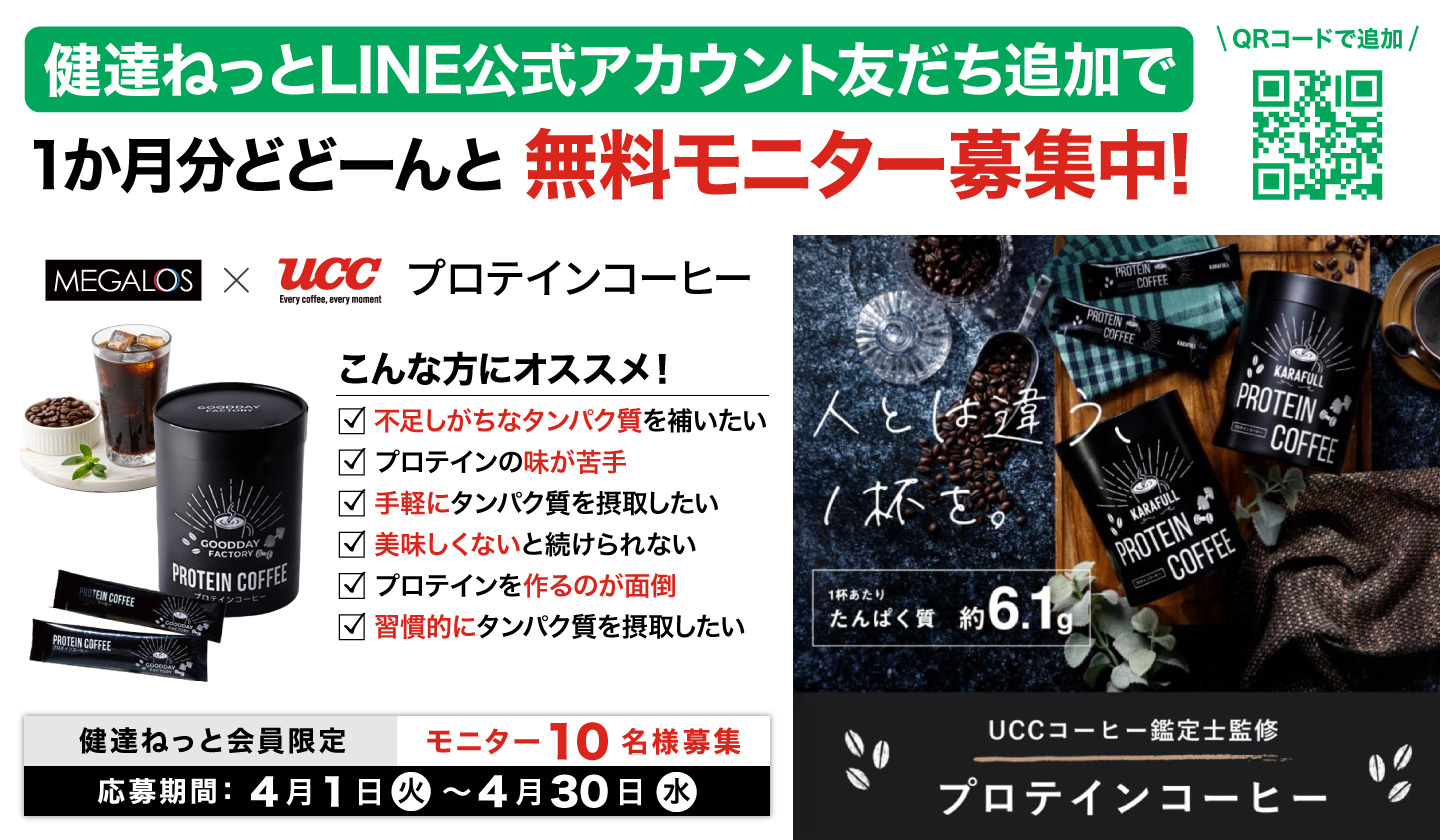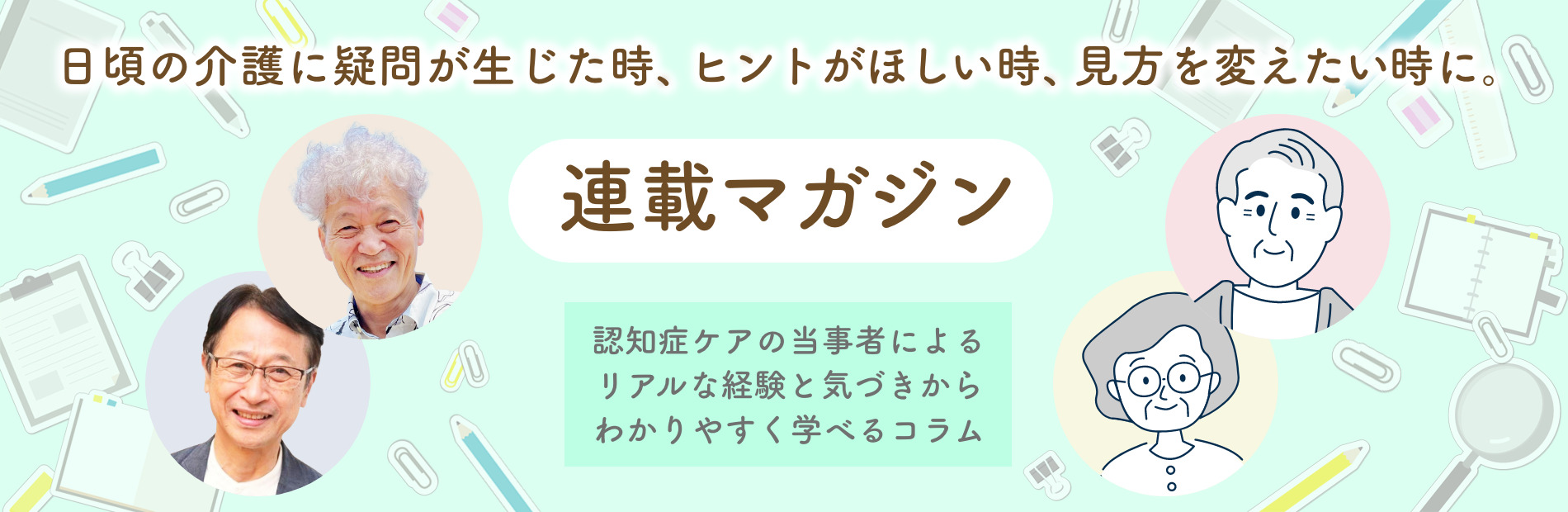メモリークリニックお茶の水
朝田 隆 先生
スポンサーリンク
ウィズ・ポストコロナ時代に必要なのは、「共生」のためのサポート
新型コロナウイルスを語るとき、引き合いに出されるのが「スペインかぜ」です。これは第一次世界大戦中に生じた世界的大流行(パンデミック)で、当時の日本の人口5,500万人に対し、約2,380万人(43%)が感染、約39万人が死亡したとされ、今回のコロナウイルスよりもはるかにひどいものでした。スペインかぜの流行の大波は3つあり、第1波が到来した1918年から、第3波が収まる1921年まで、丸3年間は続きました。
当時と違って、現在では新型コロナウイルスにはワクチンがありますが、仮に新型コロナウイルスの流行が3年間続くとしたら、今はまだ折り返し地点に過ぎません。しかも今年7月以降、一旦落ち着いたかに見えた感染者数は、変異株の出現によって世界各地で再び激増しています。
それだけに、コロナ禍の今でもできることをやる、また終息後に備えることが、認知症サポートにおいても必須になりました。
サポートの場における基本は、まず新型コロナウイルスの感染を避けること。そして具体的なこととしては、認知症対応の基本とされる「共生」と「予防」です。ここでいう共生とは、認知症になっても住み慣れた地域で、その人が自分らしく暮らせるような社会をつくることであり、予防とは、認知症の発症と進行を遅らせることです(*1)。
とくに共生は、強調されてきた割には具体性が乏しかったといえます。コロナ禍のあと、すなわちポストコロナ時代には、その具体化が求められます。
スポンサーリンク
生活の不便を見過ごさず、解決策を考えることがサポートにつながる
最初のパンデミック「スペインかぜ」の流行が3年間続いたという歴史にならうと、前述のとおり、コロナ禍はまだ半ばに過ぎないことになります。それだけに、認知症のサポートにおいて、当面はコロナ予防抜きには語れません。
そうすると、マスクやアクリル板などは当分使われそうです。これらが汎用されるようになって久しいですが、私自身はまだ慣れず、不便を感じています。相手の言うことが明確に聞こえないし、自身が発する声もクリアに届かないからです。
ただでさえ高齢者の声は枯れやすく、小さく、不明瞭になりがちです。しかも、難聴者が多くいます。最近のハイテク製品では(高価ではあるものの)外付け補聴器という手段がありますが、筆者としては、実は量販店にあるような「拡声器」も、けっこう役に立つのではと思っています。実際に、私のクリニックではハイテク製品も拡声器も、そのときどきの状況に合わせて使い分けています。
もっとも、拡声器は運動会など戸外での活動を想定して作られているためか、下手をするとその場に大きな音が響きわたります。あらかじめ慎重に音量を調整しておいて、窓口ならカウンターの上に置き、アクリル板の向こうから話してもらうのです。難聴の人なら、拡声器を反対に向けてもらってこちらが返事をすることもできます。なお、拡声器の値段はピンキリながら、私の経験的には、1万円くらいの品で実用に足りると思われます。
コロナ禍がもたらす、認知症の人とのコミュニケーション障害
ところで、前述の加齢による声の変化は喉頭の筋力低下によるものですが、これは同時に誤嚥性肺炎のリスクも高めます。そのため以前から、声帯のストレッチとしてたくさん声を出して楽しく会話すること、また、歌うことが推奨されてきました。それができないから困る当世なのですが……。毎日1回、ラジオ体操的に、戸外や屋上などで十分な距離を取り、誰もが知る歌などを大声で合唱してみたいものです。
また近年、認知症の危険因子として、中年期からの難聴が注目されるようになりました。難聴によって認知症が進むメカニズムとしては、いくつか想定されていることがあります。
代表的なものは、難聴によるコミュニケーション不足、それによる孤独、そこからうつ、そして認知症というプロセスでしょう。
しかし私は、いわば真犯人は難聴自体ではなく、それによるコミュニケーションの不足、双方向性のやり取り不足からくる“脳の廃用”ではないかと思っています。逆に経験的には、認知症になっても、双方向の会話は優れた脳トレになるとも考えられます。
認知症の人の“願い”を汲み取り、実現する
先日、ラジオ局でいい話を聞きました。「認知症当事者とその家族の集まりで、本格的な野球場で思い切りソフトボールを楽しみたい」という声が出たそうです。関係者が知り合いをめぐった結果、これが実現。ある会社が、自社の野球場をポンと無償で貸してくださったのです。ソフトボールに限らず、フォークダンスや、オープンスペースでの芋煮会など、いくつも考えられそうです。
もっとも、このソフトボールの話がよかったのは、家族や世話人ではなく、認知症の当事者から出たところです。これまでも介護者側が当事者の願いを想定し、それを実施して喜んでもらおうとする例はありました。しかし、介護者なら誰でもご存じのように、認知症の人は、自らの「願い」、すなわち“したいこと”、“やってほしいこと”を容易に語ることができません。
今後の認知症対応の国家的基本軸の一つとなるのが “共生”、つまり認知症の人が暮らしやすい社会を目指すことですが、その具体化が進まない要因の一つがここにあると思われます。まして、コロナ禍で当事者も家族も集えない、意見交換の機会もない現状ではさらに難しいでしょう。
そこをどうするかが問題です。私は、伝え聞いたグッドプラクティスや、自分らの経験から次のようなことを考えてみました。
まずは、当事者の心に“パッと灯りがつく”きっかけが不可欠と思われます。きっかけづくりにおいては、文字は弱いかもしれません。それよりも、音楽という「聴覚」、写真などの「視覚」にともなう記憶のほうが、パワーが大きそうです。
具体例として、まず当時者と家族に集まってもらいます。そして、当事者本人の写真を綴じたアルバムと、その青年期のヒット音楽を素材とします。個人ごとのアルバムから自分の懐かしい写真を選び、当時を説明してもらいます。また、時代のヒット曲を録音、もしくは音楽療法家の生演奏で聴きます。このときの、認知症者の自律神経活動を測定するのです。
私たちは、交感神経と副交感神経の活動をリアルタイムで測定する装置を開発してきました。これを使えば、ある曲がある人に刺さったかどうか、つまり、心の高まりがわかります。そして個人ごとの発表中や聴取中の態度を、残りの皆で観察し、どこで集中が高まるかを評価します。その結果をもとに、当事者、家族、臨床心理士が合同で、“何をしたい”、“してほしい”を話し合うのです。
このように「願い」を抽出し、洗練された具体案にまとめていくのはどうでしょうか。誰もが無意識のうちに持つ「願い」を探り当て、それが実現するなら、当事者に望外の喜びを生むでしょう。それは介護の場に力を与えます。このような試みが、ポストコロナ時代にぐっと成長してほしいと、強く願います。
【参考文献】
*1 認知症施策推進関係閣僚会議「認知症施策推進大綱」
【認知機能の改善に】快脳冬虫夏草
年齢を重ねると、人の名前や物の置き場所を忘れてしまったり、判断力が鈍ってきたと感じることはありませんか?
「快脳冬虫夏草」は、そんな中高年の方の認知機能をサポートする、機能性表示食品です。
世界初発見成分「ナトリード」
冬虫夏草から抽出された希少な成分「ナトリード」には、
- 視覚的な記憶力(図形や空間を認識し、記憶する力)を維持
- 認知機能速度(視覚情報を素早く正確に判断し、行動する力)を維持
するのに役立つ機能が報告されています。
「快脳冬虫夏草」で期待できる効果
- 人の顔や名前を覚えやすくなる
- 物の置き場所を忘れにくくなる
- 判断力や集中力が維持される
- 日常生活の質の向上
| 商品名 | 快脳冬虫夏草 |
| 料金 | 11,000円(税込・送料無料) |
| 内容量 | 90粒(30日分目安) |
| 原材料名 | カイコハナサナギタケ粉末(国内製造)、マルトース/ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、二酸化ケイ素 |
| 1日摂取目安量 | 1日3粒 |
| 摂取方法 | 水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
本品は、事業者の責任において特定の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります