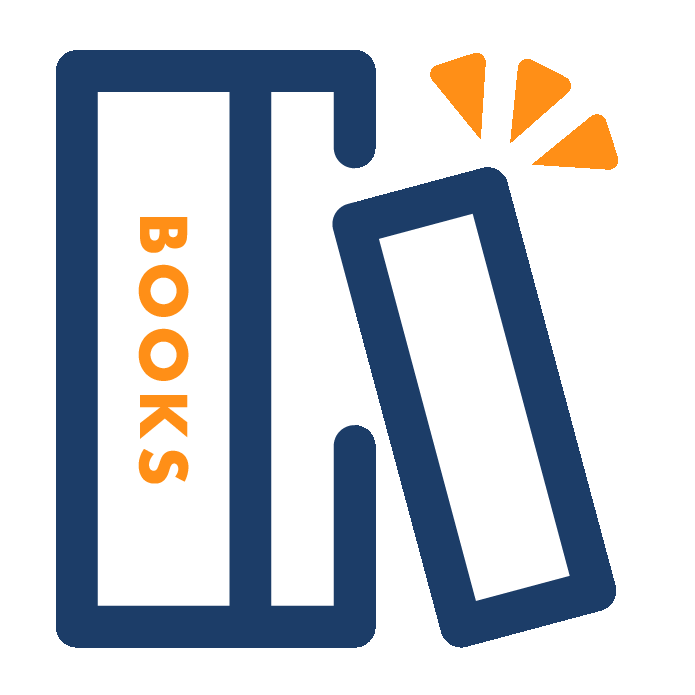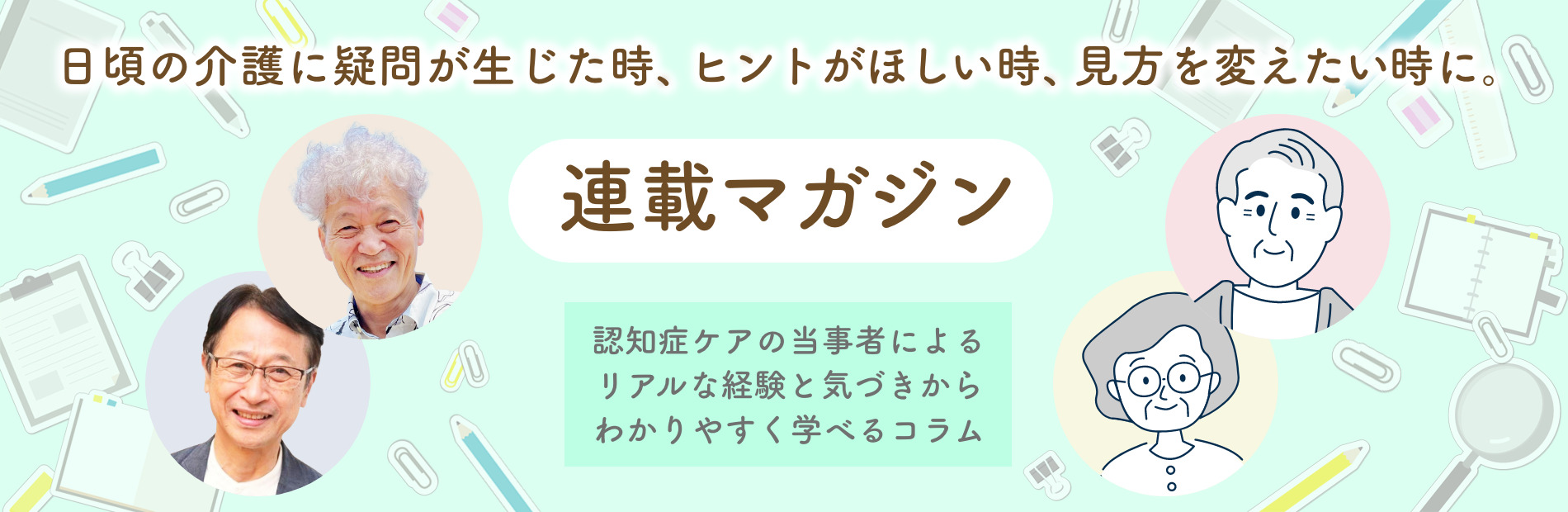誰かとコミュニケーションをとるとき、なるべく見た目の印象に惑わされることなく、お互いの関係性に見合った、公平で公正なやりとりを通じて、相手を正しく理解したいものです。
しかし、特に面識のない他者との間では、自分の態度や言葉遣いは、おそらく相手の見た目から、基準となる「何か」を無意識に引っ張り出してコミュニケーションをとっているでしょうし、またそうするしかありません。
その「何か」は、個人の人生、経験の中で醸成される偏見のことだと思います。偏見によって他者を理解し、また偏見によって自分も理解されている。人間関係は一筋縄ではいかない、その複雑さ、難しさ、面白さの根底にあるものなのではないかと思います。
普段の人間関係は、互いに誤解しながら、こじれたり、ややこしくなったり、反対にほぐれたり、打ち解けたりして育くめば良いのでしょうが、病気や障害のある方、認知症の方に対する見た目の誤解は、誤ったコミュニケーションやケアの大きな原因の一つとなります。
つまり、本当はできるはずのことが、できないものとされる、本当はわかっているはずのことが、わかっていないものとしてコミュニケーションやケアが進んでしまいます。言葉や体の動きが自由にならないことで、それに対してうまくノーを伝えることができない、本当の能力に気づいてもらえない状況があるのだとすれば、その本人はどれほどの屈辱を味わうものでしょうか。
例えば、食べ物をうまく飲み込めない方に対して、鼻から管を入れて直接胃や腸に栄養を流す経鼻経管栄養という処置があります。鼻に管が入っているだけでも、表情や頭、首の動きは乏しくなります。認知症の方が表情乏しく困り顔をされていることがあります。
私たちは、表情が乏しいというだけで相手を、受動的な人として接してしまうようです(顔の科学)。病気の方を受け身にさせ、余計な手出しをしてしまい、ますます動けない人にさせてしまう。原因は、ちょっとした見た目の偏見にあるのかも知れません。
人がそれぞれユニークな人生を経験する限り、偏見があるのは当然ですし、なくなるものではありません。自分にも、内なる声や表現されない感情があるように、病気や障害のある方、認知症の方も同じようにあるのを忘れてはならないと思います。その感情や表現の表出は、ただ小さい、少ないというだけです。だからといってその価値まで小さい、少ないのではありません。
参考図書
ジョナサンコール著、茂木健一郎監訳:「顔の科学」自己と他者をつなぐもの、PHP研究所、2011年