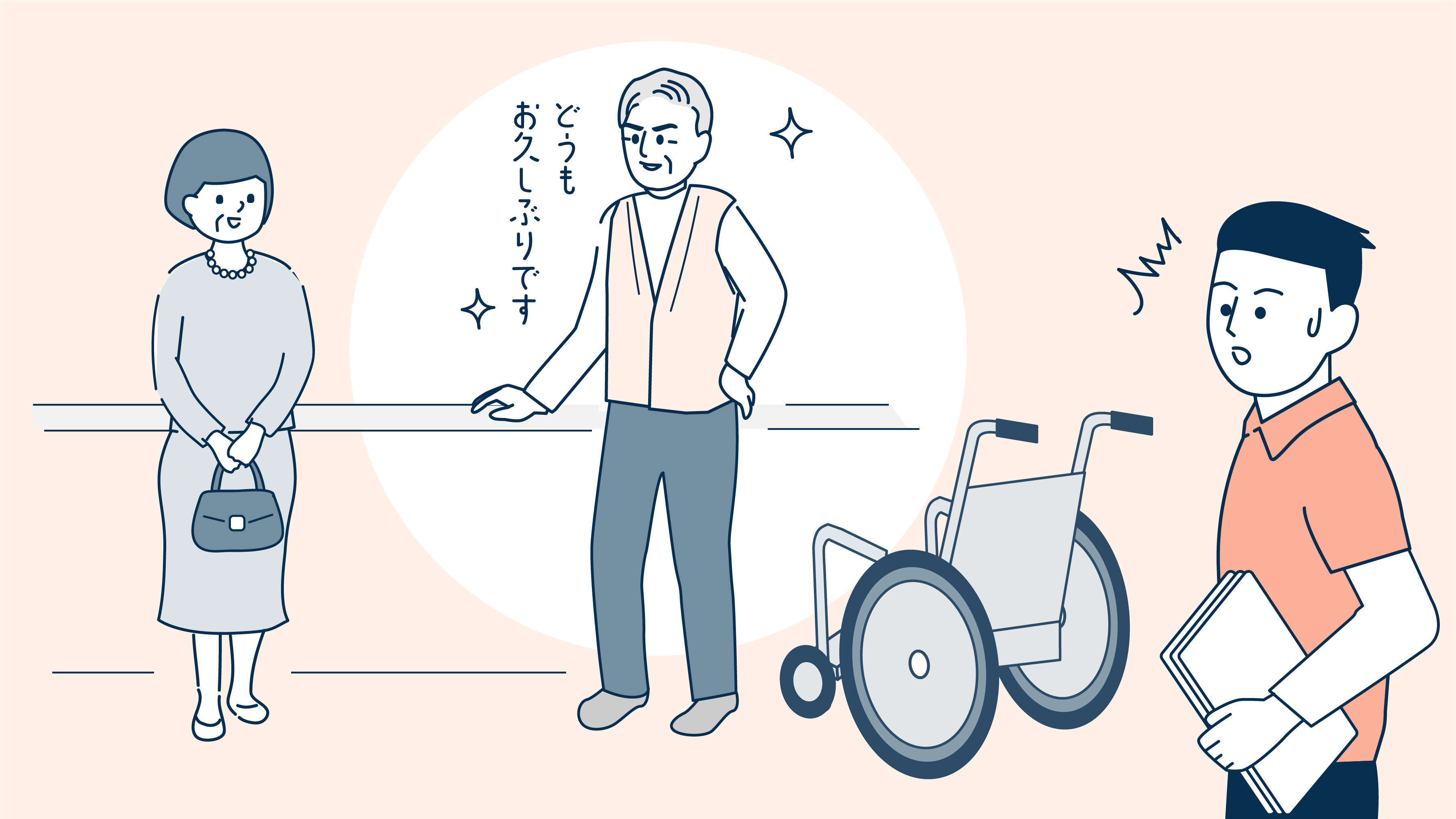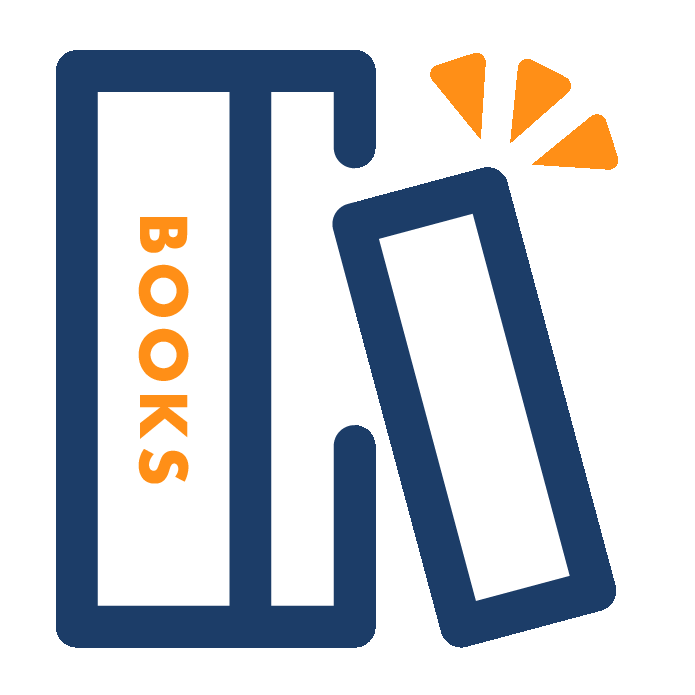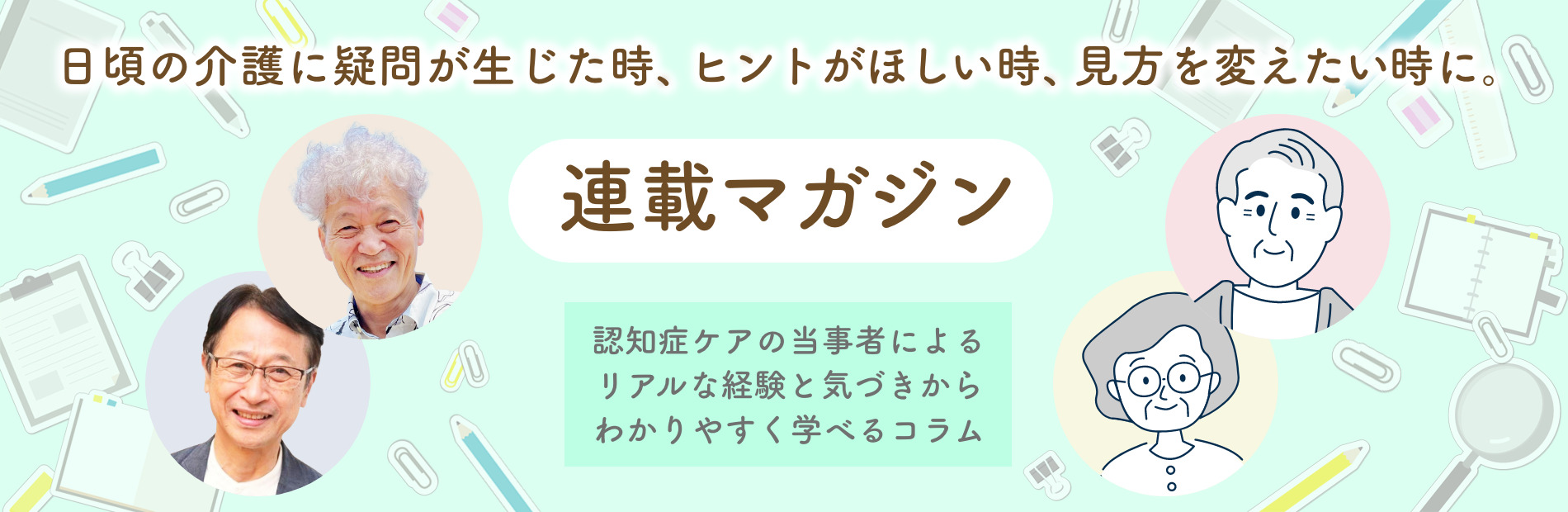私は、全国の様々な施設を訪問し、認知症の高齢者の方と初対面で関わりを持たせていただくことがあります。関わりを通じて、その方の生活動作にどのような力が残されているのか、職員の皆さんと考え日々のケアに活かしていくのが目的です。
その際に、私と高齢者の関わりを見ている施設の職員から、よく聞かれる言葉があります。それは、「いつもこんなに動いてくれないのに」、「いつもはこんなにお話されないのに」というものです。
もちろん私が特別な技術を持っているわけではありません、おそらく初対面のお客さんである私に対して“よそ行き”で応対してくれていたのだろうと思います。
つまり“格好をつけて”、良いところを見せてくれているということです。しかし、“よそ行き”であろうが“格好つけ”であろうが、大切なのは本人にその力があるという事実です。
本人が見せてくれる“よそ行きの力”には2つの大きな意味があります。まず、普段ケアにあたっている職員や、同席した家族が、本人の“よそ行きの力”を目の当たりにすることで本人に対する見る目が変わることです。
“できることは自分で”というのが介護の基本というのは誰も否定しないと思います。しかし、そもそもできることに対する気づきがなければ、結果的に過剰な介護をしてしまっているかも知れないのです。
一度でも“よそ行きの力”を見ると、普段の生活でもその力が目につきやすくなります。例えば、非常に分かりにくい間違い探しの絵も、一度気づいてしまうと次からは嫌でもその違いが目に入ってきます。一度の気づきが大切なのです。
もう一つの大切な意味は、本人が自分の能力に対して自信を取り戻すことです。介護を必要とする生活の中で、できないことと、やらなくなっていることの境があいまいになっている方がいます。
身体機能から見て間違いなくできそうなことも、「いや無理だわ」と簡単にあきらめてしまっている場面も多くみかけます。そこに私というお客さんが現れて、一人の大人として振る舞いもてなしてくれる。
例えば、挨拶をしようとベッドから起き上がろうと動き出してくれます。それは“よそ行き”の姿なのかも知れません。しかし、できない、やらないはさておき、一人の大人として応対しているとき、認知症も何もない、その人の素の力が表れるのです。
できないを意識せずに動き出すときに、体で覚えた記憶がよみがえるからです。できないではなく、やらなくなっていたのだと本人が自信を取り戻します。
その人の素の力を知るために、施設であっても在宅であっても、よそ行きの場面をあえて作ってみてはいかがでしょうか。