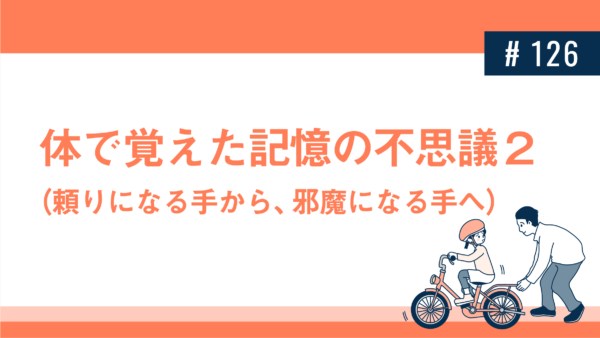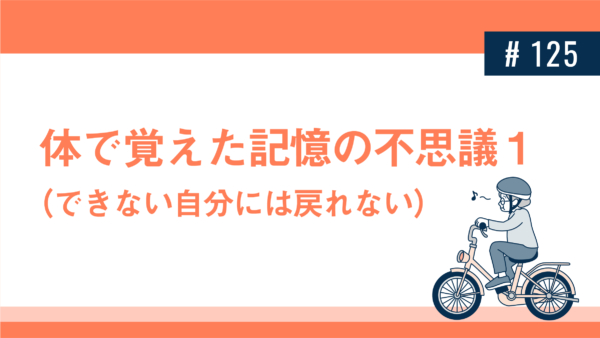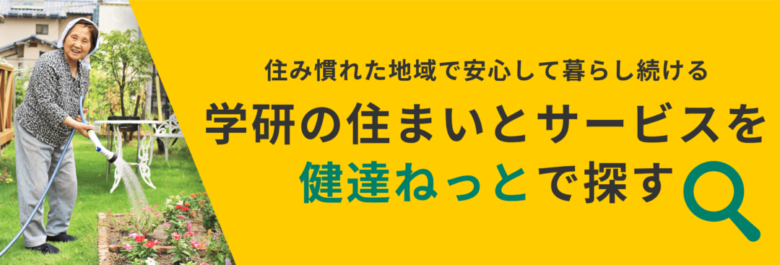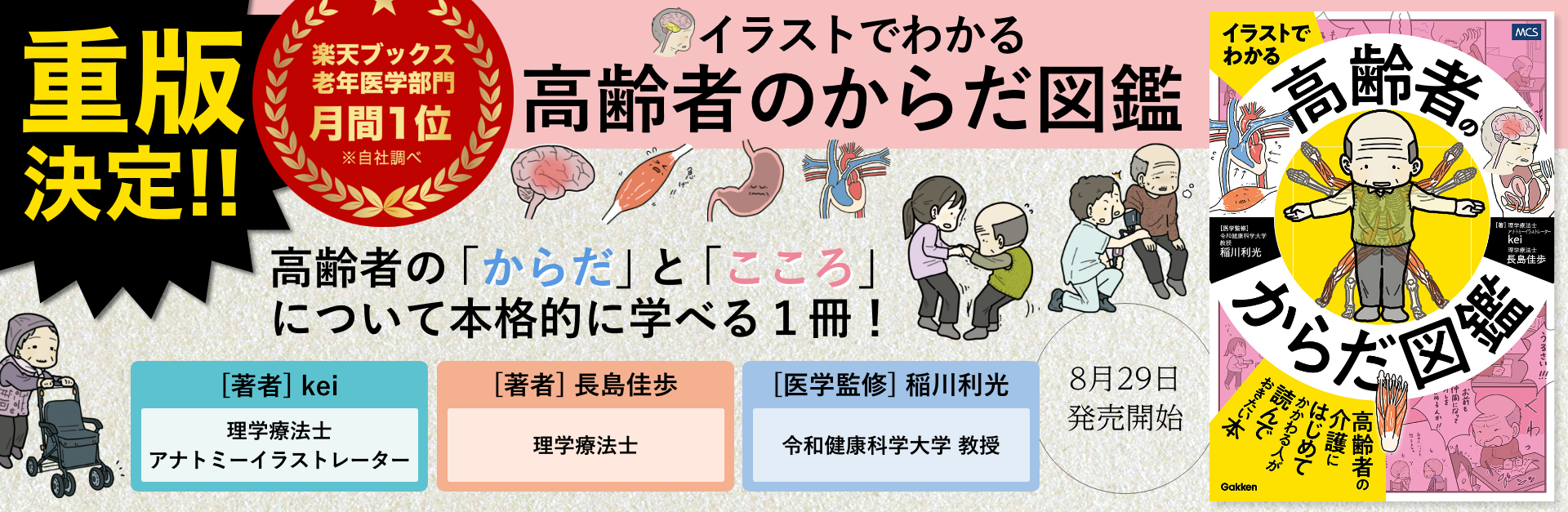介護福祉士の土橋壮之(つちはしまさゆき)と申します。
みんなからは、「ツッチー」とか「ツッチーさん」と呼ばれています。なので、みなさんにも気軽にそう呼んで頂けたらうれしいです!
2017年ごろ、私はイギリス・ロンドン郊外のジェラーズクロスという街の、Chiltern House(チルターンハウス)という障がい者施設でボランティアをしていました。
Chiltern Houseという名前も、なんだか可愛らしくて、イギリス英語風に言えば「LOVELY」です。

「LOVELY」という言葉の魅力
イギリスでは「LOVELY」という言葉は、すばらしいとか、おもしろいとか、いろんなニュアンスを含めて、とにかくよく使われます。
花がきれいに咲いていたら「LOVELY」、いい香りしたら「LOVELY」、ジョークが面白かったら「LOVELY」、仕事がうまくいったら「LOVELY」。
つまり、良いことがあったら、なんでも「LOVELY」!
僕のキャラクターもあったかもしれませんが、入居者さんたちから、何かするたびに「LOVELY」と声をかけてもらっていました。
「ありがとう」とか、「よくやった」みたいな意味合いで遣われる「LOVELY」というニュアンスや、間の取り方が、なんともイギリスっぽいなぁと感じました。
「管理」より「ゆとり」を大切にする姿勢
日本で働いていた時は、起きる時間や、ご飯を食べる時間、水分量から、排せつの時間もなんでも、その通りに動かなければならず、工場のものづくりのように「管理、管理」でした。
スタッフも入居者さんもなんだか窮屈な気分だったのを覚えています。
でも、イギリスのこの施設では、起きる時間も、ご飯を食べる時間もすべて自由。
自由といっても、スタッフと入居者さんのタイミングやコミュニケーション次第で、いつまでも起きてこれない方もいたりして。
日本人の感覚からすると、「なんだか適当だな」とか、「いい加減だな」と思う時もありました。でも、そんな「いい加減さ」や、「ゆったりとした間」こそが、日本の「管理、管理」と違って、イギリスらしい「LOVELY」な介護だなぁと感じました。
イギリスの食事ルーティン事情
さて、イギリスといえば、ご飯がまずいとよく言われますが、これほんとにそうでした。
全体的に味がないことが多かったです。「自分で味をつけて食べてください」というスタイルなのかもしれません。

ちなみに、イギリスでは「Dinner」というのは、一日のうちで最も豪華な食事を指します。なので、この施設では、昼食が「Dinner」で、夕食は「Supper」でした。
入居者の朝食は、起きてきた人から、オートミールや、ポリッジ(小麦粉のお粥みたいなもの)、あとは果物で、日本人からすると、「これだけでいいの?」と思うほどシンプル。
でも、準備と片付けは楽です。
基本的には、入居者と同じ施設の料理を食べさせてもらっていたんですが、金曜日は「フィッシュ&チップス」、土曜日は「イングリッシュブレックファスト」、日曜日は「サンデーロースト」と、金曜、土曜、日曜は毎週必ず、同じメニューでした。よく飽きないなあと思います。
日本では、管理栄養士さんが献立を考えて、朝食、昼食、夕食、1か月30日間それぞれ違うメニューが出てきますよね。ほんとうにすごいことだと思いました。

僕は2か月目で飽きて、もう食べたくないって思ったんですが、1年たって、イギリスを離れるころには、体が金曜日はフィッシュ&チップス、土曜日はイングリッシュブレックファストを求めるようになっていました! 習慣って面白いですね。
嚥下食は「マッシュ」がキホン!
日本だと、嚥下の難しい方のために様々な工夫や、食形態があります。イギリスでは、基本的には、「マッシュ」です。
マッシュポテト、ちょっと味の違うマッシュポテト、マッシュ野菜。マッシュ肉。それにトロミをかけて食べる。
もう、なんでも「マッシュ」!
そんな感じだったので、私は食に関しては、やっぱり日本のほうがいいです。
ただ、トロミに関しては、ネスレのスタッフが来て講習をしたり、飲み物や、食べ物にどのようにトロミをつけるか、勉強会や知識のテストを定期的に行っていました。
こういった専門的な教育体制は、整っている印象でした。
イギリスの介護は「LOVELY」な多文化共生
勉強会を開いたりするのは、日本でいう「ケアマネ」的な立場の、ソーシャルワーカーです。驚いたのは、そういった管理する側の立場の方がイギリス人ではなく、ポーランド人なのです。
当時、日本ではまだ、「外国人が日本人を介護する」こと自体珍しかった時代。
ましてケアマネや管理者まで外国人が担っているというのは驚きでした。日本もいまでは、だいぶ変わってきましたけどね。
そのポーランド人ソーシャルワーカーの方は、10年以上前にイギリスに移り住んで、いろいろ資格を取って、少しずつこういった立場になっていたそうです。施設には、スタッフが30人ぐらいいたのですが、イギリス人は施設長を含めて10人もいませんでした。
当時はまだ、イギリスはEU加盟国だったので、ポーランド、ブルガリア、バルト三国など東欧諸国の人たちが多く働いていました(他にもインド人や、アイルランド人などもいました)。私はあまり英語が話せず、なかなか苦労していたのですが、そんなとき、助けてくれたのは、ポーランドの方たちでした。
僕のたどたどしい英語でも、伝えたいこと、言いたいことを何とか理解してくれて、そこから困りごとが解決していくことが何度かありました。
同じように入居者さんに対しても、ポーランド人のスタッフは、ぜんぜん急かしたりしないで、ゆっくりした食事、排せつ、入浴の中で、伝えたいこと、聴きたいことをよく聞いている感じがあって、とても「LOVELY」な介護しているなぁと感じました。
外国人介護スタッフが日本の未来を担う?
その時、聞いた話では、東欧諸国がEUに入ったのが2000年代前半で、そのころは、移民が福祉や介護の仕事に就くというのはまだ珍しかったそうです。しかし、徐々に市民権を獲得し、10年以上たった今では、イギリスの福祉業界に欠かせない存在になっているとのことでした。
その時は、日本ではまだ、技能実習制度や、特定技能制度が始まる前でしたが、「いつか日本も、多文化共生の介護をする時代が来るのかもしれない。」と思いました。
日本人の介護職にも、優秀な人もいますが、制度や環境から、疲弊してしまっている部分もあります。海外からやる気のある人がたくさん来て、そういう人たちがこれからの日本の介護を引っ張っていくんじゃないかって、そんな未来が見えたんです。

Chiltern Houseの惜しまれる最期
2020年、イギリスはBrexit(Britain+Exitの造語で、イギリスのEU離脱を示す)により、EU圏内からの自由な労働者の往来は難しくなりました。その流れを受けて介護業界の労働力不足となっていきました。
そして2024年2月、Chiltern House(チルターンハウス)は閉鎖となりました。
施設の入居者さんたちは、署名運動や、入居者さん自身がプラカードを持って街中に出向いて、閉鎖に反対し必死の声をあげ、その様子はニュースにもなりました。
しかし残念なことに、あの「LOVELY」な場所は、もうなくなってしまいました。
私が過ごしたChiltern Houseは、多文化共生の中で介護が実践され、レジデンツの意思を尊重するイギリスらしい自由な施設でした。その場所がなくなってしまったことは、とても残念でなりません。
当時の入居者さんたちの運動の様子がニュースに残っているので、URLを貼っておきます。