認知症が引き起こす症状の中に、不眠症状があります。
認知症と不眠の間にはどのような関係があるのでしょうか。
今回は、認知症と不眠の関係について以下の点を中心に解説します。
- 認知症の方の不眠症状
- 不眠を引き起こす原因
- 不眠が改善されない場合の対処法
認知症による不眠と向き合うためにも、参考にしていただけると幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
スポンサーリンク
高齢者の睡眠問題

まず、高齢者の睡眠問題とは何があるのでしょうか?
解説していきます。
睡眠障害とは
睡眠障害とは、何らかの原因で睡眠に異常をきたす障害のことです。
睡眠障害は主に以下の3つがあります。
- 入眠障害
- 中途覚醒
- 早期覚醒
順番に解説します。
入眠障害
布団に入ってもなかなか寝付けず、30分~1時間経っても眠れないことを苦痛に感じる状態です。
睡眠障害の中では最も多く、不安や緊張が強い時に起きやすいといわれます。
中途覚醒
睡眠中に何度も目が覚め、その後なかなか寝付けない状態のことをいいます。
中高年から高齢者の方に多い症状です。
早期覚醒
早起きの次元を超え、自分が望む起床時間の2時間以上前に起きる状態です。
高齢化によって体内時計が崩れるため、高齢者の方に起こりやすい睡眠障害といえます。
高齢者の睡眠
睡眠は、年齢と共に変化していくものです。
高齢者の方は、退職や死別、一人暮らしに対する不安が他の年代に比べ大きくなります。
また、アルコール依存症やうつ病などの影響によって睡眠障害が起きる可能性があります。
不眠や眠気の症状を感じたら、原因を突き止めるためにまずは受診することが大切です。
通常の睡眠薬では治らない睡眠障害は以下のとおりです。
- 睡眠時無呼吸症候群
- レストレスレッグス症候群
- 周期性四肢運動障害
- レム睡眠行動障害 など
上記のような睡眠障害が疑われる場合は、専門施設での検査と診断が必要です。
睡眠障害を起こさないようにするためには、
- なるべく日中に活動する
- 規則正しい生活を心がける
- 夜間睡眠の妨げになるようなことはしない
などを意識することが大切です。
スポンサーリンク
認知症と不眠症状

認知症の不眠の原因は、認知症の種類によって異なります。
ここではアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の特徴的な不眠症状を解説します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症による不眠には、以下のような特徴があります。
- 睡眠時間が減る
- 眠りが浅くなる
- 夜間に何度も覚醒する
- 昼夜逆転傾向になる
活動と睡眠がだんだんと乱れていき、重度になると1時間眠ることも難しくなります。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症に現れやすい症状の1つに幻視があります。
そのため、アルツハイマー型認知症の不眠症状に以下のような症状が加わります。
- 眠っているのに手足をバタバタと動かす
- 悪夢をみて飛び起きる
- 眠っているのに急に叫ぶ
- 急に起き上がってわけのわからない行動をする
基本的には、不眠症状の初期に多く見られる症状です。
認知症の方が不眠になった時の対応方法

認知症の方が不眠になると、本人は不安が増し、認知症が悪化してしまう原因になります。
不眠の改善には生活リズムを整え、患者の不安を軽減する必要があります。
以下の項目に分けてポイントを解説します。
日光を浴びる
人の体内時計は日光を浴びることで整います。
そのため、夜なかなか寝付けなくても同じ時間に起きて朝日を浴びる習慣をつけることが大切です。
朝日を浴びる事で体内のメラトニンという物質が作られ、体内時間が正しくセットされます。
カーテンを開けて窓越しで日光浴をするだけでも効果があるので、ぜひやってみてください。
環境を変える
寝具の種類や部屋の明るさなど、本人が落ち着く環境を作ります。
真っ暗にしてしまうと不安になるのであれば、直接光が目に入らないように間接照明を使います。
暖かく柔らかい光なら心地よく眠りに入る事が出来るでしょう。
眠れなくてイライラしていると眠りにつけなくなってしまいます。
そんな時は一度寝室を離れ、落ち着いてから寝室に戻るなど気分を切り替えると良いです。
足先を温めるとリラックス効果があるため、足湯や入浴後冷えないように気を付けましょう。
生活サイクルを見直す
毎日規則正しく、同じリズムで過ごすのが良いとされています。
日課表を掲示し、同じサイクルで過ごす事で習慣化していきます。
認知症の患者は急な変化にストレスを感じるため、効果的な方法です。
最初はつらくても、家族と一緒に規則正しく生活していくとリズムが整ってくるでしょう。
活動量を増やす
日中の活動量が少なければ、疲れていないため熟睡できません。
日中の活動量を増やすために、趣味を楽しむ時間をつくったり、散歩など適度な運動を取り入れると良いです。
また、日中家にいる人が減ったり、1人になる機会が多い方はデイサービスを利用しましょう。
人と交流をもつと刺激になるので日中の活動が促されます。
軽食やマッサージ
夕飯を食べすぎると、消化に時間がかかり不眠を引き起こす可能性があります。
夕食をヘルシーにし、消化に時間がかからないようにしましょう。
しかし、ヘルシーな食事を意識しすぎて、あまりに空腹だと眠れなくなるため、負担にならない程度に行いましょう。
また、マッサージなどのリラクゼーションも効果的です。
心地よく、リラックスした状態では副交感神経が優位になるため、ぐっすり眠ることが期待できます。
不安を取り除く
不安があるとなかなか寝付けないのは健康な時も同じです。
本人がどんなことを不安に思っているのかきちんと聞いてあげましょう。
すぐにその不安が解消出来なくても、話す事ですっきりする場合もあります。
また、気持ちの問題以外にも寝室の環境に不安を感じる場合もあります。
本人が心地よいと感じる環境作りが大切です。
睡眠パターンを観察する
不眠症の改善には、その人の睡眠パターンを把握する事が大切です。
睡眠日記などをつけることをおすすめします。
何時ごろ起きていて、次に眠りにつくまでどれくらいかかるのか記録しましょう。
薬の副作用を確認する
薬の副作用や、飲み合わせによっては、興奮を誘発し睡眠を妨げたり、睡眠の質を下げる原因になる場合があります。
また、薬を長く内服することで不眠が起きることもあるので注意が必要です。
不眠が気になり始めたら、医師に相談し処方箋の確認をしてもらいましょう。
すでに睡眠導入剤などを処方されている場合は、内服する時間を守ることも重要です。
内服する時間を日によって変えてしまうと、正しいリズムが付かず不眠症が悪化してしまいます。
薬を処方されていて、不眠に困っている方は一度医師の方の診察を受けることがおすすめです。
認知症が不眠を引き起こす理由

一般的に高齢者は睡眠の質が落ち、身体的な特徴からも不眠症を引き起こしやすいとされています。
さらに認知症の患者は症状の経過とともに不安が強くなるため不眠症を併発しやすいのです。
そこで、認知症になるとなぜ不眠を引き起こしやすいのかについて解説します。
脳の機能低下
脳には体内時計をつかさどる視床下部や松果体と呼ばれる場所があります。
認知症は脳が委縮したり、脳細胞が破壊されて起こる病気です。
そのためこの視床下部や松果体という場所も病気の影響を受け、機能が低下します。
人の体内時計はメラトニンなどの影響を受けるため、脳の機能低下によりリズムが崩れやすいのです。
活動量の低下
認知症になると家にひきこもりがちになる場合も多いため、活動量が低下します。
日中活動しなければ疲れないため眠りにくく、認知症そのものの悪化にもつながります。
意識的に日光浴を取り入れ、日中の活動を増やしていく必要があります。
見当識障害
見当識障害は時、場所、人の順にわからなくなっていく症状です。
見当識障害によって、時間の感覚が乱れて理解できなくなるので、昼夜逆転が起こりやすくなります。
昼夜逆転すると、昼間に眠くなり昼寝が増えることでより夜に眠れなくなります。
夜しっかり眠るためにも、昼寝をしないように心がけましょう。
夜間せん妄
夜間せん妄とは、せん妄の中でも夜に混乱や興奮をきたす症状です。
せん妄は短期間で一過性に起こる症状なので正しく理解し早期に対処すれば改善していきます。
しかし、夜間の興奮が続くと不眠が習慣化してしまうため、夜間せん妄の症状が起きたら原因を探って、取り除きましょう。
過去のトラウマ
認知症の方の中には、過去の出来事と現在の出来事を正しく認識できない方もいます。
つまり、過去に起きた嫌な経験や、怖かった事を思い出し、現在起きていると勘違いするため、恐怖や不安で眠れなくなります。
寝つきにつく前の感情が原因となるため、入眠前は話題に注意し、明日の楽しみや、本人の好きな話をするようにすると、予防できます。
不快感
認知症の方が、不快感をうまく表現できていない可能性もあります。
どこかに苦痛や不快感を感じても表現できないため、落ち着きがなくなり、紛らわそうとする方が多いです。
よくある原因は寝衣が合っていなかったり、おむつが汚れていることです。
本人は認知症の影響で自分の意思を伝えにくいので、周りの方が観察して、苦痛や不快感を取り除いてあげましょう。
認知症の不眠が改善しない場合
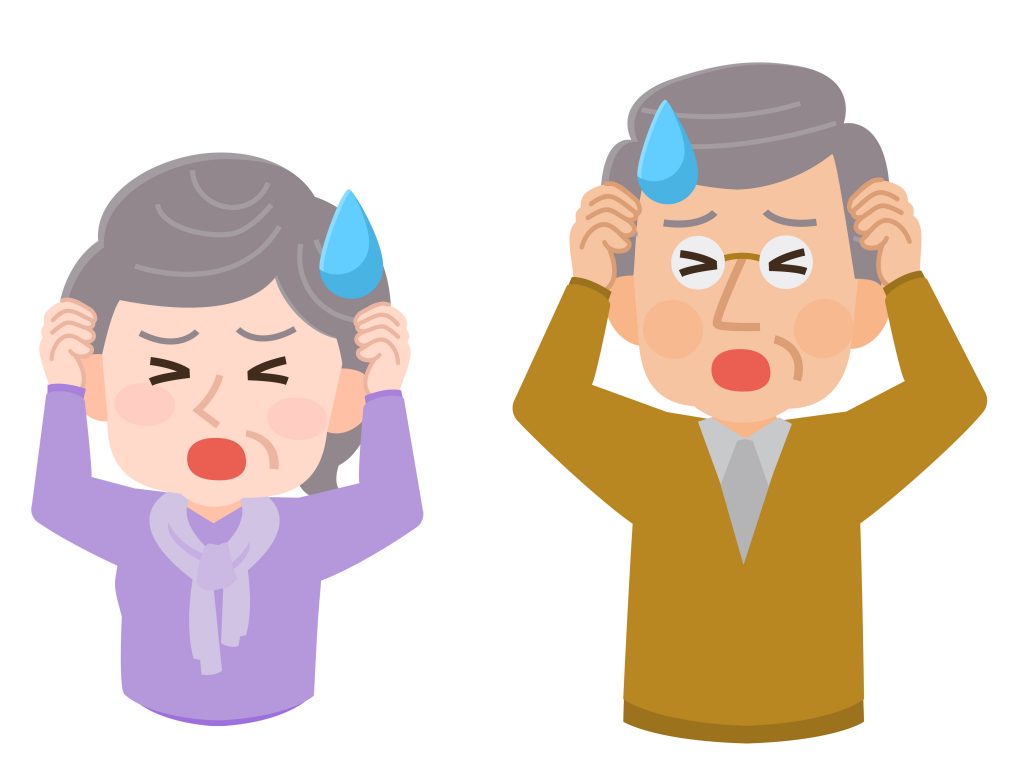
家庭で出来る様々な取り組みをしても不眠が改善されない場合もあります。
そのままにしていても改善は難しいため、以下のような対策を取りましょう。
医師に相談する
充分な睡眠がとれない場合、本人はもちろん、家族の負担も増えます。
不眠に悩む期間が長ければ長いほど、家族の疲労が蓄積し疲弊してしまうのです。
あまり悩まず、初期からかかりつけ医に相談しましょう。
睡眠薬
医師へ相談すると軽めのものから、その人にあった睡眠薬を処方してもらえます。
生活リズムを整えながら薬の力も借りて、睡眠の質を改善していきましょう。
よく処方される睡眠薬の効果を簡単に解説します。
ゾルデビム
主に寝つきが悪い時に処方される事が多い薬で、朝まで残りにくいとされています。
作用時間は2時間と効果は短時間です。
ゾビクロン
寝つきが悪い時に処方される薬で、効果が4時間と少し長くなります。
エスゾビクロン
比較的新しい薬で、副作用が出にくい事から高齢者に処方されやすい薬です。
眠りを深くして途中で起きないようにする作用があります。
ラメルテオン
他の睡眠導入剤の補助として処方される事が多く、夜は眠くなるようリズムを整えます。
効果は弱く、ある程度飲み続ける事で効果を発揮する薬です。
クエチアビン
興奮や混乱を鎮める作用があり、効果は4時間持続します。
やや効果が強い薬なので、ふらつきなどの副作用に注意して内服します。
認知症と不眠のまとめ
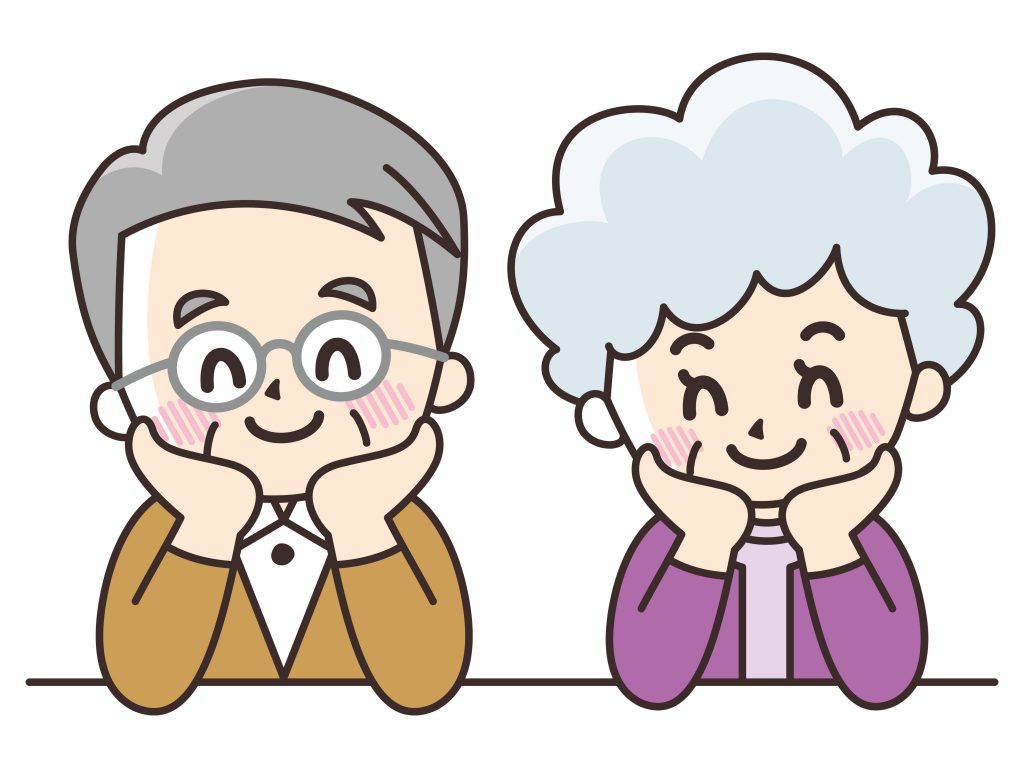
ここまで、認知症と不眠の関係についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 高齢者が認知症になると、不安などの間接的な理由が加わり不眠を発症しやすい。
- 生活リズムを整え正しく生活することや、日光浴が効果的。
- 見当識障害による強い不安や夜間せん妄など、不眠を引き起こす原因はいくつもある。
- 不眠が改善されない場合は早めにかかりつけ医を受診する。
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


















