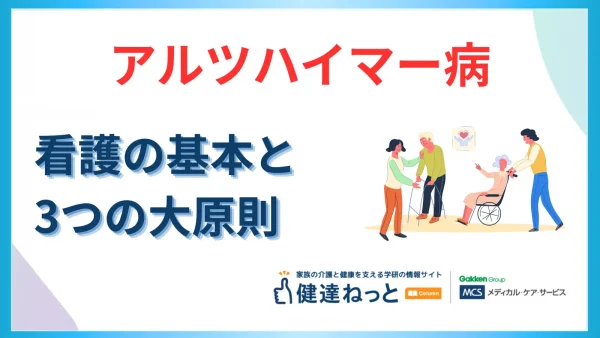超高齢社会の日本において、年々認知症の方は増加しています。
認知症の方による電話のトラブルがあることを知っていましたか?
ここでは認知症の方が電話をかける理由やその対処法などをお伝えします。
- 電話を頻繁にかける原因
- 電話を減らす対処法
- 実際の電話によるトラブル
- 電話以外のコミュニケーションツール
認知症の方による電話トラブルで困っている方のお役に立てば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
認知症患者が電話を頻繫にかけてしまう原因

認知症の方が頻繁に電話をかけてしまう理由は何が原因なのでしょうか?
以下項目ごとに解説していきます。
不安感や混乱
認知症の方は自分自身について強い不安や恐怖を抱えています。
一つずつ何かができなくなり、大事な人を忘れてしまうという自分に自信を無くします。
そのため、一人で生活している場合、家族から見捨てられているという感覚があるかもしれません。
強い孤独感と、現状に対する不満や助けを家族に伝えたいと感じるでしょう。
認知症の方本人の意思を尊重したうえで電話対応しましょう。
電話したこと自体を忘れている
認知症には記憶障害があるため、電話したこと自体を忘れてしまうことがあります。
また、電話をした後に電話の相手や内容を聞いても覚えていないことが多くなります。
そして、本人の精神的な不安定さと認知症の症状の両方で、何回も電話をかけるといったことが起きます。
そのため留守番電話設定にし、電話を取らなくしたり、録音したりするなど工夫しましょう。
物盗られ妄想による電話
認知症の方が電話をする理由として何かの被害を受けていると訴えてくる場合があります。
「誰かがお金を盗んだ」と訴えるのは記憶違いと精神的な不安によることが多いです。
自分が認知症であると認めたくない不安があり、その感情から結果的に「誰かが盗んだ」と考えてしまいます。
ご家族の対応としては、認知症の方の記憶が失われ、居場所や役割がなくなる恐怖を癒してあげることが大切です。
電話の内容が妄想なのか真実なのかを冷静に聞き、認知症の方の深層心理を感じ取りましょう。
スポンサーリンク
認知症患者の電話を減らす対処法

上述した通り、認知症の方は不安を抱えきれず、ご家族などに頻繁に電話をかけてきます。
そうするとご家族は忙しい中で時間を取られることにストレスを感じるでしょう。
ここからは、認知症の方が電話をかけてくる頻度を減らす方法についてご紹介していきます。
電話をかけてくる原因をさぐる
認知症の方の行動や発言には、何らかの理由があることが多いです。
生活に何か問題が発生し、自分の体調に関する不安を訴えている場合もあります。
そのため気持ちに余裕を持って、ご本人の話す内容をゆっくり聞いてみましょう。
現在の病状や生活の困難などを把握するきっかけになります。
実際に問題が起きていれば早い段階で問題を解決でき、電話の回数が減るかもしれません。
また、診察の付き添い時に、医師に普段の状況を伝えることで適切な治療に繋がります。
繋がる時間帯を制限
介護者や家族の都合をベースに、電話を受ける時間を決めましょう。
本人に電話ができる時間を伝え、その時間帯に連絡をするようにお願いをします。
しかし記憶障害があるため、電話を何度もかけてくるかもしれません。
また電話が繋がらない場合には、不満をぶつけてくる場合もあるでしょう。
周囲の方々が無理をしないようにバランスをとり、電話をする時間を決めましょう。
家族から電話をかける
決まった時間にご家族から電話をしてみましょう。
同じ時間に電話がもらえることを本人が理解すると、定期的に話ができることに安心します。
認知症の方の孤独感が完全になくなることはなくても、家族と話せるのは心強いです。
そして電話の時間を習慣化できれば、お互いの精神的な負担は減るでしょう。
電話内容に工夫を行う
認知症の方の不安を聞くことも大切ですが、それでも不安が完全に消えることはないでしょう。
ときには、会話の切り口を変えて楽しい会話をすることでお互いの心を明るくすると良いです。
楽しい会話をすることで、孤独や恐怖感から気分転換でき電話をすることへの意識が薄れる場合があります。
認知症の方が楽しめるような会話を心がけましょう。
外部のサポートを活用する
対応に限界を感じるようであれば、相談窓口などで人の助けを借りましょう。
一人で抱え込まず地域などのサービスを利用しましょう。
下記は認知症に特化した相談先ですので、秘密は守られ安心して利用できます。
- 地域包括支援センター
- 認知症に関する電話相談
- 認知症疾患医療センター
こちらに詳しく掲載されています:福祉・介護認知症に関する相談先
認知症患者の実際の電話トラブル

高齢の認知症の方が販売購入してしまう形態の4割が訪問販売、3割が電話勧誘販売です。
健康食品や新聞の購入をしてしまいトラブルに発展することが増えています。
ここでは買い物にかぎらず認知症の方に起きている具体的な問題をみてみましょう。
テレビショッピングでの注文
買い物に関する相談や問題は、認知症の方の中で多々起きています。
「認知症の母親がテレビショッピングで健康食品や電化製品を勝手に購入しました」といった事例が多発しています。
返品ができるかは事業者によりますし、対応も様々ですので確認する必要があります。
また事業者によっては今後、注文を受けないように対応してくれるところもあるので一度聞いてみることをおすすめします。
対応しきれない場合は、成年後見制度の利用を検討するのも方法の一つです。
そもそも勧誘に対して的確な判断ができないため、販売対応をさせないことが重要になります。
警察や救急への電話
認知症の症状で突然救急車や警察を呼んでしまったという相談がたびたびみられます。
「お金を取られた」などの被害妄想や物盗られ妄想は認知症の代表的な症状です。
本人は本当に危機感を感じて警察などに助けを求めています。
発信制限のある電話機に変えたり、施設入所を検討したりするなどといった対応を考えましょう。
携帯電話の紛失
認知症の中核症状に物忘れがあるように、認知症の方は自分が行ったことの多くを忘れてしまいます。
具体的には、「ATMに行ってお金をおろしたら、お金と携帯をその場に忘れてきた」などが発生します。
携帯電話や鍵、財布、お金などの置き忘れはよく起こります。
対策としては、GPS付きのタグをつけるなどして、モノの所在地をはっきりさせることが考えられます。
記憶障害によるものですから本人を責めず、具体的な対策を取るようにしましょう。
家族に10回以上電話がくる
認知症の方は、自分の症状に対する不安を常に感じています。
そのため、下記のように頻繁に電話がかかってくるという相談は非常に多くあります。
- 3分おきに電話がかかってくる
- 電話の内容が毎回同じ
自分だけで対応せずに専門家に相談し、地域や施設などに助けを求めましょう。
認知症と電話のまとめ

ここまで認知症の方の電話にまつわるトラブルやその対処法をお伝えしました。
病気による問題は根本から改善することは難しいので対処を工夫することが必要です。
以下は本記事のまとめです。
- 電話を頻繁にかけるのは記憶障害による場合と実際に問題が起きている場合
- ご本人の病気への不安を減らし会話内容を工夫すると電話回数が減る可能性がある
- 電話によるトラブルの多くはテレビショッピング、訪問販売、電話販売
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。