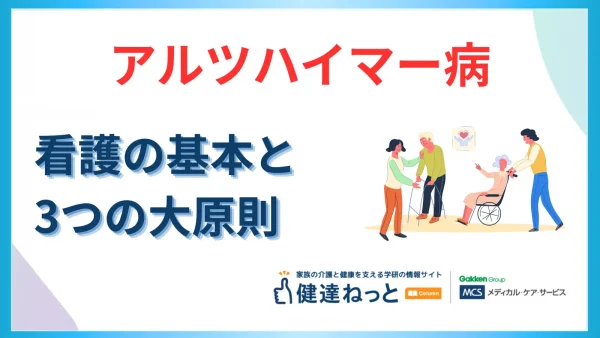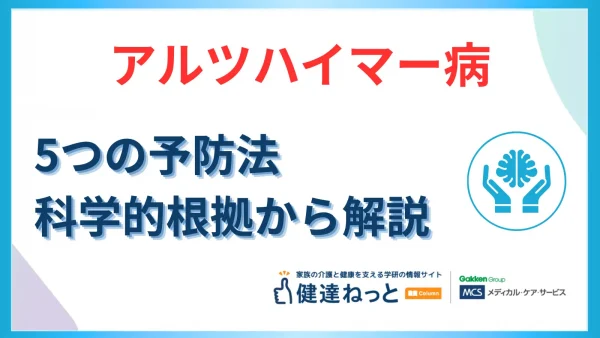超高齢社会の日本において、年々増加している認知症。
重度になればなるほど介護の負担も大きくなります。
では、進行が進むと具体的にどうなるのかご存知ですか?
スムーズに介護するためにも事前に把握しておくことが大切です。
今回は、重度の認知症について以下の点を中心にご紹介します。
- 認知症が重度になったときの症状
- 認知症の進行具合
- 認知症治療を中止する時期
- 認知症が重度になったときの心構え
不安を解消するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
重度の認知症症状(種類別)
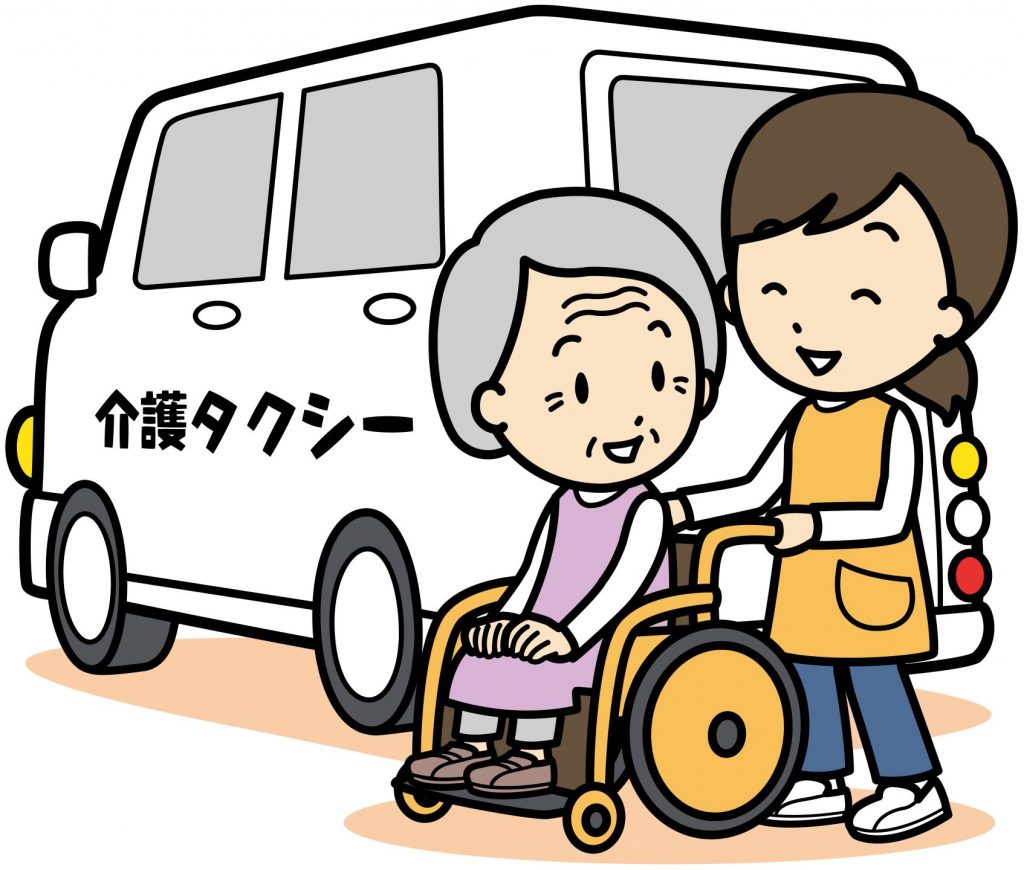
認知症は、軽度認知障害、軽度、中度、重度と段階を踏んで進行します。
認知症が重度まで進行した時にできなくなること、現れる症状についてご紹介します。
代表的な認知症の種類別にまとめました。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、全認知症の半分以上を占める代表的な認知症です。
脳全体が少しずつ萎縮して、認知機能が低下していきます。
できなくなること
重度のアルツハイマー型認知症は、寝たきりに移行していきます。
家族の顔や会話の仕方が全く分からず、排泄の失敗などが常態化する方が多いです。
症状
代表的な症状は以下の通りです。
- 身体能力の低下
- 自発性や意欲の低下
- 転倒
- 排泄の失敗
- 筋固縮(筋肉がこわばり、身体がスムーズに動かない)
- 嚥下障害(食べ物を飲み込めなくなる)
脳血管性認知症
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血などによって起こる認知症です。
脳の場所や障害の程度によって現れる症状が異なります。
脳血管性認知症は、比較的男性の方が多いです。
また、症状にばらつきがあるため「まだら認知症」とも呼ばれています。
他の認知症と違い、時間の経過とともに進行するわけではありません。
脳循環が悪化するたびに進行します。
できなくなること
感情をコントロールできなくなります。
普通に歩行できなくなり、小刻み歩行や幅広歩行が見られます。
言葉をはっきり発音することができなくなり、食べ物や飲み物が飲み込みにくくなります。
症状
症状は以下の通りです。
- 歩行障害
- めまい
- 意欲低下
- 構音障害(うまく発音できない)
- 嚥下障害
- 記憶障害
- 失禁
- 抑うつ気分
- 感情失禁(感情をコントロールできない)
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、レビー小体という異常なタンパク質が脳内に蓄積することで発症します。
アルツハイマー型認知症は女性に多い一方、レビー小体型認知症は比較的男性に多いです。
できなくなること
些細なことで転倒や転落が起き、ふらつきや立ちくらみも頻繁に見られます。
そのため、重度になると身体介護なしでは日常生活を送れない方がほとんどです。
飲み込む機能が弱まり、むせやすいので誤嚥性肺炎を引き起こす心配も出てきます。
症状
代表的な症状は以下の通りです。
- 記憶障害の更なる進行
- うつ症状
- レム睡眠行動障害(夜中に奇声をあげたり騒いだりする)
- パーキンソン症状の進行(筋固縮、嚥下障害)
- 自律神経症状の進行(ふらつき、立ちくらみ)
スポンサーリンク
認知症の進行具合
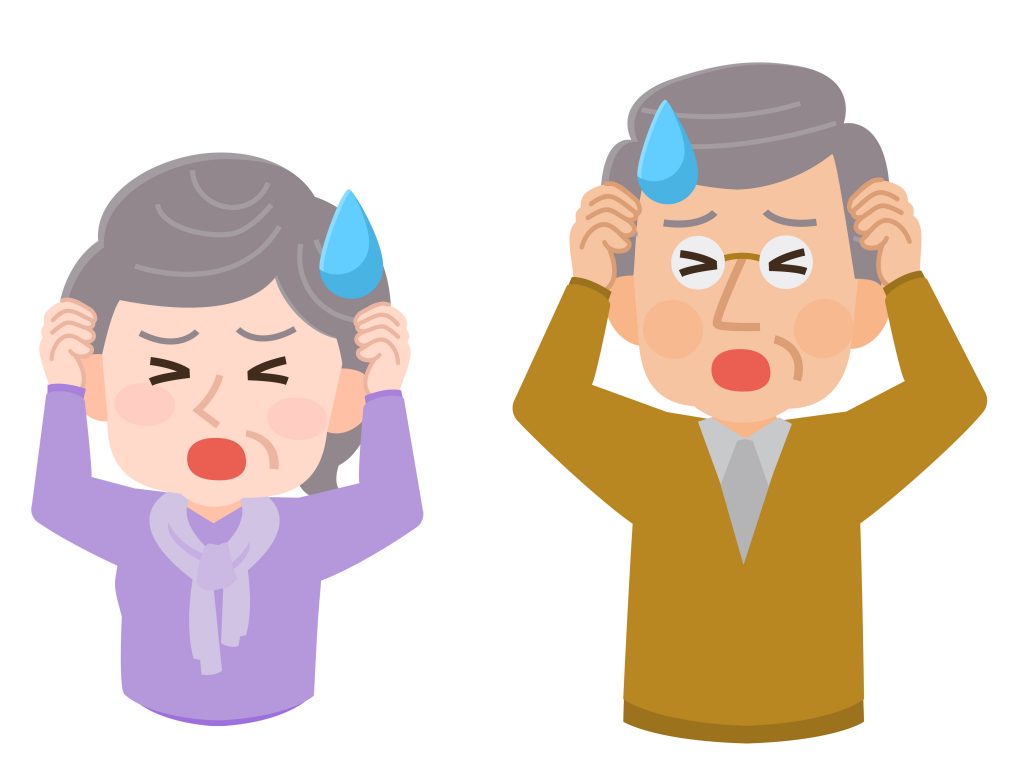
ここでは、代表的なアルツハイマー型認知症に焦点を当てて解説します。
アルツハイマー型認知症は、ゆっくりと時間をかけて進行していきます。
物忘れから始まり、人や物の名前も思い出せなくなります。
会話できないほど理解力が低下してくると、問題行動も起こり得ます。
重度になると、介護なしでは日常生活を送れなくなります。
認知症と診断されてから5年~10年かけて中度、重度と進行するのが一般的です。
認知症治療を中止するタイミング

現在、認知症を根本的に治す方法はまだありません。
認知症治療の目的は、進行を抑えて生活の質を高めることです。
認知症の治療方法には薬物療法と非薬物療法があります。
ここではこれらの治療方法を中止するタイミングについてご紹介します。
薬物療法を中止するタイミング
薬物療法は、大きく分けて二つあります。
一つ目は、認知機能改善薬によるものです。
中核症状の進行を抑えることを目的としています。
二つ目は、向精神薬や睡眠薬によるものです。
幻覚や妄想といった周辺症状の軽減を目的としています。
症状が進行し、寝たきり状態になると投薬は不要と考えても問題ありません。
抗認知症薬の効果の測定が困難になってしまうからです。
しかし、投薬は医師の判断で行われます。
いつまで治療が続くかは症状の継続期間によるので、明確な期間は不明です。
非薬物療法を中止するタイミング
非薬物療法では、薬を使わず脳の活性化を促します。
回想法や音楽療法、運動療法など様々な方法で症状にアプローチします。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家の指導のもとで行われます。
いつまで続けるのかを明確に言うことはできません。
長期間に渡ることが予想されるので介護される当事者が負担なく取り組むことが大切です。
認知症が重度になったときの心構え

認知症が重度になると、介護者の負担が大きくなります。
家族だけで問題を抱え込まずに周囲に現状を知らせて協力者を得ることが大切です。
介護する側と介護される側の両方を守ることにつながります。
家族が認知症であることを隠す必要はまったくありません。
地域包括支援センターなど、公的な相談機関でぜひ相談してみましょう。
亡くなった際に揉めない方法

認知症の方を含めた遺産分割協議は、どのように進めるのでしょうか?
相続の事前対策や方法について解説します。
認知症の家族が相続人にいる場合
例えば父親が亡くなり、相続人は母親とその子どもたちで、母親が認知症である場合を想定してみましょう。
この場合、残された子どもたちは想像以上に複雑な相続手続きが必要になります。
相続人の一人が認知症で判断能力がない場合は、銀行の預金引き出しや不動産を処分するときに必要な遺産分割協議ができません。
遺産分割協議をするために成年後見制度を利用することもできますが、使いづらい点も多く見受けられます。
最善の対策は、父親が亡くなる前に遺言を作って誰に何を相続させるか決めておくことです。
故人が認知症の場合
故人が認知症だった場合を想定してみましょう。
認知症の父親が亡くなる前に「長男にすべて相続させる」という内容の遺言を残していたとします。
他の子どもたちが「父親は認知症で遺言を作る判断能力がなかったから、遺言書は無効だ」と主張してくることもあるでしょう。
遺言が無効になると相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、そこで合意に至らなければ裁判に進みます。
裁判が泥沼化してしまうリスクもあります。
高齢になって物忘れが心配になった段階で遺言を作りましょう。
遺言を作る判断能力があったと証明する診断書を医師に書いてもらうことが必要です。
まとめ:重度の認知症
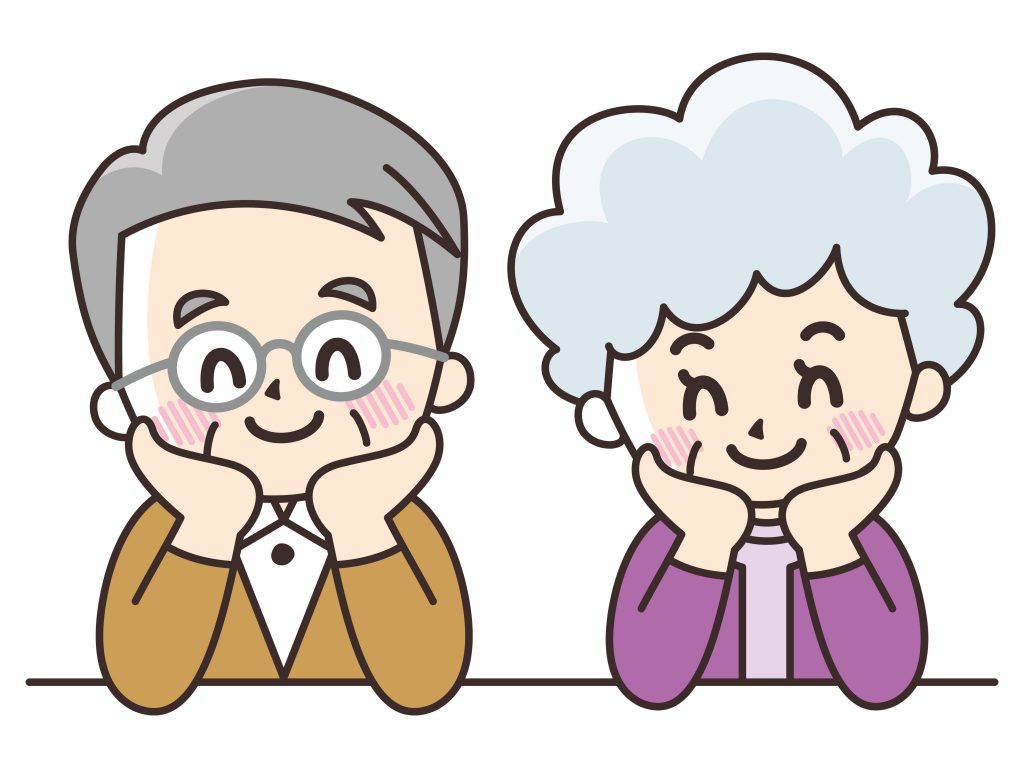
ここまで重度の認知症についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- アルツハイマー型認知症が重度になると、寝たきりになる
- 多くの認知症は5年〜10年かけて徐々に進行する
- 寝たきりになった場合、認知症治療の中止を検討する
- 家族が重度の認知症になったときは周囲に協力を得る
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。