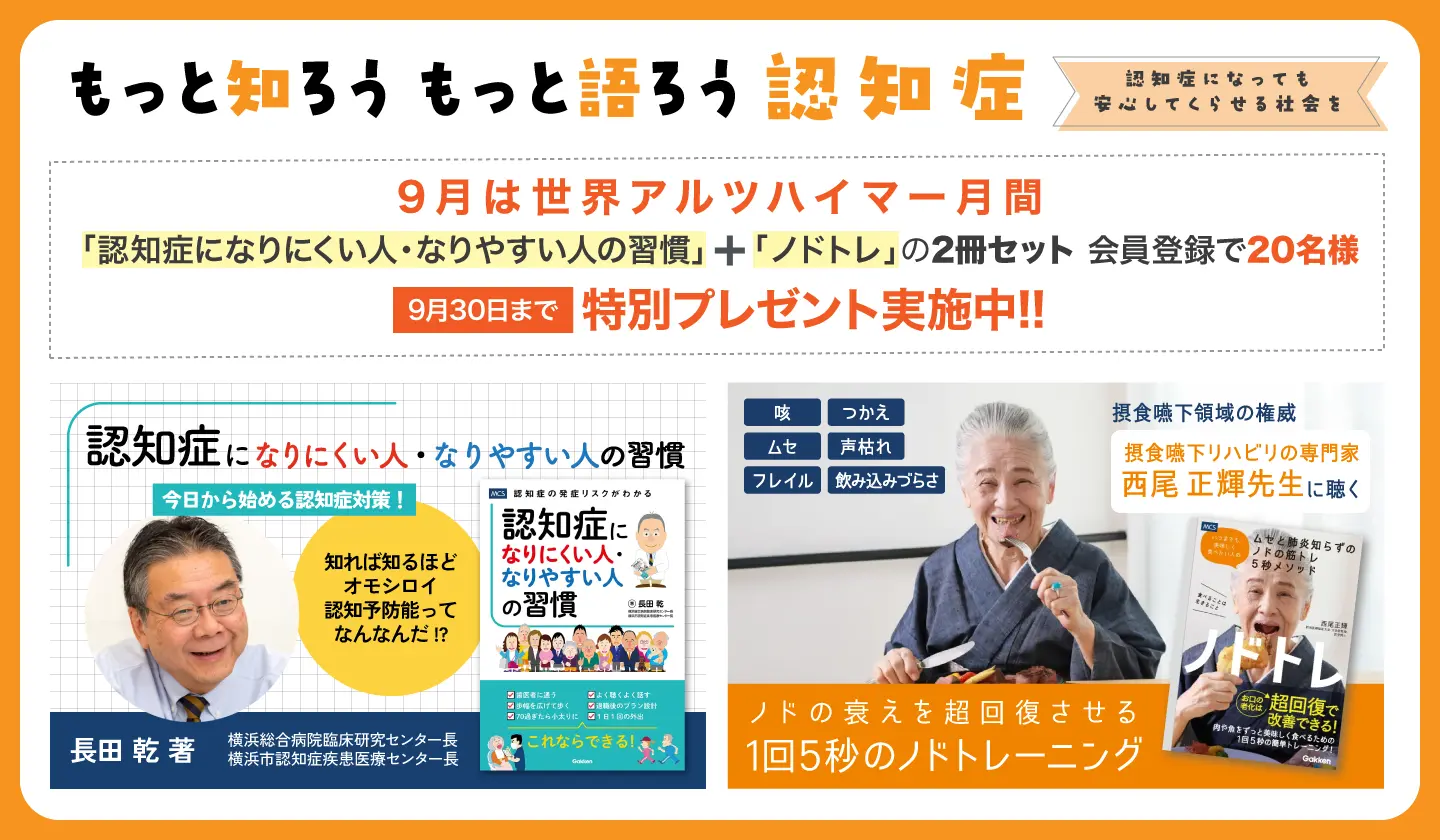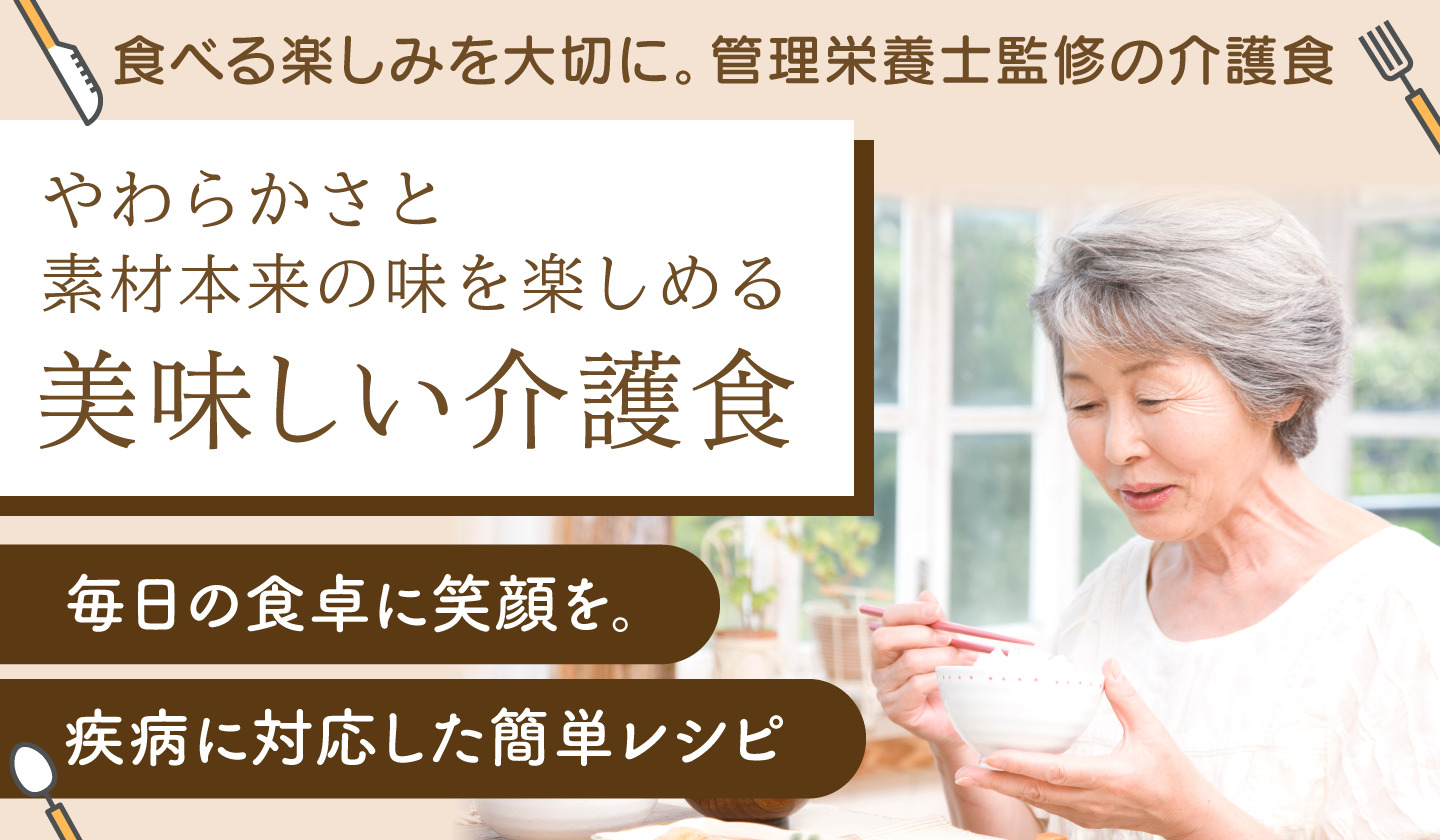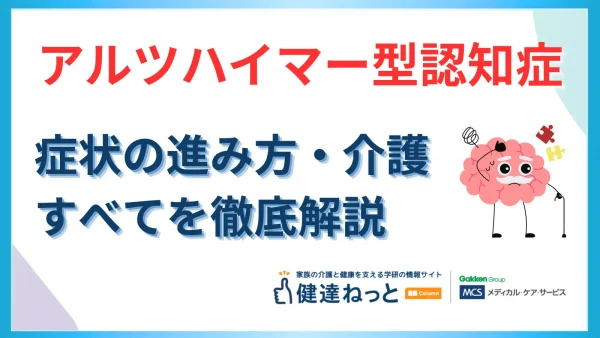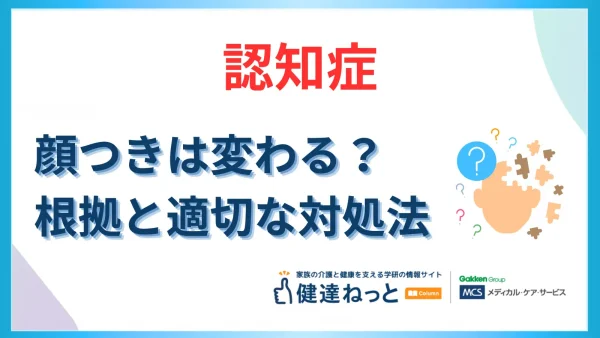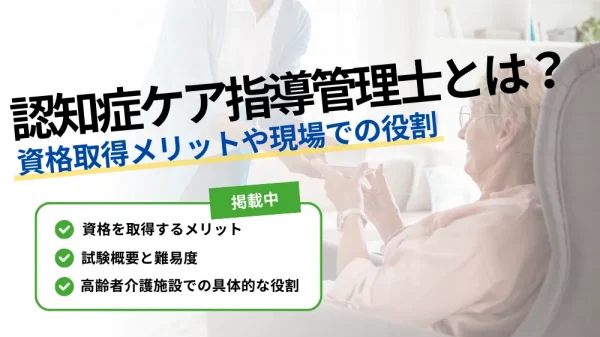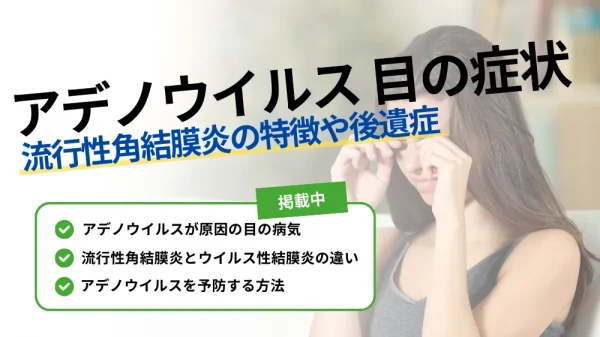超高齢社会のなか、年々増加している認知症。
記憶障害や見当識障害など、現れる症状はさまざまです。
その他、排泄障害のリスクがあることもご存知ですか?
本人だけでなく家族も事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、認知症と排泄について以下の点を中心にご紹介します。
- 認知症による排泄障害の症状
- 認知症が排泄障害を引き起こす原因
- 排泄障害の対策
排泄障害が起きたときのためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
認知症による排泄障害

認知症が進行していくと、様々な排泄障害がみられます。
では、認知症による排泄障害にはどのような症状があるのでしょうか。
ここからは、「認知症による排泄障害の症状」を四つご紹介します。
トイレに間に合わない
認知症の方は尿意を感じてもトイレに間に合わず、結果的に漏らしてしまう場合があります。
トイレに行きたくても介護者に訴えらえないことが原因の一つです。
また、筋力や膀胱、尿道などの身体機能の低下によってトイレに間に合わない場合もあります。
くしゃみや咳などでお腹に力が入ったときに漏らしてしまう「腹圧性尿失禁」のリスクも高まります。
その他、急に強い尿意を感じ漏らしてしまう「切迫性尿失禁」があります。
トイレではない場所で用を足す
認知症が進行すると部屋や廊下などのトイレではない場所で用を足す行為がみられます。
また、汚れた下着をタンスなどに隠す、排泄物を触るなどの行為を行う方もいます。
先ほどご紹介した「トイレに間に合わない」ことも原因の一つです。
また、トイレに対して「臭い」「暗い」などの不快な場所と認識している方もいます。
トイレの前に人が並んでいるという「幻視」が起こることも考えられます。
認知症によるものだと分かっていても、片付けを行う介護者にはかなりの負担やストレスがかかります。
おむつを嫌がる
排泄トラブルが続くと、認知症の方にオムツの使用を考える介護者の方は少なくありません。
しかし、認知症の方が不快感から、着用に苦手意識を感じる場合があります。
また、認知症の方は何のためにおむつを着用するのかが理解できず、苦手に思うことも考えられます。
おむつを着用することに恥ずかしさや情けなさを感じ、自尊心が傷付けられるという心の負担も大きいです。
おむつは介護者の負担を軽減することができますが、認知症の方にとってストレスになることも珍しくありません。
そのため、おむつの着用が苦手な認知症の方に対しては、さらに心のダメージを与えてしまわないような対応が問われます。
パンツやおむつを捨てる
認知症の方はおむつを嫌がるだけではなく、人によってはトイレに流してしまうことがあります。
パンツやおむつが濡れたことによる不快感が原因の一つです。
また、トイレにおむつを流す場合は流したことでトイレが詰まるということを理解できていない可能性があります。
ゴミ箱であれば捨てても問題ありませんが、トイレに流されると詰まってしまい修理が必要になる場合があります。
そのため、トイレにゴミ箱やバケツなどを置いてそこに捨てるよう認識してもらうなどの対応が必要です。
スポンサーリンク
認知症が排泄障害を引き起こす原因
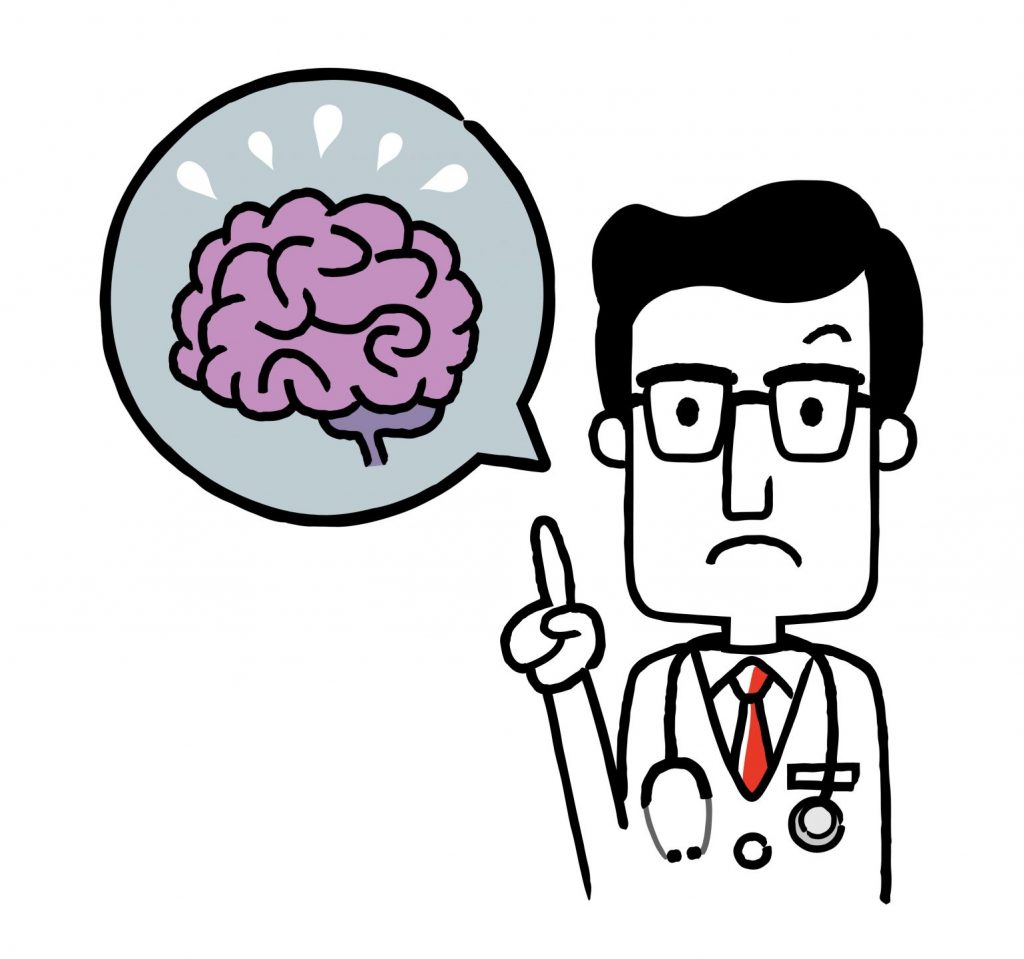
私たちは、トイレに行ってから排泄するまでの流れを何不自由なく行うことができます。
しかし、認知症の方にとっては簡単な動作ではありません。
もちろんわざと漏らしているわけではなく、排泄障害にも原因があります。
ここからは、「認知症による排泄障害の原因」を三つご紹介します。
歩行が難しい
認知症により身体機能が低下すると歩行が困難になります。
歩くスピードが遅くなるだけでなく、転びやすくなることもあります。
以上のような歩行問題が起こると、トイレに間に合わず漏らしてしまうといった排泄障害に繋がります。
トイレの場所がわからない
記憶障害や見当識障害によりトイレの場所が分からなくなると、排泄障害が起こることがあります。
自宅にいてもトイレの場所が認識でき自力でトイレに辿り着けない方もいます。
トイレ以外の場所で排泄する方も多いです。
トイレそのものが分からないといった、基本的なことまで理解できなくなる可能性もあります。
このように、認知症の方は「トイレの場所や使い方」「排泄の流れ」などが分からなくなります。
尿失禁などの排泄障害を起こしやすいです。
自宅に限らず施設入所や病院への入院など、新しい環境でトイレの場所が分からなくなることもあります。
また、暗い夜間は周囲の状況を認識しづらいです。
トイレまでの距離や方向感覚が掴めずトイレに行けないケースもみられます。
おむつを使うのが恥ずかしい
おむつは介護者の負担を軽減しますが、場合によっては認知症の方の精神的負担になります。
「おむつを使うのが恥ずかしい」気持ちから、プライドや自尊心が傷つくこともあります。
そのため、おむつの着用を拒否し、結果的に排泄障害に繋がります。
無理におむつを着用させようとすれば余計にプライドや自尊心を傷つけてしまいます。
排泄障害への対策

ここまで、認知症による排泄障害の症状と原因をご紹介しました。
排泄は非常にデリケートな問題です。
どのような対応をしながら認知症の方と向き合っていくかを考えることが重要な鍵となります。
毎日排泄トラブルが起こると、認知症の方はもちろん介護者の方のストレスがより蓄積されていきます。
そのため、排泄障害への対策は必要不可欠です。
ここからは、「認知症の方の排泄障害への対策」を四つご紹介します。
トイレの表示をわかりやすくする
排泄障害には、トイレの表示を分かりやすくすることが効果的です。
トイレに辿り着きやすくするために、リビングや廊下に「トイレはこちらです→」と誘導する貼り紙を貼ります。
そして、トイレのドアにも大きく分かりやすい字で「トイレ」と書いた貼り紙を貼りましょう。
もしも認知症の方が「トイレ」という言葉を使わないのであれば、「お手洗い」「便所」と表示すると良いです。
また、文字を認識しづらくなっている場合は、トイレのイラストを書くのも一つの方法です。
トイレ周辺の環境を整える
歩行が困難になりトイレへ行くのに時間がかかることを考慮し、トイレ周辺の環境を整えることが大切です。
トイレへの通り道を片付け、通路やトイレ内に手すりを付けることも効果的です。
障害物をなくし手すりを付ければ、認知症の方が動きやすくなります。
また、夜間は暗いため周囲を認識しづらいので、通路の電気をつけて明るくしておくと良いでしょう。
その際はトイレのドアを少し開けておき、便器が目につきやすい状態にしておくのも一つの方法です。
着脱しやすい服
認知症の方は素早い動作を行うのが困難です。
衣服の着脱に時間がかかり、その間に排泄してしまうことがあります。
特に、ボタンやファスナーなどがあると着脱に時間がかかってしまいます。
そのため、着脱しやすいウエストがゴムになっている服や下着を着てもらうと良いでしょう。
定期的にトイレに誘導する
認知症の方が尿意や便意を感じづらい場合は、定期的にトイレへ誘導すると良いです。
食事後や水分を摂って数時間後などがおすすめです。
認知症の方が行きたがらないこともありますが、トイレに連れていけばそのまま排泄することもあります。
認知症の方は自分の意思を上手く伝えることができないため、介護者が定期的に誘導することが大切です。
介護者が排泄のタイミングをつかむ方法

排泄のタイミングをどのように掴めば良いのか分からないという介護者も多いでしょう。
認知症の方は言葉で伝えることができなくても、「トイレに行きたいサイン」を出すことがあります。
ソワソワしたり家の中をウロウロしたりなどが一般的です。
以上のようなサインをしっかり見極め、タイミング良くトイレに誘導することが重要です。
認知症の方がどんなサインを出しているかを日頃から観察し、排泄パターンをメモしておくと良いでしょう。
認知症の方の排泄障害のまとめ
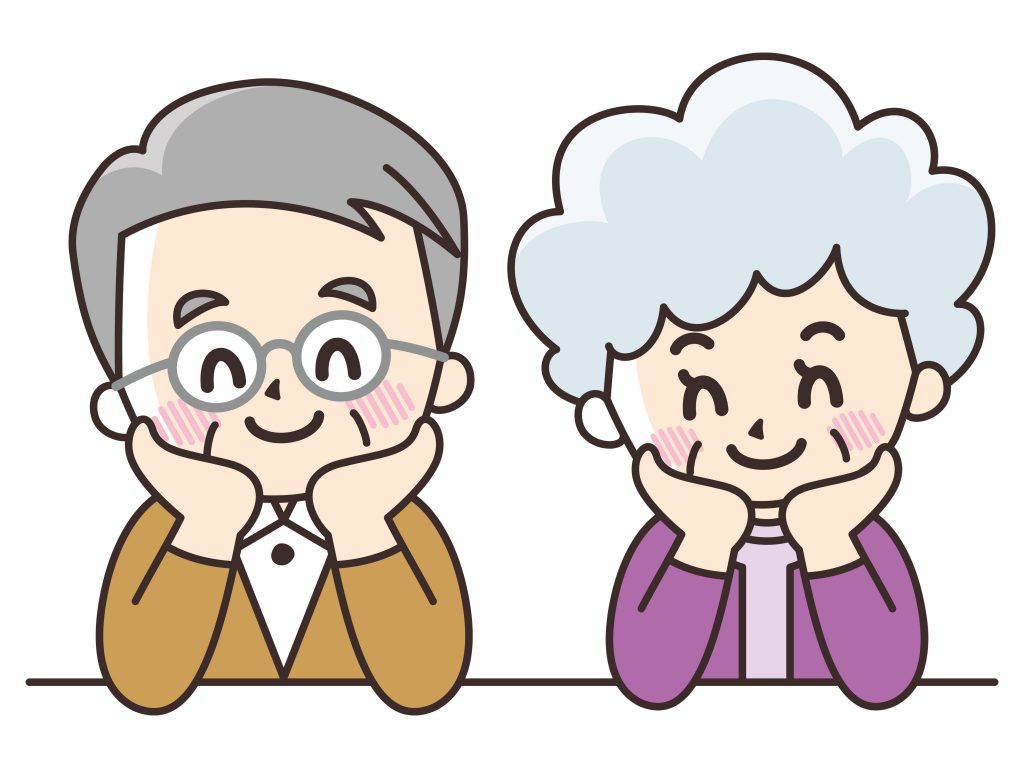
ここまで、認知症の方の排泄障害についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 認知症による排泄障害の症状は、「トイレに間に合わない」「おむつを嫌がる」など
- 認知症による排泄障害の原因は、「歩行が難しい」「トイレの場所が分からない」など
- 認知症による排泄障害の対策は、「トイレの表示を分かりやすくする」などが効果的
これらの情報が皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。