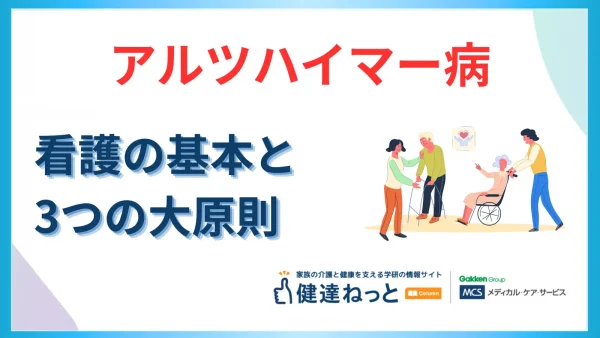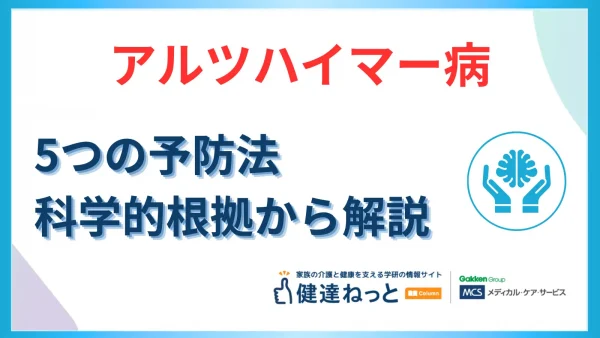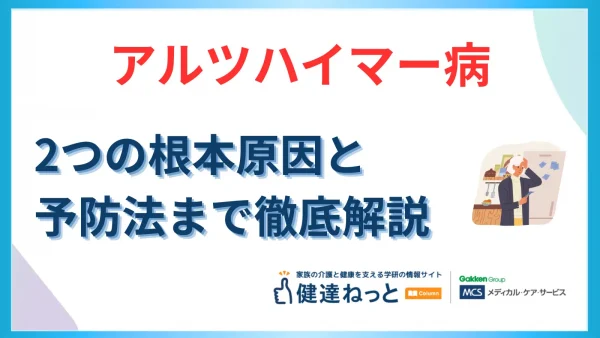認知症の発症数の上位を占める三大認知症。
種類によって認知症の症状や原因はさまざまです。
皆様は、種類ごとの特徴や違いをご存知でしょうか?
本記事では、三大認知症について以下の点を中心にご紹介します。
- 三大認知症の種類と特徴
- 三大認知症の中でもっとも多い認知症
- 三大認知症の予防法
認知症ごとの違いを把握するためにもご参考いただけますと幸いです。
是非最後までお読みください。
スポンサーリンク
三大認知症とは

三大認知症とは、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症の3つのことをいいます。
これら三大認知症は、認知症の中で発症数が多く全体の約80%を占めています。
認知症に対する理解を深めるためには、三大認知症への理解は必要不可欠です。
以下、三大認知症についてご紹介します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、三大認知症の中でもっとも発症数が多いです。
全体の半数以上を占めています。
認知症を発症すると、認知機能の低下によって記憶障害や見当識障害がみられるようになります。
記憶障害は、発症初期では短期記憶の低下から始まり、徐々に長期記憶も低下していきます。
また、見当識障害では時間・場所・人に関する認識力が低下するため、「わからない」「忘れてしまう」といった状態が日常的に起こります。
血管性認知症
血管性認知症は三大認知症のうち2番目に多い認知症です。
全体の約20%を占めています。
血管性認知症の一般的な症状は以下の通りです。
- 実行機能障害
- 物の認識ができない失認
- 簡単な日常動作ができない失行
- 言葉の理解ができない失語
また、血管性認知症では時間の経過とともに症状が進行していくわけではありません。
原因となる脳血管障害を繰り返すことで症状が進行していきます。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は三大認知症のうち3番目に多く、全体の約5%を占めています。
レビー小体型認知症では、脳の萎縮があまり目立つことはありません。
神経細胞の変性が多く見られることが特徴です。
症状としては、小刻み歩行や手足が震えるパーキンソン症状、計画立った行動ができない実行機能障害などがあげられます。
また、レビー小体型認知症の場合、幻視も代表的な症状とされています。
実際にはいない人や動物が本人にはいるように見えてしまうのが幻視です。
さらに幻視の症状が続くと妄想に発展する場合もあり、家族や介護者の負担も大きくなります。
スポンサーリンク
三大認知症の原因
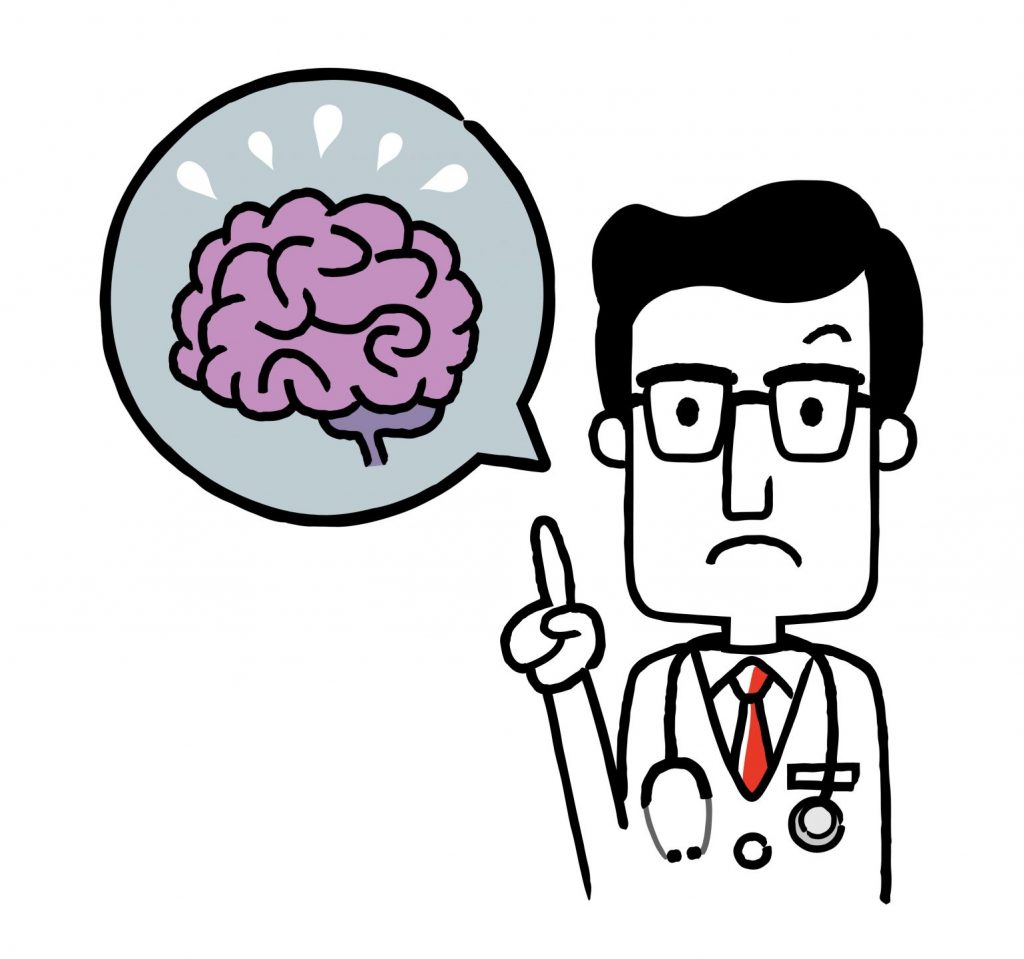
認知症の原因は、加齢や生活習慣などさまざまです。
原因を把握しておくことで予防や対策をすることもできます。
以下、三大認知症の発症原因について説明します。
アルツハイマー型認知症の原因
アルツハイマー型認知症は、アミロイドβとタウタンパク質が脳に蓄積することで発症します。
本来人間には、アミロイドβやタウタンパク質を分解し排出する機能が備わっています。
加齢により代謝機能が弱まり、上記の物質が蓄積してしまいます。
脳に蓄積したアミロイドβやタウタンパク質は脳にとって毒性のある存在となり、脳機能に障害をきたすようになります。
血管性認知症の原因
血管性認知症の原因は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害で、特に脳梗塞の方が血管性認知症を引き起こしやすいです。
血管性認知症の場合、脳血管障害が起こった場所や範囲によって、症状の度合いや傾向が異なります。
症状の進行は、脳血管障害を繰り返すことにより認知機能を低下させていくのが特徴です。
そのほか、血管性認知症の原因は脳血管障害ですが、さらにたどれば生活習慣病による動脈硬化が原因となっている場合も少なくありません。
糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は動脈硬化の原因となります。
脳血管障害の発症リスクが高くなることも指摘されています。
レビー小体型認知症の原因
レビー小体型認知症は、レビー小体というタンパク質が脳幹や大脳皮質に蓄積することで発症します。
レビー小体の主成分であるαシヌクレインは、神経細胞に対して毒性をもっています。
脳の神経細胞が死滅することが認知機能低下の直接的な原因です。
また、大脳皮質の脳幹の神経細胞に影響が出た場合、神経伝達物質であるドーパミンが減少しパーキンソン症状がみられるようになります。
三大認知症の予防法

三大認知症の予防方法は、食事や運動、生活習慣の見直しが基本となります。
以下、三大認知症の予防方法についてご紹介します。
生活習慣病の改善
前述したとおり、生活習慣病が引き起こす動脈硬化は脳血管障害の発症リスクを高めます。
その他、糖尿病や高血圧はアルツハイマー型認知症の発症リスクも高めます。
生活習慣病の改善は重要な認知症予防です。
認知症を数値で表すことはできなくても、血圧や血糖値、コレステロール値などは数値での確認が可能です。
数値が正常値になるような生活習慣を送ることで、認知症発症リスクは軽減されます。
バランスの取れた食事
バランスの取れた食事は、認知症予防としても生活習慣病対策としても有効な方法です。
過剰な塩分摂取は高血圧を、米やパンなどの糖質の過剰摂取は糖尿病を引き起こします。
脂質の過剰摂取もまた、脂質異常症などの原因にもなります。
偏った食生活は生活習慣病を引き起こし、結果として認知症発症につながりかねません。
認知症予防では栄養バランスの取れた食生活が重要になります。
適度な運動
適度な運動も認知症予防に効果的です。
運動は、脳血管の血流を活性化し、脳の活性化にもつながるとされています。
また、筋力維持の観点でも運動することは重要です。
筋力低下により日常生活での活動が減少すれば、脳を使う機会も少なくなります。
認知機能の低下につながる可能性が高いです。
他者との交流
他者との交流やコミュニケーションもまた、脳機能の活性化を期待できます。
家族間で交流の機会を設けたり、趣味サークルへの参加なども手段の一つです。
三大認知症以外の認知症

三大認知症以外の認知症には、前頭側頭型認知症やアルコール性認知症などがあります。
前頭側頭型認知症は、前頭葉や側頭葉が萎縮することによって発症します。
怒りっぽくなったり、社会性を失ったような行動などが目立つようになるのが特徴です。
アルコール性認知症はその名の通り、アルコールの過剰摂取が原因となり発症する認知症です。
原因がアルコールであることから、高齢者のみならず若い人にも発症する認知症です。
三大認知症のまとめ
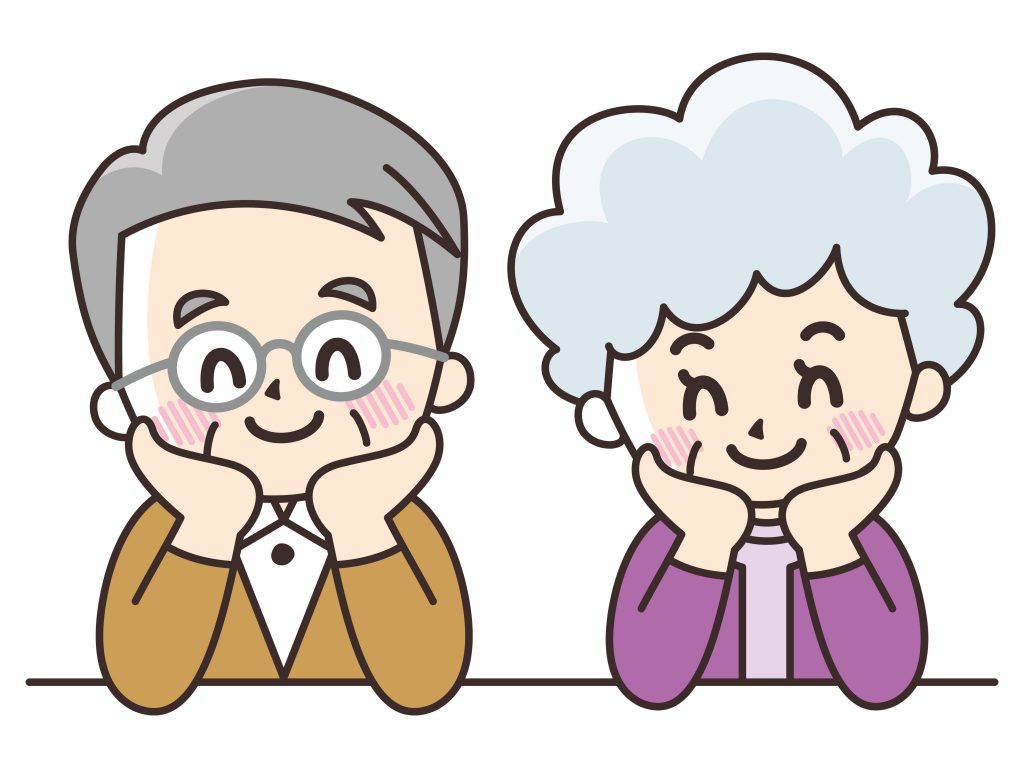
ここまで、三大認知症についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 三大認知症とは「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」
- 三大認知症の中でも、アルツハイマー型認知症が最も多い
- 三大認知症の予防法は、生活習慣病の改善、食事や運動の見直し
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。