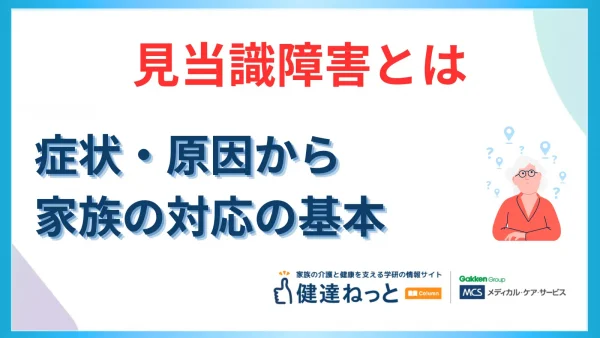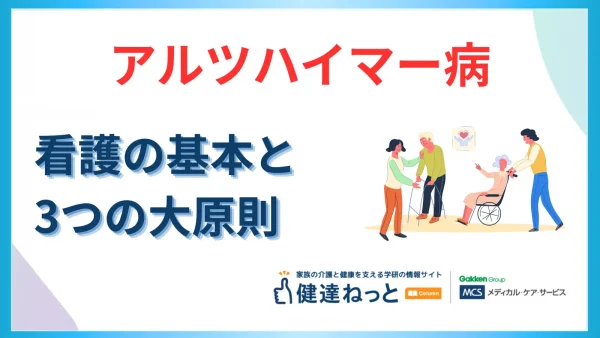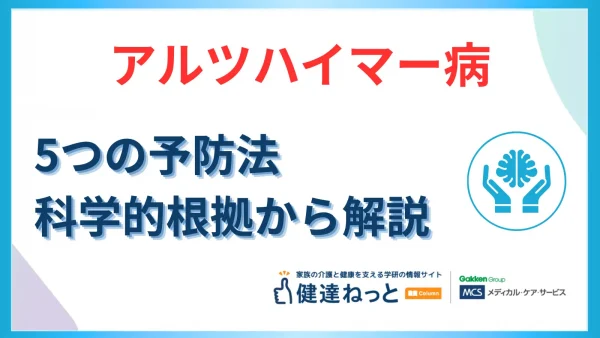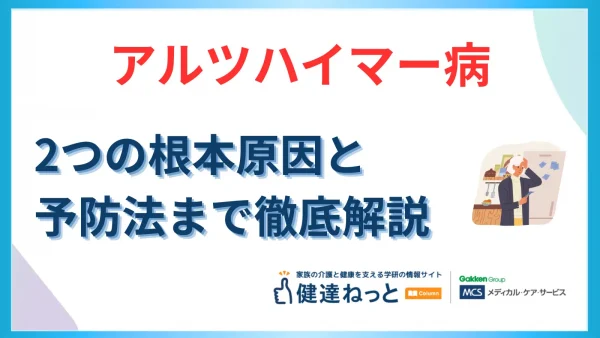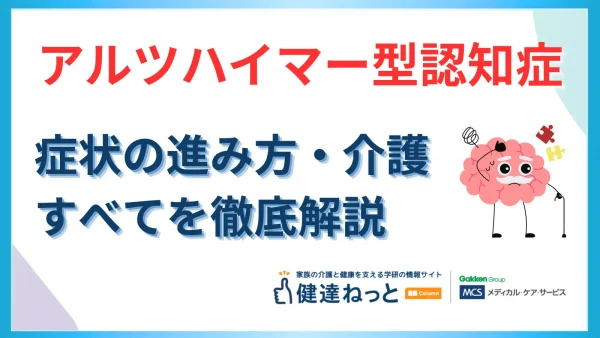- 「最近、親が日付や曜日をよく間違える…」
- 「家にいるのに『家に帰りたい』と言うようになった…」
- 「もしかして認知症の始まり…?これからどうなってしまうのだろう…」
大切なご家族の言動に変化が見られると、このような不安がよぎり、今後の生活やご本人との関係がどうなってしまうのか、心配になるのは当然のことです。
その言動は、単なるもの忘れではなく、「見当識障害」という認知症の代表的な症状かもしれません。
しかし、過度に心配する必要はありません。
見当識障害は、その症状や原因、そして正しい対応方法を知ることで、ご本人の不安を和らげ、穏やかな生活をサポートすることが可能です。
この記事では、見当識障害の基本的な知識から、ご家族が今日から実践できる具体的な関わり方まで、以下のポイントに沿って専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。
- 見当識障害の3つの代表的な症状と医学的な原因分類
- 症状が似ている「せん妄」との明確な違い
- ご本人の心を傷つけない基本的な接し方と3つの原則
- 症状の進行を緩やかにするために家族ができること
この記事を最後までお読みいただくことで、見当識障害への漠然とした不安が「具体的な知識」へと変わり、自信を持ってご家族と向き合うための第一歩を踏み出せるようになります。
スポンサーリンク
見当識障害とは?認知症で現れる記憶以外の「中核症状」
見当識障害とは、時間や場所、人物といった自分を取り巻く基本的な状況を正しく認識できなくなる症状です。
これは、認知症の中核症状とは?種類ごとの原因、対処法まで徹底解説!で詳しく解説しているように、認知症を発症した多くの方に見られる症状のひとつです。
多くの場合、記憶障害に続いて現れるといわれています。
医学的には「失見当識」
見当識障害は、医学の専門用語では「失見当識(しつけんとうしき)」と呼ばれます。
これは、私たちが普段、意識することなく行っている「今、自分がどこにいるのか」といった基本的な状況把握能力が失われてしまう状態を指します。
この能力は、私たちが社会の中で安心して生活するための、いわば”心のコンパス”のようなものです。
これが機能しなくなることで、ご本人は常に自分がどこにいるのか分からない、まるで霧の中に一人でいるような強い不安感に襲われます。
この”心のコンパス”は、以下の3つの重要な要素で構成されています。
- 時間の見当識:現在の日付、曜日、季節、時間などを認識する能力
- 場所の見当識:自分が今いる場所(自宅、病院、施設など)を認識する能力
- 人物の見当識:目の前にいる人が誰か、自分との関係性などを認識する能力
したがって、「失見当識」という言葉とその意味を理解することは、ご本人が感じているであろう深い不安に寄り添い、適切にサポートするための、ご家族にとっての最初の重要なステップといえるでしょう。
見当識障害が起こる3つの医学的な原因分類
見当識障害は、その原因によって大きく3つのタイプに分類されることを知っておくのが重要です。
なぜなら、原因によって治療法や今後の見通し、そしてご家族の関わり方も大きく異なってくるためです。
「認知症によるものだろう」と自己判断してしまうと、回復可能な原因を見逃してしまう可能性もあります。
医学的には、見当識障害の原因は以下の3つに大別されます。
| 分類 | 概要 | 具体的な原因疾患の例 |
|---|---|---|
| 器質性 | 脳の細胞が壊れるなど、脳自体の物理的な病変によって引き起こされるもの | 認知症、高次脳機能障害 |
| 症状性 | 身体の病気や使用している薬の影響で、脳の機能が一時的に低下するもの | せん妄、感染症、薬の副作用 |
| 心因性 | 強いストレスや精神的な不調など、心理的な要因によって引き起こされるもの | うつ病、解離性障害 |
例えば、器質性のように脳自体にゆっくりとした変化が起きている場合と、症状性のように体の不調が原因で一時的に脳の機能が低下している場合では、回復の見込みも大きく異なります。
このように原因は多岐にわたるため、専門医による正確な診断で原因を突き止めることが、適切なケアへの最も確実な近道となるのです。
スポンサーリンク
見当識障害の代表的な3つの症状
見当識障害は、一般的に「時間」→「場所」→「人物」の順番で症状が現れやすいといわれています。
ここでは、それぞれの段階で見られる代表的な症状の具体例を紹介します。
ご家族の言動に当てはまるものがないか、確認してみましょう。
時間の見当識障害(日付・季節が分からない)
時間の見当識障害は、見当識障害の中でも比較的早い段階から見られる代表的な初期症状です。
認知症になると時間感覚がずれる?原因から対策まで解説!でもあるように、時間という社会生活の基盤となる感覚が曖昧になることで、日々の暮らしにさまざまな混乱が生じ始めます。
時間感覚は、私たちの行動計画や生活リズムを支える重要な土台です。
この感覚が失われると、例えば約束の時間を守れなくなって社会的な信頼関係に影響が出たり、季節感のない服装で外出し体調を崩してしまったりするリスクが高まります。
具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 今日の日付や曜日、今の季節が分からない
- 約束の時間や予定を忘れてしまう
- 真夏に冬物のセーターを着るなど、季節に合わない服装をする
- 夜中に起きて「朝だ」と思い込み、活動を始めようとする
ご本人は時間を間違えている自覚がない場合も多く、周りが間違いを指摘すると混乱し、不安を強めてしまうこともあります。
そのため、このような初期サインに周りが気づき、さりげなくサポートしていくことが、ご本人の尊厳を守り、早期の専門家への相談につなげるための重要な手がかりとなります。
場所の見当識障害(今いる場所が分からない、迷子になる)
時間の見当識障害が進行すると、次に自分が今どこにいるのかを認識する「場所」の見当識が難しくなります。
長年住み慣れた自宅や、毎日通っているはずの道ですら、初めての場所のように感じてしまうのです。
この症状の根底には、記憶障害も相まって「ここは自分の知っている安全な場所ではない」という強い不安があります。
その不安から、自分の知っている「安心できる場所(昔住んでいた家など)」に帰ろうとして、結果的に徘徊や行方不明につながるケースが少なくありません。
例えば、以下のような行動が見られます。
- 自宅にいるのに「家に帰りたい」と荷物をまとめ始める
- 近所のスーパーに行ったきり、帰り道が分からなくなり迷子になる
- デイサービスなどの施設で、トイレや自分の部屋の場所が分からなくなる
実際に、メディカル・ケア・サービスが運営する愛の家グループホーム仙台実沢での事例では、「家に帰りたい」という訴えが続く玉野フミさん(仮名)がいらっしゃいました。
職員がその言葉を否定せずに理由を聞くと、大切な長男のために夕ご飯を作りたいという気持ちがあることが分かりました。
職員が一緒に外を歩きながら話を聞く対応を取ると、ご本人は落ち着きを取り戻されました。
この事例は、「帰りたい」という言葉の裏にあるご本人の世界観を尊重し、まず安心感を提供することがいかに重要かを示しています。
人物の見当識障害(家族や自分のことが分からない)
人物の見当識障害は、症状がかなり進行した段階で見られることが多く、ご家族にとっては最も精神的に受け入れがたい症状かもしれません。
毎日顔を合わせている我が子や配偶者のことが分からなくなったり、鏡に映った自分の姿さえも他人だと思ってしまったりすることがあります。
この症状は、単に「顔を忘れる」というだけではありません。
脳内で「目の前の人物の情報」と「記憶の中にある関係性の情報」を結びつける機能が障害されている状態です。
そのため、ご本人の中では、家族に対して「どこかで見かけた親切な人」といったような、新しい関係性が再構築されてしまうことがあります。
具体的な症状には、以下のようなものがあります。
- 自分の子どもを「兄」や「姉」などと間違える
- 毎日会いに来てくれるヘルパーさんの顔を毎回忘れてしまう
- 鏡に映る自分に向かって話しかける
- 自分の年齢が分からなくなる
愛の家グループホーム多賀城笠神では、入居当初「何でここにいるのか」「子どものためにご飯を作らなければ」と繰り返し、不安なご様子の中西モト子さん(仮名)がいらっしゃいました。
職員は、ご本人が置かれた状況を理解できずに不安を感じていると分析。
なぜここに入居しているのか、ご家族がどこで何をしているかを丁寧に伝え続ける対応を全職員で統一したところ、すぐに落ち着きを取り戻されました。
このケースは、状況の把握困難と人物の認識困難が複合的に現れた事例であり、一人ひとりの状況を分析し、統一したアプローチで関わることの重要性を示しています。
見当識障害の主な原因疾患
見当識障害は、さまざまな疾患が原因で引き起こされます。
ここでは、先ほど紹介した「器質性」「症状性」「心因性」の3つの分類に沿って、主な原因疾患を解説します。
原因によって治療法が大きく異なるため、正しい知識を持つことが重要です。
【器質性】認知症・高次脳機能障害など脳の病変によるもの
見当識障害の最も代表的な原因は、脳の神経細胞が少しずつ壊れていくなど、脳自体の物理的な変化によって引き起こされる「器質性」の疾患です。
その中でも特に多いのが、さまざまな種類の「認知症」です。
脳の中には、記憶を司る「海馬」や、状況判断を行う「前頭葉」など、見当識と深く関わる領域があります。
器質性の疾患では、これらの領域が損傷を受けることで、情報を正しく処理できなくなり、見当識障害が引き起こされます。
| 主な認知症の種類 | 特徴 |
|---|---|
| アルツハイマー型認知症 | 脳に特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が壊れていく。 三大認知症ってなに?それぞれの認知症の特徴と原因を徹底解説!の中でも最も多く、記憶障害から始まることが多い。 |
| 血管性認知症 | 脳梗塞や脳出血など、脳の血管の病気によって引き起こされる。 脳血管性認知症の特徴とは?他の認知症との違いも解説!で解説されているように、症状の出方にムラがあるのが特徴。 |
| レビー小体型認知症 | 脳にレビー小体という特殊なたんぱく質が溜まる。 幻視やパーキンソン症状を伴うことが多い。 |
また、交通事故による頭部外傷や脳卒中の後遺症である「高次脳機能障害」も、器質性の原因のひとつです。
このように器質性の原因は、脳の不可逆的な変化を伴うことが多いです。
そのため、完治を目指すのではなく、症状の進行を穏やかにし、穏やかな生活をサポートすることがケアの基本となります。
【症状性】せん妄など身体疾患や薬剤が引き起こすもの
見当識障害は、脳以外の体の病気や普段飲んでいる薬の影響で、一時的に脳の機能が低下して引き起こされる「症状性」の場合もあります。
これを見逃してはならない理由は、原因となっている身体の問題を治療したり、薬を見直したりすることで、症状が劇的に改善する可能性があるためです。
代表的なものに「せん妄」がありますが、これは脳の病気ではなく、体が発する”SOS”のような状態といえます。
特に高齢者は、若い頃と比べて体の予備能力が低いため、ちょっとした体調の変化が脳の機能に影響を与えやすいのです。
せん妄を引き起こす主な原因には、以下のようなものがあります。
- 身体疾患:肺炎や尿路感染症などの感染症、脱水、栄養失調、心臓や肝臓の病気など
- 薬剤:睡眠薬、抗不安薬、痛み止めなど、複数の薬の相互作用
- 環境の変化:入院や手術、引っ越しなど、急激な環境の変化によるストレス
特に急に見当識障害のような症状が現れた場合は、まず身体的な問題を疑い、認知症と決めつけずに内科などのかかりつけ医に相談することが非常に重要です。
【心因性】うつ病など心理的な要因によるもの
強いストレスや精神的な不調、特に「うつ病」が原因で、見当識障害と非常によく似た症状が現れることがあります。
これは「心因性」と呼ばれ、脳の機能自体に問題があるわけではないのに、心理的な要因が脳の働きを低下させている状態です。
高齢者のうつ病は「仮性認知症」とも呼ばれ、意欲や思考力、集中力が著しく低下するため、周りからは認知症と誤解されやすいという特徴があります。
ご本人は質問されても「分かりません」と答えることが多くなったり、日付や出来事に無関心になったりするため、見当識が障害されているように見えてしまうのです。
両者を見分けるポイントとして、うつ病の場合はご本人がもの忘れに対して自覚的で、「自分はダメになってしまった」と自責的になる傾向があります。
それに対し、認知症の場合はもの忘れの自覚がないことが多い、といった違いが挙げられます。
このように、原因が心因性であれば認知症とは全く異なる治療アプローチが必要となるため、精神科や心療内科での適切な診断と治療が症状改善の鍵を握るのです。
見当識障害と「せん妄」の具体的な違い
見当識障害とせん妄の違いとは?その他の症状やケア方法も徹底解説で詳しく解説しているように、見当識障害とせん妄は症状が似ていますが、全く異なる状態です。
原因や対処法が違うため、両者の違いを理解しておくことが大切です。
見分けるための主なポイントとして、「発症のスピード」「症状の変動」「意識レベル」の3つを詳しく見ていきましょう。
発症のスピード
両者を見分ける上で、最も分かりやすく重要なポイントが、症状の「発症スピード」です。
ご家族が「いつから始まったか」を把握しておくことは、医師が診断する上での極めて重要な情報提供となります。
- 見当識障害(認知症):
数か月から数年という長い時間をかけて、ゆっくりと症状が進行していきます。
「そういえば、半年前くらいから日付をよく間違えるようになったかな」というように、「いつから始まったか」がはっきりしないのが特徴です。 - せん妄:
数時間から数日という非常に短い期間で、突然症状が現れます。
「昨日までは普通に会話していたのに、今日の夕方から急に辻褄の合わないことを言い始めた」というように、発症時期が明確に特定できるケースがほとんどです。
このように、症状の始まり方が「緩やか」か「急激」かは、両者を鑑別する大きな手がかりとなります。
症状の変動
1日のうちで症状の波があるかどうかも、せん妄の大きな特徴です。
ご家族が1日の様子を観察し、時間帯による変化を記録しておくと、診断の助けになります。
- 見当識障害(認知症):
症状のレベルは、1日を通して比較的安定しています。
もちろん、日によって調子のよし悪しはありますが、「朝はしっかりしていたのに、夜になると全く別人になってしまう」といった急激な変化はあまり見られません。 - せん妄:
症状の変動が非常に激しいのが特徴です。
特に、夕方から夜間にかけて症状が悪化する「夜間せん妄」は典型的なパターンです。
日中は比較的落ち着いていても、夜になると興奮したり、幻覚を訴えたり、点滴を自分で抜いてしまったりすることがあります。
この症状の「波」の有無は、せん妄を疑う重要なサインといえるでしょう。
意識レベルの状態
意識がはっきりしているか、それともどこか朦朧としているか、という「意識レベル」の違いも重要な鑑別点です。
せん妄の種類とは?種類別の症状を徹底解説します!でもあるように、せん妄は医学的に「意識障害」の一種と定義されています。
- 見当識障害(認知症):
症状が進行しても、会話をする際の意識レベルは比較的はっきりしていることが多いです。
見当識は障害されていても、意識そのものは保たれています。 - せん妄:
意識が混濁し、注意力が散漫になっている状態です。
具体的には、話しかけても注意が逸れやすかったり、ボーっとして一点を見つめて反応が鈍かったり、話の辻褄が合わなかったりします。
ご本人と話しているときに「意識がクリアか、どこか曇っているか」という視点で観察することが、両者を見分けるヒントになります。
| ポイント | 見当識障害(認知症) | せん妄 |
|---|---|---|
| 発症スピード | 緩やか(数か月~数年) | 急激(数時間~数日) |
| 症状の変動 | 比較的安定 | 激しい(特に夜間に悪化) |
| 意識レベル | はっきりしていることが多い | 混濁し、注意散漫 |
見当識障害のある方への基本的な接し方と心構え
見当識障害のある方は、常に不確かで不安な世界に生きています。
そのため、周りのご家族の対応が、ご本人の心の安定に大きく影響します。
家族が認知症かも?ご家族の向き合い方から対応まで解説を参考に、まずは基本的な心構えを理解しましょう。
対応の3つの基本原則「否定しない・安心させる・自尊心を尊重する」
ご本人と接する上で、最も大切にしたいのが「否定しない」「安心させる」「自尊心を尊重する」という3つの基本原則です。
この原則を常に心に留めておくだけで、介護に重要なコミュニケーションとは?コツや声掛け方法を解説!は、より温かく、穏やかなものになります。
なぜなら、ご本人の言動は、ご本人が見ている「真実の世界」に基づいているためです。
それを周りが否定することは、ご本人の存在そのものを否定することにつながり、混乱と不安を増大させてしまいます。
- 否定しない:
ご本人の間違いを「違うでしょ」と指摘したり、無理に訂正したりするのは避けましょう。
ご本人の世界観をまずは「そうなんですね」と受け入れ、話に耳を傾けることが信頼関係の第一歩です。 - 安心させる:
不安な気持ちに寄り添い、「大丈夫ですよ」「ここにいるから安全ですよ」といった言葉で、安心感を与えましょう。
穏やかな口調で、ゆっくり話すことも効果的です。 - 自尊心を尊重する:
子ども扱いしたり、できないことを責めたりせず、人生の先輩として敬意を払う姿勢が重要です。
ご本人ができることや得意なことを見つけ、役割を持ってもらうことも自尊心を保つ上で役立ちます。
メディカル・ケア・サービスが独自に開発した「MCSケアモデル」では、科学的根拠に基づいた再現性の高いケアに取り組んでいます。
約250項目のアセスメントでご本人の状態を科学的に分析し、一人ひとりに合ったケアを提供することで、見当識障害による「不確か」で「不安」な状況を、「確か」で「安心」できる状況へと変化させていきます。
日常生活での工夫
3つの基本原則を土台としながら、日常生活の中で少し環境を整える工夫をすることで、ご本人の混乱を減らし、穏やかな生活を具体的にサポートできます。
これは、ご本人に「頑張らせる」のではなく、周りの環境を「ご本人が分かりやすいように変えてあげる」という発想の転換です。
この工夫は、ご本人が自分の力で状況を把握する手助けとなり、自信や安心感を取り戻すきっかけにもなります。
- 時間や日付の手がかりを置く:
大きな文字で見やすいカレンダーや時計を、いつも座る場所から見える位置に置きましょう。
デジタル時計など、日付と曜日が一緒に表示されるものがオススメです。 - 季節感を取り入れる:
季節の花を飾ったり、旬の食材を使った食事を用意したりして、五感で季節を感じられる工夫をしましょう。
「柿が美味しい季節になりましたね」といった会話のきっかけにもなります。 - 環境をシンプルに保つ:
部屋の模様替えを頻繁に行うのは避け、慣れ親しんだ家具の配置を保つことが大切です。
トイレや寝室のドアに、文字だけでなく写真や絵で分かりやすく表示するのもよいでしょう。 - さりげなく情報を伝える:
「今日は〇月〇日、よい天気ですね」「もう12時だから、お昼ごはんにしましょうか」など、会話の中に自然に時間や状況に関する情報を含めるようにしましょう。
これらの小さな工夫の積み重ねが、ご本人の混乱を防ぎ、穏やかな時間を増やすことにつながります。
見当識障害の症状の進行を緩やかにするために家族ができること
見当識障害を完全に治すことは難しいですが、症状の進行を緩やかにしたり、ご本人の生活の質(QOL)を維持したりするために、ご家族ができることは多くあります。
大切なのは、特別なリハビリではなく、日々の生活の中での少しの心がけです。
生体リズムの安定と心身の健康維持
認知症と生活習慣病には関係がある?改善すべきポイントも解説!でも指摘されているように、規則正しい生活と健康的な習慣は、脳の機能を健やかに保つ上で非常に重要です。脳も体の一部であり、体全体の健康状態が脳の働きに直結するためです。
実際に、国立循環器病研究センターの研究によると、アルツハイマー病と診断された患者さんを対象に、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙といった生活習慣病をすべて管理した群では、全く管理しなかった群と比較して、2年半後の認知機能評価で大きな差が見られました。
これは、生活習慣病の管理が認知機能の維持に重要であることを示しています。
特に「睡眠」「食事」「運動」の基本的な生活習慣のバランスを整えることは、誰でも今日から始められる効果的なアプローチといえるでしょう。
健達ねっとでも、認知機能の維持に役立つ生活習慣として、以下の点を推奨しています。
- 十分な睡眠:
朝日を浴びて体内時計をリセットし、夜はリラックスできる環境を整え、質のよい睡眠を心がけましょう。
質のよい睡眠は、脳の老廃物を除去する働きがあるといわれています。 - バランスのよい食事:
介護の食事|高齢者の食事をサポートするための実践ガイドを参考に、塩分や糖分を控えめにし、野菜や魚、大豆製品などをバランスよく摂ることが大切です。
よく噛んで食べることも脳へのよい刺激になります。 - 適度な運動:
無理のない範囲で、散歩やラジオ体操などの有酸素運動を習慣にしましょう。
運動は脳の血流をよくするだけでなく、気分転換やストレス解消にもつながります。
バランスのよい食事を基本としつつ、科学的根拠に基づいた機能性表示食品を活用することも、認知機能の維持に役立つ選択肢のひとつです。
健達ねっとSHOPでは、機能性表示食品として認められた認知機能サポート成分を取り扱っています。
※これらは健康食品であり、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。
社会とのつながりと役割の維持をサポートする
人は社会的な生き物であり、他者との交流や、誰かの役に立っているという実感は、脳にとって最高の栄養であり、生きる喜びそのものです。
見当識障害があっても、ご本人が孤立することなく、社会とのつながりを持ち続けられるようサポートすることは、ご家族にできる非常に重要な役割といえます。
認知機能が低下してくると、ご本人は自信を失い、人との交流を避けがちになります。
しかし、そこで孤立してしまうと、さらに認知機能が低下するという悪循環に陥りかねません。
- 役割を持ってもらう:
簡単な調理の手伝いや洗濯物たたみなど、ご本人が「できること」「得意なこと」を見つけて役割をお願いしましょう。
「ありがとう」「助かるわ」といった感謝の言葉が、ご本人の自尊心と意欲を高めます。 - 趣味や好きなことを続ける:
昔からの趣味や好きなことを続けられる環境を整えましょう。
地域のサークルやデイサービスなどに参加し、新しい仲間と交流するのもよい刺激になります。 - 家族や友人との交流:
家族団らんの時間を大切にしたり、親しい友人と会う機会を作ったりして、コミュニケーションの機会を積極的に設けましょう。
メディカル・ケア・サービスでは、全国の小・中・高校生を対象とした「認知症教育の出前授業」を実施しています。
2022年12月から2024年12月にかけて実施した授業後のアンケート調査では、92%の生徒が「認知症がよいイメージに変わった」と回答し、「認知症の祖父を避けていたけれど、これからは多く訪れたい」といった声も寄せられました。
このような社会全体の理解が深まることが、認知症の方が安心して社会参加できる環境づくりにつながります。
もしかしてと思ったら?見当識障害の検査・治療・相談できる場所
ご家族の様子に「おかしいな」と感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家や専門機関に相談することが大切です。
【2025年最新】若年性認知症とは?症状や特徴・予防方法を正しく理解の記事でも強調されているように、早期発見・早期対応が、その後のご本人とご家族の生活を大きく左右します。
何科を受診すべき?
いざ病院へ行こうと思っても、「何科に行けばよいのか分からない」と迷う方は少なくありません。
見当識障害が疑われる場合、まずはいつも診てもらっているかかりつけ医に相談するのが第一歩です。
その上で、専門的な診断が必要だと判断された場合に、以下のような専門の診療科を紹介してもらうのが一般的な流れとなります。
各診療科にはそれぞれ特徴があります。
- もの忘れ外来:
認知症を専門に診断・治療する外来で、近年設置する病院が増えています。
認知症の専門医が総合的に診察してくれます。 - 精神科・心療内科:
うつ病やせん妄など、認知症以外の精神的な要因が考えられる場合に特に適しています。
ご本人の不安な気持ちにも寄り添ったケアが期待できます。 - 神経内科:
脳梗塞やパーキンソン病など、脳や神経の病気が専門です。
脳の画像診断などを用いて、原因を詳しく調べます。
どの科がよいか迷う場合は、まずかかりつけ医に相談し、症状を詳しく伝えた上で、最適な専門医を紹介してもらうのがよいでしょう。
病院で行われる検査の概要
「病院でどんなことをされるのだろう」と不安に思うご本人やご家族もいらっしゃるかもしれません。
事前に検査の概要を知っておくことで、心の準備ができ、安心して受診に臨めます。
見当識障害の原因を特定するために行われる主な検査は、ご本人への負担が少ないものから段階的に行われます。
主な検査の流れは以下の通りです。
- 問診:
医師がご本人やご家族から、いつからどのような症状があるか、生活の様子、既往歴などを詳しく聞き取ります。
ご家族が事前に症状のメモを用意しておくとスムーズです。 - 認知機能検査:
MMSE(ミニメンタルステート検査)やHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)といった質問形式のテストで、記憶力や見当識の状態を客観的に評価します。 - 画像検査:
CTやMRIなどで脳の萎縮の程度や脳血管障害の有無などを調べ、脳の状態を視覚的に確認します。 - 血液検査など:
甲状腺機能の低下やビタミン不足など、認知症に似た症状を引き起こす身体疾患がないかを確認するために行われます。
これらの検査を総合的に判断し、診断が下されます。
主な治療法は薬物療法と非薬物療法
見当識障害の治療は、原因となっている疾患によって異なりますが、主に「薬物療法」と、薬を使わない「非薬物療法」を組み合わせて行われます。
治療の目的は、病気の進行を緩やかにし、ご本人ができるだけ穏やかに自分らしい生活を続けることをサポートすることです。
- 薬物療法:
アルツハイマー型認知症などに対しては、症状の進行を遅らせることを目的とした薬(抗認知症薬)が処方されます。
また、せん妄やうつ病が原因の場合は、それぞれの原因疾患に対する治療薬が使われ、症状の改善を図ります。 - 非薬物療法:
薬に頼るだけでなく、リハビリテーションなどを通じて脳の活性化や精神的な安定を図るアプローチです。
代表的な非薬物療法に「リアリティオリエンテーション(現実見当識訓練)」があります。
これは、日常生活の中で「今日は〇日ですね」とさりげなく声かけをしたり、少人数のグループでカレンダーや時計を見ながら会話をしたりすることで、見当識を優しく刺激し、現実認識を促すリハビリテーション手法です。
ただし、効果は比較的初期の認知症に限定されることが多く、中等度以上で見当識障害が進行し混乱している患者にとって、見当識を確認しすぎることはかえって混乱を深め自尊心を傷つけることになるので注意しなければなりません。
ご家族が日常生活の中で意識的に取り入れることも可能な、効果的なアプローチのひとつです。
家族が相談できる公的な窓口
医療機関での治療と並行して、介護や生活に関する悩みを相談できる公的な窓口を積極的に活用しましょう。
介護で家族崩壊は起こる?原因や対処法などを解説します!の記事にあるように、介護者が一人ですべてを抱え込んでしまうことは、最も避けるべき状況です。
専門家の力を借りることで、心身の負担が軽くなり、よりよい介護につながります。
以下のような相談窓口は、無料で利用できる身近な味方です。
- 地域包括支援センター:
高齢者の介護、福祉、医療に関する総合相談窓口で、全国の市町村に設置されています。
保健師や社会福祉士などの専門家が、介護保険サービスの申請手続きや地域のサービスについて教えてくれます。 - 認知症疾患医療センター:
認知症の専門的な診断や治療、リハビリテーション、家族からの相談など、総合的なサポートを行っている専門病院です。 - 若年性認知症コールセンター:
65歳未満で発症する若年性認知症に関する専門の電話相談窓口です。
就労や経済的な問題など、特有の悩みについて相談できます。 - 認知症の人と家族の会:
同じ悩みや経験を持つ当事者や家族が集まり、情報交換や相談、交流ができる会です。
「一人じゃない」と感じられる貴重な場となります。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、見当識障害の症状や原因、そしてご家族ができる基本的な対応について、具体的な事例を交えながら解説しました。
見当識障害は、ご本人にとって常に世界が不確かで不安な状態です。
その症状の背景にあるご本人の気持ちを理解し、「否定しない・安心させる・自尊心を尊重する」という3つの原則を心がけることが、ご本人の心の安定につながります。
そして、その温かい関わりは、ご家族自身の心の負担を軽くすることにもなるでしょう。
もしご家族に見当識障害のサインが見られたら、一人で悩まず、できるだけ早く専門機関に相談するようにしましょう。
正しい知識を持ち、早期に対応を始めることが、その後のご本人とご家族の生活の質を大きく左右します。
なお、厚生労働省の最新の推計(2024年公表)によると、2025年には65歳以上の高齢者のうち約12.9%(471.6万人)が認知症になると予測されています。
これは、以前予測されていた700万人(20%)よりも大幅に修正された数値です。
認知症は誰もがなり得るものであり、正しい知識を持つことがますます重要になっています。
この記事が、見当識障害への理解を深め、ご家族とご本人が共に穏やかな日々を過ごすための一助となれば幸いです。
まずは、認知症予防できていますか?効果的な食べ物やトレーニング内容を解説の記事も参考に、今日からできることから始めてみましょう。