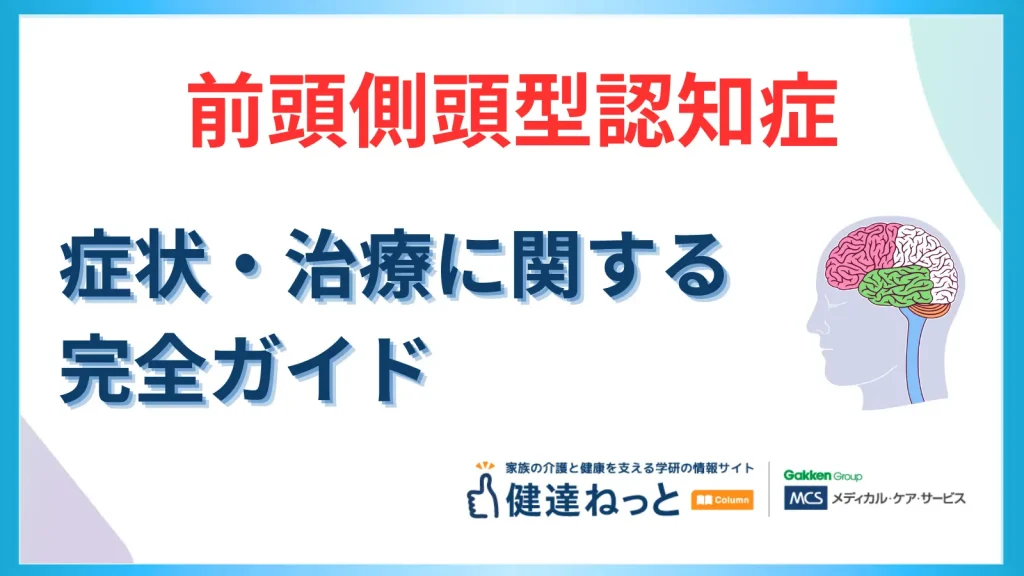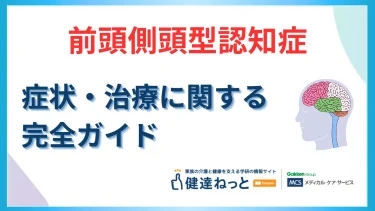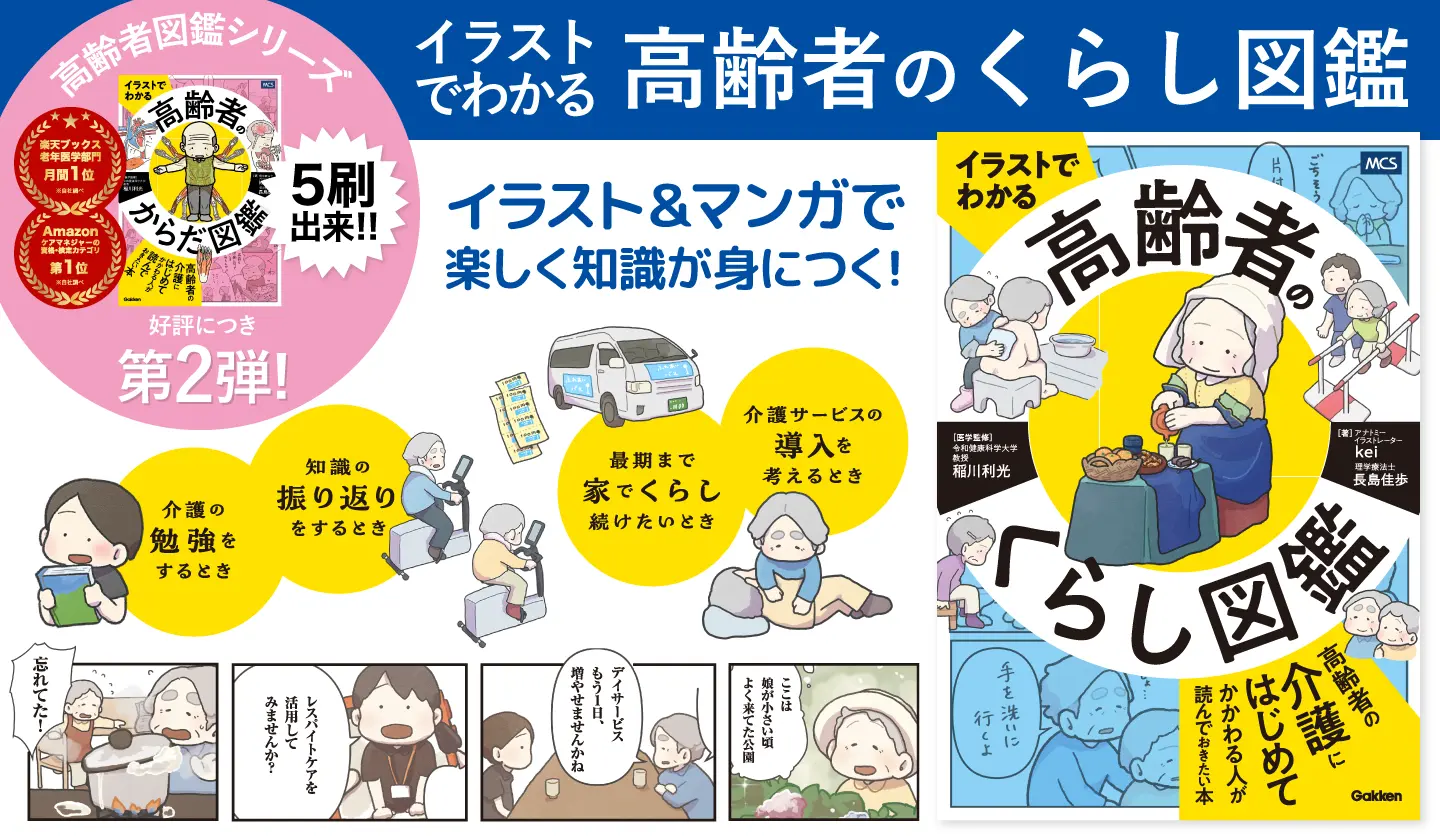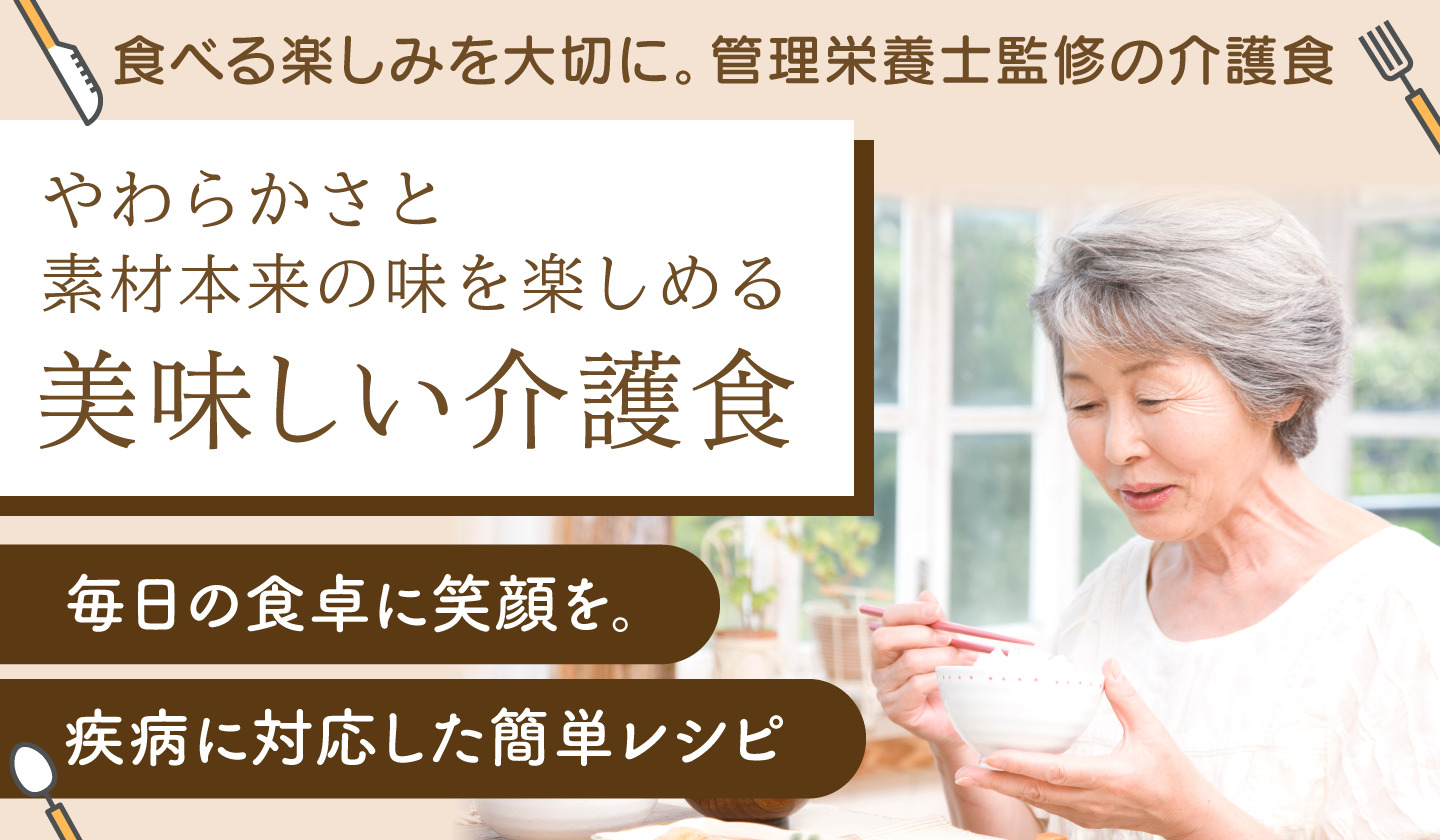- 「最近、家族の性格がまるで別人のように変わってしまった…」
- 「理解できない行動が増え、どう接すればよいか分からない」
- 「もしかしたら認知症かもしれないけど、誰に相談すれば…」
- 「この先どうなるのか、経済的なことも含めて不安で仕方がない」
このような深刻な悩みを、誰にも打ち明けられずに一人で抱え込んでいませんか。
愛する人の不可解な変化に戸惑い、先の見えない不安に押しつぶされそうになるお気持ち、お察しいたします。
この記事は、そのような暗闇の中にいるあなたとご家族を照らす道しるべです。
前頭側頭型認知症は、正しい知識を身につけ、適切な対応と支援を得ることで、穏やかな時間を共に過ごすことが可能な病気です。
この記事を最後まで読めば、以下のことが明確になります。
- 前頭側頭型認知症の特有の症状と、その原因
- ご本人とご家族の安全を守るために、今すぐやるべきこと
- 診断後の治療法と、心の負担を軽くするケアの技術
- 必ず活用すべき公的制度と、将来への経済的な備え
この記事を通じて、あなたの抱える漠然とした不安が「次に何をすべきか」という具体的な行動計画に変わります。
そして、決して一人ではないと知り、希望を持って次の一歩を踏み出すきっかけとなるはずです。
スポンサーリンク
前頭側頭型認知症(FTD)とは
前頭側頭型認知症(FTD)は、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症する認知症です。
もの忘れが中心となるアルツハイマー型認知症とは異なり、人格の変化や行動の異常が先に現れるという大きな特徴があります。
脳のどこで何が起きているのか?前頭葉・側頭葉の役割
前頭側頭型認知症の症状を理解するには、まず脳のどの部分に問題が起きているのかを知ることが重要です。
この病気は、名前の通り「前頭葉」と「側頭葉」という、人間が社会生活を営む上で極めて重要な役割を担う部分が、神経細胞の変性によって縮んでしまう(萎縮する)ことで発症します。
それぞれの脳の役割は以下の通りです。
| 脳の部位 | 主な役割 | 障害されると現れる症状例 |
|---|---|---|
| 前頭葉 | 思考、判断、感情のコントロール、計画、実行 | 社会性のない行動、感情が抑制できない |
| 側頭葉 | 記憶、聴覚、言葉の理解 | 言葉の意味が分からない、物の名前が出ない |
つまり、理性を司る前頭葉が障害されると、感情のブレーキが効かなくなったり、社会のルールを無視した行動をとったりするようになります。
また、言葉を司る側頭葉が障害されると、コミュニケーションに問題が生じるのです。
前頭側頭型認知症が発症する原因
前頭側頭型認知症がなぜ発症するのか、その正確な原因はまだ完全には解明されていません。
しかし、研究によって、脳の神経細胞内に「タウたんぱく質」や「TDP-43」といった異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が壊れてしまうことが原因であると分かっています。
これにより、前頭葉や側頭葉の萎縮が引き起こされるのです。
ご家族に同じ病気の方がいるケースは比較的まれで、多くは遺伝とは関係なく発症します。
50〜60歳代で発症することが多く、働き盛りの世代が罹患する若年性認知症の代表的な疾患のひとつとしても知られています。
アルツハイマー型認知症との違い
前頭側頭型認知症は、最も一般的なアルツハイマー型認知症としばしば混同されますが、その特徴は大きく異なります。
最大の違いは、初期に現れる症状です。
アルツハイマー型認知症が「新しいことを覚えられない」といった記憶障害から始まるのに対し、前頭側頭型認知症は「人格の変化」や「社会性の欠如」といった行動面の変化が先に現れます。
両者の主な違いを以下にまとめます。
| 項目 | 前頭側頭型認知症 | アルツハイマー型認知症 |
|---|---|---|
| 初期症状 | 人格の変化、行動異常、言語障害 | 記憶障害(もの忘れ) |
| 記憶 | 比較的保たれる | 早期から障害される |
| 発症年齢 | 50〜60代の若年発症が多い | 高齢での発症が多い |
| 病識 | 本人に病気の自覚がないことが多い | 初期にはもの忘れの自覚があることが多い |
このように、症状の現れ方が全く異なるため、周囲は認知症だと気づきにくく、「性格が変わった」「わがままになった」と誤解してしまうケースが少なくありません。
前頭側頭型認知症の3つのタイプ
前頭側頭型認知症は、最初に現れる症状によって、主に3つのタイプに分類されます。
どのタイプであっても、病気が進行するとそれぞれの症状が混じり合ってくることが一般的です。
三大認知症(アルツハイマー型、レビー小体型、血管性)とは別の第4の認知症ともいわれるこの病気のタイプを理解することは、適切な対応につながります。
主な3つのタイプは以下の通りです。
- 行動障害型前頭側頭型認知症(bvFTD)
人格の変化や社会性のない行動が目立つタイプです。
前頭葉の萎縮が主で、最も多いタイプといわれています。 - 意味性認知症(SD)
言葉の意味が分からなくなったり、物の名前が出てこなくなったりするタイプです。
側頭葉の萎縮が主となります。 - 進行性非流暢性失語(PNFA)
呂律が回らない、文法的な間違いが多いなど、話すこと自体が困難になるタイプです。
ご本人の症状がどのタイプに近いかを把握することで、コミュニケーションの方法を工夫するなど、より的確なケアが可能になります。
スポンサーリンク
前頭側頭型認知症からあなたと家族を守るための最初のステップ
「もしかして…」と感じたら、ご本人とご家族の安全と尊厳を守るために、迅速に行動を起こすことが何よりも重要です。
混乱する中で、まず何から手をつけるべきか、具体的なステップを解説します。
危険なサインを見逃さないためのチェックリスト
ご家族の行動に変化を感じたら、それが病気のサインかどうかを客観的に確認することが大切です。
以下のチェックリストに当てはまる項目が多いほど、専門機関への相談を急ぐ必要があります。
これは診断そのものではありませんが、受診の際に医師へ的確に症状を伝えるための重要な資料となります。
- 他人の気持ちを考えない、自己中心的な言動の増加
- 信号無視や万引きなど、社会のルールを平気で破る行動
- 毎日同じ時間に同じコースを散歩するなど、決まった行動への固執
- 甘いものばかり大量に食べるなど、食生活の極端な変化
- 身だしなみに全く構わず、お風呂にも入りたがらない状態
- これまで好きだった趣味や活動への興味の完全な消失
- 簡単な冗談が通じない、感情の起伏の乏しさ
これらの行動は、本人の意思ではなく、病気による症状であることをまず理解しましょう。
本人の意志とどう向き合うのか
前頭側頭型認知症の方は、ご自身が病気であるという認識(病識)がない場合がほとんどです。
そのため、病院に行くことを頑なに拒否したり、家族の心配を「余計なお世話だ」と怒り出したりすることも少なくありません。
無理に説得しようとすると、かえって関係が悪化してしまう可能性があります。
「健康診断に行こう」「もの忘れの検査ではなく、血圧の相談に行こう」など、ご本人が受け入れやすい口実で誘う工夫が必要です。
また、万が一、自傷や他害の危険性が切迫している場合は、ご本人の安全を守るために「医療保護入院」という制度を利用することも選択肢のひとつです。
これは、精神保健福祉法に基づき、ご家族等の同意と精神保健指定医の診察により入院する制度です。
今すぐ相談できる窓口
一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家とつながることが、問題解決の第一歩です。
前頭側頭型認知症について相談できる主な窓口には、以下のような場所があります。
信頼できる相談先を知っておくことは非常に重要です。
- もの忘れ外来
認知症を専門とする外来で、総合病院などに併設されています。
神経内科医や精神科医が診察にあたります。 - 認知症疾患医療センター
都道府県や指定都市が指定する認知症の専門医療機関です。
令和6年12月現在で全国に509か所設置されており、診断から治療、地域の介護サービスとの連携までを担います。 - 地域包括支援センター
高齢者の暮らしを地域でサポートするための中核機関です。
保健師や社会福祉士などの専門職がおり、認知症に関する相談や適切な医療機関の紹介などを行っています。
まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターに電話してみることから始めるのがよいでしょう。
前頭側頭型認知症による代表的な4つの症状
前頭側頭型認知症の症状は、もの忘れよりも人格や行動の変化が中心です。
ご家族が最も戸惑う代表的な症状を理解することで、冷静に対応するための心構えができます。
これらの行動心理症状(BPSD)は、記憶障害よりも目立つ周辺症状として現れます。
人格の変化
これまで穏やかだった人が急に怒りっぽくなったり、逆に活動的だった人が無気力になったりと、まるで別人のようになってしまうのが、この病気の最もつらい症状のひとつです。
理性を司る前頭葉の機能が低下するため、感情のコントロールが効かなくなり、共感性が失われます。
家族が悲しんでいても平気な顔をしていたり、TPOをわきまえない発言をしたりすることがありますが、決して悪気があるわけではありません。
愛の家グループホーム福富の実践報告でも、「性格の変化や同じ行動を繰り返すのが大きな特徴」として、専門的な理解に基づいたケアの重要性が強調されています。
※参考:【認知症を知ろう!】前頭側頭型認知症ってどんな病気? | 愛の家グループホーム福富
常同行動
常同行動とは、目的もなく同じ行動を何度も繰り返すことです。
毎日決まった時間に、一字一句違わないルートで散歩をする「周徊(しゅうかい)」や、同じ言葉を繰り返すことなどが見られます。
これは、新しい行動を計画・実行する機能が低下するために起こると考えられています。
この行動を無理に止めさせようとすると、ご本人は混乱し、不安になってしまいます。
危険がない限りは、その行動を否定せずに見守り、日課として生活スケジュールに組み込んでしまう方が、お互いのストレスを軽減できる場合があります。
ルーティンを尊重することが、穏やかな生活につながるのです。
食行動の異常
食に関するこだわりが強くなったり、異常な行動が見られたりするのも特徴です。
これまで好きではなかった甘いものばかりを大量に食べたがる「嗜好の変化」や、満腹感を得られずに食べ続けてしまう「過食」などが代表的です。
ひどい場合には、食べ物ではないものを口にしてしまう「異食」が見られることもあります。
これらの行動も、脳の機能低下によるもので、本能的な欲求を抑えられない状態です。
叱ったり食べ物を取り上げたりするのではなく、手の届く場所にお菓子などを置かない、一回の食事量を減らして回数を増やすなどの環境調整が有効です。
言葉の問題
言葉を司る側頭葉の機能が低下することで、コミュニケーションにさまざまな問題が生じます。
これは「失語」とよばれる症状で、タイプによって現れ方が異なります。
言葉の問題の例は以下の通りです。
- 物の名前が出てこない(呼称障害)
「あれ」「それ」といった指示語が増え、物の名前を思い出せなくなります。 - 言葉の意味が分からない(語義失語)
「コップ」という言葉を聞いても、それが何を指すのか理解できなくなります。
前頭側頭葉変性症の一種である意味性認知症で顕著です。 - 流暢に話せない(非流暢性失語)
言葉が途切れ途切れになったり、努力しないと発話できなかったりします。
ご本人も、言いたいことが伝わらないもどかしさを感じています。
短い言葉でゆっくり話しかけたり、実物や絵を見せたりするなど、言葉以外のコミュニケーション手段を工夫することが大切です。
前頭側頭型認知症の正式な診断までの道のり
正しい診断を受けることは、適切な治療とケア、そして公的な支援を受けるためのスタートラインです。
しかし、前頭側頭型認知症の診断は簡単ではなく、時間がかかることも少なくありません。
診断までの流れを理解しておきましょう。
診断に受診するべき科
前頭側頭型認知症が疑われる場合、受診すべき診療科は主に「神経内科」または「精神科(老年精神科)」です。
どちらの科にも認知症の専門医がいますが、それぞれ得意とする領域が少し異なります。
- 神経内科
脳や脊髄、神経、筋肉の病気を専門とします。
CTやMRIなどの画像検査を通じて、脳の器質的な変化を捉えることを得意とします。 - 精神科(老年精神科)
気分の落ち込みや意欲の低下、幻覚、妄想といった心の症状を専門とします。
うつ病など他の精神疾患との鑑別を得意とします。
かかりつけ医がいる場合は、まずはそこで相談し、専門の医療機関を紹介してもらうのがスムーズです。
症状に応じた適切な相談窓口の選び方を考えることが重要です。
診断に使われる検査内容
前頭側頭型認知症の診断は、ひとつの検査だけで決まるものではなく、さまざまな検査の結果を総合的に評価して行われます。
専門的な診断基準に基づき、慎重な判断が求められます。
診断のために行われる主な検査は以下の通りです。
| 検査の種類 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 本人や家族から、いつからどのような症状があるか詳しく聞き取り |
| 神経心理検査 | 計算や記憶、図形模写などを行い、認知機能の状態を評価 |
| 画像検査 | MRIやCTで脳の萎縮の部位や程度を確認、SPECTやPETで脳の血流や代謝を調査 |
| 血液検査 | 認知症に似た症状を引き起こす他の体の病気の有無を調査 |
特に、家族からの詳細な情報(いつから、どのように行動が変化したかなど)は、診断において極めて重要な手がかりとなります。
誤診が多い理由
前頭側頭型認知症は、他の精神疾患、特にうつ病や統合失調症、更年期障害などと誤診されやすいという課題があります。
その理由は、発症初期の症状にあります。
誤診されやすいポイントは以下の2点です。
発症の初期段階では記憶障害などが現れず、人格変貌や社会性の欠如などが目立つため、精神病と誤診されやすい傾向にあります。
また、軽微であれば認知機能に大きな支障は現れないことから、単なる性格の問題として見過ごされてしまうケースも少なくありません。
前頭側頭型認知症は、他の認知症と異なり認知機能や判断力にはあまり影響が出ません。発症年齢や初期段階の症状など、その他の情報が診断基準とされます。知らない間に症状が進行していたという方も多いのではないでしょうか?本記事では[…]
このように、もの忘れがないために認知症が見過ごされたり、意欲の低下が無気力と判断されたりして、適切な治療につながるのが遅れてしまうことがあるのです。
診断基準とセコンドオピニオンの重要性
前頭側頭型認知症の診断には、国際的な診断基準が用いられます。
この基準では、人格や行動、嗜好などの変化が重視され、6つの項目(脱抑制、無関心・無気力、共感性の低下、常同行動、食行動の変化、神経心理検査での異常)のうち3つ以上が当てはまると、前頭側頭型認知症の可能性が高いと判断されます。
もし、診断結果に疑問を感じたり、治療方針に納得がいかなかったりした場合は、セカンドオピニオンを求めることも非常に重要です。
セカンドオピニオンとは、現在診療を受けている主治医とは別の医療機関の医師に、診断や治療方針について意見を求めることです。
早期診断の重要性を理解し、納得のいく診断を受けることが、その後の長い道のりを支える土台となります。
前頭側頭型認知症と診断されてからの治療とケア
診断が確定した時、多くのご家族はショックを受け、先の見えない不安に襲われることでしょう。
しかし、ここからが新たなスタートです。
根本的な治療法はまだありませんが、症状を和らげ、穏やかな生活を送るための方法は存在します。
まず知っておきたい薬物療法の限界と可能性
現時点で、前頭側頭型認知症を根本的に治したり、進行を止めたりする薬は開発されていません。
アルツハイマー型認知症の治療薬は、症状を悪化させる可能性があるため、基本的には使用されません。
ただし、薬物療法が全く無意味というわけではありません。
攻撃性や興奮、うつ状態、こだわりといった行動・心理症状(BPSD)に対して、症状を緩和させる目的で薬が処方されることがあります。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬や、非定型抗精神病薬などが、医師の慎重な判断のもとで用いられます。
薬物療法はあくまで対症療法であり、副作用のリスクもあるため、非薬物療法と組み合わせて行うことが基本です。
本人の尊厳を守るケアの原則
前頭側頭型認知症のケアにおいて最も重要なのは、薬ではなく、周囲の関わり方です。
メディカル・ケア・サービスが実践する「MCSケアモデル」は、科学的根拠に基づき、ご本人の「できること」に着目し、その人らしさを尊重するケアを目指しています。
ケアの基本原則は以下の通りです。
- 行動を否定せず、理由を探る
一見不可解な行動にも、本人なりの理由や安心を求める気持ちが隠されていることがあります。
頭ごなしに否定せず、まずは受け入れる姿勢が大切です。 - 安心できる環境を整える
毎日同じ時間に同じことを行うなど、変化の少ない穏やかな環境は、ご本人の混乱を減らし、安心感につながります。 - 短い言葉で、具体的に伝える
複雑な話は理解しにくくなっています。
「お風呂に入りましょう」など、してほしいことをひとつずつ、短い言葉で伝えます。
このような、その人の独自性を尊重した生活支援が、前頭側頭型認知症特有の症状への適切な対応を可能にするのです。
介護者の心を守る技術
ご本人のケアと同時に、介護をするご家族自身の心と体を守ることも同じくらい重要です。
終わりの見えない介護は、誰であっても心身を消耗させます。
介護疲れは特別なことではなく、誰にでも起こりうることです。
介護者の心を守るためには、以下の点を意識しましょう。
- 完璧を目指さない
「100点満点の介護」は存在しません。
できないことがあっても自分を責めず、「今日はここまでできた」と自分を認めましょう。 - 自分の時間を持つ
デイサービスやショートステイなどの介護サービスを積極的に利用し、介護から離れて心身を休める時間(レスパイト)を意識的に作ることが不可欠です。 - 気持ちを吐き出す場所を持つ
愚痴や悩みを話せる友人や、同じ境遇の仲間がいる家族会などに参加し、一人で抱え込まないようにしましょう。
介護は一人で背負うものではありません。
社会資源を上手に利用し、チームで支えるという発想が大切です。
最新の治療研究
前頭側頭型認知症の根本治療薬はまだありませんが、世界中で原因解明や治療薬の開発に向けた研究が精力的に進められています。
原因物質である異常なたんぱく質(タウやTDP-43)を標的とした治療薬の開発や、遺伝子治療の研究など、さまざまなアプローチが試みられています。
また、メディカル・ケア・サービスでは、慶應義塾大学との共同研究などを通じて、日々のケアの記録といったデータを活用した「科学的介護」を推進しています。
どのようなケアがご本人の状態改善につながるのかを科学的に分析し、ケアの質を向上させる取り組みです。
このような地道な研究の積み重ねが、未来の治療やケアの発展につながっていくのです。
【重要】前頭側頭型認知症から未来へ備える知識
前頭側頭型認知症と向き合うことは、介護だけでなく、経済的な問題や法的な手続きなど、さまざまな備えが必要になるということです。
診断されたら、できるだけ早い段階で将来を見据えた準備を始めることが、ご家族の負担を軽減し、ご本人の尊厳を守ることにつながります。
必ず使うべき3つの公的制度
日本の社会保障制度には、介護や病気によって生活が困難になった人々を支えるための仕組みがあります。
これらは申請しなければ利用できないため、正しい知識を身につけておくことが非常に重要です。
最低限、以下の3つの制度は必ず確認しましょう。
| 制度名 | 内容 | 相談・申請窓口 |
|---|---|---|
| 難病医療費助成制度 | 前頭側頭型認知症は指定難病です。 認定されると医療費の自己負担額に上限が設けられます。 | 保健所 |
| 介護保険制度 | 40歳以上であれば利用可能。 デイサービスや訪問介護、施設入所などの介護サービスが1〜3割の自己負担で受けられます。 | 市区町村の介護保険担当課 |
| 障害年金 | 病気やけがで生活や仕事が制限される場合に支給される年金です。 現役世代の方でも受給できる可能性があります。 | 年金事務所 |
これらの制度を上手に活用することが、経済的な負担を大きく軽減します。
お金と財産の問題
認知症が進行すると、ご本人が預金の引き出しや不動産の売買などの契約行為を自分で行うことが困難になります。
判断能力が低下してからでは手遅れになる可能性があるため、早期の対策が必要です。
対策としては、「成年後見制度」の利用が一般的です。
家庭裁判所が選んだ後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。
また、まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて任意後見契約を結んだり、家族信託を活用したりする方法もあります。
お金の問題は家族間でも話しにくいことですが、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、早めに道筋をつけておくことが大切です。
介護離職を防ぐ方法
前頭側頭型認知症は若年で発症することが多いため、介護の中心となる家族が働き盛りであるケースが少なくありません。
介護のために仕事を辞めてしまう「介護離職」は、経済的な困窮や社会からの孤立につながりやすく、できる限り避けるべきです。
仕事と介護を両立するためには、国の支援制度を最大限に活用しましょう。
育児・介護休業法では、仕事と介護の両立支援制度として、以下の権利が労働者に保障されています。
- 介護休業:対象家族1人につき、通算93日まで取得可能
- 介護休暇:対象家族1人につき、年5日まで時間単位で取得可能(2人以上の場合は年10日まで)
- 所定外労働の制限:残業の免除を申請可能
まずは会社の就業規則を確認し、人事部や上司に相談することが第一歩です。
一人で抱え込まず、職場の理解と協力を得ながら、働き続けられる方法を探しましょう。
症状の進行を見据えた人生設計
前頭側頭型認知症は、ゆっくりとですが確実に進行していく病気です。
発症からの平均余命は、行動障害型では約6〜9年、意味性認知症では約12年という厚生労働省のデータもあり、個人差は大きいものの、いつかは終末期を迎えることになります。
病気が進行すると、食事の飲み込みが悪くなる(嚥下障害)、歩けなくなる、寝たきりになるといった身体的な問題も出てきます。
将来、どのような医療や介護を望むのか、ご本人の意思が確認できるうちに、家族で話し合っておくことが大切です(アドバンス・ケア・プランニング)。
また、どこで最期を迎えたいか(自宅、病院、施設など)、延命治療を望むかといったデリケートな問題についても、価値観を共有しておくことが、いざという時の難しい判断を助けてくれます。
あなたは一人ではない!同じ状況下の仲間とのつながり
介護の道のりは長く、時に孤独を感じることもあるでしょう。
しかし、日本全国には、あなたと同じ悩みや痛みを抱えながら、懸命に家族と向き合っている仲間が多くいます。
専門家や仲間とのつながりを持つことが、あなたの心を支える大きな力になります。
同じ悩みを持つ仲間と出会える場所
同じ境遇にある人々の話を聞くことは、「自分だけじゃないんだ」という安心感につながり、有益な情報交換の場にもなります。
メディカル・ケア・サービスでは、全国規模で認知症ケアの実践事例を共有する「認知症ケア実践・研究報告会」を開催しており、多くの介護者がつながる機会を創出しています。
具体的な交流の場の例は以下の通りです。
- 認知症(本人・家族)の会
各地域に、認知症の当事者やその家族が集まる会があります。
体験を語り合い、共感し合うことで、心の負担が軽くなります。 - 認知症カフェ
認知症の人やその家族、地域の人、専門家が気軽に集える場所です。
お茶を飲みながら、リラックスした雰囲気で交流できます。
お近くの認知症カフェを探してみてはいかがでしょうか。
いつでも相談できる専門家たち
日々の介護で困った時、気軽に相談できる専門家を知っておくことは、心の安定剤になります。
介護はチーム戦です。
さまざまな専門職があなたの家族を支えるチームのメンバーとなってくれます。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険サービスの利用計画(ケアプラン)を作成する専門家です。
介護全般に関する相談の最も身近なパートナーとなります。 - かかりつけ医
認知症だけでなく、ご本人の全体的な健康状態を把握してくれる存在です。 - 地域包括支援センターの専門職
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されており、医療、介護、福祉に関する総合的な相談に対応してくれます。
オンラインでつながれるコミュニティ
地理的な制約や時間の問題で、直接集まるのが難しい場合でも、オンライン上には多くのコミュニティが存在します。
SNSの家族会グループや、介護者向けのオンラインサロンなど、匿名で参加できる場所も多いです。
自宅にいながらにして、悩みを共有したり、情報を得たりできます。
ただし、オンラインの情報は玉石混交です。
公的機関や信頼できる企業が運営しているコミュニティを選ぶようにしましょう。
顔が見えないからこそ、お互いを尊重し、思いやりを持ったコミュニケーションが大切です。
参考になる書籍や体験談ブログ
前頭側頭型認知症について深く理解するためには、書籍や信頼できるウェブサイトから体系的な知識を得ることも有効です。
また、実際に介護を経験した人の体験談は、具体的な対応のヒントや、精神的な支えになることがあります。
健達ねっとSHOPでは、認知症専門医が監修した『認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣』など、認知症理解を深めるための専門書籍を提供しています。
また、メディカル・ケア・サービスでは、認知症への社会的理解を深めるため、全国の小・中・高校生を対象とした「認知症教育の出前授業」も実施しています。
このような社会全体の理解を促進する活動も、間接的にあなたと家族を支える力になっていくはずです。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、前頭側頭型認知症の基本的な知識から、症状、診断、治療、そしてご家族のケアや将来への備えまでを網羅的に解説しました。
前頭側頭型認知症は、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも大きな影響を与える深刻な病気です。
しかし、その不可解に見える行動が病気の症状であることを正しく理解し、適切なケアと支援につながることで、穏やかな時間を取り戻すことは決して不可能ではありません。
最も大切なことは、一人ですべてを抱え込まないことです。
この記事で紹介したように、あなたを支える専門家、公的な制度、そして同じ痛みを知る仲間が必ずいます。
どうか勇気を出して、相談窓口のドアを叩いてみてください。
「健達ねっと」は、これからも学研グループの一員として、ご家族の介護と健康を支えるため、中立な立場から信頼できる情報をお届けし続けます。
この記事が、先の見えない不安の中にいるあなたにとって、未来を照らす一条の光となることを心から願っています。