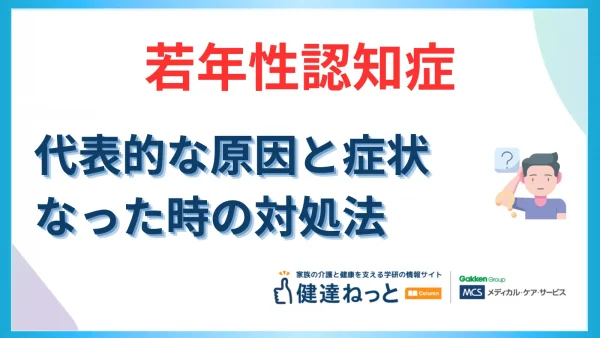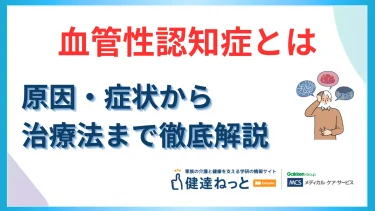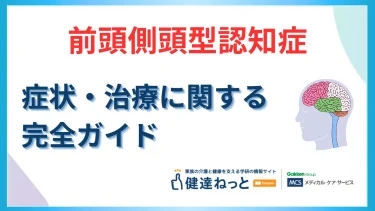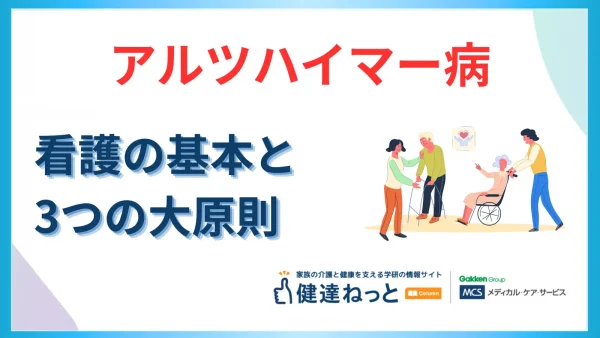- 「最近、仕事のミスが目立つようになった…」
- 「親のもの忘れがひどいが、まだ若いし年のせいだろうか?」
- 「もし若年性認知症だったら、仕事や家族、これからの生活はどうなってしまうのだろう…」
働き盛りの世代にとって、心身の些細な変化は「疲れのせい」で片付けてしまいがちです。
しかし、その変化が若年性認知症のサインである可能性もゼロではありません。
将来への漠然とした不安、経済的な心配、そして家族への影響を考えると、なかなか現実と向き合えないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そのような不安を抱えるあなたのために、若年性認知症に関する正しい知識と具体的な対処法を網羅的に解説します。
この記事で分かること
- 若年性認知症の基本的な知識と高齢者の認知症との違い
- 本人や周囲が気づきやすい初期症状のチェックリスト
- 最新の治療法や公的な支援制度(仕事・お金)
- 今日から始められる予防・対策
この記事を最後まで読めば、若年性認知症への漠然とした恐怖が、具体的な知識と「今、なにをすべきか」という前向きな行動へと変わります。
一人で悩まず、まずは正しい情報を知ることから始めましょう。
また、若年性アルツハイマーを患った奥様の軌跡をマガジンで公開していますので、あわせて参考にしてみてください。
スポンサーリンク
若年性認知症とは?高齢者の認知症との違い
若年性認知症は、単に若い人がなる認知症というだけではありません。
高齢者の認知症とは異なる特有の課題があり、正しい理解が不可欠です。
若年性認知症は65歳未満で発症する認知症の総称
若年性認知症とは、18歳から64歳までの間に発症する認知症性疾患の総称です。
「若年性認知症」という固有の病気があるわけではなく、アルツハイマー病など、認知症を引き起こすさまざまな疾患を発症した年齢で区分した呼び名です。
発症が働き盛りの世代と重なるため、ご本人やご家族の生活に与える影響が非常に大きいという特徴があります。
そのため、病気への理解だけでなく、経済面や就労・子育てなど、多角的なサポート体制を知っておくことが重要です。
若年性認知症は若い世代でも発症する可能性があります。
詳しくは「20代の若年性認知症とは?症状やチェック方法を解説します」で解説していますので、あわせてご覧ください。
高齢者の認知症との3つの大きな違い
若年性認知症と高齢者の認知症は、原因となる疾患は共通するものが多いですが、ご本人やご家族が直面する状況に大きな違いがあります。
主な違いは以下の3点です。
| 比較項目 | 若年性認知症 | 高齢者の認知症 |
| 経済的影響 | 家計の主軸を担っている場合が多く、失職による収入減の影響が深刻 | 年金受給世代が多く、直接的な収入減の影響は比較的小さい |
| 社会的影響 | 働き盛りで、住宅ローンや子どもの教育などの責任が大きい | 子育てが一段落しているケースが多い |
| 診断 | 本人も周囲も「年のせい」と考えにくく、他の疾患(うつ病など)と間違われ、診断が遅れがち | もの忘れを年齢によるものと考え、受診につながりやすい |
これらの違いから、若年性認知症の場合は、病気の治療と並行して、経済的な問題や今後の生活設計について早期に考え始める必要があります。
日本の患者数は約3.57万人
2017~2019年度に実施された日本医療研究開発機構(AMED)の調査によると、日本の若年性認知症の患者数は約3.57万人と推計されています。
これは、18歳から64歳までの人口10万人あたり50.9人にあたり、決して他人事ではないことが分かるでしょう。
厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要」によると、18歳~64歳人口における人口10万人当たり50.9人の有病率に相当し、前回調査(平成21年3月)の3万7,800人から微減です。
特に、年齢が上がるにつれて有病率は高くなる傾向にあり、働き盛りの50代後半から60代前半にかけて急増します。
この事実は、早期発見と社会全体でのサポート体制の重要性を示しています。
スポンサーリンク
本人や周囲が気づく若年性認知症の初期症状と確認方法
若年性認知症は、初期段階では疲れやストレス、更年期障害など他の不調と間違われやすいのが特徴です。
早期発見のために、些細な変化に気づくことが重要です。
日常生活で現れる変化のチェックリスト
日常生活の中に、若年性認知症のサインが隠れていることがあります。
以下のような変化が複数当てはまる場合は、一度専門機関への相談を検討しましょう。
| 分類 | 具体的な変化の例 |
| 記憶の問題 | ・約束やスケジュールを忘れることが増えた ・同じことを何度も話したり、質問したりする |
| 実行機能の問題 | ・料理や仕事など、段取りよく進められなくなった ・家電の操作が分からなくなる |
| 見当識の問題 | ・慣れているはずの道で迷う ・今日の日付や曜日が分からなくなる |
| 性格・感情の変化 | ・以前より怒りっぽくなった、または無気力になった ・趣味など、好きだったことへの関心を失った |
これらの症状は、あくまでひとつの目安です。
詳しくは「認知症の初期症状とは?注意するべき症状と対策を解説します」でも解説していますので、気になる方はあわせてご覧ください。
年を重ねて生じる「もの忘れ」との違い
誰でも年を重ねるともの忘れは増えますが、若年性認知症によるもの忘れと加齢によるもの忘れには質的な違いがあります。
体験したことの一部を忘れるのが加齢によるもの忘れ、体験したこと自体を忘れてしまうのが認知症によるもの忘れです。
| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ | |
| 忘れる範囲 | 体験の一部(例:朝食のおかず) | 体験の全体(例:朝食を食べたこと自体) |
| 自覚 | もの忘れの自覚がある | もの忘れの自覚がないことが多い |
| 進行 | あまり進行しない | ゆっくりとだが確実に進行する |
| 日常生活 | 大きな支障はない | 次第に支障が出てくる |
加齢によるもの忘れは生理的な現象ですが、認知症によるもの忘れは病的なものであり、放置すると進行してしまうため注意が必要です。
職場で見られるサイン
若年性認知症は、家庭よりも先に職場で問題が顕在化することが少なくありません。
ご本人に自覚がなくても、同僚や上司が変化に気づくことがあります。
- 会議の内容を理解できない、覚えていない
- 仕事の段取りが悪くなり、ミスが増える
- 顧客の名前やアポイントを忘れる
- 電話の取り次ぎがスムーズにできなくなる
- 遅刻が増える、または身だしなみが乱れる
これらのサインは、うつ病や適応障害など他の精神疾患の可能性も考えられます。
しかし、若年性認知症の可能性も視野に入れ、産業医や専門窓口に相談することが大切です。
家族が気づける変化
家庭は最もリラックスできる空間だからこそ、ごく自然な言動の中に変化が現れることがあります。
家族だからこそ気づけるサインを見逃さないようにしましょう。
- 料理のレパートリーが減り、同じものばかり作る
- 会話が噛み合わなくなる、話の辻褄が合わない
- 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなる
- ささいなことで怒ったり、頑固になったりする
- 服装に無頓着になる、季節に合わない服を着る
このような変化に気づいたときは、頭ごなしに否定したり問い詰めたりせず、まずは心配しているという気持ちを伝え、一緒に相談窓口へ行くことを提案してみましょう。
認知症の前兆については「早期発見のキーポイントである認知症の前兆とは?予防策も」で詳しく解説しています。
若年性認知症が発症する6つの主な原因
若年性認知症は、さまざまな病気が原因で引き起こされます。
原因疾患によって症状の現れ方や進行の仕方が異なるため、正しい診断が極めて重要です。
アルツハイマー型認知症
若年性認知症の原因として最も多いのが、アルツハイマー型認知症で、全体の52.6%を占めます。
脳内にアミロイドβという異常なたんぱく質が蓄積し、脳の神経細胞が破壊されることで発症します。
- 主な初期症状:もの忘れ(特に新しい記憶)、日付や場所が分からなくなる見当識障害
- 進行:ゆっくりと進行する
- 特徴:若い世代で発症する場合、もの忘れよりも先に、段取りが組めなくなる実行機能障害や、空間を認識しにくくなる視空間認知障害が現れることもある
アルツハイマー病と認知症の違いについては、「アルツハイマー病と認知症に違いはあるの?徹底解説します!」で詳しく解説しています。
参考情報:厚生労働省の最新調査(2017-2019年)によると、アルツハイマー型認知症(52.6%)、次に血管性認知症(17.1%)、前頭側頭型認知症(9.4%)の順となっています。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血など、脳の血管の病気によって神経細胞がダメージを受けることで発症します。
アルツハイマー型に次いで多い原因疾患で、17.1%を占めています。
- 主な症状:脳のどの部分が損傷したかによって症状が異なり、「まだら認知症」とも呼ばれる
- 症状の例:手足の麻痺、言語障害、感情のコントロールが難しくなる感情失禁など
- 進行:脳血管障害が再発するたびに、階段状に悪化する傾向がある
生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症)がある方はリスクが高まるため、日頃の健康管理が予防につながります。
血管性認知症の詳細は以下も参考にしてみてください。
「最近、親の物忘れが気になる…」 「さっきまで穏やかだったのに、急に怒り出すことがあるのはなぜ?」 「血管性認知症という言葉を聞いたけど、どのような病気なんだろう?」ご家族のこのような変化に戸惑いや不安を感じてい[…]
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症します。
感情や理性をコントロールする部分が障害されるため、人格の変化や社会性の欠如といった特有の症状が現れます。
- 主な症状:社会のルールを守れなくなる(万引きなど)、相手の気持ちを考えず思ったことをそのまま口にする、毎日同じ時間に同じ行動を繰り返す常同行動
- 特徴:初期にはもの忘れがあまり目立たないため、認知症と気づかれにくい
この病気は国の指定難病であり、専門的な診断とケアが不可欠です。
前頭側頭型認知症の詳細は以下も参考にしてみてください。
「最近、家族の性格がまるで別人のように変わってしまった…」「理解できない行動が増え、どう接すればよいか分からない」「もしかしたら認知症かもしれないけど、誰に相談すれば…」「この先どうなるのか、経済的なことも含めて不安で仕方が[…]
頭部外傷による認知症
交通事故や転倒などで頭に強い衝撃を受けた後、数か月から数年経ってから認知症の症状が現れることがあります。
慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症などが原因となることもあります。
- 主な症状:注意力の低下、無気力、記憶障害など
- 特徴:原因によっては、手術などで症状が劇的に改善する可能性がある
頭を打った後に、歩き方がおかしくなったり、失禁したり、ぼーっとするようになったりした場合は、すぐに脳神経外科を受診することが重要です。
レビー小体型認知症/パーキンソン病認知症
脳の神経細胞に「レビー小体」という特殊なたんぱく質が溜まることで発症します。
パーキンソン病の症状(手足の震え、筋肉のこわばりなど)が先に出るか、認知機能の低下が先に出るかで病名が異なります。
- 特徴的な症状:実際にはないものが見える「幻視」、日によって頭がはっきりしたりぼーっとしたりの差が激しい「認知機能の変動」、睡眠中に大声で叫んだり暴れたりする「レム睡眠行動異常症」
薬に対して過敏に反応することがあるため、薬剤の選択には専門的な知識が求められます。
レビー小体型認知症の詳細は以下も参考にしてみてください。
三大認知症の一つであるレビー小体型認知症。認知症と一括りにされていても、原因や症状の特徴などに違いがあります。では、レビー小体型認知症とは一体どのような認知症なのでしょうか。今回はレビー小体型認知症の症状を経過ごとに[…]
アルコール関連障害
長期間にわたる過度な飲酒は、ビタミンB1欠乏による「ウェルニッケ脳症」や、脳そのものが萎縮する「アルコール性認知症」を引き起こす可能性があります。
- 主な症状:もの忘れ、作り話、無気力、見当識障害など
- 特徴:断酒をすることで、症状の進行を止められたり、改善したりする可能性がある
アルコール依存症が背景にあることが多く、精神科での専門的な治療が必要となります。
若年性認知症かも?と思ってからの診断・治療の流れ
「もしかして?」と感じたら、ためらわずに専門機関を受診することが、その後の人生を大きく左右します。
ここでは、診断から治療までの一般的な流れを解説します。
まず受診するのは何科?
認知症が疑われる場合、どの診療科を受診すればよいか迷うかもしれません。
以下のような専門の診療科が窓口となります。
- もの忘れ外来
- 精神科・心療内科
- 神経内科・脳神経外科
まずは、かかりつけ医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのもよい方法です。
お住まいの地域の地域包括支援センターでも、医療機関の情報を提供してくれます。
診断までの流れと標準的な検査方法
若年性認知症の診断は、さまざまな検査を組み合わせて総合的に行われます。
これは、他の病気の可能性を排除し、原因疾患を特定するために非常に重要です。
- 問診:本人や家族から、いつからどのような症状があるか、生活状況などを詳しく聞き取る。
- 神経心理学検査:計算問題や図形の模写などを行い、記憶力や判断力といった認知機能を客観的に評価する。
- 画像検査:CT・MRIで脳の萎縮や脳血管障害を、SPECT・PETで脳の血流や代謝を調べる。
これらの検査結果を総合的に判断し、診断が確定します。
認知症診断の詳しい流れは「認知症は早期診断が大切!診断の流れや必要な情報を解説し」でも解説しています。
最新の治療法である新薬の効果
若年性認知症の原因で最も多いアルツハイマー病に対して、近年、画期的な新薬が登場し、治療に大きな希望をもたらしています。
2023年12月に保険適用となった治療薬「レカネマブ(レケンビ)」は、病気の原因物質である脳内のアミロイドβに直接作用し、病気の進行を約7.5か月遅らせる効果が確認されています。
この薬は、病気の原因物質に直接働きかける初めての薬(疾患修飾薬)として注目されています。
ただし、誰でも使えるわけではなく、いくつかの条件があります。
| 項目 | 詳細 |
| 対象者 | 軽度認知障害(MCI)または軽度のアルツハイマー病の方 |
| 投与方法 | 2週間に1回の点滴(原則18か月間) |
| 年間薬価 | 約298万円(高額療養費制度の対象) |
| 注意点 | 脳浮腫や脳出血などの副作用のリスクがある |
レカネマブは、働き盛りの若年性認知症の方々が、より長く社会で活躍し続けるための重要な選択肢となりえます。
詳しくは「【動画あり】認知症の権威と語る「アルツハイマー病の新治療薬『レカネマブ』とは」」をご覧ください。
参考情報:
- レカネマブは2023年12月20日に保険収載が開始されました(日本老年医学会)
- 臨床試験では、症状の進行をおよそ7.5か月遅らせる効果が認められています(国立長寿医療研究センター)
【結論】若年性認知症は完治するのか
残念ながら、2025年現在、アルツハイマー型認知症などの多くの認知症を根本的に治す(完治させる)治療法はまだ見つかっていません。
しかし、これは決して絶望を意味するものではありません。
新薬の登場により、病気の進行を緩やかにすることが可能になりました。
また、薬物療法だけでなく、リハビリテーションや生活環境の調整、適切なケアによって、症状を和らげ、ご本人らしい穏やかな生活を長く続けることは十分に可能です。
原因疾患によっては、手術などで症状が改善する場合もあります。
早期に診断を受け、適切な治療とサポートにつながることが、未来への希望を拓く鍵となります。
若年性認知症診断後の生活を守る仕事・お金の公的支援制度
若年性認知症と診断されると、ご本人だけでなくご家族も、将来の生活、特に仕事やお金のことで大きな不安を抱えることになります。
しかし、日本には生活を支えるためのさまざまな公的支援制度があります。
仕事はどうする?退職せずに働き続けるための支援
診断後すぐに仕事を辞める必要はありません。
病状や仕事内容に応じて、働き続けるためのさまざまな選択肢があります。
- 上司や人事部、産業医に相談し、時短勤務や部署異動など無理なく働ける環境を整えてもらう(合理的配慮)
- まずは治療に専念するために、休職制度や傷病手当金を利用する
- ハローワークの障害者専門窓口で、病状に合った仕事探しをサポートしてもらう
- 地域障害者職業センターで、職業評価や職場復帰の支援など専門的なサポートを受ける
働き続けることは、経済的な安定だけでなく、社会とのつながりを保ち、ご本人の自尊心を守る上でも非常に重要です。
経済的負担を軽減する4つの柱
収入の減少や医療費の負担など、経済的な不安を和らげるための公的な制度があります。
これらはご自身で申請しないと利用できないため、積極的に情報を集めましょう。
| 制度名 | 内容 |
| 障害年金 | 病気やけがで生活や仕事が制限される場合に支給される年金。若年性認知症も対象。 |
| 介護保険 | 40歳以上であれば、若年性認知症(特定疾病)として認定されると介護サービスが1~3割負担で利用可能。 |
| 自立支援医療制度 | 認知症の通院医療費の自己負担が原則1割に軽減される制度。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 税金の控除や公共料金の割引など、さまざまな福祉サービスが受けられる。 |
これらの制度は複雑なため、お住まいの市区町村の障害福祉課や地域包括支援センター、若年性認知症支援コーディネーターなどに相談するのがオススメです。
介護に関する相談窓口は「介護の相談窓口はどこ?相談先を紹介!」でも詳しく解説しています。
その他に利用できる制度
上記の4つの柱以外にも、生活状況に応じて利用できる制度があります。
困ったときには、一人で抱え込まずに相談することが大切です。
- 生活福祉資金貸付制度:低所得者世帯などを対象に、生活費や医療費などを無利子または低金利で貸し付ける制度。
- 生活保護制度:病気などで働けなくなり、あらゆる支援制度を活用してもなお生活に困窮する場合に、最低限度の生活を保障する制度。
これらの制度は「最後のセーフティネット」です。
利用には条件がありますので、まずは市区町村の福祉担当窓口に相談してみてください。
もし若年性認知症と診断されたら?本人と家族を支える相談窓口と支援サービス
診断の告知は、ご本人にとってもご家族にとっても大きな衝撃です。
しかし、一人で、また家族だけで抱え込む必要はありません。
社会にはあなた方を支える多くの専門家や仲間がいます。
まず相談がオススメな全国の専門相談窓口
どこに相談すればよいか分からないときは、まず以下の専門相談窓口に電話してみましょう。
専門の相談員が、悩みを聞き、必要な情報提供や関係機関への橋渡しをしてくれます。
- 若年性認知症コールセンター(0800-100-2707)
- 各都道府県の若年性認知症支援コーディネーター
- お住まいの地域の地域包括支援センター
これらの窓口は、匿名での相談も可能です。
まずは今の気持ちを話してみるだけでも、心が少し軽くなるはずです。
同じ悩みを分かち合える場所
専門家への相談とあわせて、同じ病気や悩みを抱える仲間とつながることも大きな支えになります。
同じ立場だからこそ分かり合えることがあり、孤独感を和らげてくれます。
- 本人・家族の会(当事者会):若年性認知症のご本人やその家族が集まり、情報交換や交流を行う会。日頃の悩みや不安を気兼ねなく話せる貴重な場所です。
- 認知症カフェ(オレンジカフェ):認知症の人やその家族、地域住民、専門家などが気軽に集える場所。お茶を飲みながらリラックスした雰囲気で交流できます。
認知症の方とのコミュニケーションに悩んだ際は、「認知症患者の会話の特徴と注意点」も参考にしてみてください。
若年性認知症の親を持つ子どものための支援
親が若年性認知症になった場合、思春期や青年期の子どもたちは、進学や就職、結婚といった自身のライフイベントと、親の介護(ヤングケアラー問題)という二重の課題に直面することがあります。
子どもたちが正しい知識を持つことは、不安の軽減と家族関係の改善につながります。
当社が実施した「認知症教育の出前授業」では、授業後に認知症や介護施設に対して「よいイメージに変わった」と回答した子どもは92%に達しています。
身近に認知症の祖父母がいる子どもからは「これからは今までよりも多く祖父母の家を訪れ、元気に過ごしてもらえるようにしたいと思った」という感想も寄せられています。
(参考:メディカル・ケア・サービス 認知症教育の出前授業に関する調査)
これは、子どもたちが病気を正しく理解することで、親への接し方が前向きに変わる可能性を示唆しています。
子ども世代を対象とした支援団体や相談窓口もあるため、家族だけで抱え込まず、外部のサポートを活用することが大切です。
今からできる若年性認知症の予防と進行を遅らせるための対策
若年性認知症の発症を完全に防ぐ方法はまだありませんが、リスクを減らすための生活習慣は科学的に明らかになってきています。
今日から始められる対策で、脳の健康を守りましょう。
適度な運動
運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の活動を活発にすることが分かっています。
特に、運動と頭の体操を組み合わせた「コグニサイズ」がオススメです。
- 運動の目安:ウォーキングなどの有酸素運動を、週に3回以上、1回30分程度行う。
- ながら運動:散歩をしながらしりとりをする、計算をしながら踏み台昇降をするなど。
- ノドの筋トレ:当社が開発した「ノドトレ」は、嚥下機能を鍛え、誤嚥性肺炎だけでなく認知症予防にもつながる手軽なトレーニングです。
無理のない範囲で、楽しんで続けられる運動を見つけることが長続きの秘訣です。
専門医による詳しい解説は「生活習慣から認知症を予防する」をご覧ください。
バランスのよい食事
特定の食品だけを食べれば認知症を防げるというものはありませんが、バランスのよい食事は脳の健康の基本です。
特に、魚や野菜、果物を中心とした食生活が推奨されています。
| 積極的に摂りたい栄養素 | 多く含まれる食品 |
| DHA・EPA | アジ、サバ、イワシなどの青魚 |
| ビタミン類 | 緑黄色野菜、果物 |
| ポリフェノール | 大豆製品、ベリー類、緑茶 |
逆に、糖質や飽和脂肪酸の過剰な摂取は、アルツハイマー病のリスクを高める可能性が指摘されています。
日々の食生活を見直すことが、未来の脳への投資となります。
「認知症予防できていますか?効果的な食べ物やトレーニング」でも詳しく紹介しています。
認知機能をサポートするサプリメント
バランスのよい食事を基本としつつ、科学的根拠に基づいた機能性表示食品を活用することも、認知機能の維持に役立つ選択肢のひとつです。
近年、認知機能の維持をサポートするさまざまなサプリメントが開発されており、以下のような成分が注目されています。
- プラズマローゲン:記憶力や認知機能の維持をサポート
- ビフィズス菌(特定株):腸脳相関を通じた認知機能への働きかけ
- 冬虫夏草由来成分:認知機能速度(視覚情報処理能力)の維持
これらの機能性表示食品は、健常な中高年の方の認知機能維持をサポートする目的で開発されており、日々の生活習慣の改善とあわせて活用することで、より包括的な認知症予防対策が期待できます。
詳しくは「認知機能改善サプリ」をご覧ください。
※注意事項
- サプリメントは医薬品ではなく、認知症の治療薬ではありません
- あくまで健常な方の認知機能維持をサポートする目的のものです
- 気になる症状がある場合は、まず専門医への相談を優先してください
人とのコミュニケーション
人と会話したり、笑い合ったりすることは、脳にとって非常によい刺激となります。
社会的な孤立は認知症の大きなリスク要因のひとつです。
- 家族や友人との会話を大切にする
- 趣味のサークルや地域の活動に参加する
- ボランティア活動などに挑戦してみる
積極的に社会と関わり、知的で活動的な生活を送ることが、脳の若さを保つことにつながります。
定年退職後なども、新たなコミュニティを見つけることが重要です。
生活習慣病の予防と治療
高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、血管性認知症の直接的な原因となるだけでなく、アルツハイマー型認知症のリスクも高めることが分かっています。
- 定期的な健康診断で自身の健康状態を把握する
- 塩分・糖分・脂肪分を控えたバランスのよい食事を心がける
- 禁煙し、飲酒は適量を守る
生活習慣病のコントロールは、全身の健康を守るだけでなく、脳の健康を守ることにも直結します。
詳しくは「認知症と生活習慣病には関係がある?改善すべきポイントも」をご覧ください。
MCI(軽度認知障害)段階での対策
MCI(軽度認知障害)は、もの忘れなどの症状はあるものの、日常生活に支障はない、健常な状態と認知症の中間の段階です。
この段階で適切な対策を行えば、健常な状態に回復したり、認知症への進行を遅らせたりすることが可能です。
科学的根拠に基づいたケアは、症状の改善につながる可能性があります。
当社グループが実践する科学的介護「MCSケアモデル」では、4,489名の対象者のうち3,821名(85%以上)で認知症の周辺症状や心身の状態改善が確認されています。(参考:メディカル・ケア・サービス MCSの取り組み)
このMCIの段階で気づき、予防に取り組むことが極めて重要です。
MCIについて詳しく知りたい方は「MCI(軽度認知障害)とは?認知症との違いとすぐできるセルフ」もぜひご覧ください。
参考情報:MCIから正常な状態に回復する割合は1年で16~41%、MCIから認知症に進行する割合は1年で5~15%です(東京都健康長寿医療センター)
スポンサーリンク
若年性認知症に関するよくある質問
ここでは、若年性認知症に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
若年性認知症になりやすい性別はどちらか
厚生労働省の調査によると、若年性認知症の有病率は男性の方が女性よりも高い傾向にあります。
2017-2019年度の最新調査では、男性の有病率が女性よりも高く、特に18歳から49歳までの層では、男性の有病率が女性の2倍以上となっています。
しかし、50歳以降は男女差が縮まる傾向にあり、性別に関わらず誰もが注意すべき病気といえます。
参考情報:2006-2008年調査では、男性57.8人、女性36.7人(人口10万人当たり)と男性の有病率が高い結果でした(厚生労働省)
若年性アルツハイマー病は早くて何歳から発症するか
若年性アルツハイマー病は、遺伝的な要因が関わる「家族性アルツハイマー病」の場合、30代や40代といった非常に若い年齢で発症することがあります。
しかし、これは非常に稀なケースです。
多くの若年性認知症は50代以降に発症しますが、20代での発症例も報告されており、年齢だけで「自分は大丈夫」と考えるのは禁物です。
認知症になりにくい人の性格はあるか
認知症の発症に直接的な性格の因果関係は証明されていません。
しかし、結果的に認知症のリスクを下げる可能性のある性格傾向は指摘されています。
- 好奇心旺盛で新しいことに挑戦するのが好き
- 社交的で人との交流を楽しむ
- 真面目で誠実(健康管理をきちんと行う傾向)
- ストレスを溜め込まず、楽観的
このような性格の方は、知的活動や社会参加に積極的で、生活習慣も整っている傾向があるため、結果として認知症のリスクを下げている可能性があります。
食生活と認知症リスクの関係は「認知症になりやすい食べ物ってなに?」で解説しています。
若年性認知症になった人の余命はどれくらいか
若年性認知症の余命は、原因疾患や発症年齢、健康状態、受けるケアの質など、さまざまな要因によって大きく異なるため、一概に「何年」とはいえません。
診断を受けてから20年以上穏やかに過ごされる方もいます。
重要なのは、残された時間をどう生きるかです。
適切な治療とサポートを受け、ご本人らしい生活を一日でも長く続けられるよう、周囲が支えていくことがなによりも大切です。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、若年性認知症の症状や原因、そして最新の治療法から公的な支援制度まで、幅広く解説しました。
若年性認知症は、働き盛りの世代に発症するため、ご本人やご家族の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
しかし、決して絶望的な病気ではありません。
重要なのは、病気を正しく理解し、早期に適切な対応をとることです。
また、日々の生活習慣の改善とあわせて、科学的根拠に基づいた認知機能改善サプリメントの活用も、健常な方の認知機能維持をサポートする選択肢のひとつとして検討できます。
「もしかして?」と感じたら、ためらわずに専門の相談窓口や医療機関を訪れてください。
早期の診断と適切なサポートは、病気の進行を穏やかにし、あなたとあなたの大切な家族の未来を守るための最も確実な一歩となります。
この記事が、あなたの不安を和らげ、次への行動を起こすきっかけとなれば幸いです。