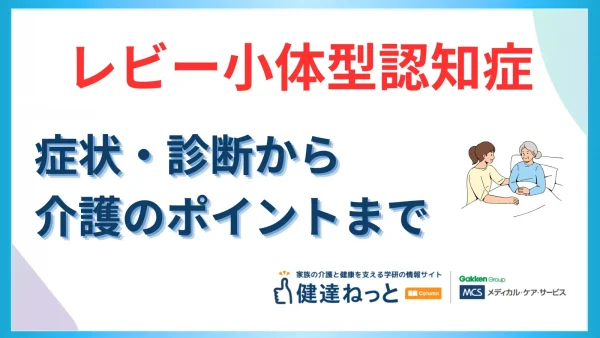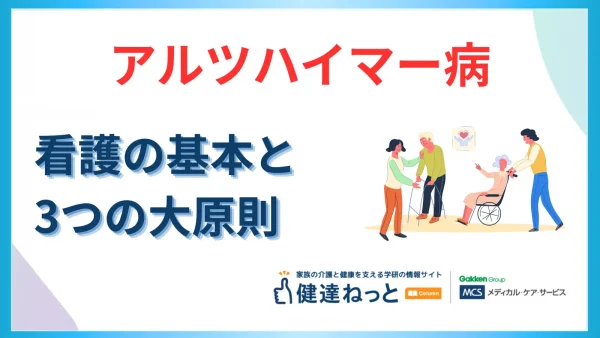- しっかりしている時と、ぼーっとしている時の差が激しい
- 誰もいないのに「人がいる」といい、不安そうにしている
- 歩き方がおぼつかなくなり、よくつまずくようになった
- 夜中に突然、大声を出したり手足をばたつかせたりする
このようなご家族の変化に、「これは単なる年のせい?それとも何かの病気?」と戸惑い、どう対応すればよいか分からず、ひとりで悩みを抱えていませんか。
そのお悩みは、決してあなただけのものではありません。
この記事は、そのような不安を抱えるあなたのために、レビー小体型認知症の正しい知識と具体的な対応策を網羅した「完全ガイド」です。
この記事を読めば、以下の点が明確になります。
- レビー小体型認知症に特徴的な症状とアルツハイマー病との違い
- 診断までの流れと最新の検査方法
- 症状をコントロールする治療法と、家族ができる介護の具体的なポイント
- ひとりで抱え込まないために利用できる公的制度や相談窓口
最後までお読みいただくことで、病気への漠然とした恐怖が「やるべきこと」への具体的な理解に変わり、ご本人とご家族が安心して前に進むための一歩を踏み出せるでしょう。
スポンサーリンク
レビー小体型認知症とは?
レビー小体型認知症は、脳の神経細胞に「レビー小体」という特殊なたんぱく質が蓄積することで発症する認知症です。
特徴的な症状を正しく理解し、早期に対応することが、ご本人とご家族の穏やかな生活につながります。
そもそもレビー小体(αシヌクレイン)とは
レビー小体とは、「α(アルファ)-シヌクレイン」というたんぱく質が脳の神経細胞内に集まってできた異常な構造物です。
本来、α-シヌクレインは脳内で重要な働きを担うたんぱく質ですが、何らかの原因で異常な形に変化し、凝集してしまうと考えられています。
このレビー小体が脳の広範囲、特に思考や行動を司る大脳皮質や、体の動きを調整する脳幹に出現すると、神経細胞がダメージを受けて減少します。
その結果、認知機能の障害やパーキンソン症状といった、レビー小体型認知症特有の多様な症状が引き起こされるのです。
レビー小体型認知症は日本で2番目に多い認知症
レビー小体型認知症は、決して珍しい病気ではありません。
厚生労働省の統計データによると、日本ではアルツハイマー型認知症が認知症全体の67.6%を占めており、レビー小体型認知症は認知症全体の4.3%を占めています。
これにより、レビー小体型認知症は2番目に多い認知症のひとつといわれています。
高齢者の認知症の主要な原因のひとつであり、多くは65歳以上で発症します。
しかし、その特徴的な症状から他の病気と間違われたり、本人や家族が認知症と気づかなかったりするケースも少なくありません。
正しい知識を持つことが、早期発見・早期対応への第一歩となります。
アルツハイマーやパーキンソン病との違い・比較表
レビー小体型認知症は、初期症状がアルツハイマー型認知症やパーキンソン病と似ているため、しばしば混同されます。
しかし、原因となる脳の変化や症状の現れ方に明確な違いがあり、この違いを理解することが適切な治療やケアにつながります。
主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | レビー小体型認知症 | アルツハイマー型認知症 | パーキンソン病 |
|---|---|---|---|
| 初期の主な症状 | 幻視、パーキンソン症状、認知機能の変動 | もの忘れ(記憶障害) | 手の震え、動作が遅い |
| 記憶障害 | 比較的軽度(もの忘れより注意・遂行機能障害が目立つ) | 早期から重度 | 認知症を合併しなければ目立たない |
| 幻視 | 詳細でリアルな幻視が繰り返し出現 | 稀、または末期に見られる | 稀、または薬の副作用で出現 |
| パーキンソン症状 | 多くのケースで早期から出現 | 末期まで見られないことが多い | 中核症状として必ず出現 |
| 原因物質 | α-シヌクレイン(レビー小体) | アミロイドβ、タウたんぱく質 | α-シヌクレイン(レビー小体) |
| 病変の主な部位 | 脳幹から大脳皮質まで広範囲 | 海馬、側頭葉、頭頂葉 | 脳幹(黒質) |
特に、レビー小体型認知症は初期からもの忘れよりも幻視やパーキンソン症状が目立つ傾向にあります。
このような特徴を把握しておくことが重要です。
スポンサーリンク
レビー小体型認知症の4つの主な症状と見逃しやすいサイン
レビー小体型認知症には、他の認知症とは異なる特徴的な症状が現れます。
これらのサインに早く気づくことが、適切な診断とケアの始まりです。
ここでは代表的な4つの「中核症状」と、見逃されやすいその他の症状を解説します。
認知機能の変動
レビー小体型認知症の最も特徴的な症状のひとつが、認知機能の著しい変動です。
まるで別人のように「はっきりしている時」と「ぼんやりしている時」を数時間から数日の単位で繰り返します。
注意力が散漫になったり、会話が噛み合わなくなったりする時間帯があるかと思えば、普段と変わらず論理的に話せる時間帯もあるのです。
この波は、脳内の神経伝達物質の働きの不安定さが原因と考えられています。
ご家族からは「わざとやっているのでは?」と誤解されがちですが、これは病気による症状なのです。
認知機能の維持に関心がある方には、機能性表示食品として認められた認知機能サポート成分やプラズマローゲンなどが注目されていますが、これらは健康食品であり医薬品ではありません。
リアルな幻視
「そこに子どもが座っている」「虫がたくさんいる」など、実際にはないものが、あたかも本物であるかのようにリアルに見える「幻視」も、レビー小体型認知症の代表的な症状です。
多くの場合、ご本人はその光景をありのままに体験しており、強い不安や恐怖を感じています。
幻視の内容は、人物や小動物、虫など具体的であることが多いのが特徴です。
ご家族が「そんなものはいない」と強く否定すると、ご本人は混乱し、ますます不安が強くなってしまいます。
幻視について詳しくは、レビー小体型認知症の症状ってどんなものがあるの?の記事もご参照ください。
パーキンソン症状
レビー小体型認知症では、パーキンソン病で見られるような運動症状が出現します。
これは、脳内の動きをスムーズにするドパミンという神経伝達物質が、レビー小体の影響で減少するために起こります。
パーキンソン症状の代表的なものは、以下の通りです。
- 動作緩慢:動きが遅く、のっそりとなる。
- 筋強剛(きんきょうごう):筋肉がこわばり、他人が手足を動かそうとすると抵抗がある。
- 振戦(しんせん):じっとしている時に手足が震える。
- 姿勢反射障害:体のバランスがとりにくく、転びやすくなる。すり足、小刻み歩行も特徴。
これらの症状は転倒による骨折のリスクに直結するため、早期からの対策が不可欠です。
手の震えの原因については、手の震えの原因は認知症?レビー小体型認知症との関係で詳しく解説しています。
レム睡眠行動障害
夜、眠っている間に突然大声で叫んだり、隣で寝ている人を殴ったり蹴ったりするような激しい行動が見られることがあります。
これは「レム睡眠行動異常症(RBD)」とよばれ、レビー小体型認知症の非常に重要な初期サインのひとつです。
通常、夢を見ているレム睡眠中は、体が金縛りのように動かない状態(筋弛緩)になっています。
しかし、レビー小体型認知症ではこの仕組みがうまく働かず、見ている夢の内容がそのまま行動として現れてしまうのです。
ご本人に自覚はないことが多く、ご家族が最初に気づくケースがほとんどです。
睡眠障害と認知症の関係については、寝言は認知症の前兆?レム睡眠行動障害についてもご覧ください。
その他、見逃されやすい症状
上記の中核症状以外にも、レビー小体型認知症ではさまざまなサインが現れます。
これらは他の病気や加齢による変化と間違われやすいため、注意が必要です。
見逃されやすい主な症状は以下の通りです。
- 自律神経症状:頑固な便秘、頻尿、立ちくらみ(起立性低血圧)、失神など。
- うつ症状:理由なく気分が落ち込む、何事にも興味がわかないなど。
- 嗅覚の低下:食べ物のにおいが分かりにくくなる。
- 錯視:壁のしみが人の顔に見えるなど、ものを見間違える。
これらの症状は、認知機能の低下よりも早く現れることもあります。
複数のサインに気づいた場合は、専門医への相談を検討しましょう。
レビー小体型認知症の進行と余命
レビー小体型認知症と診断された時、ご本人やご家族が最も気になることのひとつが、「この先どうなっていくのか」という病気の進行や予後でしょう。
進行の仕方には個人差がありますが、一般的な経過を知っておくことは、将来への備えにつながります。
初期~中期~後期の症状の進行
レビー小体型認知症の進行は、一般的に「初期・中期・後期」の3つの段階に分けて考えられます。
それぞれの段階で現れやすい症状は異なります。
| 段階 | 主な症状の変化 |
|---|---|
| 初期 | ・もの忘れは軽度だが、注意力の低下が見られる ・リアルな幻視やレム睡眠行動異常症が出現 ・パーキンソン症状が出始め、歩きにくさや動作の遅さが目立つ ・うつ症状や自律神経症状(便秘など)が現れる |
| 中期 | ・認知機能の低下が明らかになり、日常生活に支障が出る ・幻視や妄想がより頻繁になる ・パーキンソン症状が進行し、転倒のリスクが非常に高まる ・嚥下(えんげ)障害が出始める |
| 後期 | ・認知機能が著しく低下し、コミュニケーションが困難になる ・パーキンソン症状が重度化し、寝たきりの状態になることも ・誤嚥性肺炎などの合併症を起こしやすくなる |
このように、レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に比べ、初期から身体的な症状が目立つのが特徴です。
段階に応じたケアプランを立てることが大切になります。
平均余命は診断から5~8年とされるが個人差が大きい
医学文献によると、レビー小体型認知症の平均余命は診断を受けてからおよそ5~7年といわれています。
これはアルツハイマー型認知症(約8~10年)と比べると、やや短い傾向にあります。
日本の久山町研究では、診断からの10年生存率はレビー小体型認知症で2.2%と報告されているのです。
ただし、これはあくまで平均的なデータです。
進行の速さには大きな個人差があり、年齢・合併症の有無、そして何より治療やケアの内容によって、予後は大きく変わります。
個人によっては20年以上生存する場合もあるとされています。
特に、転倒による骨折や誤嚥性肺炎などの合併症を防ぐことが、穏やかな生活を長く続けるための鍵です。
数字に一喜一憂するのではなく、今できる最善のケアに集中することが重要です。
レビー小体型認知症の診断・検査方法
「もしかしてレビー小体型認知症かも?」と感じたら、専門の医療機関を受診し、正確な診断を受けることが第一歩です。
認知症のさまざまな検査方法の中でも、レビー小体型認知症の診断には特有の基準と検査が用いられます。
診断の必須項目と中核的特徴
レビー小体型認知症の診断は、2017年に改訂された国際的な専門的な診断基準に基づいて行われます。
まず必須条件として「進行性の認知機能低下」があり、その上で、先に解説した4つの「中核的特徴」のうち、いくつ当てはまるかによって診断されます。
【診断のための中核的特徴(2017年診断基準)】
- 認知機能の変動:注意や覚醒レベルの著しい変動。
- 幻視:繰り返し現れる、具体的で詳細な幻視。
- レム睡眠行動異常症(RBD):睡眠中の異常な言動(2017年基準では中核的特徴に格上げ)。
- パーキンソン症状:動作緩慢、筋強剛、振戦などのうち、ひとつ以上が存在。
これらの特徴を、問診や診察を通じて丁寧に評価していきます。
診断の決め手となる検査(MIBG心筋シンチ、DaTscanなど)
問診や診察だけでは診断が難しい場合、より客観的な詳細な検査が行われます。
特に以下の2つの核医学検査は、レビー小体型認知症の診断において非常に重要な役割を果たします。
- MIBG(エムアイビージー)心筋シンチグラフィ
心臓の交感神経の働きを調べる検査です。レビー小体型認知症では、脳だけでなく心臓の交感神経にも異常が現れるため、心臓への放射性医薬品の取り込みが低下します。これは他の認知症には見られない特徴で、診断の精度を大きく高めます。 - DaTscan(ダットスキャン)
脳内のドパミントランスポーターの密度を画像化する検査です。レビー小体型認知症では、パーキンソン病と同様にドパミン神経細胞が減少するため、この検査で異常が見られます。
これらの検査は、健達ねっとが提携する医療機関など、専門的な設備を持つ施設で受けることが可能です。
画像検査
脳の状態を視覚的に確認するために、CTやMRIといった画像検査も行われます。
レビー小体型認知症では、アルツハイマー型認知症で見られるような著しい脳の萎縮は、初期の段階では目立たないことが多いのが特徴です。
そのため、CTやMRIは、脳梗塞や脳腫瘍など、認知症に似た症状を引き起こす他の病気がないかを確認する「鑑別診断」のために重要な検査といえます。
また、脳の血流を調べるSPECT(スペクト)検査では、後頭部の血流低下という、レビー小体型認知症に比較的特徴的な所見が見られることがあります。
診断分類の違い
ここまでの診察や検査の結果を総合的に評価し、診断基準に沿って確定診断が行われます。
確実性の度合いによって、以下のように分類されます。
- Probable DLB(ほぼ確実にレビー小体型認知症)
中核的特徴が2つ以上ある場合、または中核的特徴がひとつでもMIBG心筋シンチグラフィなどの指標的バイオマーカーで異常が認められた場合に診断されます。 - Possible DLB(レビー小体型認知症の疑い)
中核的特徴ひとつのみで、指標的バイオマーカーの異常がない場合に診断されます。
この分類によって、その後の治療方針やケアの計画を立てていきます。
診断時の持ち物・医療者に伝えるべき情報
正確な診断のためには、ご家族からの情報が非常に重要になります。
受診する際は、以下のものを準備しておくと診察がスムーズに進みます。
【準備しておくとよいもの】
- 症状のメモ:いつから、どのような症状が、どのような時に起こるか。特に認知機能の変動や幻視、睡眠中の様子など、具体的に記録したもの。
- お薬手帳:現在服用しているすべての薬(サプリメント含む)。
- 既往歴のメモ:これまでにかかった大きな病気や手術歴。
- 介護保険証:(お持ちの場合)
ご本人がうまく説明できない部分を、ご家族が補足して伝えることで、医師はより多くの情報をえられます。
普段の何気ない変化でも、診断の重要な手がかりになることがあります。
レビー小体型認知症の治療法
レビー小体型認知症を根本的に治す治療法は、残念ながらまだ確立されていません。
しかし、治療方法の目標は、症状をコントロールし、できる限り穏やかに、その人らしい生活を長く続けていくことにあります。
治療は「薬物療法」と「非薬物療法」の二本柱で進められます。
薬物療法による症状のコントロール
レビー小体型認知症の症状を和らげるために、いくつかの治療薬が用いられます。
症状に合わせて薬を使い分けることが重要です。
- 認知機能障害に対して
「ドネペジル塩酸塩(商品名:アリセプトなど)」が、2022年11月にレビー小体型認知症の認知機能障害に対して保険適用されています。
特に注意障害や幻視の改善に効果が期待できます。
レビー小体型認知症では通常1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量する用法・用量が定められています。 - パーキンソン症状に対して
パーキンソン病の治療薬が用いられますが、幻視などの精神症状を悪化させる可能性があるため、少量から慎重に使用されます。 - 幻覚や妄想、興奮に対して
漢方薬の「抑肝散(よくかんさん)」が第一選択となることが多いです。
副作用が比較的少なく、幅広い精神症状に効果を示すといわれています。
非薬物療法による生活の質を上げるアプローチ
薬だけに頼るのではなく、リハビリテーションや環境調整といった非薬物療法を組み合わせることが、QOL(生活の質)の維持・向上に不可欠です。
非薬物療法には、以下のようなアプローチがあります。
- 理学療法:歩行訓練や筋力トレーニングを行い、転倒を予防する。
- 作業療法:日常生活の動作(着替え、食事など)をスムーズに行うための訓練や、趣味活動を取り入れる。
- 環境調整:部屋を明るくして幻視を起きにくくしたり、手すりを設置したりして安全な環境を整える。
- 回想法:昔の写真や音楽を用いて思い出を語り合い、精神的な安定を図る。回想法は、ご本人の自尊心を高める効果も期待されます。
BPSD対策の具体例
BPSD(行動・心理症状)とは、幻覚・妄想・興奮・攻撃性・うつ・不安など、認知症の中核症状に伴って現れる行動や心理状態のことです。
このBPSDへの対処は、介護における大きな課題となります。
メディカル・ケア・サービスが実践する「MCSケアモデル」では、BPSDの根本原因をアセスメントし、個別のケアプランで対応します。
例えば、「落ち着かない」「常に興奮」といった症状に対して優先するのは、ご本人が安心できる環境調整や、不快感の原因となっている身体的な問題(痛み、便秘など)を取り除くケアです。
これにより、85%以上の方でBPSDの改善が見られており、薬に頼らないアプローチの有効性が示されています。
抗精神病薬への過敏性とは
レビー小体型認知症の治療において、最も注意すべき点のひとつが「薬剤過敏性」です。
特に、幻覚や妄想を抑えるために安易に抗精神病薬を使用すると、深刻な副作用を引き起こす危険性があります。
副作用の主な症状は以下の通りです。
- パーキンソン症状が急激に悪化する
- 意識障害や傾眠(眠り続ける)が起こる
- 嚥下障害が悪化し、誤嚥性肺炎のリスクが高まる
- 最悪の場合、生命に関わることもある
このため、レビー小体型認知症の方への抗精神病薬の使用は原則として避けるべきとされています。
やむを得ず使用する場合も、専門医の管理のもと、ごく少量から極めて慎重に投与する必要があります。
ご家族もこのリスクを理解し、医師と密に連携することが重要です。
この過敏性は、レビー小体型認知症の末期症状にも関連してくる重要な知識です。
家族ができる症状別の対応と介護のポイント
レビー小体型認知症の方と穏やかに暮らしていくためには、ご家族の適切な対応方法が何よりも大切です。
病気の特性を理解し、ご本人の気持ちに寄り添う具体的な介護方法を学びましょう。
【症状別】具体的な対応方法
特徴的な症状に対して、どのように接すればよいのでしょうか。
シーン別の対応のヒントをまとめました。
| 症状 | 推奨される対応(DO) | 避けるべき対応(DON’T) |
|---|---|---|
| 幻視 | 「そう見えるのね」と一度受け止め、本人の不安な気持ちに寄り添う。「一緒に追い払いましょうか」などと、安心させる言葉をかける。 | 「そんなものはいない」と頭ごなしに否定する。無視したり、馬鹿にしたりする。 |
| 認知機能の変動 | 調子がよい時間帯を把握し、大切な話やリハビリはその時に行う。ぼんやりしている時は、無理強いせず、休息を促す。 | 「さっきはできたのに、なぜできないの?」と責める。「しっかりして!」と叱咤激励する。 |
| 妄想 | まずは本人が訴える内容(「財布を盗られた」など)に耳を傾け、「それは心配ですね」と気持ちに共感する。一緒に探すふりをするなど、安心感を与える。 | 「盗る人なんていない」と事実を突きつけて論破しようとする。犯人捜しをする。 |
メディカル・ケア・サービスの施設では、「感情記憶」を重視したケアを実践しています。
日常の出来事は忘れても、職員との関わりで感じた「嬉しい」「安心する」といったよい感情は記憶に残りやすく、これが信頼関係の基盤となります。
このことは、よい感情体験の積み重ねこそが、不安や混乱を和らげる最良のケアであることを示しているのです。
>参考:体験談「思い出の味を夫婦で囲む」|愛の家グループホーム帯広東12条
介護で心がけたい5つのポイント
日々の介護生活では、以下の5つのポイントを常に意識することが、ご本人と介護者双方の負担を軽減します。
転倒しない環境を整える
パーキンソン症状により転倒リスクが非常に高いレビー小体型認知症の方にとって、環境整備は命を守ることに直結します。
部屋の段差をなくし、滑りにくい床材を選び、廊下やトイレに手すりを設置しましょう。
また、夜間でも足元が確認できるよう、センサーライトなどを活用するのも有効です。
十分な水分・栄養摂取と運動による筋力維持も、転倒予防の土台となります。
生活リズムを整える
日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつけることが、認知機能の変動や夜間の睡眠障害を安定させる鍵です。
午前中に散歩やデイサービスなどで活動する機会を作り、太陽の光を浴びるようにしましょう。
昼寝が長くなりすぎないように注意し、就寝前はテレビやスマートフォンの光を避けてリラックスできる環境を整えることが大切です。
本人の自尊心を傷つけない
病気によってできなくなることが増えても、ご本人のプライドや自尊心を尊重する姿勢が重要です。
失敗を責めたり、子ども扱いしたりすることは絶対に避けましょう。
「ありがとう」「助かるわ」といった感謝の言葉を積極的に伝え、役割やできることを見つけてもらうことで、ご本人は自信を取り戻し、穏やかに過ごせます。
叱ったり否定したりしない
幻視や妄想、失敗など、病気の症状によって引き起こされる言動に対して、叱ったり、正論で否定したりしても、状況は改善しません。
むしろ、ご本人の混乱や不安を煽り、BPSDを悪化させる原因になります。
まずは「なぜそのような言動に至ったのか」という背景にあるご本人の感情を想像し、受け止める姿勢が大切です。
介護者自身が休息をとる
「介護者自身の心と体の健康が、最も大切なケアの資本である」ということを忘れないでください。
介護は長期戦です。
完璧を目指さず、「まあ、いいか」と力を抜く時間も必要です。
デイサービスやショートステイなどの介護サービスを積極的に利用し、介護から離れて自分のための時間を作る「レスパイトケア」を意識的に取り入れましょう。
公的サービスと相談窓口を活用する
介護の悩みや負担は、ご家族だけで抱え込む必要はありません。
むしろ、積極的に外部の専門家やサービスを頼ることが、よりよい介護につながります。
主な公的サービスと相談窓口は以下の通りです。
- 介護保険サービス:訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなど。
- 地域包括支援センター:介護に関する総合相談窓口。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが対応。
- かかりつけ医、専門医療機関:病状や薬に関する相談。
- 認知症の人と家族の会:同じ境遇の仲間と情報交換や悩みを共有できる場。
これらの社会資源をうまく活用し、「チーム」でご本人を支える体制を築きましょう。
ひとりで抱え込まないために!使える制度と相談窓口
レビー小体型認知症の介護は、情報戦でもあります。
利用できる制度や相談窓口を知っているかどうかで、ご家族の精神的・経済的負担は大きく変わります。
ひとりで抱え込まず、社会の力を積極的に活用しましょう。
経済的負担を軽くする公的制度
介護には費用がかかります。経済的な不安を少しでも和らげるために、利用できる制度を確認しておきましょう。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 介護保険制度 | レビー小体型認知症は特定疾病に指定されており、40歳以上から利用可能。 自己負担1~3割でさまざまな介護サービスを受けられる。 |
| 障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳(認知症状)や身体障害者手帳(パーキンソン症状)を取得すると、税金の控除や公共料金の割引などが受けられる。 |
| 障害年金 | 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金。 |
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超えた金額が支給される制度。 |
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。
介護保険とは?サービス・制度内容も参考にしてみてください。
悩みや不安を話せる相談窓口
介護の悩みや日々のストレスは、誰かに話すだけで心が軽くなることがあります。
専門的なアドバイスがもらえる窓口も多数あります。
【主な相談窓口】
- 地域包括支援センター:介護に関する最初の相談窓口として最適。
- 認知症疾患医療センター:専門的な医療相談や鑑別診断に対応。
- 認知症の人と家族の会:同じ立場の介護者同士で悩みを分かち合える。
- 若年性認知症コールセンター:65歳未満で発症した場合の専門相談窓口。
どこに相談してよいか分からない場合は、まずはお住まいの介護の相談窓口である地域包括支援センターに電話してみることをオススメします。
「ケアチーム」を作るという考え方
ご本人を中心に、家族・医師・看護師・ケアマネジャー・理学療法士・ヘルパーなど、関わるすべての人々が情報を共有し、同じ目標に向かって連携する。
これが「ケアチーム」という考え方です。
愛の家グループホーム弥富の実践例では、地域住民の協力も得て見守り体制を築くことで、「自由に外出したい」というご本人の強い欲求を満たし、BPSDの劇的な改善に成功しました。
これは、ご家族だけでなく、地域社会全体がケアチームの一員となり得ることを示しています。
また、健達ねっとが実施した小中学校での認知症教育では、92%の子どもが認知症へのイメージがよくなったと回答しました。
若い世代の理解は、将来的に地域全体で認知症の方を支える強力な基盤となります。
介護は決して孤独な戦いではありません。多様な専門家や地域の人々とつながり、チームで支える体制を構築することが重要です。
>参考:全国の小中高生3,423名を対象とした「認知症に関する意識調査」結果
スポンサーリンク
レビー小体型認知症の予防と最新研究
「認知症になりたくない」と願うのは、誰もが持つ自然な気持ちです。
現時点でレビー小体型認知症を完全に予防する方法はありませんが、発症リスクを低減させる可能性のある生活習慣や、未来の治療につながる研究について解説します。
今からできる予防につながる生活習慣
認知症予防には、特定の万能薬があるわけではなく、日々の生活習慣の積み重ねが重要です。
これはレビー小体型認知症も例外ではありません。
科学的に見て、認知症リスクの低減につながると考えられている習慣は以下の通りです。
- 定期的な運動:ウォーキングなどの有酸素運動は、脳の血流を改善し神経を保護します。
- バランスの取れた食事:野菜、果物、魚などを多く摂る地中海式食事が推奨されます。
- 知的活動の維持:新しいことを学んだり、趣味に没頭したりして脳に刺激を与える。
- 社会的な交流:友人や地域とのつながりを持ち、社会的に孤立しない。
- 生活習慣病の管理:高血圧、糖尿病、脂質異常症などを適切に治療する。
メディカル・ケア・サービスが実践する「MCS版自立支援ケア」では、適切な水分摂取(1日1.8L)、たんぱく質摂取、運動を組み合わせ、心身機能の改善を図っています。
特に日中の覚醒レベルを上げる水分摂取は、認知機能の変動改善にもつながる可能性があり、生活習慣の改善の重要性を示しています。
>参考:MCS版科学的介護
日頃の食事で十分な栄養素を摂取することが難しい場合は、機能性表示食品として認められた認知機能サポート成分の活用も検討されています。
ただし、これらは健康食品であり、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。
治療の未来が変わる?最新の研究動向
世界中でレビー小体型認知症の根本治療薬の開発に向けた研究が精力的に進められています。
近年、特に注目されているのは、病気の原因に直接アプローチする研究です。
【最新研究の主なトピック】
- 血液バイオマーカーの開発:血液検査でα-シヌクレインの異常を検出し、発症前に超早期診断を目指す研究。
- α-シヌクレインPETの開発:脳内に蓄積したレビー小体を画像で直接可視化する技術。診断精度を飛躍的に向上させると期待される。
- 疾患修飾薬(DMD)の開発:α-シヌクレインが凝集するのを防いだり、除去したりすることで病気の進行そのものを止める新薬の研究。
これらの研究成果が実用化されれば、レビー小体型認知症の診断と治療は大きく変わる可能性があります。
未来の医療につながりうる研究の進展に、これからも期待が寄せられています。
スポンサーリンク
レビー小体型認知症に関するよくある疑問
ここでは、レビー小体型認知症について、ご家族から寄せられることの多い質問にお答えします。
レビー小体型認知症は治る?
残念ながら、2025年8月現在、レビー小体型認知症を完全に治す(病気になる前の状態に戻す)治療法は見つかっていません。
病気の進行を止める薬もまだ開発されていません。
しかし、この記事で紹介した薬物療法や非薬物療法によって、症状を緩和し、生活の質を維持・向上させることは十分に可能です。
「治らない病気」と悲観するのではなく、「付き合っていく病気」と捉え、前向きに治療やケアに取り組むことが大切です。
どのような人がなりやすい?
レビー小体型認知症の明確な危険因子は、まだ完全には解明されていません。
現時点で最も確実なリスク因子は「加齢」です。
その他、いくつかの遺伝子が発症リスクと関連することが報告されていますが、特定の生活習慣や職業が直接的な原因となるという明確なエビデンスはありません。
ただ、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が、間接的にリスクを高める可能性は指摘されています。
遺伝することはある?
レビー小体型認知症のほとんどは、遺伝とは関係ない「孤発性」です。
親や兄弟がレビー小体型認知症だからといって、必ずしも自分も発症するわけではありません。
ごく稀に、特定の遺伝子変異によって家族内で発症しやすい「家族性」のケースも報告されていますが、全体のごく一部です。
過度に遺伝を心配する必要はないといえるでしょう。
専門機関を受診すべきサインは?
以下のようなサインが複数見られる場合は、一度もの忘れ外来や神経内科などの専門機関に相談することをオススメします。
【受診を検討すべきサインの例】
- 具体的でリアルな幻視を繰り返し訴える
- 日によって理解力や注意力の差が激しい
- 理由もなく転びやすくなった、歩き方が変わった
- 睡眠中に大声を出したり、暴れたりする
- 頑固な便秘や立ちくらみが続くようになった
これらの症状は、ご本人が自覚していないことも多いため、ご家族の「気づき」が何よりも重要になります。
最後はどのような状態になる?
レビー小体型認知症が進行し、終末期を迎えると、多くの場合は寝たきりの状態になります。
言葉によるコミュニケーションは困難になり、食事を口から摂ることも難しくなる(嚥下障害)ため、経管栄養や胃ろうなどの選択が必要になる場合もあります。
パーキンソン症状も重度化し、自力で体を動かすことはほとんどできなくなってしまうのです。
最終的には、誤嚥性肺炎や老衰、心不全などの合併症で亡くなる方が多いです。
どのような最期を迎えたいか、元気なうちにご本人と家族で話し合っておくことも大事となります。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、レビー小体型認知症の基本的な知識から、症状、診断、治療、そしてご家族ができる介護のポイントまでを網羅的に解説しました。
重要なポイントを改めて振り返ります。
- レビー小体型認知症は、幻視、パーキンソン症状、認知機能の変動、レム睡眠行動異常症が特徴的な、日本で認知症全体の4.3%を占める認知症です。
- 診断には、MIBG心筋シンチグラフィなどの専門的な検査が有効です。
- 根本治療法はありませんが、薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、症状を和らげ穏やかな生活を送ることが可能です。
- 介護では、ご本人の言動を否定せず、安全な環境を整え、何よりも介護者自身が休息をとることが大切です。
- 介護保険制度や地域包括支援センターなど、利用できる社会資源は多数あります。ひとりで抱え込まず「チーム」で支える体制を築きましょう。
レビー小体型認知症と向き合うことは、ご本人にとってもご家族にとっても、決して簡単な道のりではありません。
しかし、病気を正しく理解し、適切なケアと支援につながることで、その人らしい尊厳のある生活を続けることは十分に可能です。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、未来へ向かうための一助となれば幸いです。
より詳しい情報をお求めの方には以下も参考にしてみてください。
- 認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣(認知症専門医による科学的根拠に基づいた予防指南書)
- ハルと思い出めぐりごはん(回想法を活用した懐かしレシピ集)