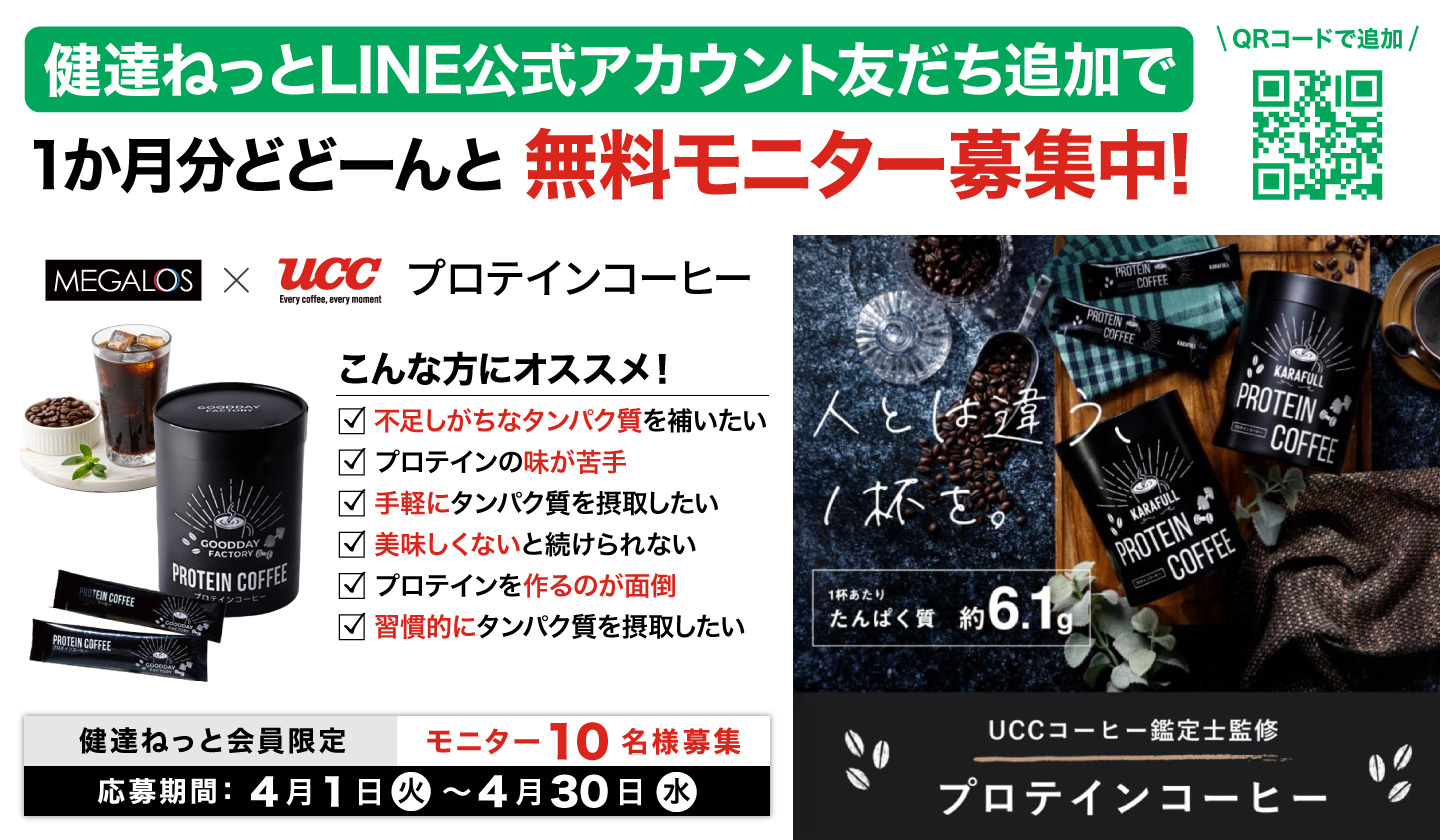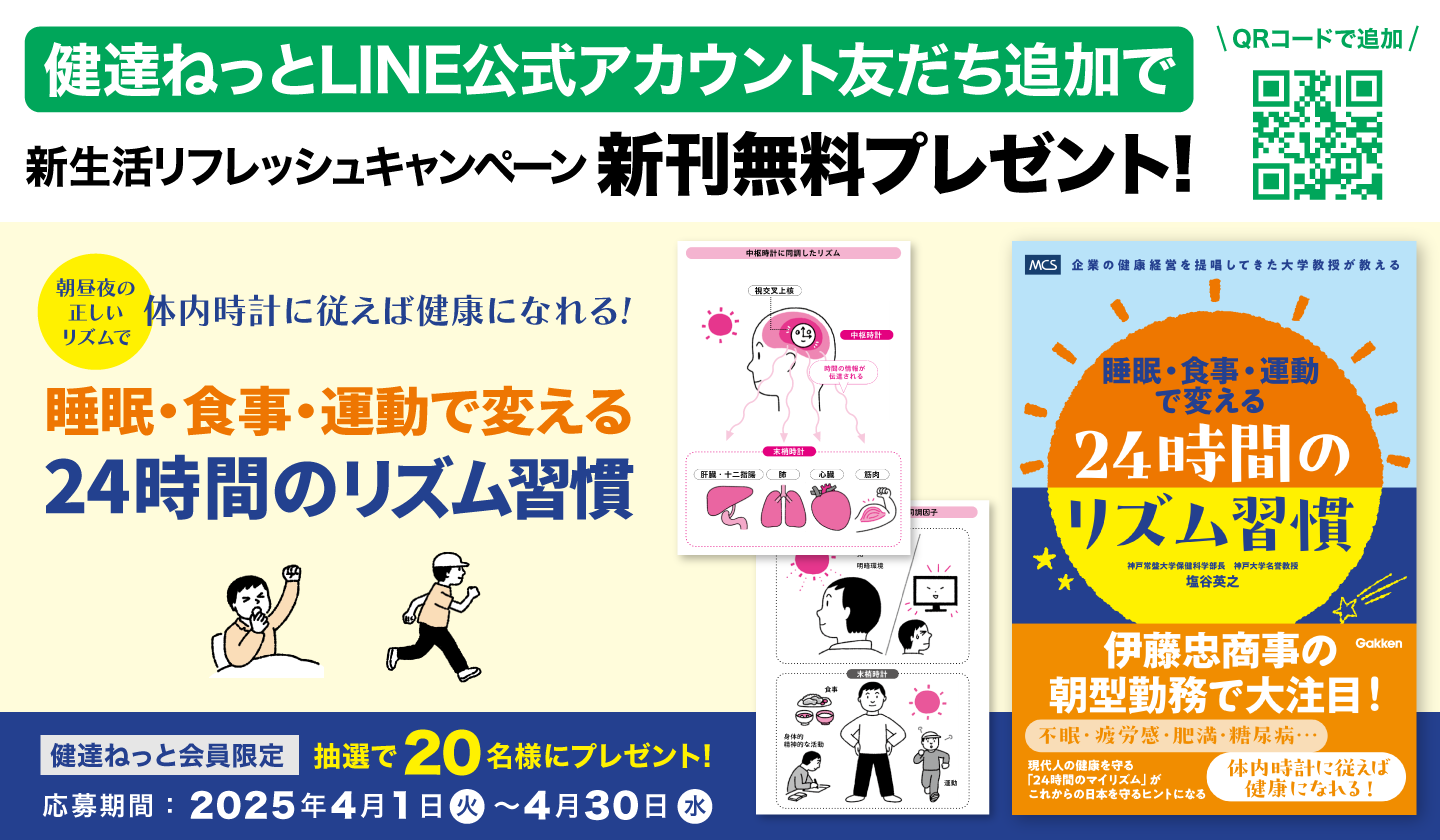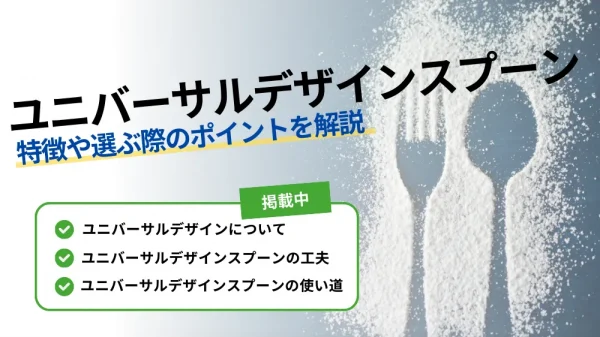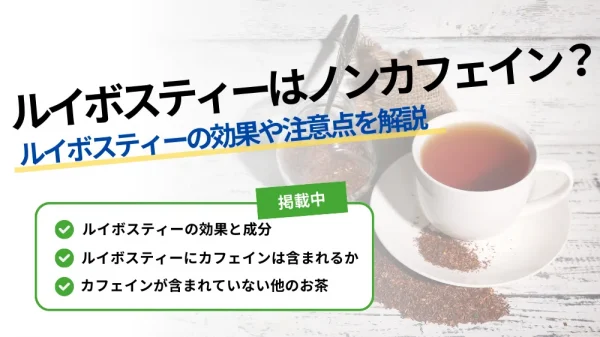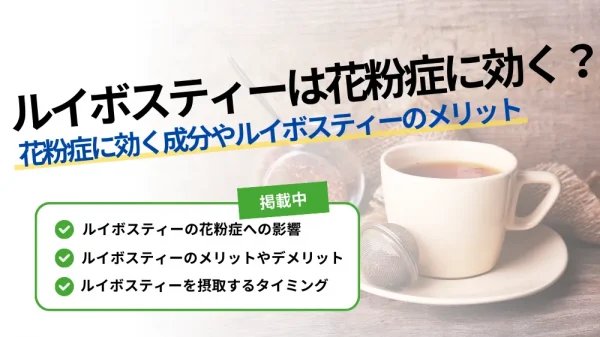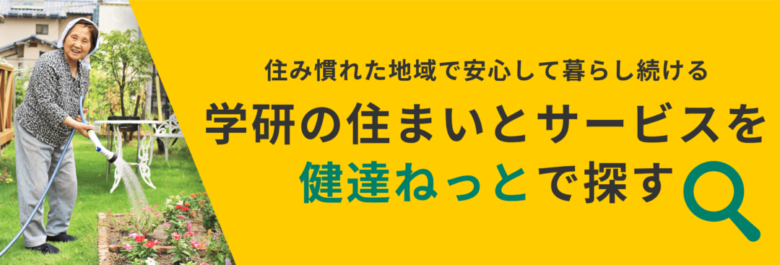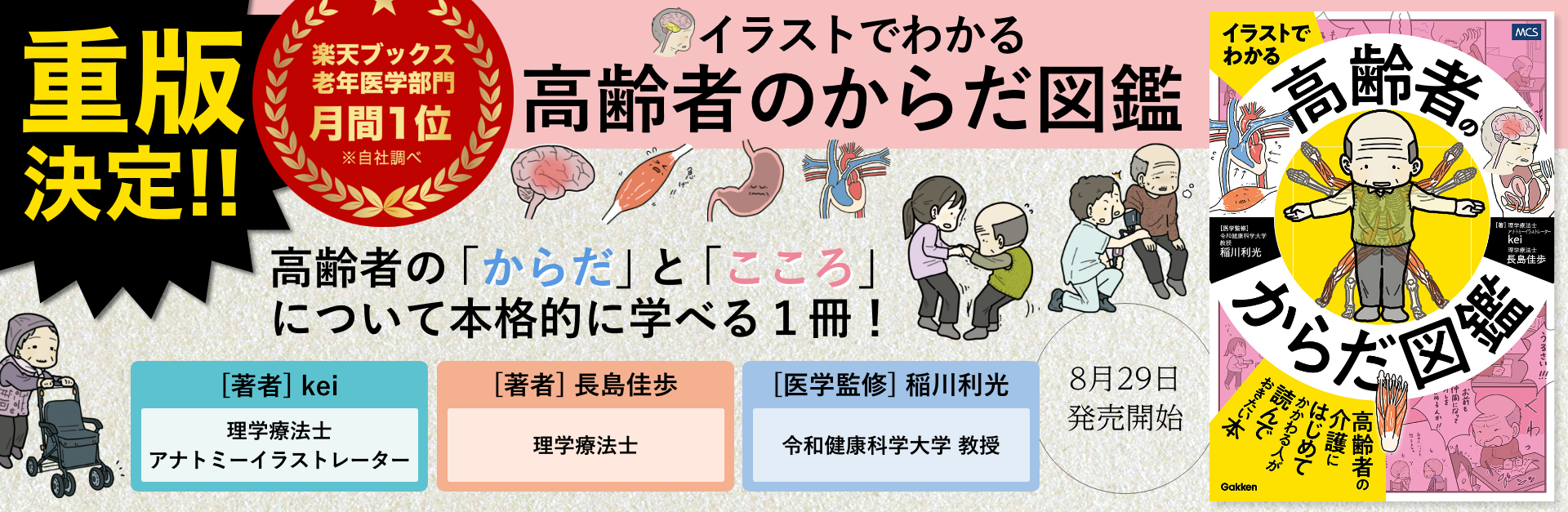どのような薬でも多少の副作用があります。
しかし、薬を飲むことは病気を治す手段、というのも事実です。
では、薬を飲まない方がいいのはどのような場合なのでしょうか。
本記事では、薬の服用について以下の点を中心に紹介していきます。
- 医師の指示に従うべきこと
- 服用時の飲み物
- 薬の副作用
薬の服用方法について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
薬の副作用について知りたい方は以下の記事もお読みください。
スポンサーリンク
医師の指示に従いましょう

薬に関しては、医師と薬剤師というプロフェッショナルがいます。
薬剤師は飲み方や飲み合わせについては聞けますが、薬を処方するのは医師の指示です。
薬を服用することに抵抗がある、薬の種類や形状について相談や希望がある、などの場合には、自己判断せず必ず医師に相談しましょう。
服薬指導について知りたい方は以下の記事もお読みください。
薬剤師による服薬指導は、患者様の医薬品トラブルを予防するうえでとても重要です。しかし、ただ薬の効果や注意事項を説明するだけでは、適切な服薬指導とはいえません。服薬指導とは具体的にどのようなものなのでしょうか?また、服薬指導で[…]
スポンサーリンク
妊娠・授乳中の薬の服用

妊娠・授乳中は薬の服用に制限があります。
妊娠中と偏にいっても、妊娠初期、中期、後期と時期によって、薬による赤ちゃんへの影響が異なります。
妊娠4週から3ヶ月間は、赤ちゃんの重要な器官が作られる期間です。
薬の影響を受けやすい時期のため、服用する際は十分注意しましょう。
これから妊娠を望んでいる方は、万が一に備えて妊娠初期に飲んでも心配ない薬を服用すべきです。
もし、妊娠したかなと思った場合は、妊娠していないことを確認するか、薬が大丈夫であることを医師や薬剤師に確認するまでは、薬を飲まない方がいいでしょう。
例えば、風疹ワクチンは妊娠している場合は接種できません。
妊娠前に接種した場合、接種後2か月間は避妊する必要があります。
男性ホルモン作用があるものや解熱鎮痛剤、抗ウイルス剤などの中にも、妊娠中は飲めない薬があります。
授乳中の場合、お母さんが服用した薬が母乳に分泌され、赤ちゃんに移行します。
妊娠中よりは赤ちゃんへの影響は少ないと考えられていますが、授乳中は飲まない方がいい薬もあるので、必ず医師に相談しましょう。
また、妊娠・授乳中に医療機関を受診する際は、必ず申告しましょう。
同様に、市販薬を購入するときも、薬剤師や登録販売者に確認することが必要です。
タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]
子どもの薬の服用

子どもの風邪の症状や腹痛などは、市販薬を買って試すという保護者の方もいるかもしれません。
しかし、市販薬はどれも同じだろうと判断するのは危険です。
子どもの薬の服用は、1回の用量に決まりがあります。
小児の場合、薬の用量は体重を目安にすることが多いので、知識がないと判断が難しくなります。
また、処方薬でも古い薬は飲まない方がいいでしょう。
処方されたときの体重に対する薬の量なので、成長過程にある子どもの場合、十分な効果が得られないことがあります。
解熱剤の服用

熱が出た場合、無理に熱を下げない方がいいと考えられています。
発熱は免疫機能が活性化している状態です。
ほとんどのウイルスは熱に弱いため、熱が上がるとウイルスの力が弱くなります。
つまり、発熱はウイルスを排除するための身体の防御反応の1つ、と言えるでしょう。
解熱剤を飲んで熱が下がったとしても、病気が治ったわけではありません。
熱という症状を抑えることで、本来備わっている免疫力を下げてしまいます。
解熱鎮痛剤を使用するのは、熱や痛みのために休息がとれない、食事や水分摂取ができない場合に限られます。
熱があっても元気で水分摂取ができていれば、解熱剤は飲まない方がいいのかもしれません。
ただし、高熱が続く場合は、風邪とは別の病気が潜んでいる可能性もあるため、受診し医師の指示に従いましょう。
抗生物質の服用

抗生物質とは、重要で強力な医薬品であり、適切に服用すれば生命を救うこともできます。
しかし、不適切に服用すると有害になります。
勘違いされやすいのですが、抗生物質は細菌に対して有効であり、ウイルスには効果がありません。
風邪の症状や喉の痛みなどの多くは、ウイルスが原因です。
細菌とウイルスの違いを理解せずに抗生物質を乱用すると、抗生物質が効かない抗生物質耐性菌が増加します。
また、身体でうまく栄養を吸収するために必要な、腸内細菌なども殺すことになりかねないので注意しましょう。
不適切な服用は身体に害を与えますが、医療機関で処方された薬は、医師の指示に従い、症状が改善しても飲み切る必要があります。
残薬の服用

症状が改善したり、別の薬が処方されたりしたときに、薬が手元に残る場合があります。
同じ症状が再発したからといって、自己判断では残薬を飲まない方がいいでしょう。
一般の方が残薬の新旧を判断するのは難しく、使用期限が過ぎた残薬を服用してしまうと、十分な治療効果が得られません。
体調を崩してしまい、飲むべき薬が増えてしまう悪循環に陥ってしまうこともあります。
また、薬の適正使用や医療費の観点から、残薬は社会問題となっています。
厚生労働省の調査によると、年間残薬額を推定することは難しいが、年間8000億円以上となる可能性があると言われています。
処方された薬は、医師の指示がない限り、飲み切ることが大切です。
もし残薬がある場合は、必ず医師や薬剤師に指示を仰ぎ従いましょう。
参考:医療保険財政への残薬の影響とその解消方策に関する研究(中間報告)
長期間継続しての服用

持病があったり、症状改善が見込めずにいた場合、長期間継続して薬を服用することがあります。
そのときに、薬の副作用などの不安や心配を感じる方もいるでしょう。
市販薬を長期間継続して服用すると、副作用や状態の悪化などのリスクがあります。
そのため、多くの商品の「してはいけないこと」欄には、長期連用を禁止する文言が記載されています。
市販薬は1週間を目処に服用し、症状が改善されない場合は医療機関を受診することにしましょう。
医療機関で処方された薬であれば、長期間の継続服用への不安や身体の状態などを医師に相談しましょう。
スポンサーリンク
水以外で飲まない方がいい?

薬は、コップ1杯の水やぬるま湯で飲みましょう。
水が少ないと、薬が胃や腸の粘膜にくっついて溶け出し、粘膜にダメージを与える可能性があります。
水以外の飲み物で飲むと、薬の効果に影響が出たり、副作用が出現しやすくなったりすることがあります。
例えば、グレープフルーツジュースは、含まれる成分によって薬の代謝に影響を与え、薬物の血中濃度を上昇させてしまうことがあります。
効果が強く現れることで、薬によっては血圧低下や、頭痛やめまいなどの症状を引き起こすことがあります。
アルコール飲料や濃いお茶なども、薬の作用に影響を与えかねません。
薬は、水やぬるま湯以外の飲み物では飲まない方がいいでしょう。
なかには、子どもに薬を飲ませるのに苦労している方がいるかもしれません。
薬によっては、ミルクやジュースなどで紛らわせて飲んでも良い場合もあります。
最近では、薬を飲みやすくするための「服薬補助ゼリー」を見かけます。
しかし、薬と飲食物の組み合わせによっては、逆に苦みがあったり効き目が弱くなったりする組み合わせもあります。
自分で判断せずに、医師や薬剤師に確認してから、子どもに服用させましょう。
スポンサーリンク
副作用情報の報告

薬を服用したあとに具合が悪くなったり、飲む前と異なる症状が現れたりした場合は、医療機関を受診しましょう。
副作用の状態により、医師は薬の減量・中止・変更することになります。
市販薬で副作用が出現した場合は、医療機関を受診後、薬を購入した店の薬剤師に相談しましょう。
医薬品の安全対策に活用するためにも、以下のURLから一般人が副作用情報の報告もできます。
※PMDA医薬品医療機器情報提供ホームページ
上記機関は、本人または家族から、医薬品による副作用報告を受付、整理し、厚生労働省へ報告します。
副作用に対しての「医薬品副作用被害救済制度」も整っています。
報告された症状について、PMDAから報告者へ診断・評価結果等に関する個別対応はしておらず、あくまでも、医薬品の安全性維持のために活用されます。
ただ前述の通り、副作用の可能性がある症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診して、医師の指示を仰ぐことが最優先です。
スポンサーリンク
薬を飲まない方がいい場合についてのまとめ

今回は、薬を飲まない方がいい場合についてご紹介しました。
薬の服用についての要点を以下にまとめます。
- 薬の疑問点・変更などは医師の指示に従うことが必要
- 薬はコップ1杯の水かぬるま湯で服用する
- 薬の副作用が出現したら、まずは医療機関を受診する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。