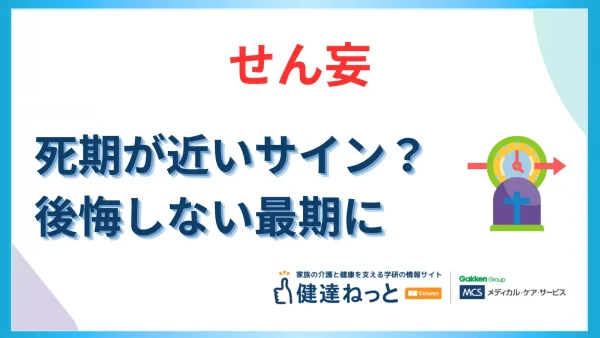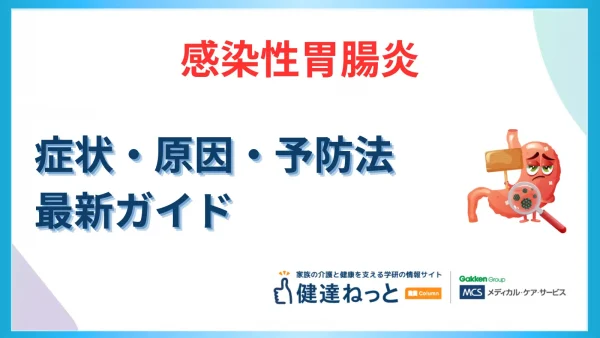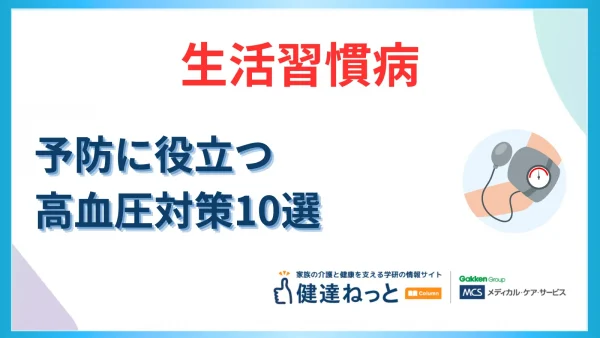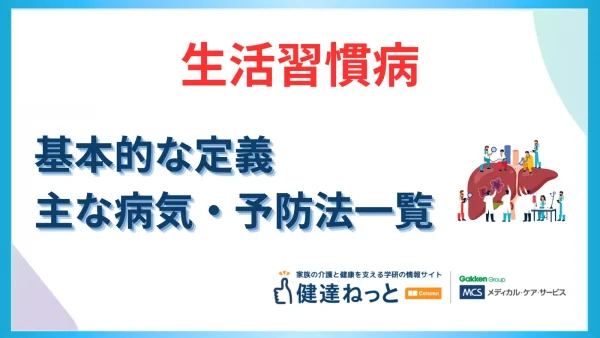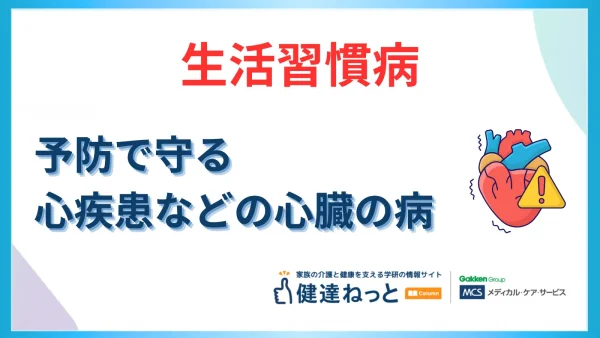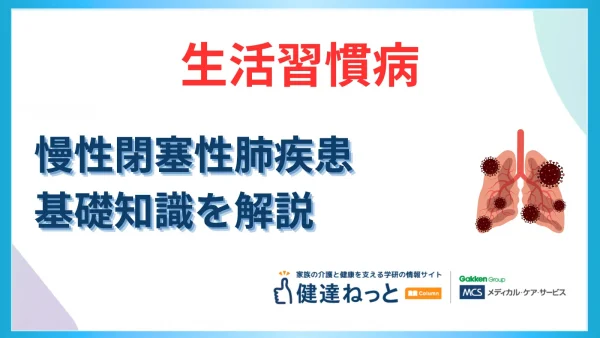大切なご家族の様子が、急にいつもと違うと感じることはありませんか。
- 急に話の辻褄が合わなくなった…
- いないはずの人が見えるという…
- もしかして、これはお別れが近いサインなのだろうか…
このような状況に直面し、どう接すればよいか分からず、強い不安や戸惑いを感じていらっしゃるかもしれません。
「本人を傷つけたくない」「でも、どうすれば…」と悩み、後悔だけはしたくないと願うお気持ちは、非常に自然なことです。
この記事では、そのようなご家族の不安に寄り添い、せん妄の正しい知識と、穏やかな時間を過ごすための具体的な関わり方について解説します。
この記事を読むことで、以下の点が分かります。
- 終末期のせん妄が「死期が近いサイン」といわれる理由
- せん妄の具体的な症状と原因
- ご家族だからこそできる、心に寄り添う対応法
- 後悔しないために、今から準備できること
この記事を通じて、あなたの不安が少しでも和らぎ、大切な方との残された時間を、より穏やかに、そして心を通わせて過ごすための一歩を踏み出せるはずです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
せん妄は死期が近い?もしかしたら「お別れが近いサイン」かも
ご家族にせん妄の症状がみられると、多くの方が「死期が近いのではないか」と不安に駆られます。
このセクションでは、せん妄と終末期の関係について、そして「後悔しない看取り」のために何が大切なのかを解説します。
【結論】終末期のせん妄は回復が難しい一方で改善する可能性もある
結論からいうと、がんの終末期や老衰など、身体の状態が全体的に低下している時に起こるせん妄は、残念ながらお別れが近いサインである可能性が高いといえます。
日本サイコオンコロジー学会「がん患者におけるせん妄ガイドライン2019年版」によると、終末期には約90%近くの患者にせん妄がみられ、死亡直前には88%と非常に高率で発症することが報告されています。
身体機能の低下が脳の働きに直接影響しているため、せん妄からの完全な回復は難しいのが現実です。
しかし、すべてのせん妄が回復不可能というわけではありません。
同ガイドラインでは、脱水や電解質異常、薬物(特にオピオイドなど)によるせん妄は終末期においても回復の可能性があると示されています。
脱水や便秘、薬の影響、環境の変化といった「原因」を取り除くことで、症状が改善するケースも多くあります。
大切なのは、せん妄を「もう終わりだ」と諦めるのではなく、症状を和らげ、本人の苦痛を少しでも取り除くためのケアを考えることです。
私たちが提唱するMCSケアモデルでは、終末期のせん妄を身体状態の変化を示す重要なサインと捉え、適切なケアによってご本人の安心に繋げることを目指しています。
これは、最期の時までその人らしい「当たり前の生活」を支えるという理念に基づいています。
「後悔しない看取り」のために知っておきたいこと
「もっと何かできたのではないか」。
看取りの後、多くのご家族がこのような後悔の念に苛まれます。
後悔しないために最も大切なことは、せん妄という「症状」の奥にある、ご本人の「感情」に寄り添うことです。
厚生労働省の「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」では、患者本人の意思を可能な限り尊重し、医療・ケアチームと家族が話し合いを重ねることの重要性が示されています。
認知症ケアの現場では、たとえ出来事そのものの記憶が失われても、「楽しかった」「安心した」という温かい感情は心に残り続けることが分かっています。
これは「感情記憶」とよばれるものです。
北海道にある「愛の家グループホーム帯広東12条事例」の事例では、職員との楽しい思い出の感情記憶によって、ご本人が「ここが私の居場所」と心からの安心を口にされる様子がみられました。
せん妄で混乱しているように見えても、ご家族の優しい声かけや穏やかな態度は、必ずご本人の安心感につながります。
正しい知識を持つことは、ご家族が自信を持って、愛情ある関わりを続けるための力になるのです。
スポンサーリンク
せん妄について改めて知っておきたい基礎知識
せん妄への適切な対応は、まず「せん妄とは何か」を正しく知ることから始まります。
ここでは、症状の具体的なチェックリストから原因、そして多くの方が混同しがちな「お迎え現象」との違いまで、基本的な知識を分かりやすく解説します。
せん妄の症状チェックリスト
ご家族の様子が「せん妄かもしれない」と感じたら、まずは客観的に症状を確認してみましょう。
日本サイコオンコロジー学会のガイドラインによると、せん妄は「身体的異常や薬物の使用を原因として急性に発症する意識障害(意識変容)を本態とし、失見当識などの認知機能障害や幻覚妄想、気分変動などのさまざまな精神症状を呈する病態」と定義されています。
以下の項目に当てはまるものが多いほど、せん妄の可能性が高いといえます。
| チェック項目 | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 注意力の低下 | 会話に集中できず、話がすぐ逸れる。質問に的確に答えられない。 |
| 思考の混乱 | 話の辻褄が合わない。まとまりのない話をする。 |
| 意識レベルの変化 | ぼーっとしていることが多い(傾眠)。逆に興奮して落ち着かない。 |
| 症状の急な発症 | 数時間から数日の間に、急に症状が現れた。 |
| 症状の変動 | 1日の中でも、症状がよくなったり悪くなったり波がある(特に夜間に悪化)。 |
| 見当識障害 | 今いる場所や今日の日付、時間が分からなくなる。(見当識障害との関係について詳しく) |
| 記憶障害 | 直前の出来事を覚えていない。(物忘れと病的な症状の見分け方) |
| 幻覚・錯覚 | 虫や動物など、実際にはないものが見える(幻視)。壁のしみを人と見間違える。 |
これらの症状を記録しておくことは、医師や看護師に状況を正確に伝える上で非常に役立ちます。
終末期に起こるせん妄の3つの原因
なぜ、終末期にせん妄は起こりやすくなるのでしょうか。
その原因は、単独ではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。
原因は大きく3つのグループに分けられます。
- 準備因子(もともとある、せん妄になりやすい素地)
高齢であること、認知症や脳卒中の既往歴、視力や聴力の低下などが挙げられる。
これらは、せん妄を引き起こすための土台となる要因。 - 促進因子(せん妄の直接的な引き金となるもの)
脱水、栄養不足、便秘、痛み、感染症、薬の副作用、手術後、入院などの環境変化がこれにあたる。
ご家族や医療者が介入することで、取り除いたり和らげたりできる可能性のある要因。 - 直接因子(脳の機能に直接ダメージを与えるもの)
脳腫瘍や脳梗塞、頭部の外傷、重い肝臓や腎臓の病気など、病気そのものが原因となるもの。
終末期は、これらの因子が複雑に絡み合い、脳が正常に機能しにくい非常にデリケートな状態にあるため、せん妄が起こりやすくなるのです。
特に脱水や栄養不足は重要な促進因子であり、私たちの施設では科学的根拠に基づき、水分や栄養の適切な摂取をケアの基本としています。
せん妄と「お迎え現象」との違い
「亡くなったおじいちゃんが迎えに来た」。
終末期には、このような「お迎え現象」とよばれる体験をされる方がいます。
これは、せん妄の症状のひとつである「幻視」とよく似ていますが、少し性質が異なります。
医学的研究によると、終末期がん患者の約4割に「お迎え現象」がみられるという調査結果があります。
せん妄による幻視は、虫が見えるなど、ご本人にとって恐怖や不安を伴う場合が少なくありません。
一方、「お迎え現象」は、亡くなった親しい人やペット、美しい風景などが見えることが多く、ご本人は穏やかで安心した表情をされていることが多いのが特徴です。
医学的にはどちらも脳機能の低下によるものと説明されますが、ご家族としては無理に区別する必要はありません。
大切なのは、ご本人がみている世界を否定せず、「そう、会いに来てくれたのね」と穏やかに受け止める姿勢です。
それが、ご本人の心の安らぎにつながるのです。
家族にしかできない寄り添い方
専門的な治療やケアは医療者に任せるしかありませんが、ご家族にしかできない、最も重要な役割があります。
それは、ご本人の心に寄り添い、安心感を与えることです。
ここでは、具体的な関わり方のコツをお伝えします。
やってはいけない対応と心が軽くなる声かけの基本
よかれと思ってした対応が、逆にご本人を興奮させてしまうことがあります。
まずは、避けるべき対応を知っておきましょう。
| やってはいけない対応(NG例) | 心が軽くなる対応(OK例) |
|---|---|
| 否定する:「そんな人どこにもいないでしょ!」 | 受け止める:「そうなのね。会いに来てくれたのね。」 |
| 説得する:「ここは病院だよ、しっかりして!」 | 安心させる:「大丈夫よ、私がそばにいるからね。」 |
| 質問攻めにする:「誰が見えるの?何を言ってるの?」 | ゆっくり話す:「〇〇さん、お茶を飲みましょうか。」 |
| 子ども扱いする:「分かった、分かった。」 | 敬意を払う:「いつもありがとうございます。」 |
東京都の「愛の家グループホーム大田久が原事例」では、「食事をしていない」というご本人の訴えに対し、職員は否定せず、無糖の水ゼリーで対応し続けました。
この寄り添う姿勢が信頼関係を築き、ご本人の穏やかな生活につながったのです。
ポイントは、「正しさ」よりも「安心」を優先すること。
短い言葉で、穏やかに、ゆっくりと話しかけることが、ご本人の心を落ち着かせる一番の方法です。
「お迎え現象」といわれたら?否定も肯定もしない向き合い方
ご本人が「亡くなった夫が枕元に立っている」と話された時、どのように応えればよいでしょうか。
このような「お迎え現象」に対しては、否定も肯定もしすぎない、中立的な姿勢が大切です。
大切なのは、ご本人が見ている世界や感じている気持ちを、そのまま受け止めることです。
- まずは傾聴する:「そうなのね。どんな様子だった?」
- 気持ちに寄り添う:「会えてよかったわね」「少し怖かった?」
- 安心させる:「私も一緒にいるから大丈夫よ。」
ご本人は、お別れの時が近いことを無意識に感じ取り、心の準備をしているのかもしれません。
その神聖な時間を、ご家族は静かに見守り、寄り添うことが何よりのケアになります。
無理に現実に戻そうとせず、ご本人の世界観を尊重しましょう。
興奮している時と静かな時(低活動型)のタイプ別にみるケアのコツ
せん妄は、大きく2つのタイプに分けられます。
大声を出したり、落ち着きなく動き回ったりする「過活動型」と、逆に元気がなく、ぼんやりと傾眠がちになる「低活動型」です。
日本サイコオンコロジー学会のガイドラインによると、終末期では低活動型せん妄が多くみられ、活動性や反応性の低下、会話量の減少などが特徴で、抑うつ症状と誤診されやすいとされています。
それぞれのタイプで、ケアのポイントが異なります。
【過活動型のケアのコツ】
- まずは安全を確保する(転倒しそうなもの、危険なものを片付ける)
- 照明を明るくし、不安感を和らげる
- 穏やかな音楽をかけるなど、安心できる環境を作る
- ご本人の話を傾聴し、興奮の原因となっている不安を探る
【低活動型のケアのコツ】
- 「ただ疲れているだけ」と見過ごさないことが最も重要
- 日中はカーテンを開け、優しく声をかけて覚醒を促す
- 脱水や食事量の低下に注意し、記録をつける
- 褥瘡(床ずれ)予防のため、時々体勢を変える手伝いをする
特に低活動型は、静かなために問題が見過ごされがちです。
しかし、生命の危機に直結するサインである場合も少なくありません。
「いつもと違う静かさ」に気づくことが、重要なケアの第一歩です。
せん妄患者と残された時間を穏やかに過ごすために
せん妄の症状が出始めると、お別れの時が近いことを意識せざるを得ません。
残された貴重な時間を、ご本人にとってもご家族にとっても、できるだけ穏やかなものにするために、今から準備できることがあります。
終末期に起こる週・日・時間単位での変化
終末期が近づくと、身体には特徴的な変化が現れます。
国立がん研究センターの医療専門家向けガイドラインでは、死期切迫の診断に有用な身体徴候が明確に示されています。
これらのサインを知っておくことは、心の準備につながるでしょう。
| 時期 | 主な身体の変化のサイン |
|---|---|
| 数週~数日前 | ・食事や水分の量が減る ・眠っている時間が長くなる ・活動量が減り、会話が少なくなる |
| 数日~数時間前 | ・呼びかけへの反応が鈍くなる ・意識が朦朧とすることが増える ・手足が冷たくなり、紫色になることがある |
| 数時間~臨終直前 | ・呼吸が不規則になる(下顎呼吸、チェーン-ストークス呼吸) ・喉の奥でゴロゴロという音がする(死前喘鳴) ・血圧が低下し、脈が弱くなる |
これらの変化は、身体が少しずつお休みに入るための自然なプロセスです。
一つひとつのサインに一喜一憂せず、穏やかな気持ちで見守ることが大切です。
看取り期間の過ごし方についても知っておくと、より落ち着いて対応できるでしょう。
在宅?入院?家族が考えるべきことと相談先
最期の時をどこで迎えるかは、ご本人とご家族にとって非常に重要な選択です。
厚生労働省の意識調査では、国民の54.6%が「自宅で最期を迎えたい」と回答しているにもかかわらず、実際には74.6%が病院で死亡している現状があります。
在宅での看取りと、病院や施設での看取りには、それぞれメリットとデメリットがあります。
- 在宅での看取り
メリットは、住み慣れた環境で、ご家族との時間を自由に過ごせることです。デメリットは、ご家族の介護負担が大きく、急変時の不安があることです。 - 病院・施設での看取り
メリットは、医療者が常にそばにいて、急変時にすぐ対応してもらえる安心感があることです。デメリットは、面会時間に制限があったり、環境の変化がご本人のストレスになったりすることです。
札幌星置の施設では、職員が介護を担うことで、ご夫婦が「介護者と被介護者」の関係から本来の「夫婦」の関係に戻り、最期まで二人だけの時間を重ねられた事例があります。
介護の負担を専門家に任せることで、ご家族は心理的な余裕を取り戻し、大切な人との関係性に集中できるという側面もあります。
在宅介護サービスの活用方法やターミナルケアの基本を知り、かかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センターなどとよく相談し、ご本人とご家族にとって最もよい形を選びましょう。
始めるなら早めに!「人生会議」で本人の想いを形に
もしもの時に備え、ご本人がどのような医療やケアを望むか、元気なうちから話し合っておくことを「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」といいます。
これは厚生労働省が2018年に普及・啓発を目的として付与した愛称で、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」として定めています。
せん妄が進行すると、ご本人の意思を確認することは難しくなります。
「延命治療は望むか」「最期はどこで迎えたいか」など、ご本人の価値観や想いを事前に共有しておくことは、残されたご家族が迷い、苦しむことを減らすために非常に重要です。
これは、一度話して終わりではありません。
ご本人の気持ちは、体調や時間とともに変化することもあります。
日々の会話の中で、「もしもの時、どうしたい?」と、繰り返し話し合う機会を持つことが大切です。
ご本人の想いを尊重することが、何よりの看取りケアといえるでしょう。
忘れてはいけないせん妄患者の家族のケア
ご本人のケアに懸命になるあまり、ご家族自身の心と体が限界を迎えてしまうことがあります。
しかし、介護するご家族が倒れてしまっては、元も子もありません。
ここでは、ご家族自身のケアの重要性についてお伝えします。
「自分のせいだ」と責めるのはNG!感情との上手な付き合い方
「私の対応が悪かったから、せん妄が悪化したのではないか」。
多くのご家族が、このような罪悪感を抱えてしまいます。
しかし、せん妄は病気や身体の衰弱が引き起こす症状であり、決してご家族のせいではありません。
まずは、「辛い」「悲しい」「疲れた」といったご自身の感情を、ありのままに認めてあげましょう。
- 感情を言葉にする:信頼できる友人や他の家族に、今の気持ちを話してみる
- 完璧を目指さない:「100点満点の介護」は存在しないと割り切る
- 専門家を頼る:ケアマネジャーや医師、看護師は、介護のプロであると同時に、ご家族の相談相手でもあります
一人で抱え込まず、周りに助けを求めることは、決して悪いことではありません。
むしろ、上手な介護を続けるために必要なスキルなのです。
休息をとるための具体的な方法
介護は24時間続く、終わりの見えないマラソンのようなものです。
意識的に休息をとり、心と体をリフレッシュする時間を作りましょう。
- レスパイトケア(一時的な休息)の活用
ショートステイやデイサービスなどを利用し、介護から離れる時間を作ること。
数時間でも離れることで、心に余裕が生まれる。 - 家族内で役割分担をする
介護を一人で背負わず、兄弟姉妹や親戚と協力し、役割を分担すること。
「情報収集する係」「手続きをする係」「話し相手になる係」など、できることはさまざま。 - 自分のための時間を持つ
30分だけでも、好きな音楽を聴いたり、散歩をしたり、自分のためだけの時間を確保すること。
介護による家族への影響と対策について知り、社会資源や周りの人々の力を上手に借りることが、長い介護生活を乗り切るための重要な鍵となります。
まとめ
この記事では、終末期のせん妄について、その症状や原因、そしてご家族にできる寄り添い方について解説してきました。
せん妄は、お別れが近いことを示すサインである可能性があり、ご家族にとっては非常に辛く、不安なものです。
しかし、せん妄はご本人のせいでも、ご家族のせいでもありません。
それは、人生の最終段階で起こる、身体の自然な変化のひとつなのです。
最も大切なことは、せん妄という症状に振り回されるのではなく、その奥にあるご本人の心に寄り添い、安心感を与え続けることです。
- ご本人の世界を否定せず、穏やかに受け止める
- 短い言葉で、優しく話しかける
- 危険がないように環境を整え、安全を守る
これらの関わりは、ご本人の苦痛を和らげるだけでなく、ご家族自身の「できる限りのことをした」という納得感にもつながります。
後悔のないお別れのために、この記事で得た知識を力に変え、大切な方との残された時間を、どうか穏やかにお過ごしください。