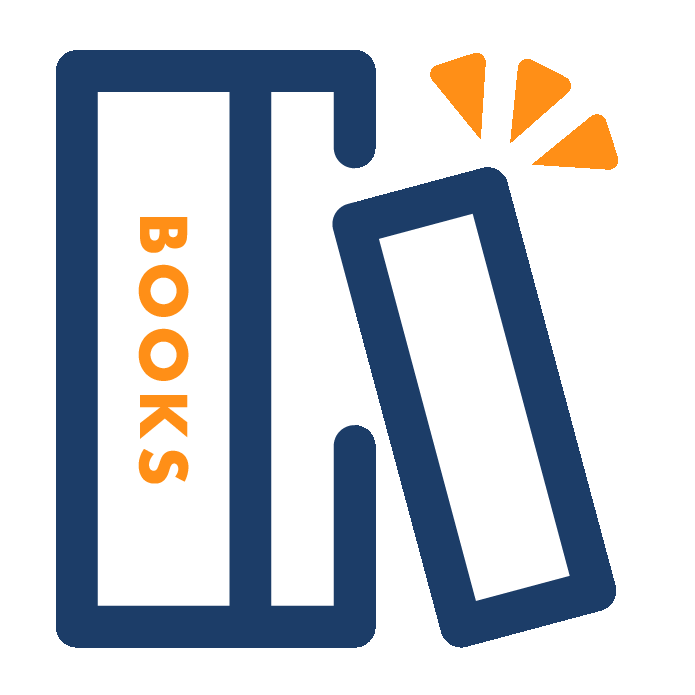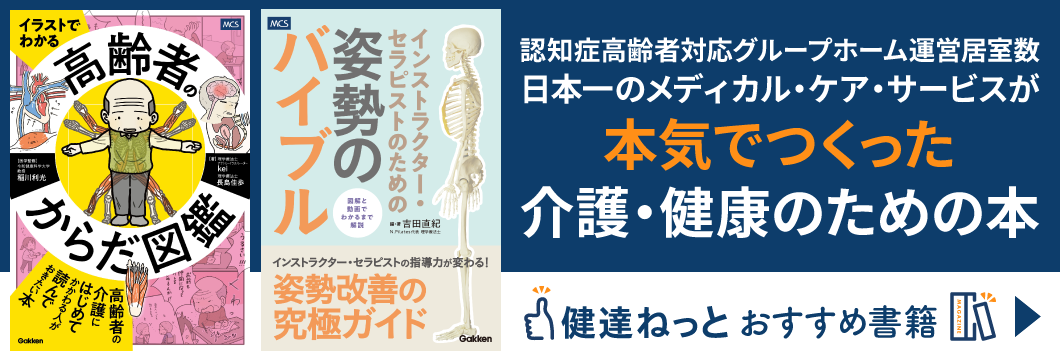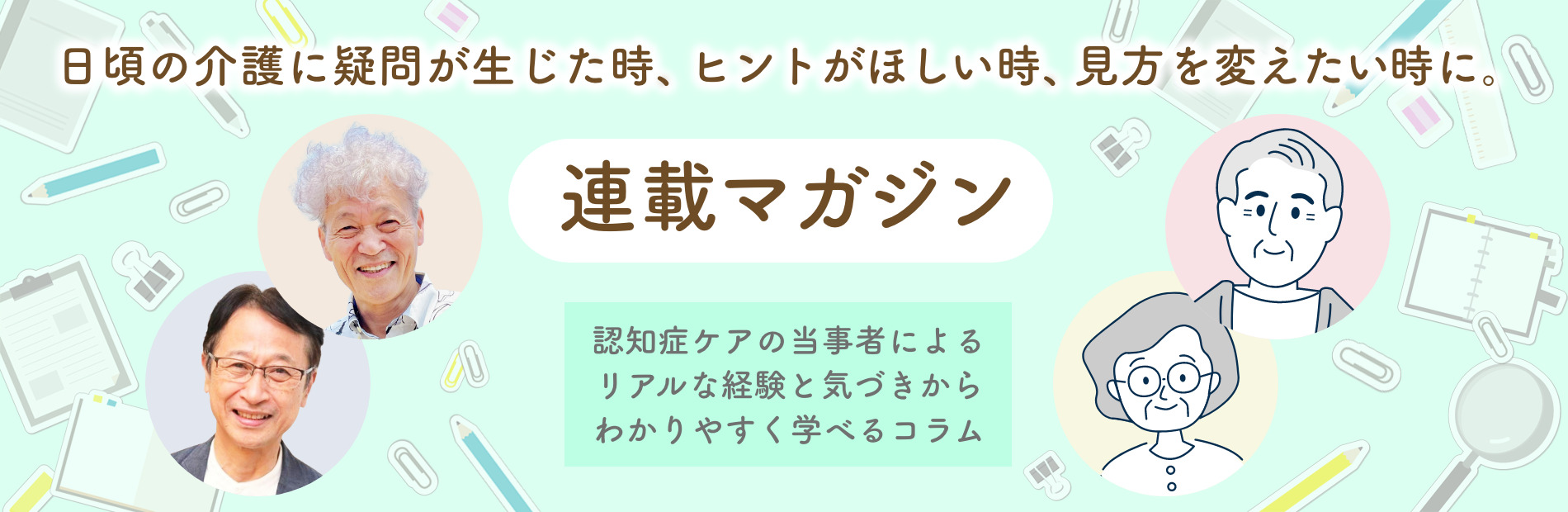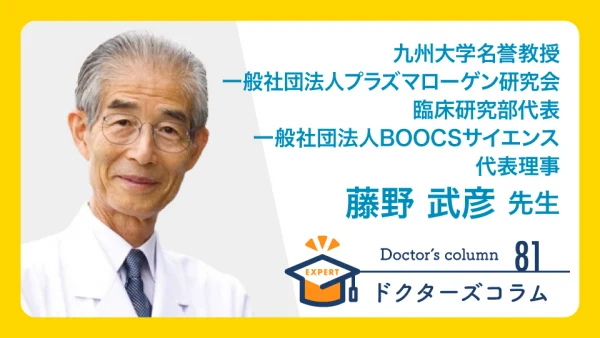公益社団法人 認知症の人と家族の会 理事・事務長
鎌田松代 先生
スポンサーリンク
両親が認知症に 「私が介護をすべきでは」施設入所まで悩んだ日々
2004年からの4年間に、九州で暮らしていた両親が、相次いで認知症と診断されました。
認知症のことを1990年から「公益社団法人 認知症の人と家族の会」(以下「家族の会」)で学んでいましたが、ショックでした。
これからどうなっていくのか知っていても、心の中は悲しみとともに、一生懸命に生きてきた両親の人生が変更を余儀なくされることに切なさを感じました。
「認知症にはなりたくなかった」ではありません。
両親が意欲をもってしていたことが、今までうまくできていたことができにくくなっていく。そのことを自覚して受け入れていかなくてはいけない両親の心の内を思うと、胸が張り裂けるような気持ちでした。
私のいる京都と、両親が2人で暮らす九州とは離れていて、数年に1回しか帰省していませんでしたが、毎月九州の実家に帰って両親を手助けすることにしました。その生活は11年間続きました。
自宅の環境を整え、介護保険サービスの利用など手助けをしても、この病気の性か症状は進行。徘徊が続き、最終的には在宅生活を断念して、介護施設に入所しました。
入所までには、症状が進行するたびに落ち込みました。
また、遅れて認知症を発症した母、排泄トラブルが出てきた父の介護……。
「介護の仕事をしている私が、認知症で不自由な暮らしとなった両親を看るのが当然だ」との思いが、私にはありました。他人様のお世話ではなく、親の介護をすべきではないか。そんな思いが日に日に強くなりました。
しかし両親は、子である私の生きたい進路を、さまざまな経済的支援も含め応援してくれていました。
私自身、介護の仕事は好きでやりがいを感じ、役割も多くもっていました。
そんな迷い悩んでいるときに、救われ、方向性が定まったのは、「家族の会」の京都府支部の世話人の人たちが、話を聞いてくれたことがきっかけでした。
スポンサーリンク
両親が本当に望んでいることは? 自分に置き換えて考えてみる
世話人の人たちは、私の父が認知症の診断を受けたときから、「どうしてはるの? 大丈夫?」と、会うごとに、またメールなどでも近況をたずねてくださっていました。
私からは、相手のご都合もあるし、「今、話をしていいのだろうか」との遠慮があり、なかなか話すことができませんが、たずねてくださると一気に話をしていました。
すべてを受け止めてくださる、包容力のある話し相手でした。それは認知症の人を介護した同じ経験者や、たくさんの相談を受けて、認知症の人の介護家族の心情をよく知っている、専門職であったからでした。
「ご両親は、鎌田さんが仕事を辞めて介護をしてくれることを、喜ばれるやろうか」
その日の話は、この問いかけから始まりました。
両親、特に母は、認知機能が低下して不自由になる暮らしのなかでも、私が帰るときには「気いつけて帰らんば」「また来んね」でした。
決して「帰らんといて」「看てくれんね」と言ったことはありません。
なぜそう言うのか? 私は自身のことに置き換えて考えました。
私には3人の子どもがいます。その子どもたちの生きたい人生を変更し、私の介護をしてほしいとは、私は思いません。
子どもたちはそれぞれに努力して、今のやりたい仕事に邁進しています。子どもたちが介護してくれなくても、介護してくれるサービスや人はいます。でも気持ちだけは、不自由になった親のことを思っていてほしいです。
やりたい仕事をがんばる自分の姿こそ、両親が心から願ってくれたもの
両親もそうなのではないかと、これまでの認知症となってからの、またそれ以前の両親の言動を思い返しました。
やりたい仕事をしている私や弟は、両親の自慢でした。孫にそのことを話しているのを聞いたこともありました。
両親は時代もあり、自身の受けたい教育や、やりたいことができたわけではない人生でした。それを子どもに託し、経済面も含め、進路は子どものしたいこと優先でした。
そして京都府支部の世話人さんは、こう言ってくださいました。
「鎌田さんは、京都で目の前の困っている方々を助けることをがんばればいい。ご両親は暮らし慣れた田舎で介護を受けていけばいいのでは。そっちが幸せ。鎌田さんが仕事を辞めて介護することを喜んではいないと思うよ。仕事も介護も、遠距離介護の中でがんばりなさい」
悩んでいたことが吹っ切れ、目の前に道が開けた瞬間でした。
それから6年間、田舎に毎月帰省し、両親を見守りました。食事もとれなくなった母との最期の面会時に、母が話せない中で動いた唇は、「気をつけて帰り」でした。
「家族の会」のメッセージ、“認知症でも心は生きている”瞬間でした。