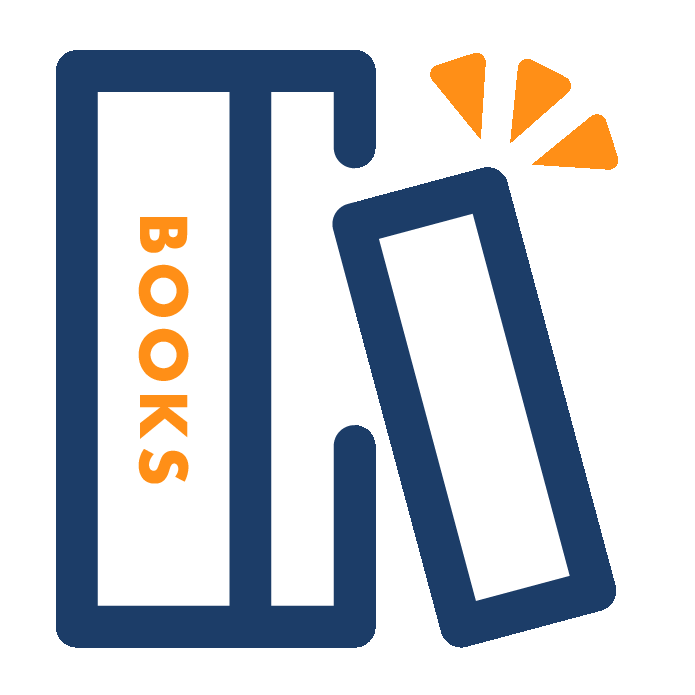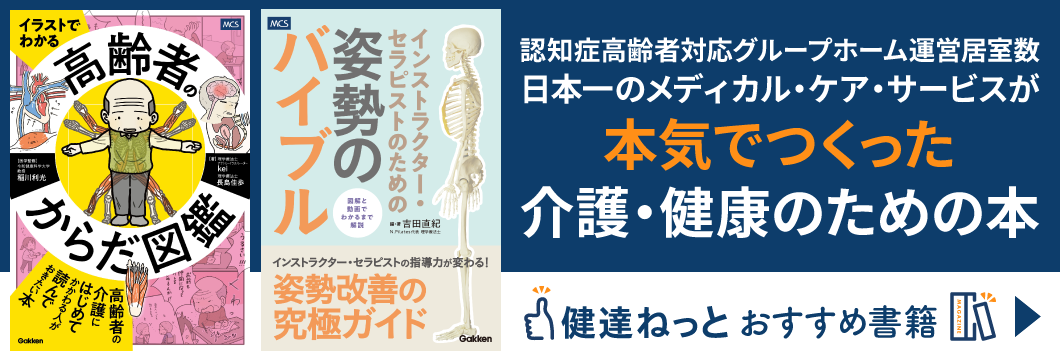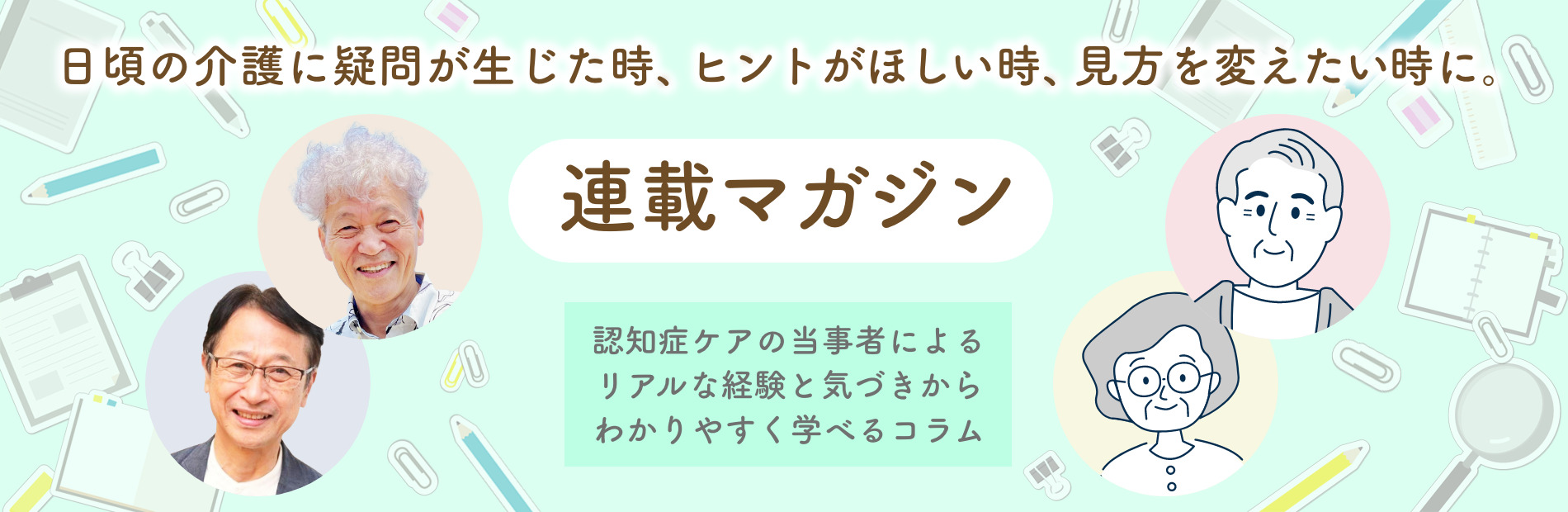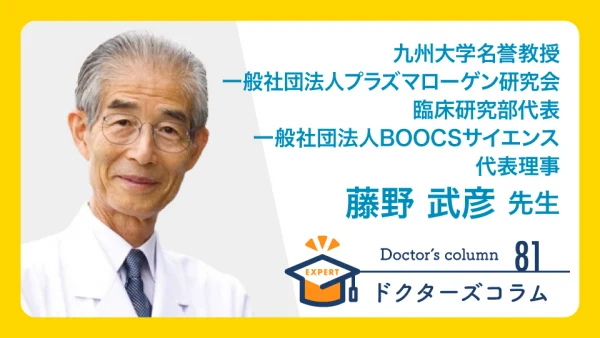日本赤十字社医療センター看護部 老人看護専門看護師
及川 咲 先生
スポンサーリンク
コロナ禍の自粛生活が、認知症の症状にも影響を与えている
新型コロナウイルスの感染が拡大し、2年近くが経過しました。私たちは不要不急の外出の自粛など、さまざまな生活制限を強いられています。
高齢の方は、ウォーキングなど適度な運動をする機会を奪われるだけでなく、カラオケの自粛など人と接する機会まで少なくなり、遠方の家族との関わりや地域住民同士の関わりが減少することで「コロナフレイル(*1)」という状態になっているといわれています。
認知症のある患者さんの場合では、デイサービスやショートステイが閉鎖され、刺激が減少し「認知症が悪化した」「表情が乏しくなってしまった」、あるいは、ご家族が介護に疲れてしまったという話も聞こえてきます。
このように、新型コロナウイルスは、感染してもしなくても、身体や心にさまざまな影響を及ぼしているという状況があります。
*1 コロナ禍で長引く自粛生活などが影響して、日々の活動量が減って体重が落ちる、疲れやすくなる、何事も億劫になるなど、身体機能や認知機能の低下が進むこと。
スポンサーリンク
同じ目線に立った接し方で、症状を引き起こす“理由”が見えてくる
認知症には、「中核症状」と「行動・心理症状」というものがあります。
中核症状には、
- 記憶障害:脳の働きの低下が原因で起こる
- 見当識障害:場所や時間、人がわからなくなる
- 理解・判断力の障害
- 実行機能障害:行動を組み立てて行うことができない
- 失語・失行
があります。
行動・心理症状は、中核症状の影響を受けて不安や混乱が生じた結果、抑うつ的になったり攻撃的になったりすることをいいます。
この行動・心理症状は、以前は「問題行動」と呼ばれていましたが、認知症の研究が進むとともに、認知症の方の行動には「何らかの意味がある」と考えられるようになりました。そして、症状が強く出ている患者さんには、患者さん本人を中心とした関わり方(パーソン・センタード・ケア)がよいとされています。
たとえば、「徘徊」は「あてもなく歩き回ること」といわれる行動ですが、「なぜ歩き回るのか」という、その方の中にある理由を探ってみることが大切です。すると「幼い頃の自分の子供を探している(自分の歳がわからず若い頃に戻ることが多い)」や、「見知らぬ場所に来ているようで、いつもの家の横の道に出たくて歩いている」など、当事者の目線に立って考えることで、解決の糸口が見えてくることがあります。
見知らぬ場所で迷子になったときの、あの漠然とした不安を感じているのだと想像するだけでも、対応は変わってくるのではないでしょうか。
不安を和らげる接し方で、普段の暮らしを思わせる環境をつくる
急性期病院に勤務していると、「入院すると認知症が悪化してしまう」という、家族の不安の声をよく耳にします。病院に限らず、生活環境が変わったときに一時的に“認知症が悪化した”ように見える、この混乱状態を「リロケーションショック」といいます。
新型コロナウイルスの蔓延により家族との面会も制限される中、入院前の生活習慣を継続することも、ましてや生活習慣を伝えることすらままならないことがあります。特に急性期病院という場所は、治療が優先されがちで日常生活とはかけ離れた場所になりやすく、身体のつらさ、慣れない環境に身を置くことによる不安、ストレスなどから、せん妄や行動・心理症状を招いてしまうことが少なくありません。
そうならないよう、私たち看護師は、認知症のある患者さんがどこにいても安心できるように、使い慣れた時計や家族写真、衣服などを持ってきてもらうことがあります。患者さんは、自分の匂いのする着慣れた肌着を着るだけで、あるいは、使い慣れた腕時計を身に着けるだけで落ち着くことがあるのです。
たとえば、ある患者さんは、何度説明をしても自分の病室が分からなくなっていました。そこでご家族にお願いし、本人が普段から愛用しているガウンや、愛犬の写真を持ってきていただき、廊下から見える位置に設置することに。すると患者さんは「ここが自分の部屋だ」と認識できるようになり、部屋を迷うことはなくなりました。
また、ある患者さんは面会制限があり、普段一緒に生活をしている家族と話すことができず、大変混乱しているようでした。ご家族もその患者さんがどのように過ごしているかと心配されており、看護師に相談に来られました。私たちは、患者さんが面会制限下でも家族の存在を感じられ、安心して療養できる環境をつくることが必要だと考えました。
そこで、ご家族に写真や、自宅でよく視界に入っていたもの(手帳やカレンダー、人形など)を持参してもらうことを提案。後日、家族のメッセージが書かれた大きなアルバムが届きました。患者さんと一緒にアルバムをめくりながら家族の思い出話をするようになると、患者さんの不安そうな表情が和らぎ、笑顔が増えたのです。また、携帯電話を持参してもらい、1日1回、通話の援助を行うことで混乱も落ち着きました。
このように、場所が変わっても、これまでの生活を継続することの大切さや、家族の力の大きさを感じることが多々あります。
その人の“歴史”を大切に。自分らしく生活できるような接し方で支援する
認知症というのは確かに、記憶力の低下や、できないことが増えていく病気です。しかし、これまでの生き方や考え方の根本は、それほど大きく変わるものではありません。
できなくなったところばかりに目が向きがちですが、できているところへの支援を重ね、たとえ生活する場所が変わっても、その人らしく生活できるとよいと思います。私たち医療者も、その方のもともとの性格や、これまで生きてきた歴史や生活を大切に、支援をしていきたいと考えています。