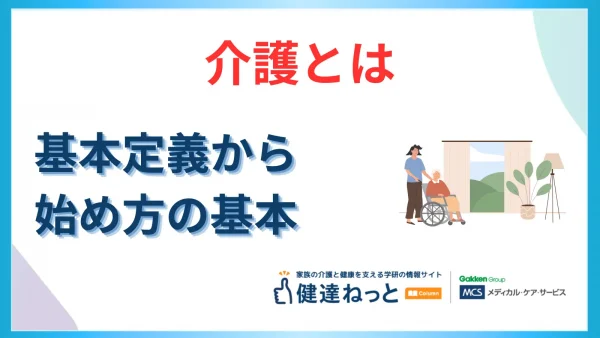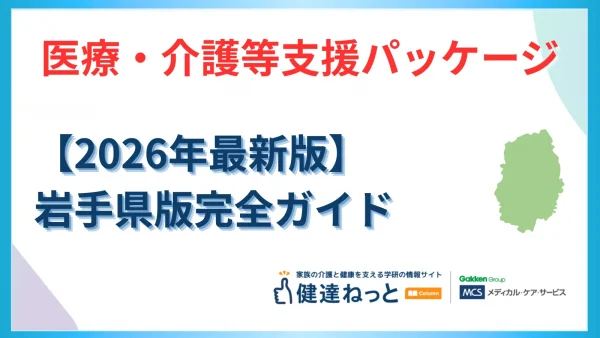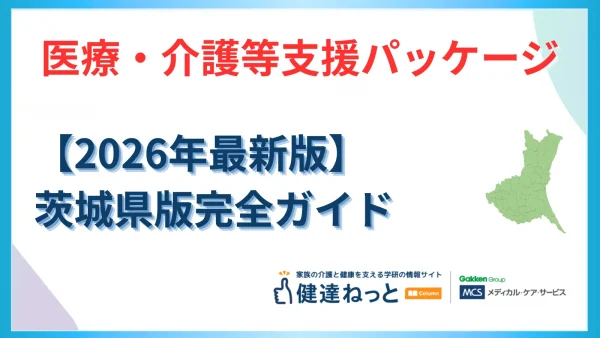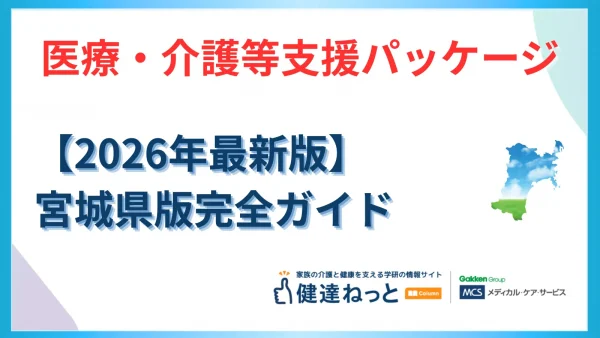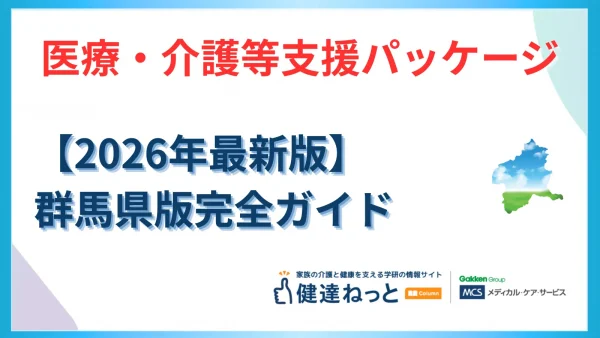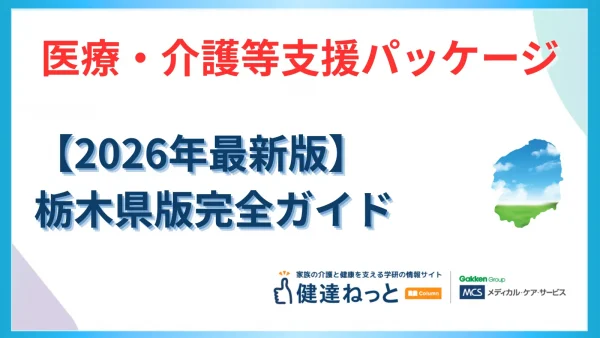介護という言葉を耳にした時、下記のような不安や疑問が頭をよぎりませんか?
- 親のことが心配だけど、何から始めればいいか分からない…
- 介護にはどれくらいの費用がかかるのだろう?
- 仕事や自分の生活と、どうやって両立すればいいの?
- 「介護」と「介助」って、具体的に何が違うの?
大切な家族のことだからこそ、先の見えない状況に一人で悩んでしまうのは当然のことです。
しかし、ご安心ください。
この記事は、そのようなあなたの「分からない」を「分かる」に変えるための羅針盤です。
この記事を読めば、以下の点が明確になります。
- 介護の本当の意味と、介助・看護との明確な違い
- 介護が必要になった時の「最初の一歩」と具体的な流れ
- 在宅と施設、それぞれの費用とメリット・デメリット
- あなたと家族の関係を守るための、よい介護の考え方
読み終える頃には、漠然とした不安は「まず、あそこに相談してみよう」という具体的な行動計画に変わっているはずです。
未来への確かな一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。
スポンサーリンク
そもそも介護とは?たった1分で分かる定義と目的
「介護」と聞くと、身の回りのお世話をする「介助」をイメージする方も多いかもしれません。
しかし、介護の本当の意味は、単なる手助けとは少し違います。
ここでは、その本質を理解することで、介護への向き合い方が変わるはずです。
介護の定義は「自立を支え、その人らしい生活を守るパートナーシップ」
介護とは、厚生労働省によると「歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与すること」と定義されていますが、より広義には、高齢や心身の障害で日常生活に支障がある人に対し、その人の能力を最大限に活かし、自分らしい生活を続けていけるよう支えることです。
単に「できないことを手伝う」のではなく、その人の「できること」を見つけ、それを維持・向上させるためのパートナーとして伴走する。
この視点が、よい介護の第一歩といえます。
健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービス株式会社(MCS)は、25年以上の認知症ケア実績から「当たり前の生活を実現する」ことを介護の本質と定義しています。
その考え方は、以下の通りです。
- 自身の想いを表出できる状態
- 何をしたいのか、どこに行きたいのか、何をすると楽しいのかを選択できる
- 自分の行動を自由に選択・実行できる状態
この定義は、全国287ホーム、3,821名のデータと実績に基づいています。
MCSの介護では、85%以上の方の認知症の周辺症状や心身の状態改善を実現しています。(参考:MCSケアモデル)
介護の目的は「お世話」ではなく「自立支援」
介護の最終的な目的は、あくまで「その人らしい自立した生活」を維持することです。
必要以上の手助けは、かえって本人の持つ能力を低下させてしまう可能性があります。
介護は、ご本人が持つ力を引き出すための支援です。
健達ねっとを運営するMCSでは、介護の目的を「お世話」ではなく「自立支援」と明確に定義し、以下の「6つの目指す状態」を設定しています。
- おいしく味わえる食事状態
- トイレでの排泄
- 自分の足でしっかりと歩ける歩行状態
- 快適な睡眠
- 自分の望み・想いを表出できる状態
- 認知症の方の「不確かさ」で「不安」な状況を「確か」で「安心」できる状況への転換
これらの状態は、科学的根拠に基づいた再現性の高いケアによって実現することが可能です。
より深く知りたい方は、認知症ケアの第一人者が語る介護のリアルな現場の声から、実践のヒントを得るのもよいでしょう。
スポンサーリンク
混同しがちな「介護」「介助」「看護」の違い
介護について調べていると、「介助」や「看護」といった言葉もよく目にするかもしれません。
これらは似ているようで、それぞれ明確な違いがあります。
正しい知識が、よりよいサービス選択へとつながります。
範囲の違い
介護、介助、看護はそれぞれ支援する範囲が異なります。
それぞれの範囲を理解することで、必要なサポートを的確に判断できるようになります。
ポイントは以下の通りです。
- 介護:日常生活全般にわたる包括的な支援
- 介助:食事、入浴、着替えなど特定の動作の手伝い
- 看護:健康管理や医療行為といった医療的な支援
介護は、介助を含みつつ、精神的なケアや社会的なつながりの支援まで行う、より広い概念と捉えるとよいでしょう。
目的の違い
範囲が異なるのは、それぞれが目指す目的が違うためです。
目的を理解することで、各専門職がどのような視点で関わっているのかが明確になります。
| 種類 | 目的 |
|---|---|
| 介護 | その人の自立を促し、生活の質(QOL)を向上させる |
| 介助 | 本人ができない動作を部分的に補い、安全に行動できるようにする |
| 看護 | 症状の改善や悪化を防ぎ、健康状態を維持・回復させる |
当社の介護現場では、約250項目にわたるアセスメント(調査・評価・分析)を実施し、一人ひとりの身体機能や認知症の症状を科学的に分析しています。
この科学的なアプローチにより、「介護」「介助」「看護」の明確な役割分担を実践。
287ホーム4,489名中3,821名(85%以上)の改善実績を達成しています。
MCS版自立支援ケア
一目で分かる比較表
これまでの内容を、ひとつの表にまとめました。
それぞれの役割の違いを、比較しながら確認してみてください。
| 項目 | 介護 | 介助 | 看護 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 自立支援 | 動作の代替 | 健康管理・医療 |
| 主な担い手 | 介護福祉士、介護職員 | 介護福祉士、介護職員 | 看護師 |
| 支援範囲 | 生活全般 | 日常生活動作(ADL) | 医療的ケア |
| 具体例 | 相談援助、環境整備、生活支援 | 食事、入浴、排泄、移乗 | 投薬管理、バイタルチェック、褥瘡の処置 |
このように、それぞれの専門性を理解し連携することが、質の高いケアにつながります。
よい介護とは?本人と家族の関係を守る「介護の三原則」
よい介護とは、単に手厚くお世話をすることではありません。
ご本人とご家族が幸せな関係を維持するための、考え方の土台があります。
それが「介護の三原則」です。
この原則を知り、実践することで、介護の質がぐっと向上します。
1.生活の継続性
「生活の継続性」とは、ご本人のこれまで培ってきた暮らし方や価値観、生活リズムをできる限り尊重し、維持することです。
環境が変わっても、好きな習慣や役割を続けられるように支援することが大切です。
たとえば、次のような配慮が考えられます。
- 昔から日課だった庭いじりを続ける
- 毎朝決まった時間に散歩に出かける
- 趣味の編み物を続けるための道具を揃える
- 食後のコーヒーは必ずブラックで飲む
愛の家グループホーム帯広東12条では、夫婦で入居された方の事例があります。
夫が亡くなってから5年経った現在でも、一緒に外出された思い出は鮮明に覚えていると話されるそうです。
「父さんがあんたに私のこと頼んでいったんだよね」「ここが私の居場所だから」と話すこの方の言葉は、認知症でも感情の記憶は残り、良い感情を積み重ねることで信頼関係と居場所感を築けることを示しています。
このような考え方を日々のケアに活かすためには、やさしい在宅介護の実践的なコツを知っておくと、より具体的なアプローチが可能になります。
2.自己決定の尊重
「自己決定の尊重」とは、たとえ介護が必要な状態になっても、ご本人の意志や希望を最大限に尊重することです。
何を着るか、何を食べたいか、どのように過ごしたいか、といった小さな選択肢を奪わないことが大切です。
これにより、ご本人の尊厳が守られ、自己肯定感を保つことにつながります。
具体的な実践例は以下の通りです。
- 日中の過ごし方について、その都度本人の希望をたずねる
- 着る服は、本人が好きな色やデザインのものを選んでもらう
- 食事メニューは、本人の好みに合わせて調整する
愛の家グループホーム弥富では、脳出血の後遺症で感情のコントロールが困難だった方の「一人で散歩がしたい」という思いを実現するため、職員が徐々に距離を置き、見守る形で支援しました。
すると、表情が明るくなり笑顔が増加。
現在では、地域の人々の見守りの中で散歩を楽しまれています。
3.残存能力の活用
「残存能力の活用」とは、ご本人がまだ自分でできることを尊重し、過剰な手助けをしないことです。
すべてを介護者が「やってあげる」と、本人の身体機能や認知機能がさらに低下してしまう危険性があります。
たとえば、以下のような配慮が大切です。
- 着替えは、できるところまで本人に任せる
- 食事は、ご自身でスプーンを持てるよう介助する
- 車椅子に乗り移る際は、自分で踏ん張るよう声かけをする
これは、ご本人の自立心を守るだけでなく、介護者の負担を減らすことにもつながる、双方にとって重要な考え方です。
親の様子が気になったら?介護を始める時の相談先とステップ
「最近、親の様子が少し心配」。
そのような気持ちが芽生えたら、それは介護の準備を始める良い機会です。
一人で抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう。
ここでは、介護を始めるための最初の相談先と具体的なステップを紹介します。
最初の相談窓口は「地域包括支援センター」の一択
介護について誰に相談すればよいか分からないという場合、まずは市区町村が設置する「地域包括支援センター」に問い合わせてみましょう。
ここは、介護・医療・福祉・健康など、高齢者の生活を支えるための総合窓口です。
具体的に地域包括支援センターがどのような場所で、どのような役割を担っているのかを事前に知っておけば、相談もスムーズに進みます。
特に、認知症に関する相談窓口としても重要な役割を果たしています。
地域包括支援センターの主な役割は以下の通りです(厚生労働省)。
- 介護に関する相談や悩みへのアドバイス
- 要介護認定の申請代行
- 介護サービス事業者の紹介
- 介護予防に関する情報提供
健達ねっとを運営するMCSは、2022年より全国の小中高校で「認知症教育の出前授業」を実施しています。
認知症への正しい理解を普及する取り組みは、将来の介護を担う世代にとって心強い存在です。
介護保険サービス利用までの5ステップ
実際に介護保険サービスを利用するためには、いくつかの手順を踏む必要があります。
まずは介護保険の制度内容や申請方法の全体像を把握し、サービスの利用に不可欠な要介護認定の基準やメリットを理解することから始めましょう。
ステップ1.相談・申請
市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで、要介護認定の申請を行います。
申請はご本人やご家族が行うことが可能です。
申請には、介護保険被保険者証とマイナンバーカード(または通知カード)が必要です。
ステップ2.認定調査
市区町村の職員などがご自宅を訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
調査員には、普段の様子を正確に伝えることが重要です。
事前に困っていることなどをメモしておくとよいでしょう。
ステップ3.審査・認定
認定調査の結果と、主治医の意見書などを元に、市区町村の介護認定審査会がご本人の「要介護度」を判定します。
この判定によって、利用できるサービスの種類や量が決まります。
ステップ4.ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ご本人の状態や希望に合わせて、どのようなサービスをどれくらい利用するかという「ケアプラン」を作成します。
ご本人とご家族の希望をしっかりと伝えることが、満足のいくサービス利用につながります。
ステップ5.サービス利用開始
ケアプランに基づき、介護サービス事業所との契約を結び、サービスの利用が始まります。
サービス開始後も、ケアマネジャーが定期的に状況を確認し、必要に応じてプランの見直しを行います。
「要支援」「要介護」とは?7段階の認定区分の違い
介護保険で利用できるサービスや、1か月に利用できるサービスの上限額は、認定された「要介護度」によって決まります。
要介護度は、介護の必要性が低い順に「要支援1〜2」、そして「要介護1〜5」の7段階に分けられます。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の動作はほぼ自立しているが、一部に見守りや手助けが必要 |
| 要支援2 | 立ち上がりや歩行に不安定さが見られ、一部介助が必要 |
| 要介護1 | 排泄や入浴などで一部介助が必要。認知機能の低下が見られることもある |
| 要介護2 | 排泄や入浴、食事などで介助が必要。歩行や立ち上がりが困難 |
| 要介護3 | 排泄、入浴、食事、着替えなど全面的に介助が必要。思考力・理解力の低下が著しい |
| 要介護4 | 介護なしでは日常生活を送ることが困難。問題行動が見られることもある |
| 要介護5 | 寝たきりの状態で、意思の伝達も困難 |
ご本人の心身の状態や、受けられるサービスを正しく把握するためにも、認定区分を理解しておくことが大切です。
在宅介護と施設介護どちらを選ぶ?後悔しないための判断軸
要介護認定を受けると、ご本人やご家族の意向に合わせて、在宅で介護を受けるか、施設で介護を受けるかという選択をすることになります。
どちらにもメリット・デメリットがありますので、ひとつずつ見ていきましょう。
【在宅介護】メリット・デメリットと受けられるサービス
住み慣れた自宅で、ご本人らしい生活を続けられることが最大のメリットです。
費用も施設介護に比べて安く抑えられるケースが多くなります。
一方で、介護者の負担が大きくなりやすい点がデメリットです。
より詳しい在宅介護のメリット・デメリットを比較検討し、ご家庭の状況に合っているかを見極めましょう。
在宅介護で受けられる主なサービスは以下の通りです。
- 訪問サービス:自宅を訪問してケアを行う(訪問介護、訪問看護)
- 通所サービス:施設に通って過ごす(デイサービス、デイケア)
- 短期入所サービス:短期間施設に宿泊する(ショートステイ)
- 福祉用具レンタルや住宅改修など
これらのサービスを組み合わせることで、介護者の負担を軽減しながら在宅生活を続けることが可能です。
【施設介護】メリット・デメリットと施設の種類
施設介護のメリットは、専門のスタッフによる24時間体制のケアを受けられる点です。
介護者の身体的・精神的な負担が大幅に軽減され、安心感を得られます。
デメリットとしては、費用が高くなりがちな点や、集団生活になる点があげられます。
主な施設の種類は以下の通りです。
- 特別養護老人ホーム(特養):費用が安く、終身利用できる公的施設。入居待ちが多い。
- 介護老人保健施設(老健):リハビリを目的とした施設で、在宅復帰を目指す。
- 有料老人ホーム:多様なサービスや設備が充実。費用やサービス内容で種類が豊富。
- 認知症対応型グループホーム:認知症の方向けの小規模な生活の場。当社が運営する認知症対応型グループホーム「愛の家」もこのひとつ。
これら12種類以上ある介護施設の詳細な選び方やメリット・デメリットを知ることで、最適な選択が可能になるでしょう。
当社では、年1回「認知症ケア実践・研究報告会」を開催し、全国から350事業所が参加して実践事例を共有しています。
ここでは、施設介護でも個別性と文化的配慮を両立できることが示されています。
選び方のポイント
後悔しないためには、以下のポイントをふまえて総合的に検討することが重要です。
どちらか一方に決めるのではなく、状況に応じて在宅と施設を組み合わせるという選択肢もあります。
| 検討ポイント | 在宅介護 | 施設介護 |
|---|---|---|
| 本人の希望 | 強く優先される | 本人の希望と施設の雰囲気を合わせる |
| 心身の状態 | 容態が安定している場合 | 専門的な医療・介護が必要な場合 |
| 家族の負担 | 負担が大きい | 負担が軽減される |
| 費用 | 安く抑えられる | 高くなる傾向 |
ご本人、ご家族、そしてケアマネジャーとよく話し合い、最適な選択をすることが大切です。
介護にかかる費用と自己負担を軽くする「お金の知識」
介護の不安の多くは「お金」に関することかもしれません。
ここでは、介護にかかる費用の目安と、自己負担を軽くするための重要な制度について解説します。
事前に知っておくことで、経済的な見通しを立てやすくなります。
在宅と施設、月々にかかる費用のリアルな目安
生命保険文化センターの2021年度調査によると、介護にかかる費用は、一時的な費用(住宅改修など)が平均74万円、月々の費用が平均8.3万円となっています。
在宅介護と施設介護では、費用に大きな差があります。
| 介護の場所 | 月額費用の目安 | 内訳 |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 5万円前後 | 介護サービス自己負担額、おむつ代など |
| 施設介護 | 10万~30万円以上 | 介護サービス自己負担額、居住費、食費、その他生活費 |
施設介護では居住費や食費がかかるため、在宅介護よりも費用は高くなる傾向があります。
自己負担は原則1割(所得に応じて2~3割)
介護保険サービスを利用した場合、かかった費用の自己負担額は原則1割です。
ただし、現役並みの所得がある場合は2割または3割となります。
ご自身の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。
しっかり活用したい負担軽減制度
介護にかかる費用は高額になることもありますが、負担を軽くする制度も用意されています。
まずは介護費用全体の目安や補助制度について理解を深め、特に利用機会の多い高額介護サービス費の仕組みと費用軽減の方法はしっかり確認しておきましょう。
主な制度は以下の通りです。
- 高額介護サービス費:自己負担額が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。
- 特定入所者介護サービス費:低所得者の施設利用を助成する制度。
- 医療費控除:所得税から控除を受けることが可能。
健達ショップで販売している書籍「認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣」や西尾正輝教授監修の「ノドトレ」も、科学的根拠に基づいた予防的アプローチを通じて、将来的な介護費用の軽減に寄与する可能性があります。
これからの介護を見据える「介護の現状と未来」
日本の介護は、これからさらに大きな転換期を迎えます。
2025年問題や2040年問題といった社会全体の課題として捉えることで、個人の不安も少し軽くなるかもしれません。
ここでは、介護の現状と、未来に向けた希望をお伝えします。
今、介護が重要となっている理由
日本では、少子高齢化が進み、介護を必要とする高齢者が増え続けると予測されています。
これは、介護が一部の家庭の問題ではなく、誰もが関わる可能性のある社会全体の課題であることを意味します。
| 指標 | データ |
|---|---|
| 高齢化率 | 29.1%(2023年) |
| 要介護認定者数 | 約694万人(2022年度) |
| 介護職員の必要数 | 2040年度に約272万人が必要と推計 |
このような状況から、国や地域、そして私たち一人ひとりが介護について考え、備えることの重要性が増しています。
介護の未来を支えるテクノロジー
介護人材が不足する中、テクノロジーの活用が注目されています。
テクノロジーは、介護の質を高め、介護者の負担を軽減する大きな可能性を秘めています。
- 介護ロボット:見守りや移乗介助などの負担を軽減する
- ICT:介護記録の共有や情報管理を効率化する
- センサー:転倒リスクを検知し、安全性を高める
健達ねっとを運営するMCSは、慶應義塾大学との共同研究を通じて、科学的介護情報システムの活用と職場環境改善の研究を推進しています。
海外の介護事情については、世界の介護を見てきた介護士の体験談が参考になります。
地域全体で支え合う「地域包括ケアシステム」とは
住み慣れた地域で、その人らしく最期まで暮らせるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体となって支え合う仕組みです。
これは、介護が家庭や施設内だけで完結するものではなく、地域コミュニティ全体で支えていくという考え方に基づいています。
MCSでは、以下のような活動を通じて、地域との連携を積極的に推進しています。
- 浦和レッズとのオフィシャルパートナーシップ
- 三井住友銀行との連携セミナー
- こども食堂の運営
これらの取り組みは、介護を特別なものではなく、地域コミュニティの一部として自然に受け入れられる社会作りに貢献しています。(参考:社会貢献活動)
スポンサーリンク
介護についてよくある疑問
介護とは一言で簡単にいうと何?
介護を一言でいうと、「自立を支援するパートナーシップ」です。
それは、できないことを補うだけでなく、できることを引き出し、その人らしい生活を一緒に築いていく行為といえます。
親の介護、何歳から考えるべき?
介護が必要になる時期は人によって異なりますが、一般的に70代後半から80代にかけては要注意です。
もしもに備え、遅くとも60歳前後から、親や家族の将来について話し合い、介護に関する正しい知識を少しずつ身につけておくことをオススメします。
健達ねっとショップで販売している書籍「認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣」や「高齢者のからだ図鑑」も、予防的な観点からオススメです。
認知症の親への接し方で一番大切なことは?
認知症の方への接し方で最も大切なのは「ご本人の感情に寄り添うこと」です。
認知症の進行により、ご本人の「不確かさ」からくる不安や混乱が大きくなります。
その感情を否定せず、「辛いよね」「大丈夫ですよ」と共感することが信頼関係を築く上で最も重要です。
より具体的な認知症の方への対応の仕方や家族のケアについては、専門的な知識を参考にするのがオススメです。
まずは認知症ケアで何が大切かを知ることから始めてみましょう。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、介護の基本的な定義から、介護保険制度、費用、そして向き合い方まで幅広く解説してきました。
介護とは、単なる「お世話」ではなく、ご本人の「自立」と「尊厳」を守り、その人らしい生活を支えるパートナーシップです。
それは、決して一人で抱え込むものではありません。
もし今、あなたが介護に不安を感じているのであれば、まずは「地域包括支援センター」に相談することから始めてみてください。
それが、あなたと大切な人の未来を守る、具体的な最初の一歩となります。
介護保険を上手に利用し、介護者の負担を軽減するコツを実践しながら、家族が感じるストレスの原因と改善策についても理解を深めていくことが、無理なく介護を続けるための鍵となります。