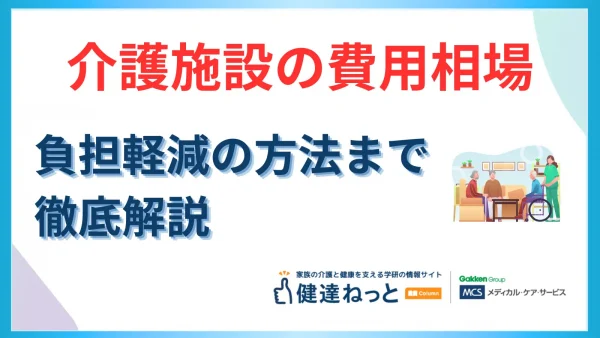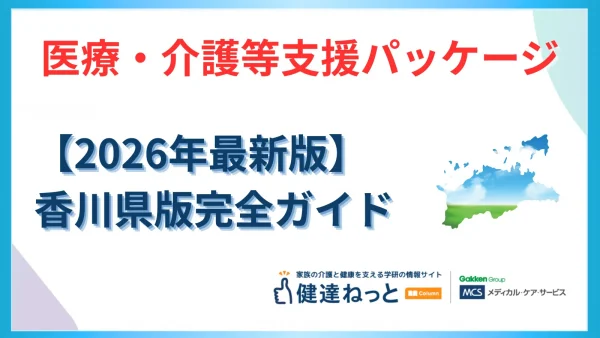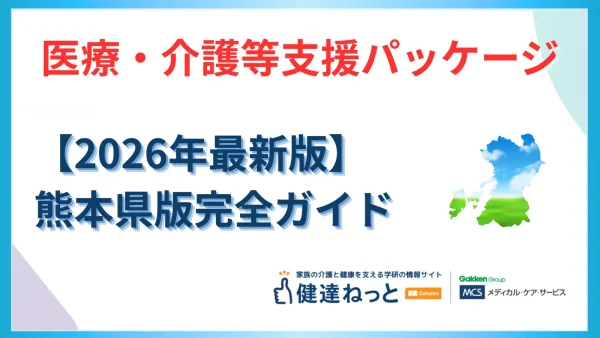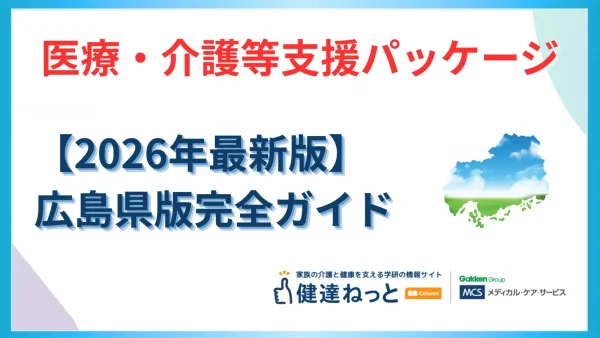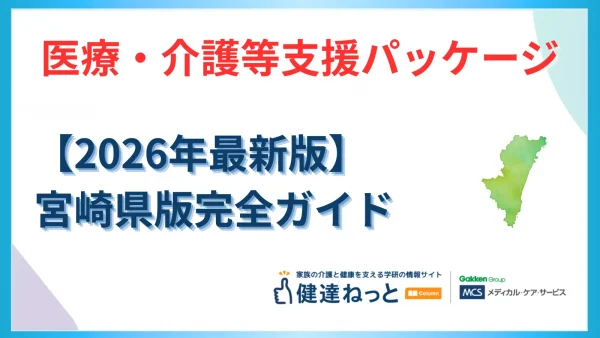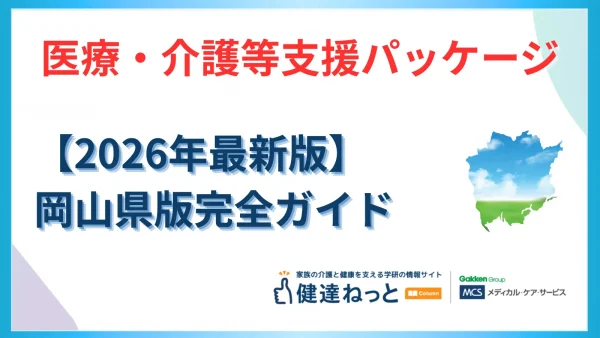「親の介護、そろそろ考えないと…」
そう思った時、多くの方が最初に直面するのが「お金」の問題ではないでしょうか。
- 介護施設って、結局いくらかかるの?
- 月々の支払いは、年金だけで足りるのだろうか…
- 何から調べて、どうやって施設を選べばいいのか分からない
このような漠然とした費用への不安、よく分かります。
しかし、ご安心ください。
この記事を読めば、複雑に見える介護施設の費用構造がすっきりと整理でき、ご自身の状況に合わせた具体的な選択肢を見つけられます。
この記事では、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 介護施設の費用は「初期費用」と「月額費用」の2つが基本
- 費用の安い「公的施設」からサービス充実の「民間施設」まで選択肢は様々
- 費用負担を大幅に軽くする公的な制度とその活用法
- 年金だけで足りない場合の具体的な資金計画の立て方
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が「我が家の場合、まずこれをやってみよう」という具体的な計画に変わっているはずです。
安心して親御さんのための施設選びを進める、その第一歩をここから踏み出しましょう。
スポンサーリンク
【大前提】介護施設にかかる費用は2つ
介護施設の費用を考える時、まず押さえるべき基本は、費用が大きく分けて「初期費用」と「月額費用」の2種類で構成されていることです。
この2つの費用の意味を理解することが、施設選びのスタートラインに立つことにつながります。
初期費用(入居一時金)
初期費用とは、施設に入居する際に支払うまとまった費用のことです。
一般的に「入居一時金」とよばれ、施設の設備やサービスを終身にわたって利用する権利を得るための費用、いわゆる「家賃の前払い」のような性格を持っています。
この入居一時金は、施設によって金額が大きく異なり、0円の施設から数千万円にのぼる施設まで様々です。
支払い方式にもいくつかの種類があります。
| 支払い方式 | 特徴 |
|---|---|
| 全額前払い方式 | 全額を初期費用として支払う。月々の家賃負担はない |
| 一部前払い方式 | 一部を初期費用、残りを月々の家賃として支払う |
| 月払い方式 | 初期費用は0円で、全額を月々の家賃として支払う |
入居一時金は高額に感じられますが、その分月々の家賃負担が軽くなるという側面も持ち合わせています。
月額費用
月額費用は、その名の通り毎月継続して支払う費用です。
これには、介護サービス費用の自己負担分に加え、家賃や食費、水道光熱費といった生活に必要なコストが含まれます。
月額費用は、施設のサービス内容や居室のタイプ、そして入居される方の要介護度によって変動するのが一般的です。
パンフレットに記載されている金額だけでなく、その内訳がどうなっているのかをしっかりと確認することが、後々の資金計画を立てる上で非常に重要になります。
どのような費用が含まれているのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
スポンサーリンク
介護施設の月額費用の5大内訳を大解剖
月額費用の中身を理解することは、施設の費用を比較検討する上で不可欠です。
ここでは、月額費用を構成する主な5つの内訳をひとつずつ詳しく解説します。
何に、どのくらい費用がかかるのかを把握しましょう。
介護サービス費(介護保険自己負担分)
介護サービス費は、施設で提供される専門的なケア(食事や入浴の介助、機能訓練など)に対する費用です。
この費用の大部分は介護保険から給付されますが、利用者はその一部を自己負担として支払います。
介護保険の自己負担割合は、所得によって1〜3割と異なります。
介護保険の負担割合の詳細な判定基準を確認して、ご自身の負担割合を把握しましょう。
>参考:介護保険の負担割合について:介護保険の解説(厚生労働省)
自己負担額は、要介護度が高くなるほど、つまりより手厚い介護が必要になるほど高くなる仕組みです。
| 要介護度 | 自己負担額(1割負担の場合の目安) |
|---|---|
| 要介護1 | 約16,750円 |
| 要介護3 | 約27,050円 |
| 要介護5 | 約36,220円 |
この費用は国が定める基準に基づいているため、どの施設でも大きな差はありません。
居住費(家賃)
居住費は、施設の居室を利用するための費用で、一般の賃貸住宅における家賃にあたります。
施設の立地や設備のグレード、そして居室のタイプによって金額が大きく変動するのが特徴です。
例えば、プライバシーが確保された個室は費用が高くなる傾向にあり、複数の入居者でひとつの部屋を共有する「多床室」は比較的安価に設定されています。
月額費用を抑えたい場合は、この居住費が大きな比較ポイントになるわけです。
なお、所得の低い方には、この居住費の負担を軽減する制度が用意されています。
食費
食費は、施設で提供される1日3食の食事にかかる費用です。
多くの施設では、栄養バランスが考慮されたメニューが提供されており、入居者の健康状態に合わせた食事形態(きざみ食やミキサー食など)にも対応しています。
費用は、1日単位や1ヶ月単位で設定されているのが一般的です。
1日あたり1,400円程度、月額で43,000円程度がひとつの目安といえるでしょう。
この食費も、所得に応じて負担を軽減する制度の対象となります。
管理費・共益費
管理費・共益費は、施設の建物や設備を維持管理するための費用や、共用スペース(食堂や談話室など)の水道光熱費、事務スタッフの人件費などに充てられます。
入居者全員が快適で安全な生活を送るために必要なコストといえます。
費用は施設によって異なりますが、月額数万円程度が相場です。
どの範囲までが管理費に含まれるのかは施設ごとに規定が違うため、見学時などにしっかりと確認しておくことが大切です。
その他の費用
上記の4つの費用以外に、日常生活を送る上で必要となる個人的な費用は、原則として全額自己負担となります。
これは介護保険の適用外の費用で、「日常生活費」や「雑費」ともよばれます。
パンフレットに記載の月額費用には含まれていないことが多いため、注意が必要です。
具体的な項目は以下の通りです。
- おむつや歯ブラシなどの消耗品代
- 理美容代
- クリーニング代
- レクリエーションやイベントの参加費
- 外部の医療機関を受診した際の医療費や交通費
これらの費用が月々どのくらいかかるのか、事前にシミュレーションしておくことで、入居後の資金計画に余裕が生まれます。
日本では少子高齢化が社会問題となっており、高齢者の割合が年々増加しています。そんな中、認知症の高齢者を専門にケアする施設も増えてきました。その施設の一つが「グループホーム」です。今回の記事では、「家族が認知症になって自宅で介護を続[…]
費用で考えた介護施設の選び方!4つの選択肢
介護施設の費用は、施設の種類によって大きく異なります。
ここでは、予算や求めるサービスに応じて、どのような選択肢があるのかを4つのルートに分けて解説します。
ご自身の状況に最も合うルートを見つけるための参考にしてみてください。
公的施設と民間施設の詳しい比較については、「有料老人ホームと特養の違い」や「特養と老健の比較」をご参照ください。
費用を最優先するなら「公的施設」
費用をできる限り抑えたい場合に、まず検討すべきなのが「公的施設」です。
国や地方自治体、社会福祉法人が運営しているため、民間の施設に比べて費用が安価に設定されています。
| 公的施設のメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | ・費用が安い ・所得に応じた負担軽減制度がある ・倒産のリスクが低い |
| デメリット | ・入居待機者が多く、すぐに入れない可能性がある ・個室が少なく、多床室が中心の場合が多い |
特別養護老人ホーム(特養)などが代表的な施設です。
ただし、費用の安さから人気が高く、入居待ちの期間が長くなる傾向にある点は理解しておく必要があります。
特別養護老人ホームは費用の安さが最大の魅力です。
特養の入居条件や費用の詳細について詳しく確認してみましょう。
費用と自由度のバランス型「軽めの民間施設」
「公的施設ほど費用は抑えられなくても、ある程度の自由度は欲しい」という方には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホームが選択肢となります。
これらの施設は、生活支援サービスは提供されますが、介護サービスは外部の事業者と個別に契約する形式が一般的です。
そのため、自分に必要なサービスだけを選んで組み合わせることで、費用をコントロールしやすいのが特徴です。
まだ自立した生活が送れるものの、少しだけサポートが欲しいという方に適した選択といえるでしょう。
手厚いサービスを求めるなら「介護付き有料老人ホーム」
費用は高めでも、24時間体制の介護や充実した設備、多彩なレクリエーションなど、手厚いサービスと安心感を求める方には「介護付き有料老人ホーム」が適しています。
民間企業が運営しており、ホテルライクな施設からアットホームな施設まで、選択肢が非常に豊富なのが魅力です。
単に費用だけで判断するのではなく、どのようなケアが受けられるかという「質」も重要な判断基準です。
例えば、メディカル・ケア・サービス株式会社が運営する施設では、科学的根拠に基づく「MCS版自立支援ケア」を実践。
その結果、236事業所3,771名を対象とした調査で、約85%にあたる3,194名の方に認知症の周辺症状や身体機能の改善が確認されています。
>【参考】効果検証について:MCS版自立支援ケアの成果
質の高いケアは、長期的に見て医療費の軽減や生活の質の向上につながる可能性があり、費用以上の価値をもたらすといえるでしょう。
認知症ケアに特化するなら「グループホーム」
認知症の症状がある方の場合は、「グループホーム」が専門的な選択肢となります。
5〜9人の少人数ユニットで、スタッフのサポートを受けながら共同生活を送るのが特徴です。
家庭的な雰囲気の中で、認知症の方が落ち着いて暮らせるよう配慮されています。
単に料金を比較するだけでは見えない価値があるのも、このタイプの特徴です。
実際の事例では、職員とのよい関わりによって築かれた安心感や信頼関係が、認知症の方の穏やかな生活の支えとなっています。
このような個別性を重視したケアが、ご本人とご家族の長期的な安心につながります。
認知症の方専用の施設であるグループホームでは、専門的な認知症ケアが受けられます。
グループホームの費用相場も併せてご確認ください。
健達ねっとが運営する検索サイトでも各種介護施設を検索いただけます。
ぜひご活用ください。
【施設の種類別】介護施設の費用相場
ここでは、施設の種類ごとに、2025年現在の費用相場を具体的に見ていきましょう。
公的施設と民間施設では、費用体系が大きく異なります。
それぞれの特徴を把握し、施設選びの参考にしてみてください。
特別養護老人ホーム(特養)
「終の棲家」ともよばれる公的施設です。
原則として要介護3以上の方が入居対象となります。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 約9万円~14万円 |
※参考データ
厚生労働省によると、要介護5の方が多床室を利用した場合の1ヶ月の自己負担の目安は約106,930円(約10.7万円)、ユニット型個室では約143,980円(約14.4万円)となっています。(厚生労働省:介護保険の解説)
入居一時金が不要で月額費用も比較的安価なため非常に人気が高いですが、その分、入居待機者が多いのが現状です。
介護老人保健施設(老健)
在宅復帰を目指すためのリハビリテーションを中心としたケアを提供する施設です。
入居期間は原則として3〜6ヶ月とされています。
老健では医療的ケアとリハビリテーションが充実しています。
老健の詳細な費用内訳と負担軽減制度についてご確認ください。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 約8万円~15万円 |
医療ケアが充実しており、病院から退院した直後の方などが利用するケースが多いです。
介護医療院
長期的な医療と介護の両方が必要な高齢者を受け入れる施設です。
看取りまで対応する「終の棲家」としての機能も担います。
長期的な医療ケアが必要な方には介護医療院が適しています。
介護医療院の特徴と入所条件を詳しく確認しましょう。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 約10万~20万円 |
医師や看護師が常駐しており、医療依存度の高い方でも安心して生活できる体制が整っています。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
身寄りがなく、自立して生活することに不安がある60歳以上の方などが対象の施設です。
所得に応じて費用負担が変動するのが大きな特徴です。
ケアハウスは所得に応じた費用負担で利用できる公的施設です。
ケアハウスの詳細な費用計算方法をご確認ください。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円~数十万円 |
| 月額費用 | 約6万円~17万円 |
自立した方向けの「一般型」と、要介護者向けの「介護型」の2種類があります。
介護付き有料老人ホーム
民間企業が運営する、介護サービスが一体となった施設です。
24時間体制の介護や、ホテルライクなサービスなど、施設によって多様な特色があります。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円~数千万円 |
| 月額費用 | 約15万円~40万円 |
※参考データ
厚生労働省の調査によると、平均月額費用は施設によって大きく異なりますが、介護・医療サービスの自己負担分を含まない基本的な費用として上記の範囲が一般的です。(厚生労働省:有料老人ホームの現状と課題について)
費用幅が非常に広く、提供されるサービスの質や設備によって料金が大きく異なります。
住宅型有料老人ホーム
食事の提供や見守りなどの生活支援サービスが中心の施設です。
介護が必要になった場合は、外部の介護サービス事業者と個別に契約します。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 中央値18.2万円 |
| 月額費用 | 中央値14.1万円 |
必要なサービスを自分で選べるため、費用を調整しやすいのがメリットです。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
高齢者向けの賃貸住宅で、「サ高住」と略されます。
安否確認と生活相談サービスが義務付けられており、自由度の高い暮らしが可能です。
自立度の高い方には、賃貸住宅の性格を持つサ高住が適しています。
サ高住のサービス内容と費用体系について詳しく解説しています。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円~数十万円(敷金) |
| 月額費用 | 約10万~30万円 |
介護サービスは、住宅型有料老人ホームと同様に外部事業者と契約します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方を専門に受け入れる、地域密着型の施設です。
少人数のユニットで共同生活を送りながら、専門的なケアを受けられます。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 0円~数十万円 |
| 月額費用 | 約15万円~20万円 |
家庭的な雰囲気の中で、他の入居者やスタッフと交流しながら穏やかに過ごせる環境が特徴です。
介護施設の費用負担を軽くする7つの方法
介護施設の費用は決して安くはありませんが、負担を軽減するための様々な公的制度が用意されています。
これらの制度をうまく活用することで、実際の自己負担額を大きく抑えることが可能です。
知っているのと知らないのとでは大違いの7つの方法を紹介します。
介護保険制度の基本的な仕組みについては、「介護保険制度の詳細解説」で詳しく説明しています。
高額介護サービス費制度
1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
例えば、住民税非課税世帯の方であれば、月々の自己負担額の上限は15,000円または24,600円に設定されています。
| 所得段階 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
| 課税所得380万円~690万円未満 | 93,000円 |
| 住民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円 |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
| 世帯全員が住民税非課税(所得等の条件あり) | 15,000円 |
| 生活保護受給者 | 15,000円 |
※参考:制度の詳細について(横浜市:介護サービスの利用者負担軽減について)
この制度は自動的に適用されるわけではなく、市区町村への申請が必要です。
月々の介護サービス費が上限を超えた場合に払い戻しを受けられます。
高額介護サービス費制度の詳細な利用方法をご確認ください。
特定入所介護サービス費(補足給付)
所得や資産が一定以下の人を対象に、介護保険施設に入所した際の食費と居住費の負担を軽減する制度です。
対象となるのは、原則として世帯全員が住民税非課税の方です。
この制度を利用すると、所得段階に応じた負担限度額までを自己負担し、超えた分は介護保険から給付されます。
最も所得の低い第1段階の方の場合、食費と居住費を合わせて月額3万円程度の負担で施設を利用できるケースもあります。
※参考:制度の詳細について(厚生労働省:介護保険の解説)
高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、著しく高額になった場合に、上限額を超えた分が支給される制度です。
高額介護サービス費制度が月単位であるのに対し、こちらは年単位で計算されます。
医療と介護、両方のサービスを頻繁に利用する方にとっては、大きな助けとなる制度です。
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営する一部の施設で、低所得で特に生計が困難な方を対象に、利用者負担額をさらに軽減する制度です。
介護サービス費の自己負担分や食費、居住費などが対象となり、おおむね4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。
対象となる施設や条件は限られているため、ケアマネージャーや市区町村の窓口で確認が必要です。
医療費控除
介護保険施設で支払った費用の一部は、確定申告の際に医療費控除の対象となり、所得税や住民税が還付される可能性があります。
例えば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設の施設サービス費、食費、居住費の自己負担額の2分の1が控除の対象です。
おむつ代も、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば対象となります。
介護施設の一部費用は医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる介護費用の詳細と高齢者介護サービスの控除対象範囲をご確認ください。
自治体独自の助成・補助金
国が定める制度のほかに、市区町村が独自に介護費用に関する助成や補助金制度を設けている場合があります。
例えば、介護用品の購入費を助成するサービスや、住宅改修費用の補助などが挙げられます。
お住まいの自治体のホームページを確認したり、地域包括支援センターに問い合わせたりしてみましょう。
費用が少しでも安い施設を選ぶ
制度の活用と合わせて、施設選びそのものを工夫することも重要です。
一般的に、都市部よりも郊外の施設の方が、土地代や人件費が安い傾向にあるため、居住費などが低く設定されています。
また、プライバシーを重視した個室よりも、複数の入居者で部屋を共有する「多床室」を選ぶことで、月々の居住費を数万円単位で抑えることが可能です。
ご本人の希望と予算のバランスを考えながら、最適な選択肢を探しましょう。
最大の関門である介護施設の初期費用を乗り越えるには
介護施設の費用を考える上で、月額費用と並んで大きな壁となるのが「初期費用(入居一時金)」です。
ここでは、高額な初期費用をどう乗り越えるか、その具体的な方法について解説します。
入居一時金0円の施設に入る
最も直接的な解決策は、入居一時金が0円の施設を選ぶことです。
近年、入居者の初期負担を軽減するため、「0円プラン」を用意する民間施設が増えています。
まとまった資金を用意するのが難しい場合でも、スムーズに入居の検討を進められるのが最大のメリットといえるでしょう。
ただし、なぜ0円なのか、その仕組みを理解しておく必要があります。
前払いプラン vs 月払いプランの比較
入居一時金は、いわば「家賃の前払い」です。
そのため、入居一時金が0円の「月払いプラン」は、前払いする家賃がない分、毎月の家賃負担がその分だけ上乗せされることになります。
どちらのプランがお得かは、入居期間によって変わってきます。
| 前払いプラン | 月払い(0円)プラン | |
|---|---|---|
| メリット | ・月々の支払いが安い ・長期入居で総額が割安になる | ・初期費用がかからない ・短期入居なら総額が安い |
| デメリット | ・初期に高額な資金が必要 ・早期退去時の返還リスクがある | ・月々の支払いが割高 ・長期入居で総額が高くなる |
一般的に、数年程度の短期的な利用であれば月払いプランが、5年以上の長期的な利用を想定するなら前払いプランの方が、総支払額は安くなる傾向にあります。
結局、どちらがよいか迷ったら
どちらのプランを選ぶべきか迷った時は、「想定される入居期間」と「手元に用意できる資金額」の2つの軸で判断しましょう。
例えば、在宅復帰を目指すリハビリ目的での入所など、入居期間が短くなることが予想される場合は、初期費用のかからない月払いプランが合理的です。
一方で、終身にわたる利用を考え、手元の資金にも余裕がある場合は、前払いプランを選ぶことで月々のキャッシュフローを安定させられます。
どちらが正解というわけではありません。
ご家庭の状況に合わせて、ケアマネージャーなどの専門家とも相談しながら、慎重に判断することが大切です。
年金だけで介護施設費用をまかなうのは可能?
「親の年金だけで、施設の費用を支払い続けることはできるのだろうか」
これは、多くの方が抱く切実な疑問です。
ここでは、年金と施設費用の関係について、現実的な視点から解説します。
年金受給者の方は、年金からの介護保険料天引きの仕組みを理解した上で、低所得者向けの施設選択肢も検討しましょう。
年金受給額の平均と施設の費用を比較
結論からいうと、施設の種類を選べば、年金だけで費用をまかなうことは可能です。
年金受給額の実態
2023年度時点の年金受給額(月額)の平均は以下の通りです。
- 国民年金:約5万7,584円
- 厚生年金(国民年金含む):約14万6,429円
※参考データ:イオンアリアンツ生命:国民年金・厚生年金の平均額
一方、費用が比較的安価な特別養護老人ホーム(特養)の月額費用は、多床室であれば約9万円~10万円程度です。
ここに、所得に応じた負担軽減制度を適用すれば、年金の範囲内で十分に支払えるケースは少なくありません。
ただし、これはあくまで一例であり、多くの場合、年金収入だけでは不足する可能性があることも事実です。
年金だけでは足りない場合の資金調達方法
年金収入だけでは費用が不足する場合、早めに資金計画を立てておくことが重要です。
主な資金調達方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 本人の預貯金を切り崩す
- 生命保険などを解約して現金化する
- 自宅などの不動産を売却する
- 自宅を担保にお金を借りる「リバースモーゲージ」を利用する
- 子どもなど家族が援助する
どの方法が最適かは、ご本人の資産状況やご家族の考え方によって異なります。
後々のトラブルを避けるためにも、早い段階で家族間でしっかりと話し合っておくことが大切です。
スポンサーリンク
費用を考慮した介護施設選びの5ステップ
ここまで介護施設の費用について詳しく解説してきましたが、実際に何から手をつければよいのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、費用を念頭に置いた施設選びを、具体的な5つのステップに分けて紹介します。
この通りに進めれば、迷わずスムーズに検討を進められます。
ステップ1.親(入る本人)の収入と資産を確認する
まず、入居されるご本人の経済状況を正確に把握することから始めます。
これがすべての基本となります。
| 確認すべき項目 | |
|---|---|
| 収入 | ・公的年金の受給額(年金証書やねんきん定期便で確認) ・個人年金や不動産収入など |
| 資産 | ・預貯金の総額 ・有価証券(株、投資信託など) ・生命保険の解約返戻金 ・不動産(自宅など) |
正確な金額を把握することで、月々の支払いに充てられる金額や、初期費用として用意できる金額の目安がつき、具体的な施設選びの基準ができます。
ステップ2.親の要介護度を把握する
次に、ご本人がどのくらいの介護を必要としているのか、そのレベルを客観的に示す「要介護度」を確認します。
要介護度は、市区町村に申請して行われる認定調査によって、要支援1・2、要介護1〜5の7段階で判定されます。
この要介護度によって、入居できる施設の種類や、介護サービス費の自己負担額が決まるのです。
まだ認定を受けていない場合は、速やかに申請手続きを行いましょう。
ステップ3.最適な施設タイプの当たりをつける
ステップ1の予算と、ステップ2の要介護度を元に、ご自身にとって現実的な施設タイプの候補を絞り込みます。
この記事の「費用で考えた介護施設の選び方!4つの選択肢」や「【施設の種類別】介護施設の費用相場」を参考に、予算内で、かつ必要なケアが受けられる施設はどのタイプかを検討します。
この段階で、いくつかの施設タイプに当たりをつけておくと、その後の情報収集が効率的になります。
ステップ4.地域包括支援センターで制度について相談する
候補となる施設タイプがある程度絞れたら、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談に行きましょう。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える公的な相談窓口です。
介護の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士が、利用できる負担軽減制度や、地域の介護施設の具体的な情報について、無料でアドバイスをしてくれます。
専門家の視点から、より良い選択肢を提案してもらえる可能性もあります。
ステップ5.家族で話し合いの場を持つ
ここまでの情報を元に、必ず家族で話し合う時間を設けましょう。
費用を誰がどのように負担するのか、どのような施設が本人にとって最善なのか、全員が納得できる結論を出すことが非常に重要です。
ご本人の意向を最大限尊重しつつ、経済的な負担や将来の見通しについて、オープンに話し合うことが、後々のトラブルを防ぎ、家族全員が安心して介護と向き合うための鍵となります。
スポンサーリンク
介護施設費用を払えなくなった時の3つの対処法
万が一、入居後に経済状況が変化し、施設の費用が払えなくなってしまったらどうすればよいのでしょうか。
事前に知っておくことで、いざという時に冷静に対応できます。
費用負担が困難になった場合の具体的な対処法については、介護費用が払えない場合の詳細な解決策をご参照ください。
まずは施設・ケアマネージャーに相談する
支払いが困難になったからといって、すぐに退去を求められるわけではありません。
まずは正直に、施設の相談員や担当のケアマネージャーに現状を相談することが最も重要です。
専門家が、支払いの猶予や分割払いの相談に乗ってくれたり、利用できる負担軽減制度を一緒に探してくれたりするなど、何らかの解決策を提示してくれるはずです。
一人で抱え込まず、早めに助けを求める勇気を持ちましょう。
負担の少ない施設への転居を検討する
相談の結果、どうしても現在の施設での支払いを続けるのが難しいと判断した場合は、より費用の安い施設への転居も選択肢のひとつです。
例えば、民間の有料老人ホームから、費用負担の少ない特別養護老人ホーム(特養)に移るケースなどが考えられます。
転居には手間や費用がかかりますが、長期的な視点で見れば、経済的な安定を取り戻すための有効な手段といえます。
生活保護の受給を申請する
あらゆる手段を尽くしてもなお、生活が困窮する場合は、生活保護の申請を検討します。
生活保護が受給できれば、介護サービス費や施設費用の自己負担分が「介護扶助」として支給されるため、費用負担なく施設での生活を継続できます。
生活保護を受給しながら入居できる施設は限られますが、生命と健康を守るための最後のセーフティネットとして、このような制度があることを知っておきましょう。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、介護施設の費用について、その内訳から負担を軽くする方法、そして具体的な選び方のステップまでを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
介護施設の費用は、「初期費用」と「月額費用」の2つで成り立っています。
そして、その費用は「公的施設」か「民間施設」かで大きく異なり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
高額に感じる費用も、「高額介護サービス費制度」などの公的な負担軽減制度をフル活用することで、実際の負担を大きく減らすことが可能です。
大切なのは、費用に対する漠然とした不安を放置せず、この記事で紹介したような知識を元に、ご自身の状況を整理し、具体的な計画へと落とし込んでいくことです。
まずは、親御さんの収入や資産を確認する「ステップ1」から始めてみませんか。
その小さな一歩が、ご本人にとってもご家族にとっても、最適な施設選びと、安心できる未来につながるはずです。