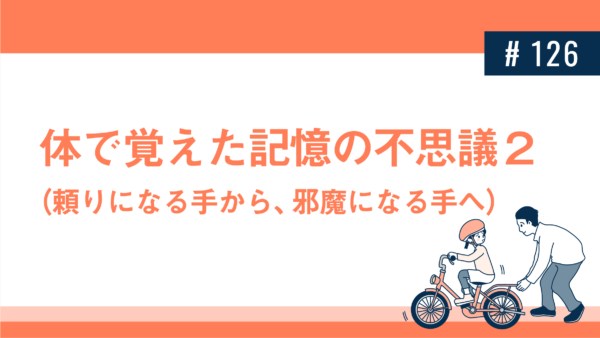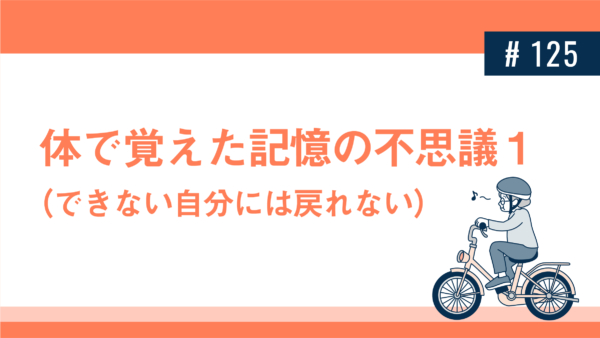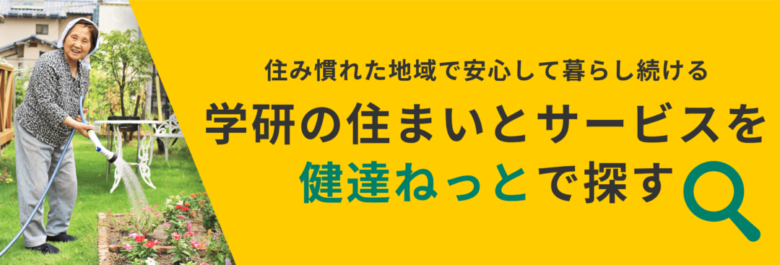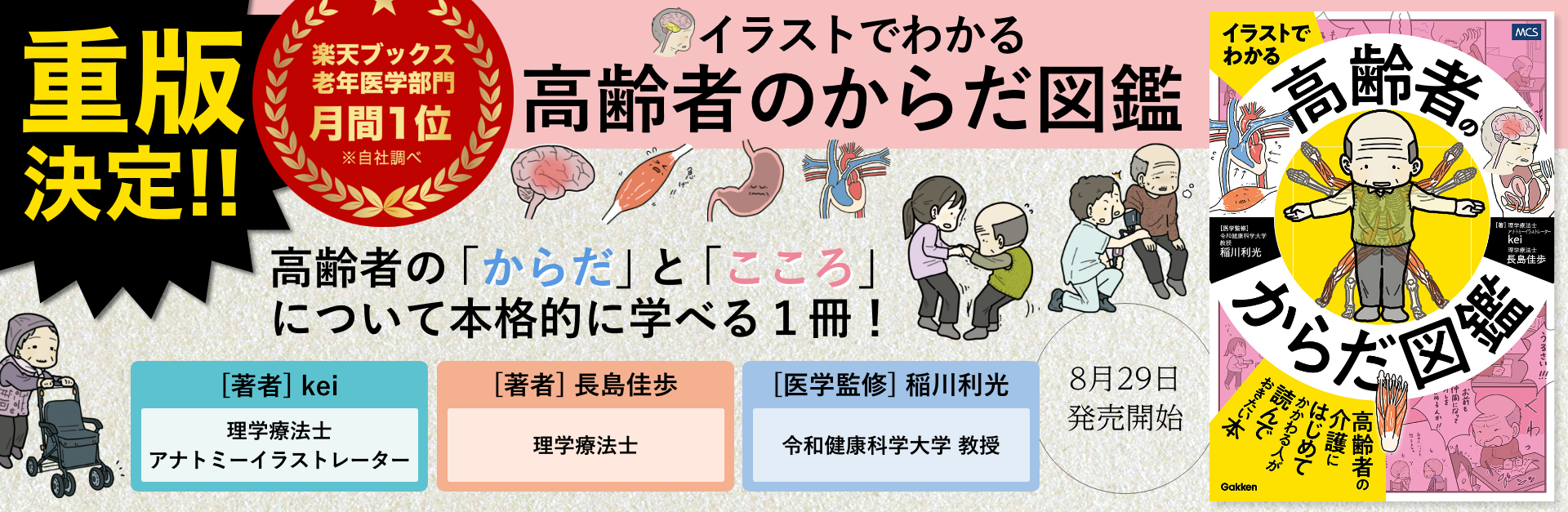呼び名ではなく「呼ばれ名」
研修会等でよく質問されることのひとつが「利用者・入居者をどのように呼ばせていただくことが良いと考えていますか」で、いわゆる「呼び名」についてです。
昨年、ある研修会でも質問されたことを思えば根深い課題になっていると思いますので、改めてここで僕の考えをのべさせていただきます。
僕がこの仕事に就いた1987年当時、僕が勤めることになった法人では「認知症という状態にある方への支援」をオーストラリアから学んでいて、オーストラリアの話を聞く機会がありました。内容のほとんどのことは憶えていないのですが、唯一憶えていることに「利用者・入居者のことをどう呼ぶか」がありました。
今どうかは「?」ですし、それがオーストラリアでは一般的なことかどうかも記憶に残っていませんので、ある所だけの実践話なのかもしれませんが、オーストラリアでは利用者・入居者のことを「どう呼ぶか」について、「本人や家族に聞いてわからなければ、過去その方が周りからどう呼ばれていたかを調査して決定するほど大事にしている」ということを聞きました。
かつて住んでいたところ、働いていたところへ聞き取り調査に行って、「その方のことをどう呼んでいたか=その方がどう呼ばれていたか」を徹底的に調べるというんです。
そのことが本当かどうかを僕に検証できるわけではないので疑問をもつことなく且つ「なるほど」と思いましたね。38年も前の話です。
というのも、この仕事の中で最初に「呼び名」については「氏にさんづけ」と上司から言われましたが、どうしても腑に落ちていなかったんです。
当時32歳の僕の経験からだけで疑問を感じて申し訳なかったのですが、僕がそれまでにかかわった人たちはスタート時点「氏にさんづけ」が多かったとしても、時間の経過とともに関係性の変化も含めて、結局自分が「どう呼ばれたいか」で着地しているのに、高齢者介護の世界では「本人に、どう呼んで欲しいかを聞かないんだ。なんでやろ」と疑問を抱いていたからです。
ましてや認知症のことを教えてもらうにつれ、記憶が逆進する(過去にさかのぼる)と言うんだったら尚の事どう呼ばれていたかは大事じゃないかと思っていたからです。
世の中を見渡すと「ししょう(師匠)」「とうりょう(棟梁)」「おかみさん」「マスター」「しゃちょう(社長)」「センセイ(先生)」など、氏名以外で日常的に呼ばれている人は多々いますし、それに不快感や違和感がなければ続くし、あれば本人から修正をお願いするか圧をかけることでしょう。逆に氏名で呼ばれることに違和感を抱く方もいますからね。
特に認知症という状態にある方にとって長年にわたって「馴染んだ呼ばれ名」であればあるほど違和感をもちにくいし応答もしやいでしょうし、それを飛び越して、かかわる側が「呼び名」を決めては、逆に違和感・他人感・距離感を抱かせかねません。
僕も同窓生からなら相手の性別にかかわらず当時のまま「和田くん」と呼ばれて違和感はないですが、単純に同級生という関係だけで呼ばれたら違和感をもちますし逆に同窓生から「和田さん」と呼ばれたら「たのむから、やめてくれ!」って叫んじゃいます。
だから、オーストラリアにおける「呼ばれていた名=呼ばれ名を大事にする」というのはしっくりきましたし、1990年代にデイサービスの責任者やグループホームの施設長を委ねられた時は「どう呼んでもらいたいですか」と本人に聞きましたし、家族に「どう呼ばせていただくのが本人にピッタリきますかね」と相談して「呼ばれ名」を決めてきました。
ちゃんづけ
グループホーム入居面接時、〇〇みつこさんに「どう呼ばれたいですか」と本人に聞くと「そうね、ずっとミッチャンと呼ばれてきたからミッチャンでお願いしようかしら」と言われ、家族からも「それでお願いします」と言われたので、呼ばれ名は「ミッチャン」としました。
あるとき見学に来られた方から「ここはおかしい。入居者のことをちゃんづけで呼んでいる」とご指摘を受けましたので「皆さんは、どう呼んでいるんでしょうか」と逆に質問をすると「もちろん、氏にさんづけですよ」と言われたので「そうですか、皆さんが呼びたい名で呼んでいるんですね。僕らは、本人や家族が呼んでもらいたい名で呼んでいるんですよ。主体は誰なんでしょうかね」と投げ返しました。
また、行政指導で「ちゃんづけ呼び」に対してご指摘を受けたこともありましたが、行政マンに説明すると「そういうことだったんですね」とすぐに理解していただき、その上で介護保険制度施行後は「介護計画書にその旨を記載しておいてください」と助言をいただきました。つまり「ちゃんづけも理由が明確ならOK」というお墨付きを得たということです。
同様に◇◇まさこさんは「まさこと呼んでください」と言われたので、「◇◇さん、さすがに呼び捨てにはできないのでマサコさんで良いでしょうか」と訊ねると「仕方ありませんね、さんをつけていただけるほどの者じゃありませんが、いいですよ」と言ってくださったので、続けて「時にはマサコと呼び捨てにしてもいいですか」と突っ込むと「いいですよ」とニコニコ。
ご家族に確認すると「本人がいいと言っているのでいいですよ」と言ってくださいましたから、グループホームにおける群れのボスである僕だけに限定して、時と場合を見計らって「マサコーッ」って呼ばせていただいていました。※群れのボスの話は改めて。
変化する呼ばれ名
氏名等は「仮」で書かせていただきますしチームで取り組んだことですが、和田ガンさん(仮名)は入居開始前面接時に本人の意思確認が難しかったので「氏にさんづけお願いします」と家族の意向に沿って呼ばせていただいていましたが、時間の経過とともに「和田さん」では応えてくれなくなりました。
そこで、家族と改めて面談して、過去の職歴や家族の記憶にある友人知人から呼ばれていた名を探りましたがどれも決め手に欠けました。
そこで、いただいた情報を基に僕らに考え付く「呼ばれ名」を試してみました。
まずは「ガンさん」「ガンちゃん」と呼ばせていただき、職業から想定して「師匠」「棟梁」と試みました。大変失礼なことなので試すのはボスであるリーダーだけと決めて挑みましたがどれも応答が鈍く決め手に欠けました。そこで、いよいよ崩しに崩して「おとっつぁん」と呼んでみると「おーッ」と応答してくださいました。
一度決めた呼ばれ名も、時間の経過(脳の病気の進行)とともに変化するということですが、「その変化も介護計画に記載、説明と同意を得るようにしてください」と言ってくれた行政マンはステキだなぁと思えましたね。
入居者の側から物事を考える
ある方から、「著名な〇〇さんとお話ししたら和田さんの話になったのだけれど、和田さんは入居者にセンセイと呼ばせていることが納得できないと言われていました」と聞きました。
グループホームの入居者たちは僕の呼び名を「おにいさん」「あなた」「せんせい」「せんせいさま」といった具合にその時々によって変えていましたが、それは「その時々の場面で本人たちが思った呼び名」を使っていたということで、それを僕からその度に否定したり修正する必要性がなければ受け止めていました。つまり、僕が入居者に呼ばせている呼び名ではなく、入居者自身が決めた呼び名への受け止めです。
「そうかぁ、今の僕はこの方にとってそう映っているんだ」
そう考えること自体がとても有意義で、自分の振る舞いをそれに合わせていましたが、それと同時に「なぜ、僕をセンセイと呼ぶか」「なぜ、呼び名を変えるのか」まで考察していました。
それは改めて書かせていただくとして、いずれにしても僕をどう呼ぶかを決めるのは入居者自身・入居者たちであり、それが「主体者たる姿」であり、そこから物事を考えるということです。
もうひとつは、職員同士の呼び名も固定化していました。
その理由は、僕らがどう呼び合うかを入居者は四六時中聞いており、能力のある入居者なら必ずや真似るだろうという想定からで、職員の呼び名を固定化することで「目に映る〇は〇さん」と入居者が記憶化しやすいようにするためです。だから家族にも同様に職員のことを呼んでいただいていました。
合わせて、利用者・入居者の呼ばれ名を決めることで、職員が入居者個々人に抱く感情の表出に制限を加える訓練にもなりますからね。それは次回に書かせていただきます。

僕のボスから「和田さん、魚釣りで一番大事なことは釣道具を海の中に垂らしているかどうかです」と教わりましたが、何でも同じですね。その構えがないところに成果は出ないってことでしょうか。
編集室のつぶやき~本稿を読んで思うこと
「呼び名から関係性が作られる」といった考え方と、「関係性があって呼び名は成立する」という考え方で、どうあるべきか検討しましたね。
私は後者の考え方で、関係性を作る過程なく親しい呼び名を使うことで会話や関わりに乱れが起きることに懸念があり、関係性が浅い間は「氏にさん付け」で統一、関係性が変わってきた後に「呼び名も変わる」ことにしていました。
「呼ばれ名」という視点から検討をすると前者で進めて懸念したことが起きないことに注力したんだろうかと当時を思い返しています。









.webp)