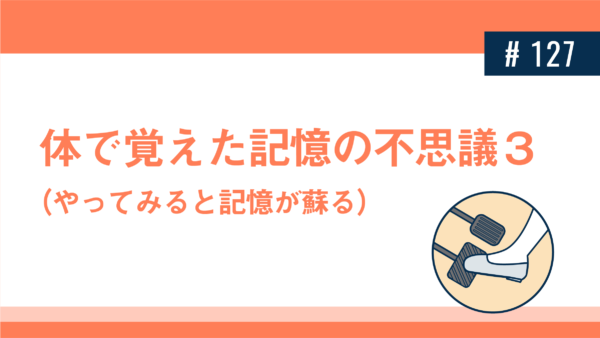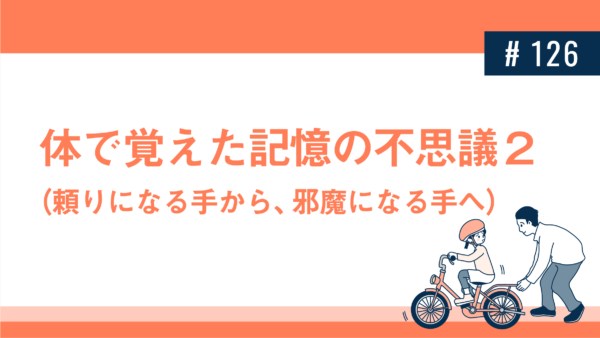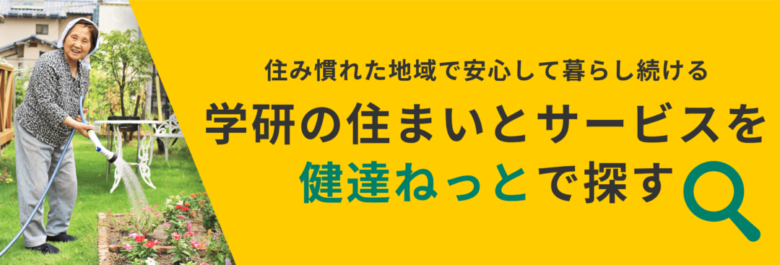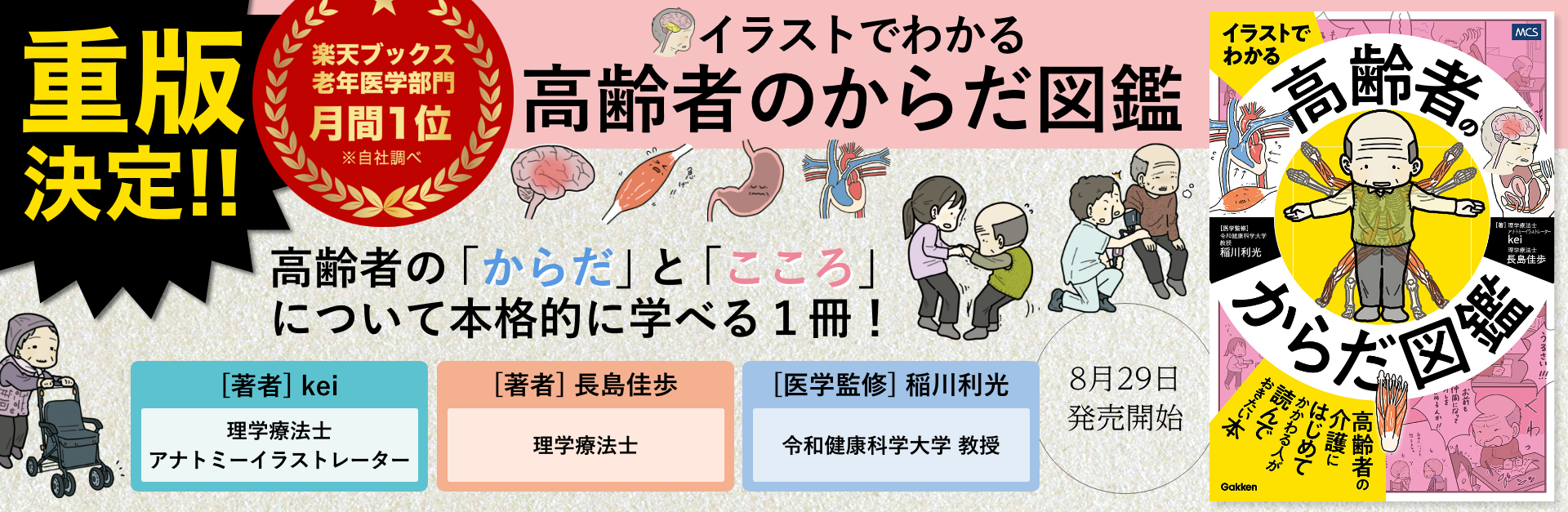呼ばれ名を決めることで「職員の入居者個々人への感情の表出に制限を加える訓練」にもなると前号でお伝えしましたが、何が訓練につながるのかを書かせていただきます。
改めてとなりますが、利用者・入居者を「呼ぶ側がどう呼ぶか」で決める呼び名に対して、僕が語る「呼ばれ名」とは、「利用者・入居者(そのご家族等)がどう呼んで欲しいか」で決める呼び名です。
おれのことはこう呼んでくれ
介護事業(以下 事業所)を利用希望された九州那覇さん(仮名)のお宅に事前面接に伺いました。
「九州さん、九州さんが事業所に来られた時、僕らが九州さんをどういう名で呼ばせていただくかについて、ご本人さんかご家族に決めていただいているのですが、どのように呼ばせていただきましょうか」
「俺はみんなからナハさんと呼ばれてきたんでナハさんと呼んでくれ」
「わかりました、ではナハさんと呼ばせていただきますね。ご家族もよろしいでしょうか」
「本人の言う通りで良いですよ」
決めたはずの「呼ばれ名」が変わるとき
事業所を利用される前に職員会議で九州さんのことを諸々お伝えし「呼ばれ名について本人の意思を確認したところ呼び名はナハさんとなりました」と伝えました。
九州さんは認知症の状態にない方なので、初めて事業所を利用していただいた時に職員は全員「ナハさん、こんにちは。私は〇〇です、よろしくお願いします」と、ご本人が決めた「呼ばれ名」で呼んでいました。
それから数か月経ったころ事業所の職員事務所内で、職員同士がナハさんのことを語り合っていました。
「ナハのことなんだけど、最近こうなんだよね」
ある職員が、とり決めた「呼ばれ名」ではない呼び方をしましたので職員会議を開いて聞いてみることにしました。
「多くは、あらかじめ決めさせていただいた呼ばれ名で呼んでいるにもかかわらず、ここ最近、複数の利用者に対して呼ばれ名以外の呼び名を使って一部職員同士が語り合っている場面を見聞きしていますが、教えてください。九州那覇さんはナハさんが呼ばれ名になっていますがナハって呼び捨てにしている理由はなんですか。又、徳島県子さん(仮名)の呼ばれ名はトクシマさんと決めているのにトクちゃんと呼ぶのはなぜですか」
職員さんたちは「・・・」と答えてくれません。そこで僕が代弁してみました。
「みんなが言えないなら僕が言いましょう。多くの利用者・入居者には自分の感情に揺れが生じたとしてもコントロールできる範疇なので決められた呼ばれ名で呼ぶことができているんでしょう。その中で、ナハさんを呼び捨てにするってことは、ナハさんに対してマイナスの感情が働いていませんか。逆にトクシマさんにプラスの感情が働いているんでしょ。
つまり、呼ばれ名以外の名で呼ぶ職員さんは、その職員自身が抱く利用者個々人への感情を呼び名に反映されているということではないですか。それって利用者を選別している意識の現われですよね。選別は不適切であり虐待の芽ではないですか」
氏を呼び捨てにして、〇〇ってわがままだよな
可愛いのよね、〇〇ちゃん
名を呼び捨てにするだけでなく短縮して、〇は言うことを聞いてくれないので面倒だなぁ
自分たちも人だから・・・自分を超えるのが職業人・専門職
僕らは職業人・専門職と言えども「人」ですから、利用者・入居者個々人に自分の感情を抱くことは無理からぬことで、その「感情を抱くな」と言うのは無理があると僕は思っています。
でも、私人としての人間関係ではない公的介護保険事業の利用者・入居者に対しては、職業人・専門職である僕らには「自分の感情をコントロールしきる専門性」が必要で、自分の感情で選別することは許されません。
だから「意識を持って従事する」ということですが、その意識が薄らいだ時(この場合で言えば利用者がいない職員事務所という環境が薄める)に自分の感情を表してしまいやすくなるのも当たり前にあることで、その表れのひとつに利用者・入居者への呼び名があります。
利用者・入居者に、手を出すわけでもないし、無視するわけでもないし、本人に向かって言うわけでもない「事務所内での職員同士の会話」なのですが「つい、本音が出た」ってことで、これは呼ばれ名を決めておいたからこそ職員の感情の揺れを見抜けたということですし、我が事業所に潜む、誰に起こってもおかしくはない「利用者・入居者の選別意識」の修正に向けて行動できたということです。
同時に、呼ばれ名を決めることで、職員は「利用者・入居者との関係に自分の感情を反映させない」ための訓練を積むことができると僕は考えています。
いい子ですよねの言葉に隠れたいい子じゃないの感情
保育にたずさわる専門職の方と話をしているときに、その方がこう表現されました。
「中には、いい子がいるんですよ」
親が、直接的に「〇ちゃん、いい子ですよね」って言われたら悪い気はしないので気づけない人が多いかと思いますが「いい子」という感情表現をするということは「この方の中には、いい子じゃない子も存在しているのかな」と僕は思ったので、
その方に「いい子ってどういう子ですか」「いい子じゃない子っているんですか」「いい子、いい子じゃないがあなたの感情表現だとしたら子供を育む専門職としていかがなものかと思いますが、僕が間違っていますでしょうか」と確かめました。
感情のコントロールは専門性
僕ら人にかかわることを業とする者にとってとても大事なことのひとつに「自分の感情をコントロールしきる」ということがあり、現に介護現場ではコントロールしきれない方が重大な事件を起こしていますね。
ある介護事業所の介護職員が「これ以上ここにいると自分を抑えきれなくなる気がするので退職させてくれ」と言ってきたそうですが、この方はとても健全で、きっと、この時点まではコントロールできていた方なんだろうなと思いました。
僕自身かつて、どちらかというと短気なので「コントロールしきれないかもしれない」と思った時は、利用者・入居者から一旦離れて自分をリセットすることがありました。感情をコントロールしきれるまでには少し時間もかかりましたので、介護の仕事について間もない職員さんたちには「一旦、利用者・入居者から離れる勇気をもとう」とお伝えします。
利用者・入居者のことをどう呼べばいいか
ぜひ、皆さんのところでも意見交換してみてください。そしてその時は「呼び名」だけでなく「呼ばれ名」という考え方や「感情の現われ」という捉え方も交えて意見交換し合っていただければと思います。
追伸
最近こんな話が飛び込んできました。
A市に住んでいるトメさん(仮名)は一人暮らし。B市に住んでいる子供さんには何かと心配事が増え介護保険制度の小規模多機能型居宅介護事業の存在を知り、A市内の事業所を訪ねたのですが断られてしまいました。その理由は「距離的に訪問できない地域なので求められる訪問サービスを提供できないから」ということでした。
トメさんの自宅は、A市とB市の市境に位置し、いろいろ調べた子供さんは自宅から一番近いB市のB小規模多機能型居宅介護事業所(以下 B事業所)を訪ねました。
事情を聴いたB事業所は「困っているのだから何とかせねば」と考えB市に掛け合うと、「B市に居住する子供さん宅にトメさんが同居してB市の住民になるのなら何ら問題はないが、住民票を移すだけでは利用させてはならない」と制度上の真っ当な回答でした。
別の話ですが、C市にある小規模多機能型居宅介護事業所Cは、C市とD市の市境に位置し、事業所の建築工事にあたっては、住民説明会の対象も大部分はD市居住者でした。
「工事でご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願いします」
「いつ自分たちも介護が必要になるかわからないなか、近くに説明を受けたような介護事業所ができるのは心強いよ。その節には、お世話になるからよろしくね」
「いや、実はD市の皆さんにはご利用いただけないんです」
「エーッ、なんで、こんなに近いのに」
「すいません、制度がそうなっているんです。皆さんには“ご迷惑かけ逃げ”になるんです。すみません」
介護保険制度って誰のために・何のためにあるんでしょうかね。
この問題点はずっと僕自身は発信し続けていますが「困っている人にはどうやったら応えられるか」を追求している者としては歯がゆい限りです。
又、地域密着型の本名は「保険者密着型」だと僕は思っていますが、「住み慣れた地域で住み続けられるように、住み慣れていない地域の、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにを謳う介護事業所にいかねばならない」なんて、笑い話になりませんよね。
 2011年、東日本大震災後の8月、災害時に要請を受けなくても互いに駆けつけ合う法人ネットワーク「災害支援法人ネットワーク(通称:おせっかいネット)」を結成し、年に二度、会員の所在する地域に出向いて学習・交流会を開催しています。今年第一回目は山形県蔵王温泉での開催でした。
2011年、東日本大震災後の8月、災害時に要請を受けなくても互いに駆けつけ合う法人ネットワーク「災害支援法人ネットワーク(通称:おせっかいネット)」を結成し、年に二度、会員の所在する地域に出向いて学習・交流会を開催しています。今年第一回目は山形県蔵王温泉での開催でした。
蔵王温泉と言えば「樹氷」なので見物してきましたが、マイナス13度の地点に立つ樹氷は素晴らしかったです。
年々雪が降らなくなり樹氷化しなくなるのではないかと危惧されていますが、今年は、雪の量もお天気も星の美しさも最高のコンディションだったようです(嵐男の僕を超越する快晴女が参加していたためと思われます)
いやぁ、写真を撮るために手袋を外しましたが、弱い風にもかかわらず「風吹くマイナス13度」は凍傷を覚悟したほどでした。
ちなみに濡れタオル(写真の赤い物 エスキモー人風は僕)を振り回せばすぐ真っすぐ突っ立てしまいましたからね。
下りるときのゴンドラ待ち時間が長かったのですがツアー客向けの「優先乗車」があるようで、後から来て先に行かれてしまうので並ぶこと1時間。沖縄から来た連中は死にかけていましたね。だって、沖縄に戻ったら19度だったようですから、気温差32度。そりゃ、きついってもんじゃないですよね。










.webp)