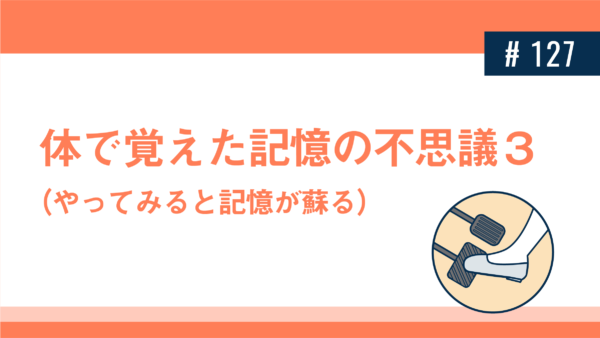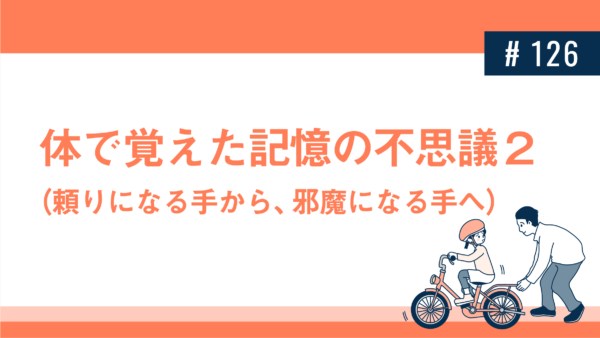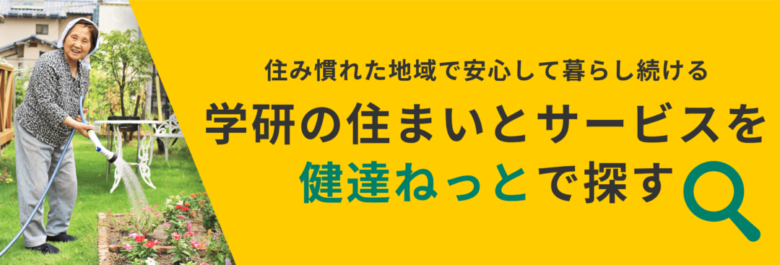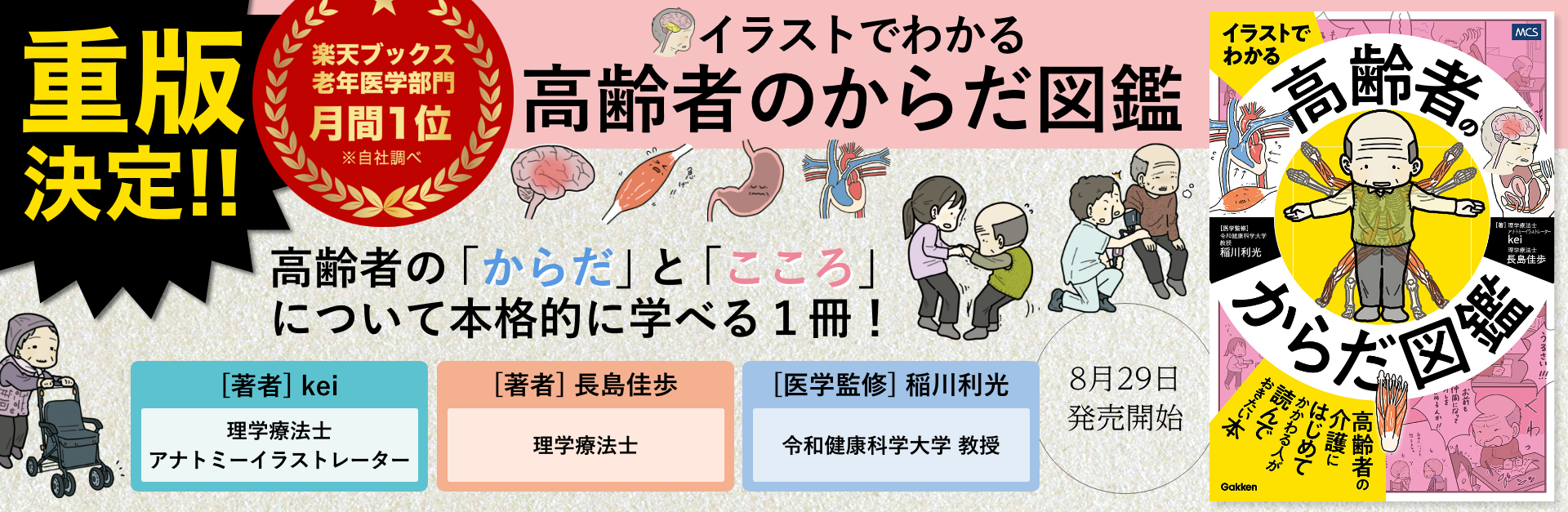本人の意向を尊重したい
トメ子さん(仮名)は、正常圧水頭症による認知症の状態にあり、認知症対応型共同生活介護(以下 グループホーム)に入居されました。
そのトメ子さんが入院となりお見舞いに行き、トメ子さんの耳元で「トメ子さん、もう(あの世に)逝きますか」と聞いてみると首を横に振られました。
布団をめくって両足の力を確かめるように寝たままの状態で屈伸すると跳ね返してきます。
「まだ、大丈夫やわ」
それから毎日お見舞いに行き、両足の屈伸運動をさせていただきながら言葉をかけました。
数日後、ドクターから「もう、ご飯を口から食べるのは難しい」と言われたので「口から食べる訓練をしていただけますか」と聞くと「そんな危険なことはできない」と言われたので「危険なことを病院でできなければ、どこでするんですか」と語気強く言うと「家族と胃ろう増設について相談してください」と言われました。
「ん」と思いましたが、僕が判断して良いことではないので家族に伝えるしかなく、家族は「少しでも長生きして欲しいから」ということで承諾されましたので、不本意でしたが胃ろうを増設して退院となりグループホームに戻って来られました。
それからしばらくして職員たちと「いつごろから口からの摂食に挑もうか」と話し合いをし、敬老のお祝い会を催したときに来てくれた家族に「口からの摂食に挑みましょう」と伝えている最中に、トメ子さんは目の前に置かれていたご馳走を手に取ってパクリ!と食べられました。
これには家族と一緒に笑うしかなかったのですが、これがきっかけとなって挑みがスタートします。
この一年前、入居者たちとの雑談の中で温泉の話になり「温泉に行きたいね」と皆さんが口々に言われるので、定例開催していた家族懇談会のときに「先の短い皆さんの願いを実現してやりたいのでお金出してくれますか」と伝えると「連れて行ってやってください」となり日光温泉に一泊二日で行くことになりました。
温泉から出た直後にヨネさん(仮名)に「いい温泉でしたか」と聞くと「温泉なんか、入っていませんよ」と返ってきました。
日光温泉は「透明・無臭の温泉」でしたので認知症の状態にある入居者が「温泉だ」と認識できなくても無理からぬことです。
そこで翌年再び家族に提案して「温泉旅行」の了解を得ることができました。
今度は、車で往復7時間かかりますが、硫黄泉で色が付き臭いもある日光温泉の奥地にある奥日光温泉に日帰りで行くことにしました。
前年の一泊二日の旅は入居者にとって良いとは思えなかったので、時間がかかっても日帰りとしました。
 そのときもヨネさんに「いい温泉でしたか」と聞いたのですが「いいお湯でしたよ」と答えてくれ、脳が「温泉だ」と認識できたこと・記憶化されたことに「やったぁ!」と思いました。
そのときもヨネさんに「いい温泉でしたか」と聞いたのですが「いいお湯でしたよ」と答えてくれ、脳が「温泉だ」と認識できたこと・記憶化されたことに「やったぁ!」と思いました。
この日帰り温泉旅行に胃ろう増設の状態になったトメ子さんを連れて行くかどうか考えましたが、家族の意向も踏まえ「湯を浴びるだけでも良いか」と言う結論を下し一緒に行くことにしました。
何が起こるかわからないためトメ子さんの入浴時は、僕と男性スタッフの二人で対応しました。
浴室に入ると温泉臭と湯気が充満して「まさに温泉にきた」って感じで、着座していただき湯を身体にかけると「気持ちいい」っていう表情を見せてくれ「一緒に来てよかった」と思ったそのときです。
何とトメ子さんは立ち上がろうされ「どうしようとされるのか」付き添っていると、明らかに湯船に浸かりたがったのです。
ほぼ瞬間の判断でしたが男性職員に「服を脱いで一緒に入れるようにして」と指示を出し、職員と一緒に入湯しました。
本当に気持ちよさそうに入っているでしょ(写真)。

意向に沿うのはリスクもつきまとう
胃ろう増設状態で硫黄泉に入っていいのかどうか瞬間迷いましたが、これまでのトメ子さんのエピソードを思い浮かべ、家族に「どういう人生の最後を送らせてあげたいか」を聞いてきた意向を考えての「入湯判断」でしたが、僕は今でも間違っていなかったと思っていますし、後日家族にお話しした時も笑いながら「それは良かった」と言ってくれました。
トメ子さんは僕が退職した後にグループホームでご逝去されましたが、その時、ベッド上で横たわるトメ子さんに「トメ子さん」と声をかける職員に家族は「もう眠らせてあげましょう」と言ったそうです。
それからしばらくして家族とお会いする機会があり、そのときに「母親が死んで寂しいけど、和田さんたちと一緒にやり切ったから辛くはない」と言われていました。
今、僕ら介護事業従事者は難しい時代を迎えています。
どんなに家族と良い関係をもって入居者の支援にあたっていても、ご逝去されたのち「介護事故ではないか」と問われかねず、どうしても「手堅く無難にいかねば」となりがちです。
僕らが「手堅く無難にいかねば」となればなるほど認知症の状態にある方たちの「生きる姿」を一般的な国民が生きる姿から遠くへ遠くへと追いやってしまいます。
歩けば転ぶ確率が上がるので職員が付き添えないときは歩こうとすることを止めてしまうでしょうし、屋外を歩けば事故の確率は高くなるから屋内での生活にとどめようとするでしょう。
世の中全体がリスクを受け止めることなしに意向に沿いにくい
僕は、「認知症の状態にあっても人として生きる姿で最期まで」と考えて実践してきましたし、今もそのことを皆さんに伝えていますが、それを成すには本人はもとより、その家族、地域住民、行政関係者たちと手をつなぐことが必要です。
でも、それだけで本当の意味で成すことはできず、今の時代は世の中全体が「認知症になっても人権があり主体性を尊重すべき、介護事業所に鍵をかけて閉じ込めてはならない、事故は生きていれば誰にでもあり得ること」といったようにならねば、介護事業者は「認知症基本法:認知症になっても基本的人権は享有」に沿って簡単には動けないことでしょう。
僕が実践していた2000年頃から20数年経ちましたが、介護事業所を利用される・入居される認知症の状態にある方への生活支援は、認知症の状態にある方への人権が強く打ち出された社会にはなりましたが、とても難しい時代に突入したと感じています。
今なら、トメ子さんの入湯を予測して家族から一筆もらうかもしれません。
ただ、難しい時代になったからといって「人として生きる姿への支援」を止めることはありませんが、より「家族と共に」に基づいて説明と同意が必要ですし、「家族と共に」を進めていたとしても「ズレ」を予測してコトを進めて行かねば介護事業の継続が難しくなることを覚悟せねばならないということです。
追伸
いつも、僕の記事を読んでいただきありがとうございます。
又、たくさんの方からコメントを寄せていただき嬉しく思っています。
この記事が2025年度のスタートとなりますので、僕の願いを追伸させていただきますが、僕はコメント者同士がお互いのコメントに対してコメントをする関係を構築できたら良いなぁと思っています。
Aさんのコメントに対してBさんがコメントをする。それに対してCさんがコメントをするといったようにですが「健達ねっと」を通して意見交換の環が広がることを望んでいます。
お力添えいただければ幸いです。
2025年度も、よろしくお願いいたします。









.webp)