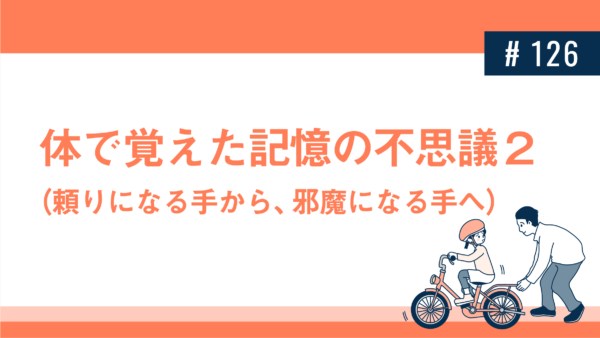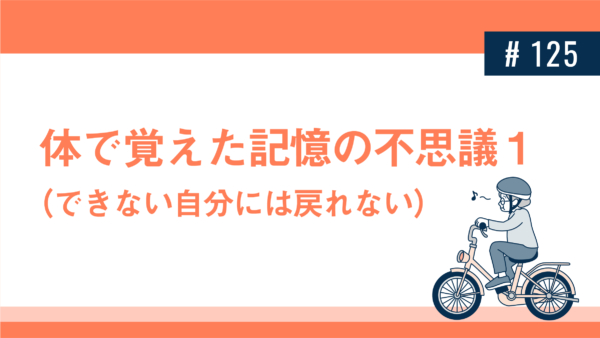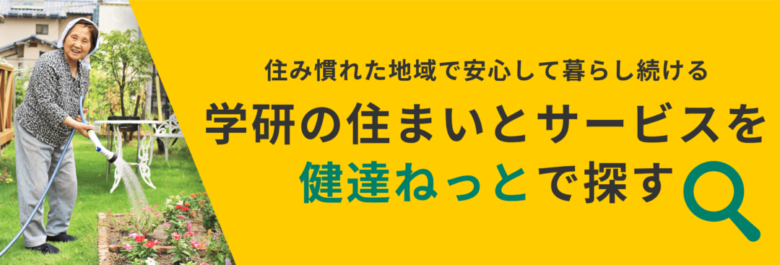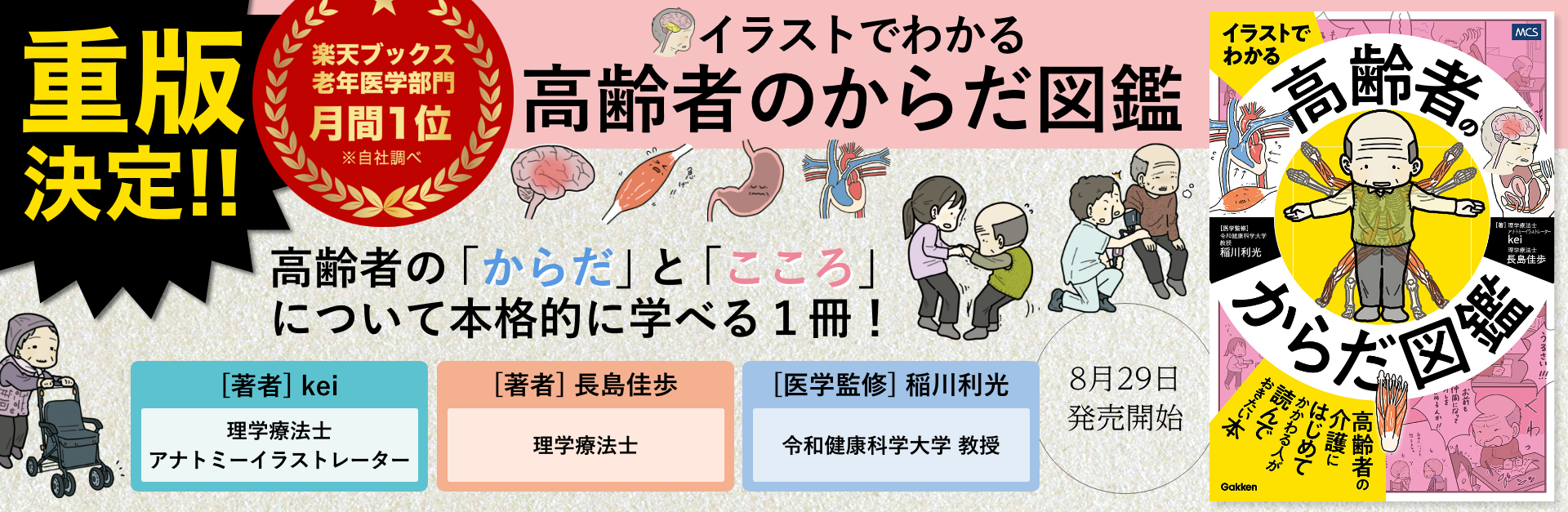介護保険法が施行される前年の1999年に老人福祉法に位置付けられた「痴呆対応型共同生活援助」(現:老人福祉法「認知症対応型共同生活援助」介護保険法「認知症対応型共同生活介護」 以下 グループホーム)の施設長を仰せつかり1999年2月に赴任、3月に開設しました。
1ユニット定員8人の民家改修型でしたが、東京都初の法制度に基づいたグループホームというインパクトもあってか、たくさんの方々(人数は憶えていない)から入居の応募が寄せられ、全員の面接をさせていただいて入居者を選定させていただきました。
この時はまだ介護保険制度施行前「措置」の時代だったため年度内入居完了(事業開設)は至上命題で、入居計画は3日間を1スパンとして、その間に3人ずつ入居していただき、1日目以降3人・4日目以降6人・7日目以降8人、年度内8人全員入居となりました。
この時の考え方や実経験(実験とも言えます)は、定員数や事業に関係なく今でも新規開設に活かしています。
エピソードとしては、初日に2人が同日入居されましたが、この二人はこれが初対面にもかかわらず、後々まで「この人は昔からのお友達なのよ」と言っておられましたので、「二人きりで寝食共にした二日間」はかなりインパクトがあったんでしょうね。
このグループホームの施設長(ボス)として8人全員が揃ったところで一席ぶちました。
「Aさん、今、歩くことができているじゃないですか。いくつから歩かれていますか?きっと随分長い期間歩かれてきたのでお疲れでしょうから、そろそろ歩くことを止めて、これ(車いすを見せた)に乗って僕に押してもらうようになりたいのではないですか」
「何言っているんですか、歩きますよ。歩きたいに決まっているじゃないですか」
「そうですか。そうですよね。歩けるってステキですよね」
「Bさん、今、お箸やスプーンを使って自分でご飯を食べているじゃないですか。いつから自分一人で食べれるようになりましたか?きっと随分長い期間自分で食べられてきたのでお疲れでしょうから、そろそろ自分で食べるのを止めて僕に食べさせてもらいたいなぁと思っていませんか」
「何言っているんですか、いくつになっても自分で食べられる間は食べますよ」
「そうですか。そうですよね。自分でお箸やスプーンを使って食べられるってステキなことですよね」
「Cさん、今、自分でトイレに行って、自分で始末して戻って来られるじゃないですか。もう疲れたから僕に始末してもらいたいと思いませんか?」
「なに言ってんのよ、バシッ!」 軽く叩(ハタ)かれてしまいました。
「皆さん、僕たちが皆さんの願いを叶えますから、僕の言うことを聞いてくださいね」
入居者の皆さんに「願い」を聞くと、誰も今できていることを止めて僕に委ねますとは言われませんでしたが、それってこの方々だけが願っている特別なことではなく、圧倒的な方たちが願っていることではないでしょうか。
もちろん「人」ですから、その時々の事情による心模様を描き、自分でできることさえも他人に委ねたくなる時やコトはあるでしょうが、根っこは「自分でできることは自分で」ではないでしょうか。
高齢者を大事にするべしの「大事」は、自分でできることを奪うのではなく、でき続けられるように支援する・取り戻せるように支援することだと僕は考えていますが、これは20歳代の頃、障がいのある方々とのお付き合いの中で学んだことだと思います。
四十数年前のことで恐縮ですが、車いすの方を見かけると「日本人は近寄らないか手を出そうとする」が欧州では「必要なことがあったら言ってくださいと本人に伝える」と聞いたことがありましたので、僕の中の「介護」は英語で言う「サポート」になったんではないかと思っています。
オーストラリアの認知症の状態にある方がNHKなどマスメディアでも多数紹介されていましたが、その方を特集したNHKの番組を見たとき、その方の旦那さんが言っていたのは「僕は、彼女のサポーターなんだ。彼女がどうしたいか、何を求めているかを知ること」というもので、言葉は正確ではないでしょうが、こんなニュアンスが一番しっくりきました。
ただし、僕は「願いに応える」だけではなく、前述したように、そもそもの「人の願い」から「今の願い」とのズレを思考して志向し試行します。
例えば、「何にも食べたくない」と言っている方に応えたら結果はおのずと見えますね。そもそも何にも食べなければ今の年齢に至れていないわけで、人は食べるし・とり込むし・排出する生き物ですから「食べたくないわけじゃなく」て「食べたくないと思う理由(わけ)がある」はずで、それを探っていくということです。
その志向のモノサシ(思考)が「自分のことは自分ですることが人の基本」で、それを邪魔する・奪うのではなくサポートするのが僕の仕事だということですが、これって自分で言うのもなんですが、なかなか簡単なことではないんですよね。一筋縄ではいかない。
この続きは次回に・・・。

この地域を走るJR西日本芸備線のこの区間は廃線の話が絶えないローカル線ですが、昔鉄道マニアの僕は「サクラの開花と芸備線」を写真に収めたくてウズウズ。
ここへ行くタイミングと桜の開花時期が合い、本数が少ない列車で撮影できる天気となると、なかなかチャンスがなかったのですが、辛うじて収めることができました。
鉄道写真を撮ろうと場所探しに走り回る自分、ここで撮ろうと決断する自分、列車がくるまで胸躍らせて待っている自分、陽が沈んでしまわないかドキドキする自分、いよいよ来る時間にワクワク感をもつ自分、撮った後に写真を確かめる自分、撮ったぞ!と言わんばかりに身内に配信する自分、たった1時間程度のことでも「生きている感」を堪能できるのですが、それにエネルギーを与えているのが「この場(健達ねっと)があること」のような気がしています。本当にありがたい限りです。









.webp)