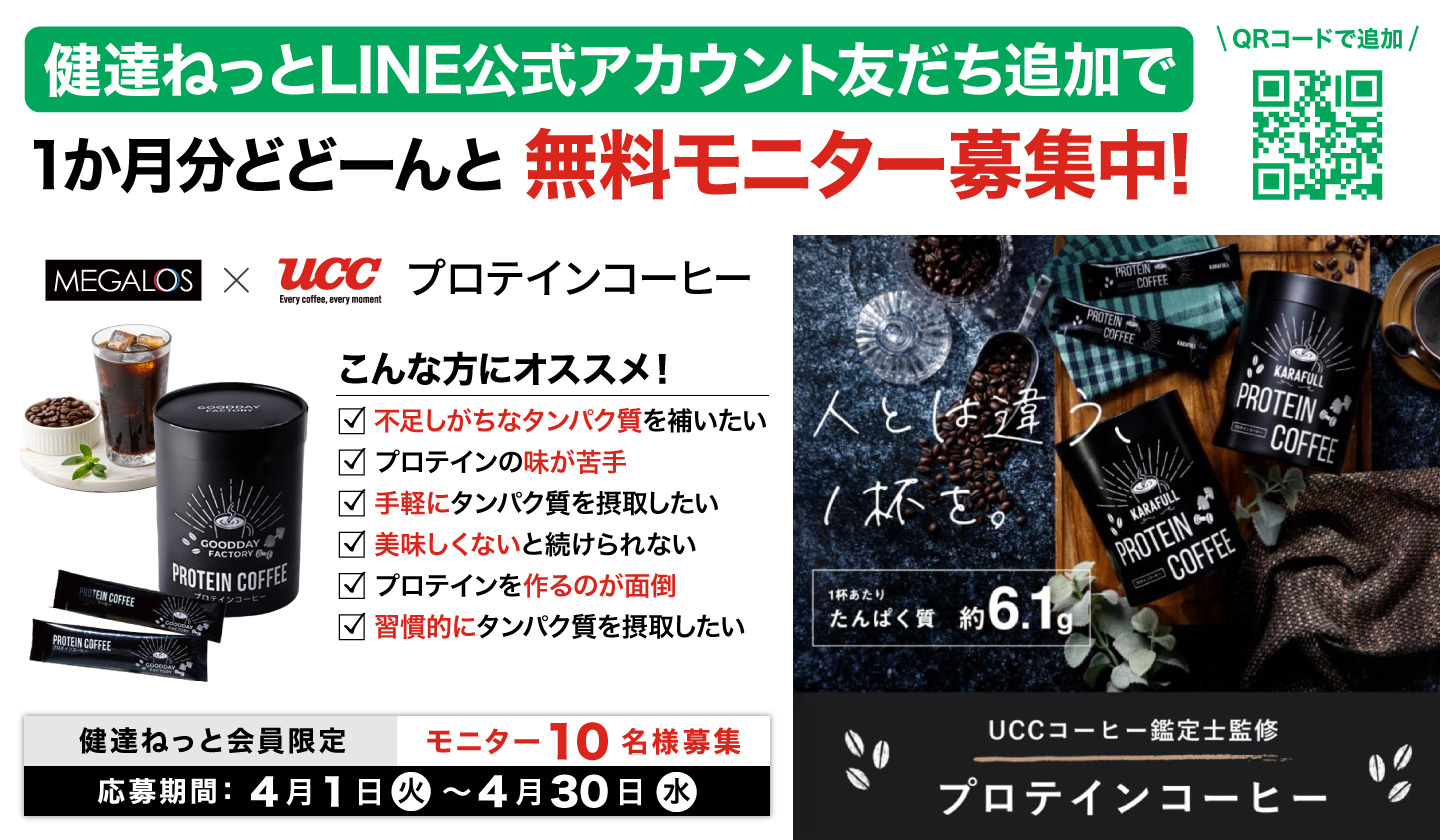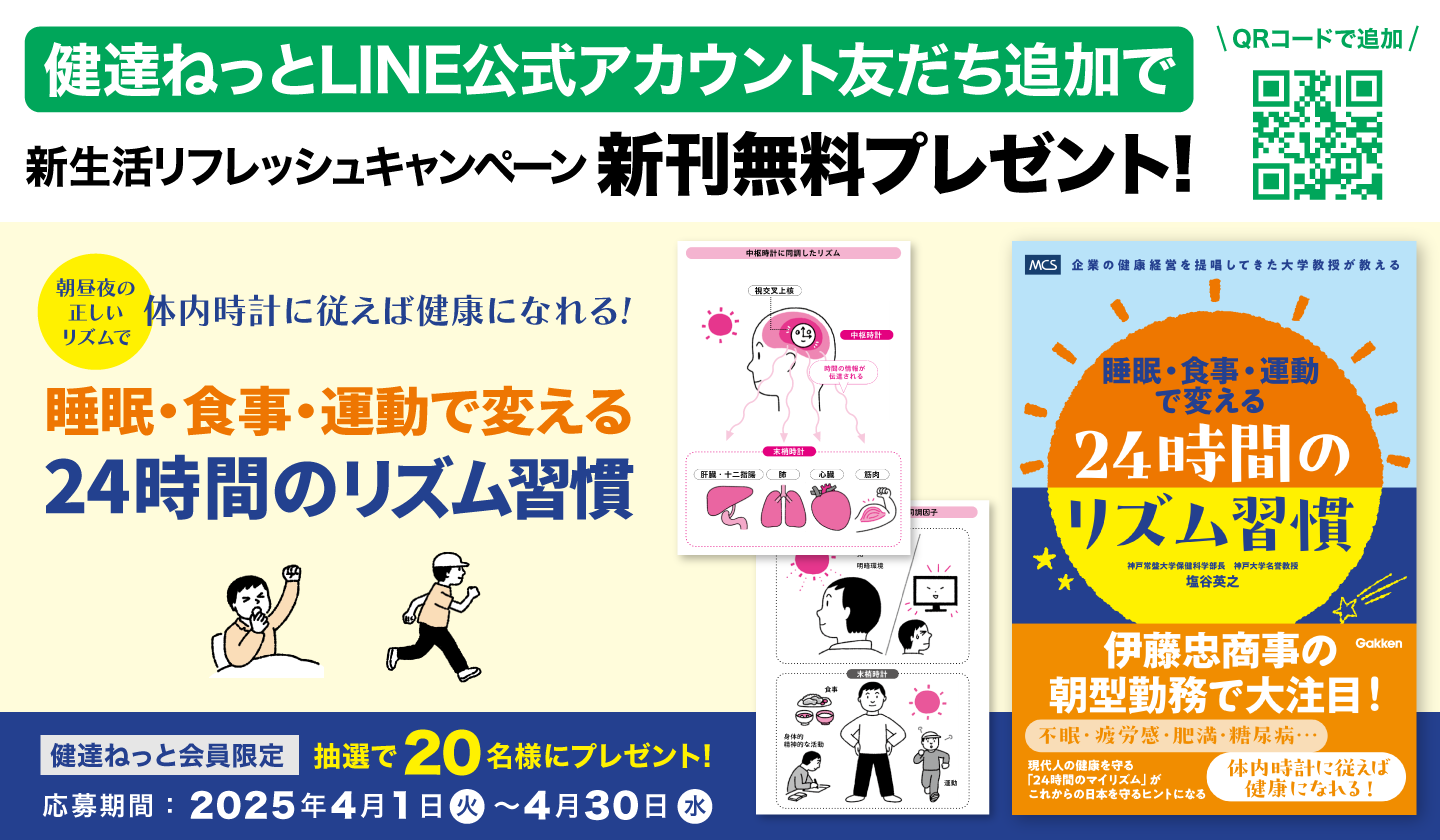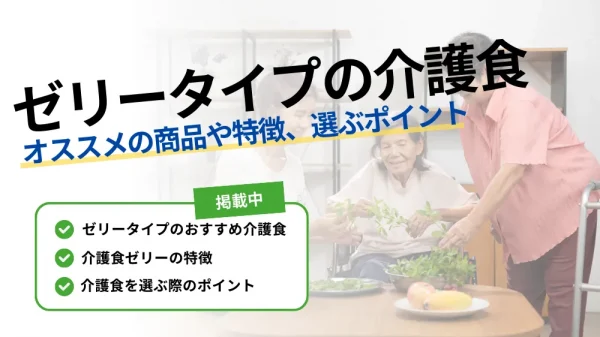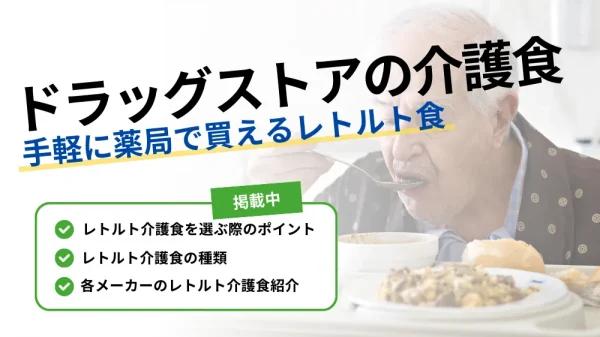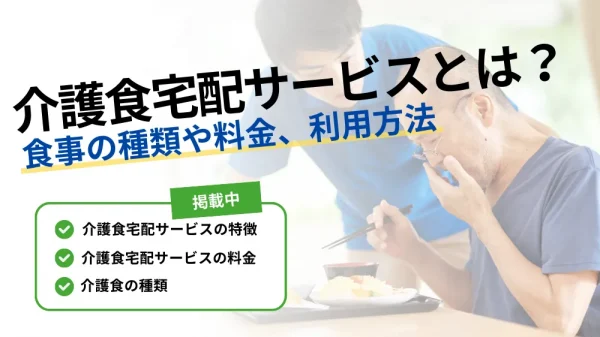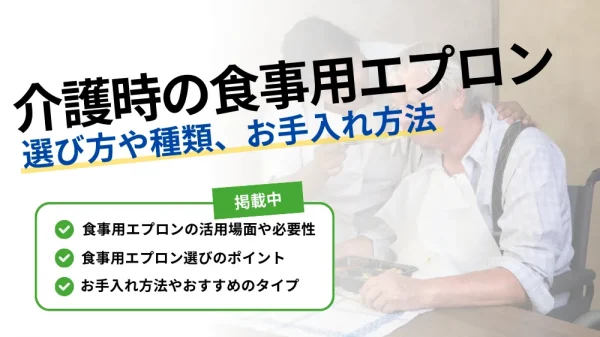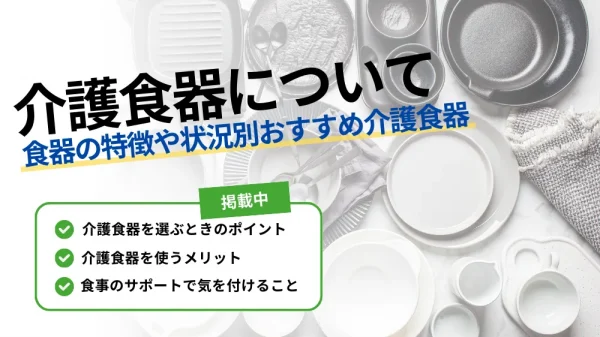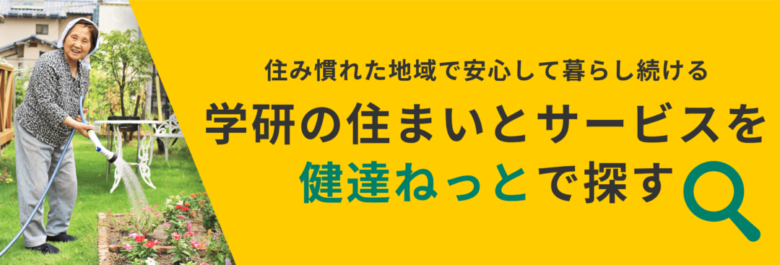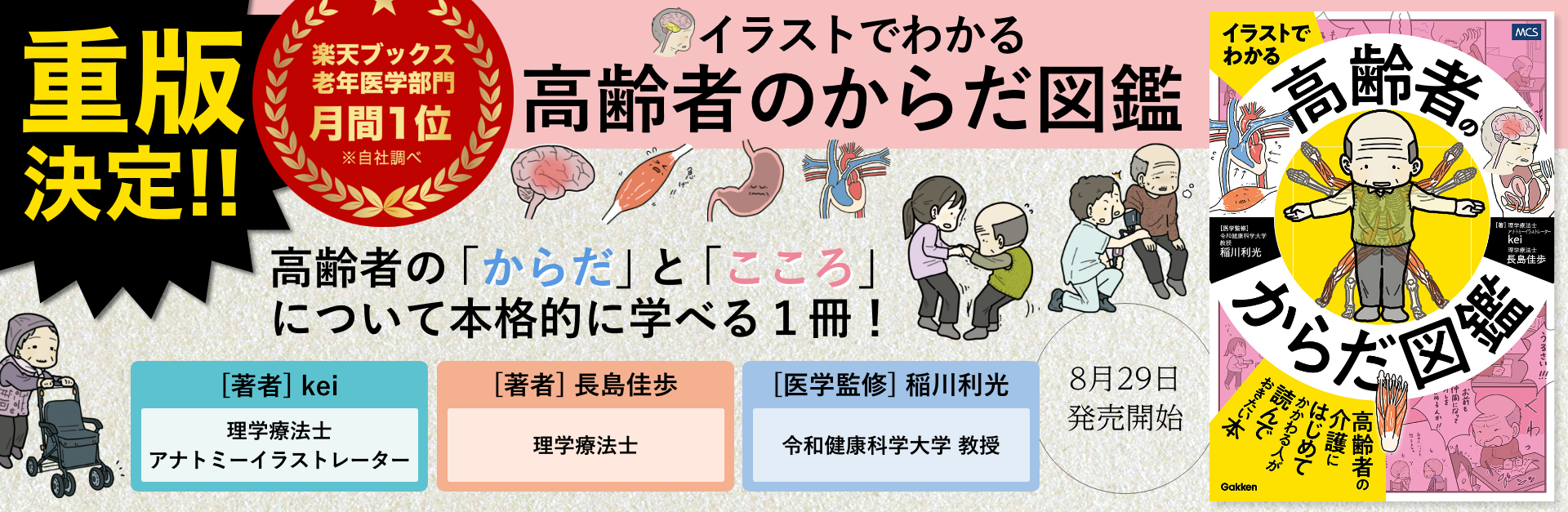老人ホームで、利用者がどのような生活を送っているのか気になりませんか?
ご自身やご家族が入居する老人ホームを選ぶ際に、実際に利用されている方がどのように過ごされているのか、事前に把握しておきたいですよね。
そこで今回は、老人ホームでの生活や利用状況などを解説していきます。
- 老人ホームの全体的な生活に関して
- 老人ホームの種類や違い
- 老人ホームの利用状況や費用に関して
この記事で実際の生活イメージを膨らませ、老人ホームを選ぶ際の参考にしていただけたら幸いです。
ぜひ、最後までご覧ください。
スポンサーリンク
老人ホームでの1日の生活

老人ホームで過ごす1日の生活の流れは、各施設で異なります。
しかし、基本的な1日の流れは似ています。おおよその生活の流れを確認していきましょう。
老人ホームの1日(朝)
- 7時
起床する時間です。着替えに介助が必要な方は、この時間で介護スタッフが介助を行います。 - 8時
朝食や服薬チェック、口腔ケア(歯磨きなど)をする時間です。施設によってルールがありますが、ご飯食かパン食かなど、入居者の希望で朝食を選べる場合もあります。 - 9時
体調の確認や血圧、脈拍、体温の測定を行い健康状態を確認します。毎日行うことによってちょっとした体調の変化にもすぐに気付くことができるようになっています。 - 10時
健康状態の確認で問題がなければ入浴をします。老人ホームによっては、自立している方は夜に入る場合もあります。
老人ホームの1日(昼)
- 12時
昼食の時間です。老人ホームでは、糖尿病食や腎臓病食など持病を持たれる方に合わせた食事を提供しています。また、刻み食など食事形態の違いにも対応しています。 - 14時
スタッフと一緒に体操をしたり、リハビリテーションという意味も含めてレクリエーションなどを行ったりします。体を動かす時間にしている老人ホームが多いでしょう。 - 15時
おやつを食べたり入居者同士で談笑したりする時間です。映画を上映するなどの取り組みをしている老人ホームもあります。
老人ホームの1日(夕方〜夜)
- 18時
談話室など共有スペースに集まって夕食の時間になります。夕食を食べ終わっても談話室に残って話をされる方や自室に戻ってテレビを観る方もいます。 - 21時
就寝の時間です。夜間帯はスタッフがそれぞれの部屋を巡回したり、ナースコールの対応などをしています。もし何かあっても、すぐにスタッフが対応できる体制を整えています。
老人ホームによって多少違いがありますが、規則正しく生活できるようにスケジュールが立てられています。
入居者みんなで買い物に行ったり桜や紅葉を見に行ったり、頻繁に外に出かける老人ホームもあります。
また、日中はデイサービスやデイケアに行くなど、人によっても違いがあります。
被介護者を抱える方の中に介護施設への入所を考える方は多いのではないでしょうか。一方で、一口に介護施設といっても種類はもとより、特徴や入所条件などは様々です。今回は、数多くある介護施設の中でも特別養護老人ホームについてご紹介します[…]
スポンサーリンク
サークル活動やレクリエーション

老人ホームでは、体の機能を維持する目的やQOL(生活の質)の向上を目的としてサークル活動やレクリエーションを行っています。
サークル活動やレクリエーションを行うことで、生活にもメリハリがつきます。
老人ホームのサークル活動
サークル活動では、下記のようなサークルがあります。
- 手芸
- 工芸
- 折り紙
- 囲碁や将棋
- カラオケ
- 体操
上記のサークル活動以外にも、それぞれの老人ホームで特有のサークル活動もあります。
必ずどれかに参加しないといけないわけではないので安心してください。
もし、興味があれば参加してみて、難しかったり合わなかったりする場合は、辞めることも可能です。
老人ホームのレクリエーション
レクリエーションには下記の4種類があります。
脳トレタイプ
計算問題や塗り絵、クイズなどを行うレクリエーションです。
認知症を予防したいと考えている方の参加が多く人気のレクリエーションです。
運動タイプ
体の機能維持を目的として体操や簡単な競技などを行うレクリエーションです。
体を動かすことが好きな男性に人気です。
作成タイプ
作品作りなどを行うレクリエーションです。
書初めなど時期に合わせたことを行うことが多いでしょう。
リフレッシュタイプ
カラオケや音楽鑑賞など楽しみつつ、精神的な落ち着きや不安の軽減を目的としたレクリエーションです。
季節ごとの行事
季節を感じるために時期に合わせたレクリエーションもあります。
| 月 | 行事内容 | 月 | 行事内容 |
| 1月 | 新年会 | 2月 | 節分、豆まき |
| 3月 | ひな祭り | 4月 | お花見 |
| 5月 | 母の日 | 6月 | 父の日 |
| 7月 | 七夕祭り | 8月 | 夏祭り |
| 9月 | 敬老会 | 10月 | 運動会 |
| 11月 | 文化祭 | 12月 | クリスマス会 |
また、毎月誕生日会も開催されており、老人ホームでは毎日楽しみながら生活できるように工夫されています。
日本では少子高齢化が社会問題となっており、高齢者の割合が年々増加しています。そんな中、認知症の高齢者を専門にケアする施設も増えてきました。その施設の一つが「グループホーム」です。今回の記事では、「家族が認知症になって自宅で介護を続[…]
健康に配慮した食事や運動

老人ホームでは、様々な観点から健康に配慮されています。
その一部をご紹介します。
老人ホームでの食事の配慮
高齢になってくるとものを飲み込む力(えん下機能)の低下や、病気によって食事の制限が必要になることがあります。
そのために老人ホームでは、1人1人に合わせた食事を提供しています。
例えば普通食や介護食、治療食などがあります。
また、刻み食やペースト食など食事の柔らかさなども調整が可能です。
老人ホームには管理栄養士が勤務しており、日々の食事で必要な栄養素やカロリーの計算などをしっかりと管理しています。
また、食事をどのくらい食べることができているのか、残量をチェックして健康管理に努めている老人ホームも多くあります。
老人ホームに調理場がなく、外部から食事を取り寄せている場合は、食事を温め直すなど、美味しく食事ができるように工夫しています。
老人ホームでの運動の配慮
運動に関しても理学療法士や作業療法士、健康運動指導士が指導するなど専門的な知識を持ったスタッフの指導の下で運動を受けることができる老人ホームもあります。
食事や運動の面からみても老人ホームでは、健康的な生活を送ることができるでしょう。
介護・医療面でのサポート

老人ホームでの生活では、介護に関して不安に感じることもあるでしょう。
しかし、老人ホームには介護福祉士やヘルパーの資格を持っている人が働いているので、生活面でも不安なく暮らしていけます。
介護面のサポート
例えば、トイレに1人で乗り移りができなくても、衣服の上げ下ろしやトイレに座るまでの介助をしてくれます。
入浴では大浴場や個浴があったり、介助量が多い方でも機械浴で入浴することも可能です。
しかし、機械浴がない老人ホームもあるので入居前に一度確認することをオススメします。
お風呂に入れない場合などは清拭(せいしき)で対応してくれる老人ホームもあります。
医療面のサポート
医療に関しては、老人ホームを運営している母体が病院である場合は、病院から往診で医師が来るなど密な連携を取っています。
一般企業が行っている老人ホームでも、周辺の病院と連携を取っており、もし何かあってもすぐに対応できるようになっている場合がほとんどです。
通院時の対応
通院時の付き添いは、付き添い費など別途費用が必要な場合がほとんどです。
基本的には家族が行うものと認識しておいた方が良いでしょう。
買い物や整髪はどうしているの?

老人ホームでは、外出や外泊などは基本的に自由となっています。
近くのお店に買い物に行きたい時は、事前に申請しておけば行くことは可能です。
入居後は、今まで通っていた理髪店や美容室が遠くなってしまい、行けなくなることも考えられます。
老人ホームでは、「訪問理美容サービス」を利用できます。
散髪だけでなく、髪染め、パーマなど多くのことに対応しています。
しかし、訪問理美容サービスは介護保険対象外なので、費用は全額自己負担となるので注意が必要です。
「介護付」と「住宅型」のちがい

有料老人ホームには大きく分けて2種類あります。
「介護付」と「住宅型」です。それぞれについて解説します。
介護付有料老人ホーム
介護付有料老人ホームは、介護等のサービスがある高齢者向けの居住施設のことを言います。
24時間365日スタッフが常駐しており、身の回りの世話や食事などの介助サービスが受けられる有料老人ホームとなっています。
介護付有料老人ホームには介護サービスを老人ホームの職員が行う「一般型」と、入居している老人ホームのスタッフではない、委託された事業所が行う「外部サービス利用型」があります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームとは、食事や掃除などの生活支援サービスを受けることができる高齢者施設のことを言います。
介護付有料老人ホームとは違い介護サービスなどは基本的にありません。
身体機能が変わり介護が必要になった場合は、訪問介護などの外部サービスを利用し介護を受けることができます。
老人ホームの利用は増加傾向
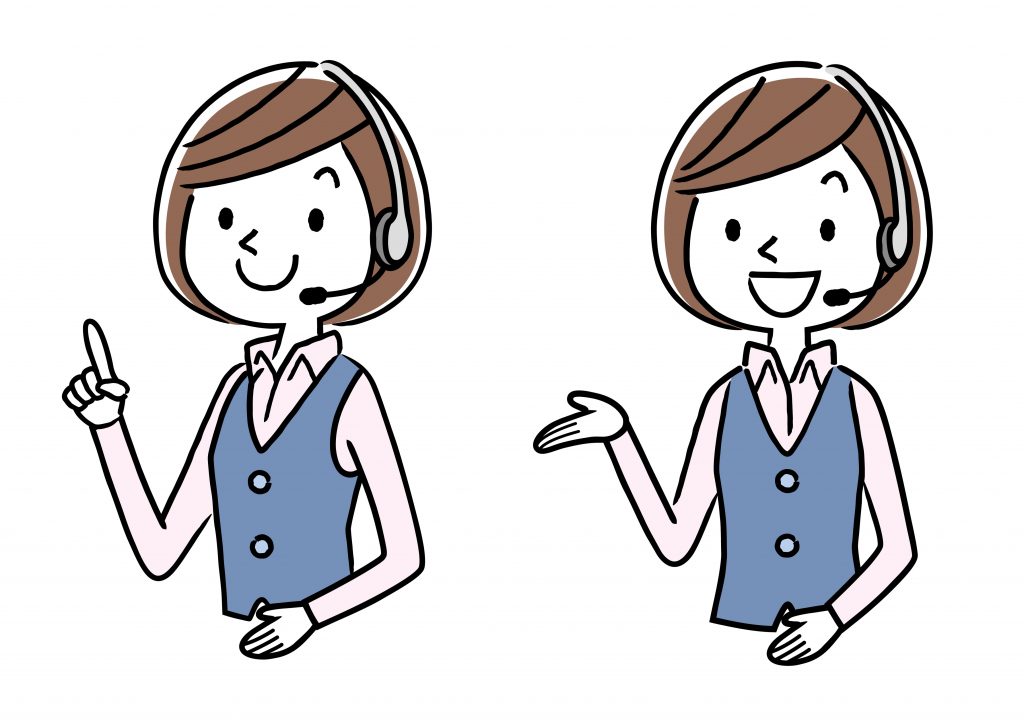
老人ホームの利用は、年々増加してきています。
総務省の調査によると(2021年9月15日現在推計)、65歳以上の高齢者の数は3640万人となり前年(3618万人)に比べ22万人も増加しています。(出典:総務省統計局「高齢者の人口」)
老人ホーム件数の増加
高齢者の数が増えてきていることで、老人ホームの数も増えてきています。
下記は厚生労働省の社会保障審議会の資料を参考に作成した表となります。
| 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
| 平成23年 (2011年) | 91,369床 | 179,404床 |
| 令和1年 (2019年) | 293,326床 | 246,194床 |
(参考:厚生労働省第179回社会保障審議会介護給付費分科会【資料7】)
この表は入居者数ではなく定員数(ベッド数)ですが、入居できる数が多くなっていることが分かります。
在宅有料老人ホームでは、平成23年と令和1年を比べると、201,957床も多くなっています。
また、介護付有料老人ホームも66,790床多くなっており、老人ホームが必要な施設となってきていることが分かります。
老人ホーム利用のメリット
老人ホームと聞いて、あまり良くない印象を持たれる高齢者の方も多いかもしれません。
しかし、レクリエーションや健康チェック、他の利用者との交流の機会など、自宅にいては得ることができないメリットも多くあります。
もちろん住み慣れた家で、生涯落ち着いて過ごしたいと思う方も多いでしょう。
しかしもしも、自宅での生活に不便を感じることが多いという場合は、老人ホームも1度検討してみてはいかがでしょうか。
スポンサーリンク
老人ホームの利用にかかる費用
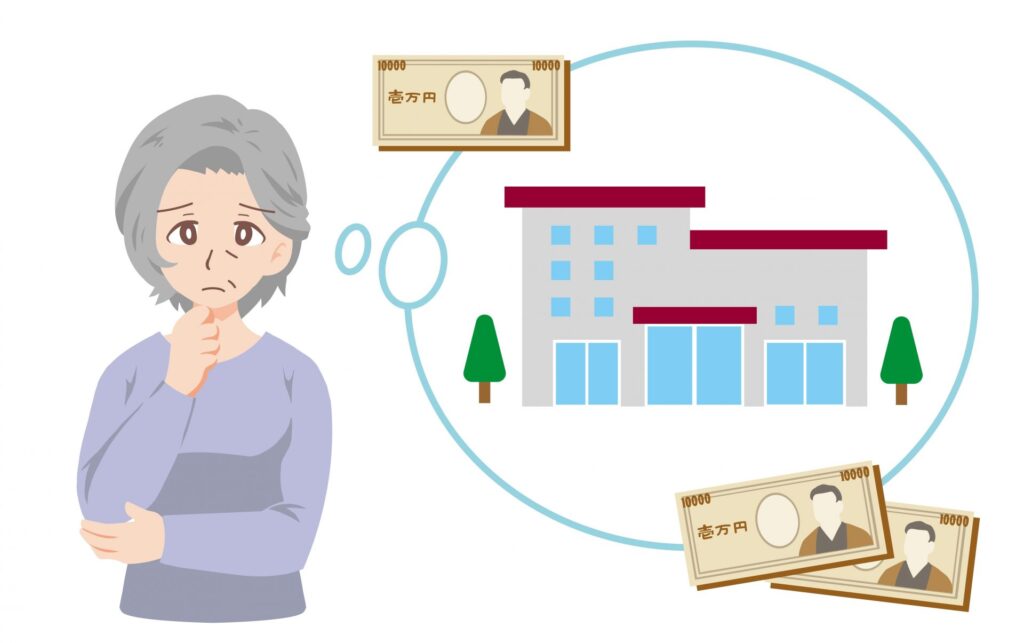
なんとなく老人ホームの利用は高額な印象を抱いていても、具体的な費用についてはよく知らない、という方は少なくないのではないでしょうか。
ここでは、老人ホームの利用にかかる費用の目安について解説していきます。
入居一時金
介護付有料老人ホームでも住宅型有料老人ホームでも「入居一時金」が初期費用として必要になる場合があります。
入居一時金は前払いや月払いなどの支払方法があり、費用は0~数千万円となっています。
月額費用
入居一時金以外にも毎月の支払いが必要となります。
管理費や食事代、日常生活費などで、施設によって異なりますが毎月20万円前後のお金が必要になります。
その他の費用
介護付有料老人ホームの入居者や住宅型有料老人ホームで介護サービスを受ける方は、さらに介護サービス費用が追加されます。
また、介護付有料老人ホームでは、立地の良さや設備が充実しているなどの理由で、費用が高くなる傾向があることも知っておきましょう。
スポンサーリンク
老人ホームでの生活まとめ

ここまで、老人ホームでの生活や老人ホームの種類、費用に関してお伝えしてきました。
- 老人ホームではメリハリのある1日を過ごせるようにスケジュールが組まれている
- 有料老人ホームには「介護付有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」がある
- 老人ホームの入居者数は増えてきており、入居一時金が高い場合では数千万円かかることがある。また、月額費用も20万円程度は必要である
これらの情報が少しでもお役に立てば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
核家族化が進み、独居老人が増えてきた昨今、将来のことを考えると有料老人ホームという選択肢も視野に入れなくてはなりません。また、介護のことを考えると家族の負担にならないようにと入居を決める方もいるでしょう。有料老人ホームにはどのよ[…]