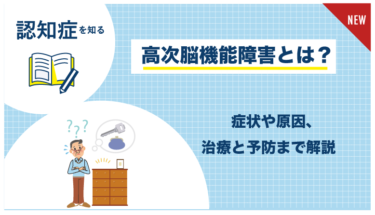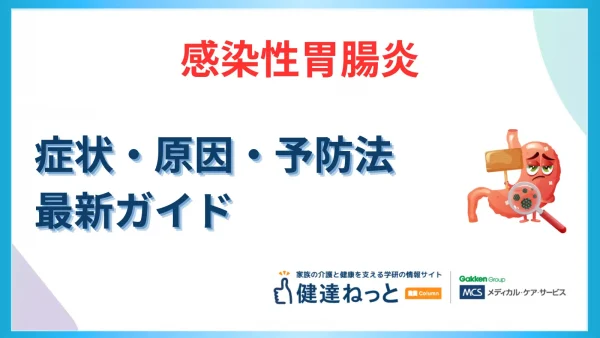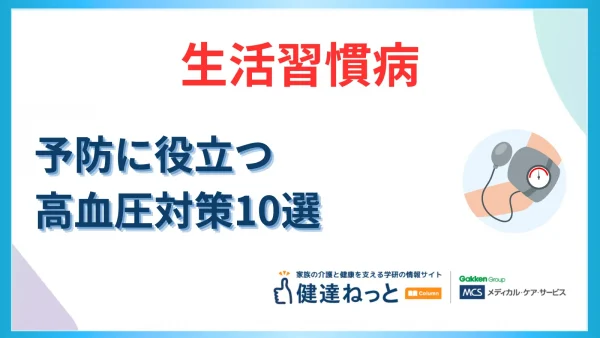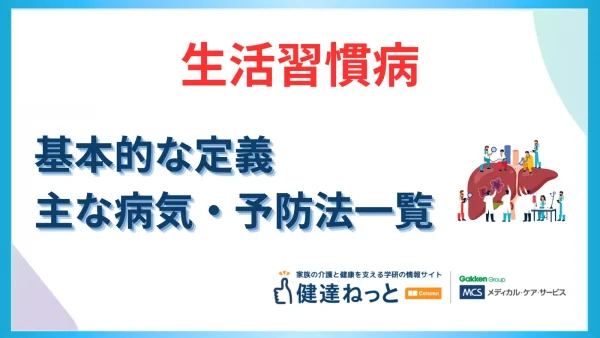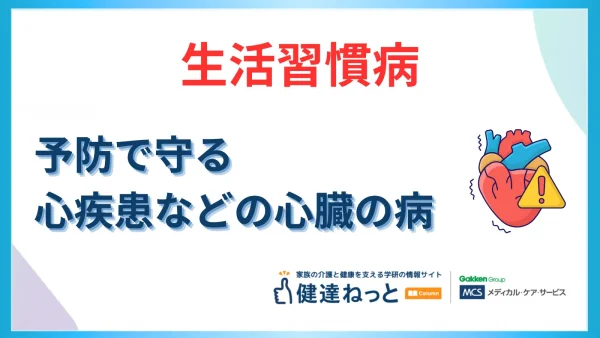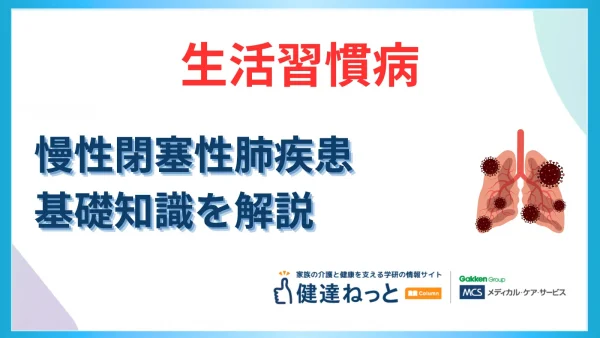高次脳機能障害という病気を聞いたことがありますか。
症状としては認知症と似ている部分もありますが、認知症とはまた異なります。
本記事では、高次脳機能障害のリハビリについて以下の点を中心にご紹介します。
- 高次脳機能障害のリハビリについて
- 高次脳機能障害患者の生活:運転について
高次脳機能障害患者がいる家族の方や周りの方の参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。
高次脳機能障害について知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。
高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人にも自覚症状が無いことが多いです。今回は、そんな高次脳機能障害の症状や原因を以下のポイントに沿ってご説明します。高次脳機能障害になった場合に失われる機能はどのようなも[…]
スポンサーリンク
高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、病気や怪我、事故などが原因で脳が損傷を受けたあとに起こる後遺症の一つです。
原因として挙げられるものはさまざまです。
病気の場合、以下の原因が挙げられます。
- 脳出血
- 脳梗塞
- くも膜下出血
- 細菌やウイルスによる脳炎
- 低酸素脳症
外傷の場合、以下の原因が挙げられます。
- 交通事故
- 転倒・転落
- 溺水
このような要因で高次脳機能障害が発症します。
原因は明確にわかっていますが、症状自体は外面からは見えないため「隠れた障害」であるとされています。
高次脳機能障害の症状については以下に詳しく紹介していきます。
注意障害
注意障害とは、集中力が持続せず、無意識に他のことに気を取られてしまう症状のことです。
そのため、2つのことを一度にできない状態です。
例えば、食事中にテレビやラジオなどが流れていると一切食事をできない状態になってしまいます。
このような場合、食事の際にはテレビを消したり、注意散漫になりそうなものは排除していくことで対処できます。
遂行機能障害
遂行機能障害とは、予定を立てて行動をすることが難しくなる症状のことです。
例えば、予定の時間に遅れてしまったり、予定自体を忘れてしまったりすることがあります。
予定を細かく紙に書いたりして時間がわかるようにタイマーなどを使用することをおすすめします。
社会的行動障害
社会的行動障害とは、感情をコントロールすることが難しくなる症状のことです。
そのため、人間関係を構築することが難しくなり、社会生活に適応できなくなります。
例えば、少しのことで声を荒立てるほど激怒したり、暴力を振るったりすることもあります。
周りの家族や介助者にとってもストレスになるため、知識や対応方法をしっかりと押さえておく必要があります。
記憶障害
記憶障害とは、少し前のことでも忘れてしまったり、新しい物事を覚えることが難しくなる症状のことです。
忘れないようにメモをして渡すなどの工夫をすることをおすすめします。
本人にも忘れないように日常生活でも細かくメモすることを指導していくことで生活がしやすくなります。
高次脳機能障害の症状について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
スポンサーリンク
高次脳機能障害患者のリハビリ方法

高次脳機能障害の症状が理解できたところで次は、リハビリ方法について紹介していきます。
症状を正確に把握し、そのうえで適切なリハビリを行うことが大切です。
適切なリハビリを行うことで症状が改善したり、進行を遅らせることが可能になるといわれています。
詳しいリハビリの内容は以下で説明していきます。
機能訓練
機能訓練の目的は、低下した能力自体を訓練することで能力の改善や機能上昇を目指すものになります。
具体例としては、注意障害の場合には計算の訓練をして集中力を向上させる注意訓練を行います。
記憶障害に対しては、簡単な数字や記号などを覚えるなどの記憶訓練を行います。
代償手段の獲得
代償手段の獲得の目的は残存している能力を最大に活かすことです。
保たれている能力を使って低下した能力を補います。
例えば、遂行機能障害に対しては予定通りに動けるようにアラームやタイマーを使用するなどです。
また、記憶障害に対してはメモを取るなどします。
このような日常の些細なことでも日常生活における効果が期待できます。
環境の調整
環境の調整をすることは非常に大切です。
環境といっても単純な生活環境以外にも人との関わり方も環境の一部になります。
生活環境であれば、物の定位置を決めておくことで生活しやすくなります。
他にも、周りの人との関わり方にも工夫が必要です。
例えば、理解しやすいように伝え方や使用する言葉を統一することが挙げられます。
高次脳機能障害の治療について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
内的記憶戦略法
内的記憶戦略法とは、自分のなかにあるイメージや視覚情報から言語を導き出す方法になります。
記憶したい人の名前とイメージを結びつける顔ー名前連想法や、身体の部位とものを関連付けるペグ法などがあります。
顔ー名前連想法やペグ法によって、残存する機能のなかで言語やものを思い出すことができるようになります。
すると、人名や持ち物を忘れることなく思い出せる可能性が高まります。
外的補助手段
外的補助手段は、人名やものの名前を外的な道具を用いて補う方法です。
メモや付箋、スマートフォンのスケジュール機能などを用いて補っていきます。
高次脳機能障害によって記憶に関する能力が低下しても、繰り返し道具を使うことで徐々に定着していく効果が期待できます。
外的な補助によって記録できる量を増やすことはできますが、道具自体の使用方法や確認自体を忘れてしまう可能性もあります。
その他の方法
その他の方法として、生活に必要な情報だけを特化して覚える方法や手がかりを徐々に減らしていく手がかり漸減法があります。
日常生活に特化した情報では、入院中であれば看護師や療法士の名前、自宅生活では家族やヘルパーの名前を重点的に覚えることに用いられます。
手がかり漸減法では、用語を1文字ずつ増やしていき思い出すパターンと1文字ずつ減らしていく方法があります。
最終的には手がかりなしで思い出すことができるまで訓練します。
高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人にも自覚症状が無いことが多いです。今回は、そんな高次脳機能障害の症状や原因を以下のポイントに沿ってご説明します。高次脳機能障害になった場合に失われる機能はどのようなも[…]
高次脳機能障害のリハビリ期間は?

高次脳機能障害が起きた場合、医療機関を受診してリハビリテーションを受けることが多いです。
リハビリテーションを手厚く受けるには、入院や通院する必要があります。
リハビリテーション目的で入院する場合、高度の高次脳機能障害を患っているときに最大180日の入院が可能となっています。
また、国立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能障害情報・支援センターによると、高次脳機能障害者が訓練を受けた場合には一定の効果があることがわかっています。
具体的に訓練を受けた人の74%が6カ月のうちの効果を実感して、94%が1年のうちに効果を実感することができています。
このように、重度の高次脳機能障害が発生してから最大半年間は医療機関に入院しながらリハビリテーションを受けることができます。
入院期間が終了して自立した生活を送る方や、生活訓練や就労移行訓練を受けながら社会復帰をする方もいらっしゃいます。
みなさんは、高次脳機能障害について、ご存じですか?高次脳機能障害はケガや病気で脳に損傷を負い、日常生活に様々な支障をきたす病気です。高次脳機能障害になってしまった場合、どのような治療を進めていけばよいのでしょうか?この記事で[…]
高次脳機能障害患者は運転できるの?

高次脳機能障害にはさまざまな症状があり、生活に支障をきたすことも考えられます。
そこで疑問に感じることが高次脳機能障害の患者さんは運転ができるのかということです。
結論から言いますと、高次脳機能障害の患者さんでも条件を満たせば運転を再開することは可能です。高次脳機能障害には注意障害のある患者さんは、運転に集中できなかったり、半側空間無視の症状がある人は見落としてしまうことが多く、事故に繋がるケースもあります。
記憶障害の症状があれば、目的地に行く道順を忘れたり、目的地自体を忘れてしまうこともあります。
これらのことから高次脳機能障害の患者さんは、運転する上でさまざまなリスクがあるといえます。
そのため、運転を再開する際には周りの協力やリハビリが大切になります。
患者さんに運転したい意思がある際には身近な存在である家族にまずは相談していく必要があります。
運転再開については家族の意思で決定することもできるため注意が必要です。
本人が運転できると考えていても、周りの人やかかりつけ医によっては運転をすることは難しいと判断するケースもあります。
高次脳機能障害者用の運転講習もありますので参考にしてください。
講習を受けられる機関は、院内や教習所の二通りがあります。
運転のシミュレーションなどの講習を受けて合格した人が運転再開可能となります。
高次脳機能障害の診断について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
高次脳機能障害は自分では気付くことが難しく、周囲からの理解が得られにくい障害のため、日常生活で困っている方も少なくありません。そのような場合、高次脳機能障害の診断を受け、適切なリハビリテーションを行うことが大切です。今回は、[…]
高次脳機能障害患者のリハビリのまとめ

ここまで高次脳機能障害やリハビリについての情報を中心にお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 高次脳機能障害とは、明確な原因があって脳に障害が起こること
- 高次脳機能障害の症状には、注意障害や遂行機能障害、社会的行動障害などさまざまな症状がある
- 高次脳機能障害は適切なリハビリをすることが大切
- 高次脳機能障害者でも講習を受けて一定の条件を満たすことができれば運転再開が可能
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。